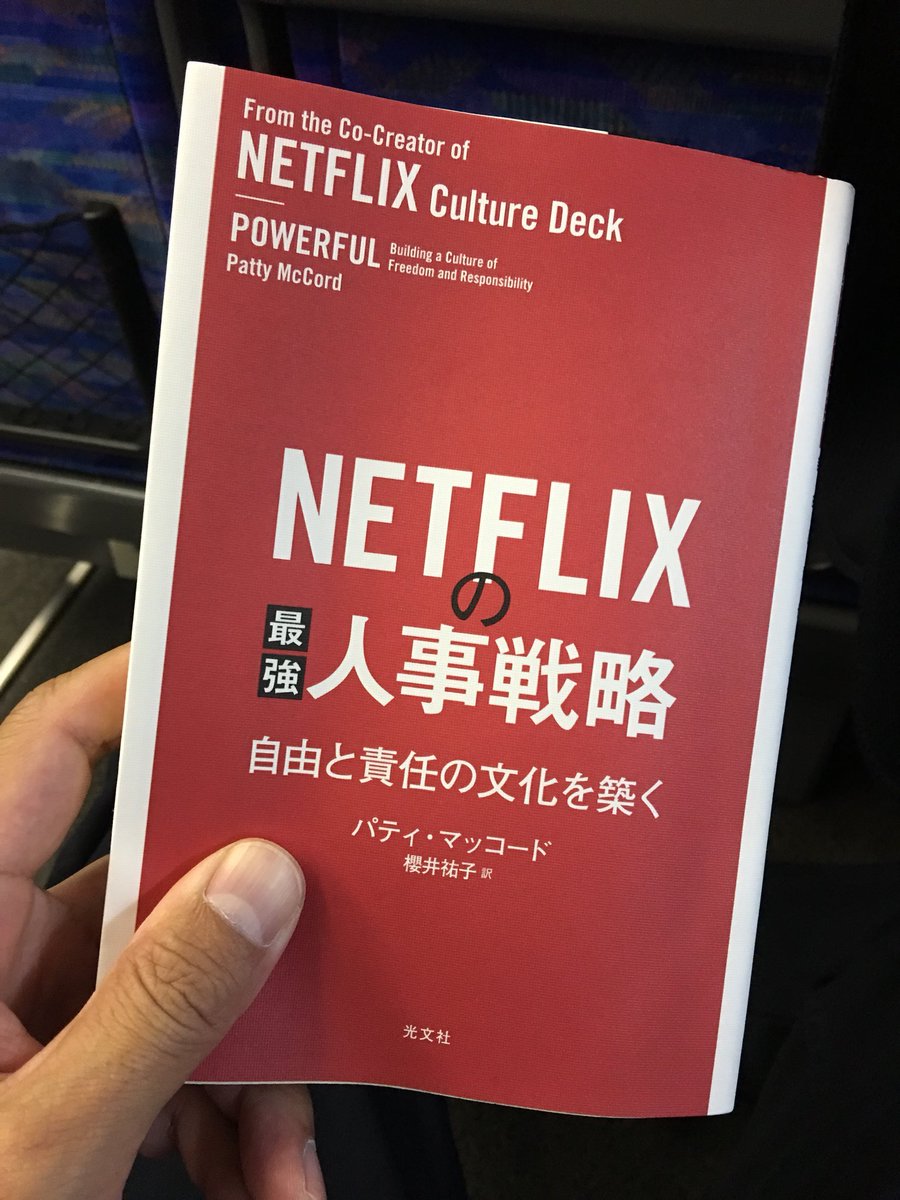251
オルテガの定義によれば、貴族=対価を求めずに何らかの役割を自ら背負い、果たそうとする人で、大衆=何らかの役割を背負うことなく対価を求める人となる。そして「貴族なしに社会は成立し得ない」と指摘する。一種のアマチュアリズムなんですね。プロって対価が前提ですから。
252
「敵をデザインする」ことを考えてみる。前向きなビジョンがあればもちろん素晴らしいけどなかなか難しい。そういう時は「世界から無くしたいもの=敵」を考えてみるといい。敵ができるとものすごく「やるべきこと」がはっきりします。モチベーションも湧きますしね。
253
モチベーションはいまや「最も希少な経営資源」になりつつあります。こういう時代になるとモチベーションの最適化、
いわば「モチベーションポートフォリオマネジメント」が経営の最重要課題になってくる。旧弊な人事部門にこの重責を担わせられるのか?
254
よく「ファーストペンギンがいない」と嘆かれますけど、本当に重要なのは「セカンドペンギン」なんです。「ファースト」って相対的な概念で、「セカンド」が出て初めて「ファースト」になれる。「セカンド」が続かないと「一人で飛び込んだ痛いヤツ」になってしまう。「セカンド」重要です。
255
外国にできるだけ出たほうが良い。それはもちろん外国を知るためでもあるんですが、なによりも日本という国がいかにたくさんの素晴らしい面を持っているか、それが貴重なことなのかというのを実感するためです。
256
副業には「クソ仕事に意味が生まれる」というメリットがあります。副業として「あまりお金にならないけどオモシロイ仕事」を続けるために「お金にはなるけどツマラナイ仕事」をちゃんとやる。ツマラナイ仕事にも戦略上の意味が生まれるのでモチベーションが上がり、結果的にパフォーマンスが上がる。
257
特定の会社でしか通用しないスキルを身につけて「成長した」と喜んでる人がいるけど、人生の袋小路へと至る危険な道を歩んでいるのだ、ということを認識したほうが良い。
258
「頭の良さ」の基本は「見る力、聞く力」です。情報処理は「入力→処理→出力」ですから「入力」が弱ければ「出力」も弱い。みんな論理思考等の「処理」やプレゼン力なんかの「出力」を鍛えてるけど「入力」が弱いとどうしようもない。資材が納入されない工場でプロセスだけ磨いてるわけですから。
259
「正しさ」に頼らない。「正しさ」でつながっている仲間は全然楽しくない。だから人間関係として長続きしないし、仕事にも繋がらない。「楽しさ」はその真逆です。
260
これ実感値ととても符合する。心が荒んだときに静かな部屋でピアノ即興で弾いてるとものすごく癒されていくのわかりますから。block.fm/news/making_mu…
261
「逃げろ」という指摘に「責任」を持ち出して噛み付いてくる人へ。どうして「無責任が良い」かは歴史が証明してます。事業失敗の責任が個人に帰された中世ではリスクが高すぎて事業は起きなかった。「責任を取らなくて良い」とする有限責任法人が生まれて初めて事業を始める人が増えたんです。
262
つまり「責任論を持ち出して他者を糾弾する」というのは社会を萎縮させてるということです。ひとたび失敗すれば責任を厳しく追及されるような社会で誰がリスクを背負うものですか。失敗はチャラにできる、つまり「無責任」だからこそ活発な経済活動が起きるわけでね。
263
多くの人がTwitterを実名でやりたがらないのは「発言には責任を持つべきだ」と考えているからでしょう。そう考えれば怖くて実名でのホンネ発言なんて出せるはずがありません。別に責任なんて気にしなくて良いのに。ホンネで話さない人に敵はできないけどそれって味方もできないってことですからね。
264
今朝の日経のビームス設楽社長の言葉。「努力は夢中に勝てない」。天才型と努力型が戦うと天才型が勝つわけですが、これは別に「才能は努力に勝る」ということではなく、「努力型の努力は天才型の努力に質量ともに劣る」ということですよね。努力を努力と思ってやってる時点で先は見えてますね。
265
コンサルの顧客によく「事例を見せてください」という人がいますけど、これって「抽象で考えることが出来ないので具体で見せてください」ということですよね。でも事例は原理的に全て過去になりますから未来を先取りすることはできません。常に「後追いして右往左往する立場」でしょうね。
266
根性論のないアメリカで、なぜ優秀な人材が生まれるのか
real-sports.jp/page/articles/…
267
「多忙」と「充実」を混同しない。「忙しさ」にも「質」があります。かつての自分がそうだったけど「質の悪い忙しさ」を「充実」と勘違いすると人生を浪費することになる。ソローが言ってますね。「アリだって忙しい。問題は何に忙しいのかいうことだ」って。
268
「頭ではわかるけど心は動かない」と「頭でわからないけど心は動く」。これから大きな影響力を発揮するのは後者ですね。
269
「迷惑をかけてはいけない」。しかしそもそも「迷惑」とはなにか?「迷惑」を決めるのは行為者ではなく受け手です。赤ちゃんが泣いていれば「かわいいな」と思いますが、中には「うるさい!」と怒鳴る人もいる。この場合「迷惑」を生んでいるのは誰か?受け手の恣意による「迷惑」が規範となる奇妙さ。
270
「完璧」を目指したら何も始められないし続けられない。この年になってつくづく思うのは「まずは70点でいい」ということです。「完璧」を目指す人ほど試すこともできずに袋小路で窮屈なままに手詰まりになってる。まず始める、続ける。明らかに他人を不幸にしてると思ったらその時点で止めればいい。
272
たよーせーたよーせーと最近はよく言われますが、多様性の増大はエントロピーの増大を招く。「砂糖だけ」より「砂糖と塩」のほうが料理の幅は広がるけど、砂糖と塩を混ぜてしまうとゴミになる。この点を理解せずに多様性だけを増大させれば単なるカオスがうまれるだけ。
273
自分の強み・弱みは内省してもよくわかりません。結局、実際にやってみて世の中からどう評価されるか試してるしかない。これを40代で初めてやるというのはリスクが大きすぎます。若い時にいろんなことにチャレンジして世の中からダメ出しされないと、何が得意かもわからないまま終わることになる。
274
単に副業がいいとか悪いとかいうことではなく、その人の能力を社会がちゃんと使い切れるかどうかが大事。ある会社だけでその人の能力を使い切れなければ、副業して社会に貢献してもらった方がいい。
275
やったことに対する後悔は日々小さくなるけど、やらなかったことに対する後悔は日々大きくなる。