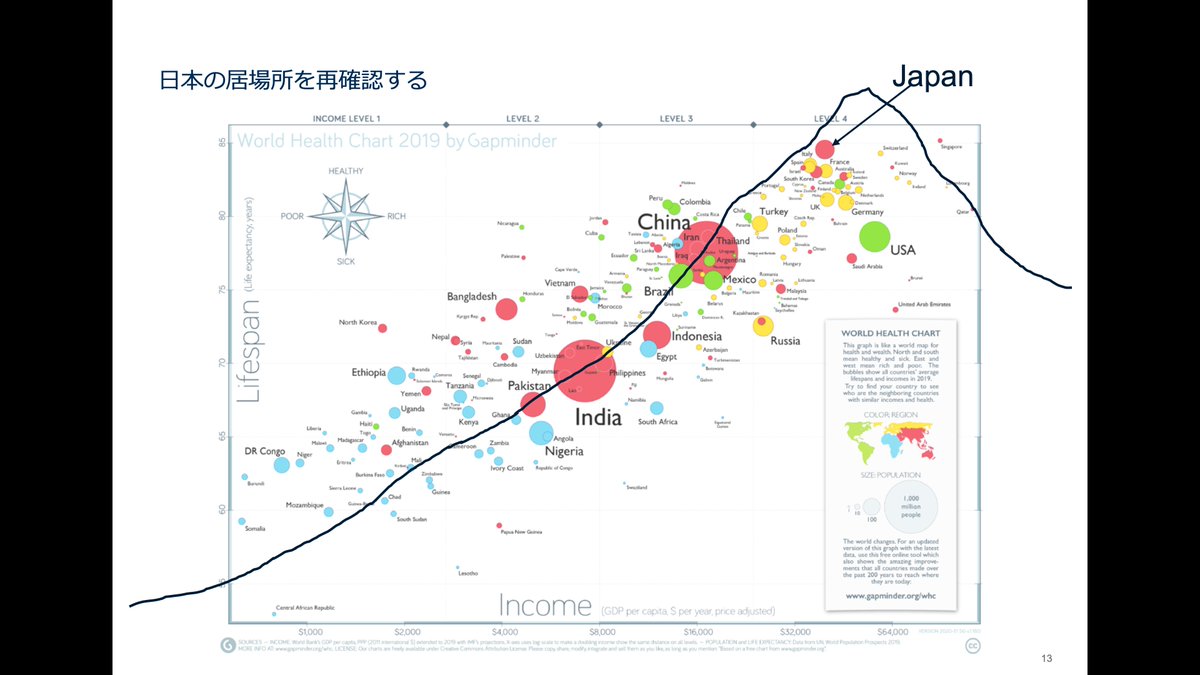351
「負ける技術」というテーマで本を書けないかなあ、と思っています。世界を巨大なトーナメントと考えれば最後は全ての人が敗者になります。全ての人が敗者になるシステムの中で生きているにも関わらず、「負け方」が教えられず、「勝ち方」ばかりが喧しく叫ばれている。需給ギャップがあるわけですね。
352
建築家の隈研吾さんは、大学院に進学する際、当時、建築は作らずに未開集落の調査ばかりしていた原広司研究室に入っています。同期は「何の役に立つの?」と哀れんだそうだけど、隈さんは「役に立たないという確信があって進んだ」と自伝に書いてます。さすがというしかない。
353
多様性の問題は本当に難しいですね。ビジョンや価値観について多様性を認めると単なる「烏合の衆」になってしまう。組織というのは一方でレーザーのようにフォーカスを絞った目標・ビジョン・価値観が求められる一方で、アイデア・手法・アプローチには多様性が求められるわけですからね。
354
「多様性」をはきちがえてるケースが多いように思います。「砂糖だけある」という状態よりも「砂糖と塩がある」という状態の方が料理の幅は広がりますが「砂糖と塩が混ざったものがある」状態では何の料理も作れません。
355
最近「多様性」は疑義を許さない絶対教義みたいになっていますけど、そもそも「多様性がなぜ組織のパフォーマンスを上げるのか?」と訊かれて答えられる人がどれくらいいるのでしょうか?多様性と組織行動のメカニズムを理解しないままにただ多様性を高めれば組織のパフォーマンスはむしろ低下します。
356
人文科学系学部を廃止して社会で役に立つ学問に片寄せ寄せするよう文科省が指導してますが、最大の問題は「社会に最適化した人材」ばかりになってしまうと「社会そのもののあり方」を批判的に考え、新しい社会のあり方を提案できる人材が居なくなってしまう、ということです。
357
他人に迷惑をかけてはいけない、というお仕着せそのものが他人にとって迷惑です。これほど人の行動の自由度を奪う呪いはありません。
358
皆、シンプルなことを忘れてると思う。それは「要らない会社は要らない」ということ。売上が下がる、利益が減る、赤字になる…いろんな手で抗おうとするけど、経営の本質は「要らない会社」を「要る会社」にする、「要る会社であり続けさせる」ということに尽きると思う。
359
以前、フランス人の同僚から「引き継ぎってなんだ?」と聞かれて説明したところ「仕事の内容を新任に説明するのはマネジャーの仕事だろう?そんなことしてるから日本人はバカンスが取れないんだよW」と言われ、グウの音も出なかった。
360
リモートワークによってコミュニケーション不足が発生してるのなら、それはもともと「記号化できない情報」に依存して組織を回していたということでしょう。それは例えば「空気」のようなものだということです。
361
アフターコロナは「何が正解がよくわからない時代」になります。こうなるととにかく早くいろいろ試してうまく行く方法がなにかを探り当てる一種の学習力が重要になるんでしょうね。
362
ピクサー社長のエド・キャットマルはいわゆる企業ビジョンが嫌いということで知られていますが、なぜ嫌いなのかというと「それが答えのように見えるから」だそうです。誰も考えなくなってしまうと。だからもっと曖昧で謎かけのようなものにするべきだ、と言うんですね。これはとても面白い指摘です。
363
ちなみに「Answer」の語源は「And Swear」で、つまり「誓う」ということです。「答え=Answer」を捉えたと思った人はそこで思考停止して旅を止めるんです。そして日本でエリートと言われている人は「早く正確にAnswerを出せる人」のことですね。
364
ニュータイプは「答え=Answer」ではなく「問い=Question」を探す。「Questionには「Quest=冒険の旅」という言葉が入っています。Never stop questioning!
365
だから「役に立つより、意味がある」が来ると言ってたでしょ?cnn.co.jp/business/35159…
366
367
「移住」という時、多くの人は「物理的な場所の移動」を思い浮かべます。でも、本当の「移住」というのは「モノサシの違う世界に移る」ということだと思うんですね。もちろん、その両者が一緒に起こることはよくあるのですが・・・昔のモノサシを捨てる。
368
生産性が上がらない理由の一つとして「遊びを知らない」というのがあると思うんですよね。余暇をSNSとゲームとテレビくらいにしか使えない人にとっては仕事を早く切り上げるインセンティブがありません。ラッセルも言ってますね「余暇を楽しむには教養がいる」って。
369
老子もディオゲネスも「足るを知る人は幸福だ」と説いたけど、皆がそうなってしまうと需要は飽和して経済成長はストップします。つまり経済成長を求め続けるというのは「永遠に幸福になることを永遠に延期する」ということなんですよね。
370
経済成長しているのに格差が拡大している、という言い方がされますけどむしろ逆で、経済成長のために格差が必要だということでしょう。経済活動は「安く買って、高く売る」という行為なので「二つの境界」が必要になります。格差はその境界を生み出すために必要になる、ということです。
371
日本の労働生産性の低さを批判する人はたくさんいますが労働生産性は「失業の問題」と表裏一体だということは意識した方が良いと思います。経済学者のタイラー・コーエンは米国の00年代の労働生産性の向上を「賃金に見合う生産性を発揮できない人を大量に解雇したから」と結論づけています。
372
微妙な違和感を無視して押し切るとやっぱりいい結果って出ないものですね。直面すれば「なんで!」と感情的になってしまうトラブルのほとんどはよくよく振り返ってみれば決断の時に「微妙な違和感」があったことを思い出す。いつも「風が吹きぬける感覚があるか」を大事にしたい。
373
学校ではチャイムが鳴ると科目が切り替わり、このリズムに同期する忍耐力と、これに反抗することの無力感を子供に植え付けます。これは何のトレーニングかというと、元々は工場労働者を育てるための仕組みなわけです。自分のリズムを持たないロボット人間を製造する仕組みです。
374
私が本当に腹からいいたいことは、仕事そのものは立派なものだという信念が、多くの害悪をこの世にもたらしているということと、幸福と繁栄に至る道は、組織的に仕事を減らしていくことにある、ということである。バートランド・ラッセル「怠惰への賛歌」p13
375
宮崎駿さんは、これらこそが街の中心部にあるべきだ、と言ってますね。商業施設ではなく。僕もまったく同じ意見です。 twitter.com/studyandourlif…