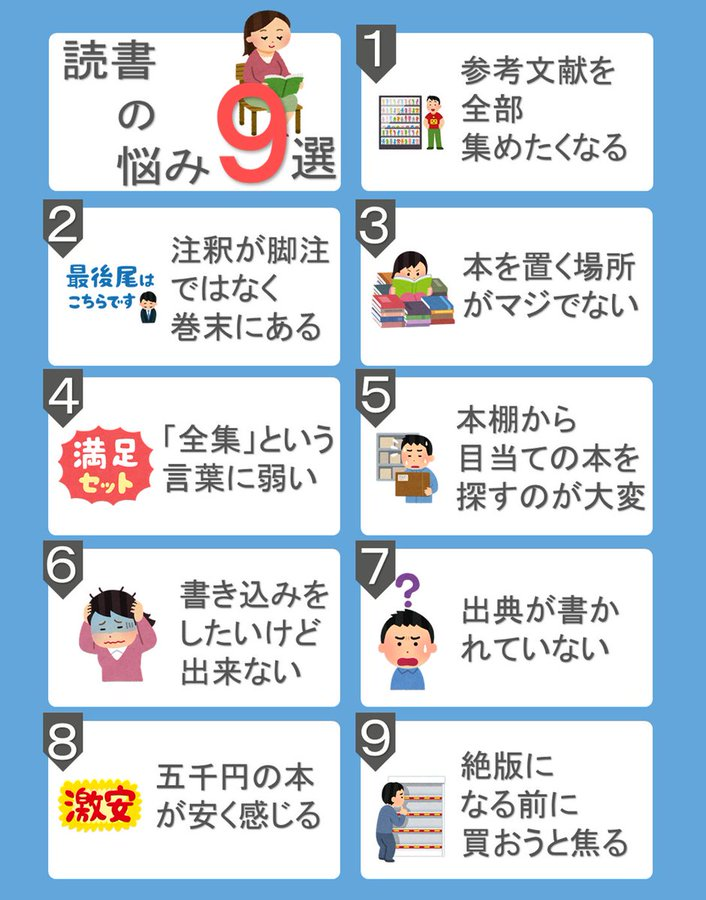26
27
28
29
30
「妻の留守中に外人の奴隷女と不倫するのが最高」というのです.現代の価値観で裁くべき事ではないですが,やはりこの一節を現代人である我々が反戦の歌として有り難く引用するのは賛成できないのではないでしょうか?これはあくまでも例えばの話ですが,古代の史料からの引用は慎重にということです.
31
これは「反戦」を歌い上げた詩に聞えますが,古代の戦争の研究者であるサイドボトムは「古代に絶対的な反戦を訴えた思想家はいない」と言います.『平和』の一節もそういった背景を知って読まないといけないわけです.さらにこの一節には衝撃の続きがありまして,平和になって何をしたいのか?
32
これはあくまでも一般論なのですが,古代の文献から「格言」や「座右の銘」として言葉を引用するときは文脈に要注意です.特に古代にない概念の場合は尚更です.どういうことかというと例えばアリストファネス『平和』という喜劇に「ムーサよ,戦争を遠ざけて親しき私と踊り給え」というのがあります.
33
34
35
36
37
39
40
昆虫食を嫌悪する心に進化的な基盤があるというトンデモ話で,進化心理学がトンデモ学問扱いされると切ないので少し呟きます.進化心理学の成果として有名なのは「エディプス・コンプレックス」の定量的な否定に成功したことです.フロイトによれば男児は父と母親を巡って性的な葛藤があるとされます.
41
42
43
44
45
46
47
50