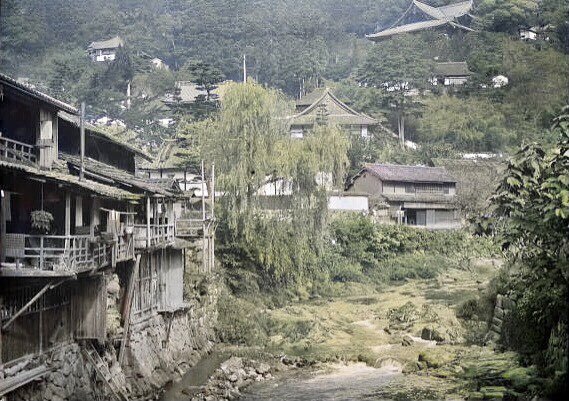227
230
渋沢栄一が明治政府に出仕した頃の登場人物たちの年齢をまとめました!
#青天を衝け
231
232
234
茨城県立歴史館に所蔵されいる、慶喜の愛猫、ハンの写真です。
政治の舞台を引退した慶喜は趣味に没頭していき、その中でも熱心に取り組んだ趣味が将軍時代から好んでいた「写真撮影」でした。
#青天を衝け
235
236
238
次期総理大臣となる岸田文雄氏は現在64歳ですが、日本初の総理大臣である伊藤博文は就任当時20歳も年下でした。
40代が中心で最年少は38歳だった日本初の内閣の閣僚たちをまとめています!
youtu.be/l_KlubVrgNY
239
240
渋沢栄一の長女の長女の歌子と二女の琴子の写真です。
歌子は枢密院議長となる穂積陳重に嫁ぎ、琴子は大蔵大臣、東京市長を務めた阪谷芳郎に嫁ぎました。
#青天を衝け
241
富岡製糸場は主要な輸出品の生糸の品質を高め、国際的信用を取り戻すために設立されました。
初代工場長は尾高惇忠が務め、旧士族の娘らから工女を集めました。
工女になると西洋人に生き血を飲まれるとの噂で工女集めは難航しますが、惇忠は噂を払拭するために娘を工女第一号としました。
#青天を衝け
242
244
245
246
247
渋沢栄一が大阪で出会ったのがのちに妾となる大内くにです。
くにとの間にできた子の文子が、尾高惇忠の子の次郎に嫁ぎ、次郎の孫が大河ドラマテーマ曲の指揮を務める尾高忠明氏になります。
妹の照子は、栄一の妻千代の姉の子で、後に富士製紙社長などを務める大川平三郎に嫁ぎました。
#青天を衝け
248
渋沢栄一は女遊びも激しく、子供は50人から100人いるともいわれています。
のちに財産管理のための「渋沢同族会」が発足しますが、この会には栄一の子と認められた人物しか入ることはできませんでした。
遺産争いを避けるためですが、それだけ子供が多かったことにもなります。
#青天を衝け
249
渋沢栄一の女遊びの激しさは妻も認めており、後妻の兼子夫人は「論語とは上手いものを見つけたよ。あれが聖書だったらてんで守れてないものね」と語ったそうです。
キリスト教では姦淫は禁止ですが、論語には性に関する戒めの記載がなく、論語を重んじた栄一をからかったものでした。
#青天を衝け