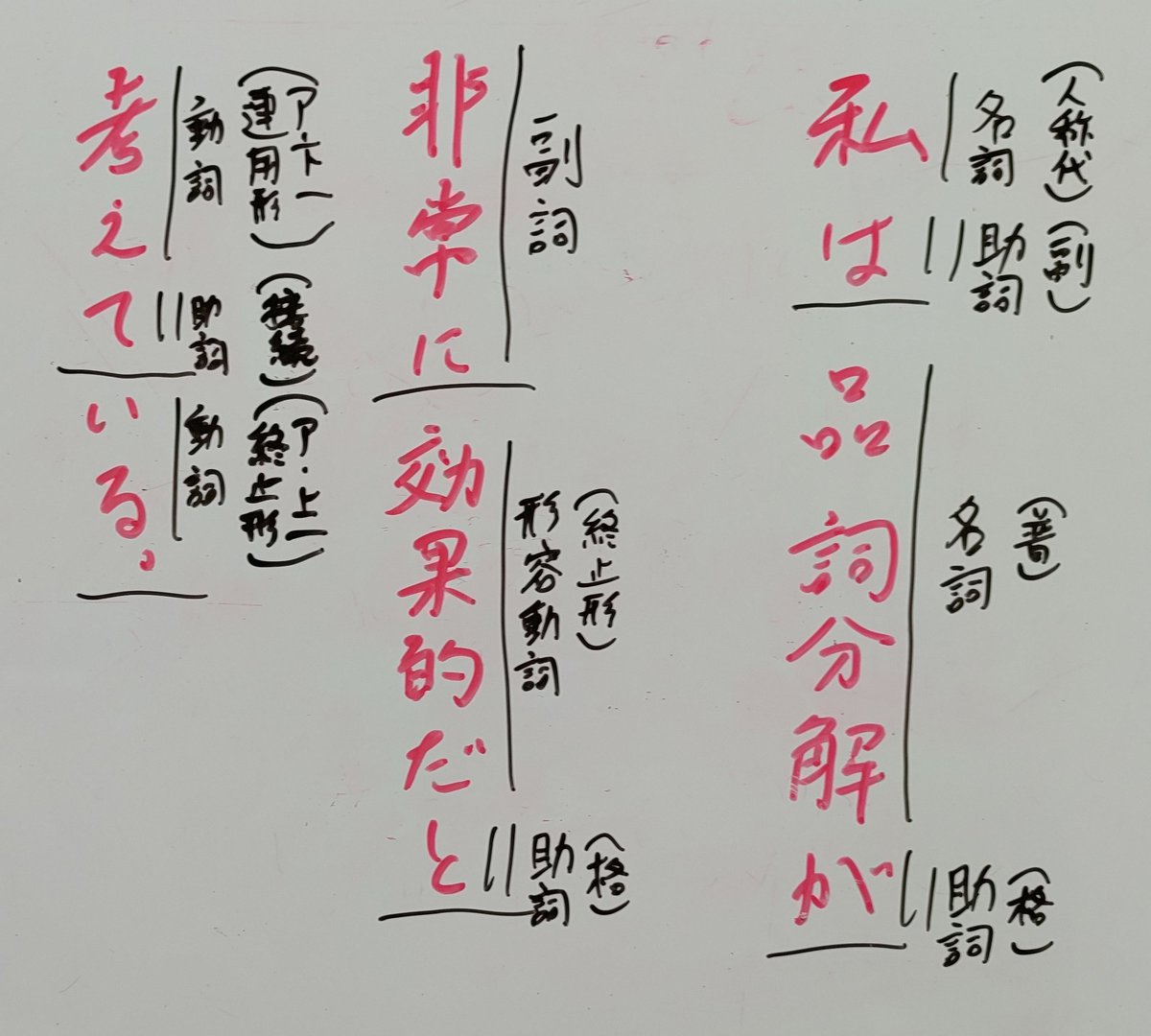701
702
日本だとピアノ習い始めの子に必ずと言ってよいほど課されるバイエルは、その夫によると、学生時代、音楽教育法の講義で「昔の悪い例」として習ったのだという。
悪い教え方の見本!
オーストラリアではとっくの昔に、その子にあった教本を探して教えるのが一般的なのだという。
703
日本の強みは労働者が強いことだった。しかも会社への忠誠心も厚いという特徴があった。戦後、労働運動が盛んで会社と労働組合との衝突が絶えない中、カネボウは企業と労働者は同じ船に乗る運命共同体だとした(労使運命共同体論)。ここから、労使協調して企業の発展に尽くすというスタイルが定着。
704
ただし父も私も、若者が説教を聞きたがらなくなった時期がある。若者が話を切りたがり、帰りたがり、異論反論を述べたりして。「偉そうな口を叩くようになったじゃないか」と思っていたら、他の学生まで同じ態度に。いや、これは特定の学生が態度を変えたのではなく、自分が変質したのだと気づいた。
705
「食べられる食品を施設に提供」といえば、善意の衣を借りることができる。そう、阪神大震災で毛布を送ったように。しかしその時、「そういえば捨てようと思っていた毛布がうちにあったわ。あれ送ろうか」という人が少なくなかったため、被災地はゴミ捨て場と化してしまった。
706
聞くと、そこにある大きな樽は、大メーカーに買い取られ、混ぜられて大メーカーの名前を冠したお酒として販売されるという。こんな美味しい飲み物があんなに不味いお酒にされてしまうの?と衝撃を受けた。
少し瓶に分けて頂き、ボランティアたちで飲んでみた。みんな一様に感動していた。
707
いざというときに大事故を防げなくなる。だから、安全を確保するための「安全余裕」は必須となる。
実は食品ロスも同じこと。もし食料が足りないとなったらどうなるだろう?飢える人が出る。食料は命を支える必須のもの。これが不足したら死ぬ人が出るかもしれない。
708
90年代末に国家1種の試験を受けたときの長文問題が興味深かった。難しい専門用語が散りばめられ、有名な思想家や哲学者の名前がてんこ盛り。すごく難しいこと書いてる風。しかしその文章の骨子は最初と最後の数行にしか書いてなかった。文章の8割はどうでもよい内容だったことに衝撃を受けた。
709
さて、食品ロスをフードバンクに、という呼びかけは、どちらに転ぶだろうか。「腹が減っているなら文句を言わんだろう、こんなものでもありがたいと思って食うだろう」と思ってモノを出していないだろうか。そうした心映えはしっかり中身に映し出される。
710
フードバンクもそうなる恐れがある。というか、すでにそれが発生している。支援している方から聞いたけれど、ゴミにするしかないようなものが送られてきて、そうでなくても生活再建ができなくて傷ついている心をさらに傷つけられた、という人がすでに。むしろこうなると、悪意よりもタチが悪い。
711
耳鳴りの少なからずが、自分の血流の音だったりするという。通常、自分の血流は脳がキャンセルし、感じないようにしているのだけど、ふとした拍子で血流が音として聞こえると、どんどん気になって、ついにやかましくて他の音が聞き取れないようになってしまうという。
712
「余ったものはみんなフードバンクや子ども食堂に送ればいい」という流れができつつある。私はそれにちょっとした憤りを感じている。食べるに食べられないものを送る流れが今後もひどくなるようなら、いずれ私はその善意の皮をはぐことをためらわないだろう。
713
子牛一頭100円、4割は値がつかず殺処分。先月辺り紹介した話が記事に。 fnn.jp/articles/-/426…
714
現代の日本は、歴史上かつてないほど子どもと触れ合わない社会なのかもしれない。私のところには研究しに学生がよく来るのだが、赤ちゃんや幼児と触れ合う機会はほとんどないらしく、赤ちゃんを初めて抱いたという学生が多かった。子どもは苦手だ、という女子学生も。でも触れるようになると楽しそう。
715
もう一つは、外国の胃袋を握ること。アメリカの輸出する穀物は安い。アメリカの平均的農家は、四人家族を養うことができないくらいにしか売上がない。妻に働きに出てもらい、農家の自分は政府から所得保障をもらってなんとか生活。なんせ、トウモロコシの価格は生産に必要な経費さえまかなえない。
716
食品ロスとは、こうした安全余裕の一種でもある。もし消費者が買い求める需要とピッタリ同じ量の野菜しか作らないようにしたら、ほんの少し足らないとなっただけで価格が高騰しかねない。すると、野菜を買いたくても買えない人が出てきかねない。そんなことのないよう、安全余裕をもたせる必要がある。
717
「内部留保」考。
私は経済の素人だから、間違っていたら他の方々の指摘があるだろうとアテにしつつ、私の曖昧な記憶に基づいて書いてみる。
内部留保がたまり出したのは、90年代後半から2000年代初め頃までに、「銀行がお金を貸してくれない」ことが原因だったように記憶する。
718
実は8月に痛風になって苦しんでいた。痛風は別名「ぜいたく病」というらしいけど、私もYouMeさんも肉がそんなに好きではなく、魚卵もまず食べないし、野菜中心生活。とってもヘルシー。なのに痛風になって、YouMeさんを悔しがらせてしまった。原因は私にある。コーヒー飲み過ぎ。
719
しかし、プランテーションには気をつけなければならない面がある。人道的問題が起きやすいこと。アフリカのコーヒー園などでは、経営者やコーヒー豆を買いとる大手企業は儲かるが、働く労働者は低賃金に据え置かれることが多い。企業は利益を最大化させようとするので、安く働ける労働力を好む傾向。
720
石油が採れづらくなっている。石油を採るのにかかったエネルギーより、たくさんの石油エネルギーが採れなければ、経済的にもエネルギー的にも意味がない。石油が噴水のように吹き出していた時代は、採掘エネルギーの200倍の石油が採れたという。しかしシェールオイルは10を切っている。
721
「男の呪い」考。
シングルマザー支援をしておられる辻由起子さんから親しくお話を伺う機会があった。辻さんは女性を支援することがもっぱらなのだけど、今の日本の男性が非常につらい立場に置かれていると考えているという。以後は私の理解なので、文責は私にあるが、書き連ねてみる。
722
未使用品の毛布でも、10年くらい押し入れにしまいっぱなしだったのだろうという、つぶれてペシャンコのとか、なんだかかび臭いようなものだとかも少なくなかった。しかし手紙を添えられたその毛布は、フカフカで心地よく眠れるよう、配慮されていた。人気があるのも当然。
723
724
アフリカでコーヒーなどの商品作物を栽培しているのは、プランテーション。賃仕事で働く人たちが大量にいる。低賃金。日本の農業も外国人研修生の力でなんとか支えられているところも多く、プランテーション化が進んでいる面がある。
725
『税金を使ってお米を配る』が、いかに税金のムダ遣いか。
体験しないとわからないと思うので、普段やっていることをレポートします。
(中略)
私たち市民は人件費・ガソリン代も含め手弁当でやっていますが、官がやると、人件費、事務費、輸送費などが発生します。