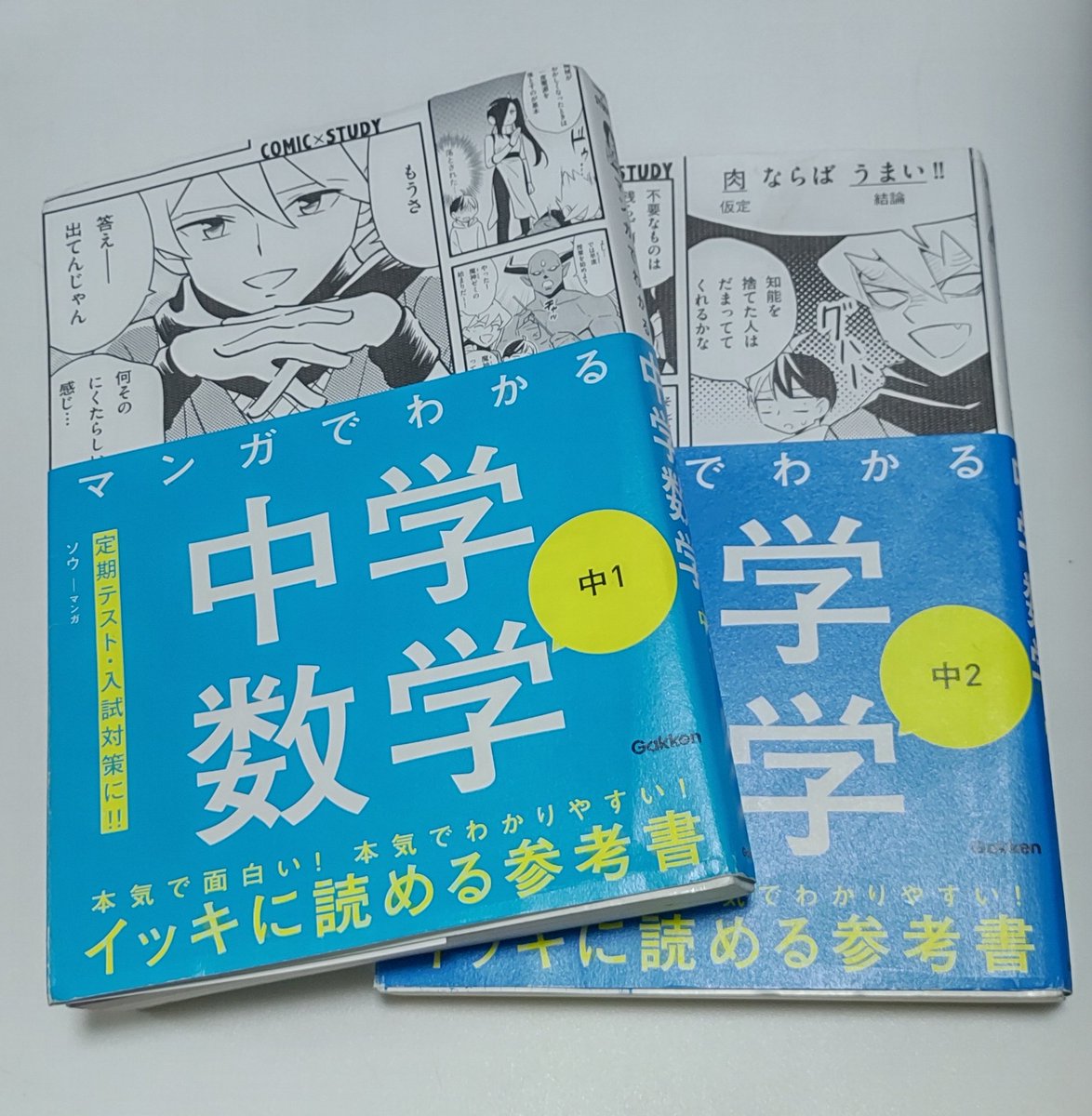626
「しぼりたての酒だ」と言って、飲ませてくれた。果物ジュースのような香りと味。それでいてどぎつさは一つもなく、味も香りも柔らかく、比喩ではなく、生まれてはじめてこんな美味しい飲み物に出会った。それは日本酒だった。
627
母親は、子どもに無償の愛、無限の愛を注げる存在であることを求められる、そんな世間からの風圧を、男である私も感じる。しかし、母親だって人間。休まなければ体力も気力も失う。孤独にさいなまれたら、精神的に不安定になって当然。休憩だってしたいし、遊びだってしたい。人間は、人間なのだから。
628
松山城がそびえる山は、もともとはげ山だったらしい。ここを緑豊かな山にするのに、面白い工夫をしたと伝えられる。麦を蒔くこと。すると、実った麦を食べに鳥たちがやってくる。ついでに鳥は、どこかで食べた木の実の種子をフンと一緒に出す。リンも種子も山にばらまかれる。
629
「自分より優れていなければ学ぶところがない」という言葉を聞くことがある。私はもったいないな、と思う。学びの機会が激減するから。どんな人からも学びが得られる。それどころか、私はイヌネコからも学ぶところがあるなあと思うし、何なら微生物からも学ぶ。いろんなところから学べると楽しい。
630
しかし、「サピエンス全史」のハラル氏が言うように、お金というものが、あるいは社会制度もが、人間の作り出した虚像でしかないなら、私達はその虚像を自ら作り出すこともできる。労働者の賃金を減らす社会じゃない社会を作ることだってできるはず。
631
とどめが、工場労働者への派遣社員の規制混和ではないか。これにより日本の労働者は、正社員と非正規社員とが反目し合う、いや、そこまでは言わなくても協働を難しくする労働環境を作った。会社の一体感を破壊し、開発力も失い、賃金は派遣社員だけでなく正社員も減っていった。
632
困ったのは、仕訳に人手がかかること。大量に積まれた段ボール箱を一つ一つ開け、何が入っているかを確認せねばならなかった。何が入っているのか外側からは全く分からないものも多かった。使えないものはゴミ。これが非常に大量で、場所も取られた。
633
無償奉仕ができるのは、実はゆとりあるお金持ちだけなんです。そして貧しい人の生活基盤を破壊する行為なんです。そうすることで、貧しい人がますます低賃金でも我慢しなきゃいけなくします。するとお金持ちは安く労働を買い叩ける。そうした狡猾さがその「無償の善意」には隠されてるんです。 twitter.com/illmagawa/stat…
634
母には申し訳ないが、親の成績良かった自慢は、子育てにおいて不要だと思う。特にあまりにも良すぎる成績は、とてもマネできなさすぎてしんどい。それよりは、「子どもの頃の親なら勝てるかも」くらいの話の方が、子どもは負けるまいと思うようになるらしい。
635
しかし竹中平蔵氏の「これからは競争社会。頑張る者は報われ、頑張らない者は貧しくなる権利がある」という主張が登場。能力のある者もない者も賃金に大差ないのは「悪平等」と言われた。自分に能力があると自信を持つ人はこの主張に乗っかり、悪平等を破壊する行動に手を貸した。
636
体操服の頑固な汚れを落とす特殊な洗剤を売ってるメーカーの方から聞いた話。ある時から、顧客が「汚れ落ちない」と苦情が相次ぐように。製造プロセスや製法などを全部チェックしたが原因が見つからない。疑うのは原料しかない。そこで原料を提供してる会社に電話してみた。すると。
637
とある、高学歴が自慢の母親が「このあたりの人はレベルが低い、話にならない」と言って小バカにしていた。その子どもが転職を重ね、学歴を活かしきれない仕事に変わると、その子どもは母親のかけた「呪い」に苦しんでいるようだった。母親の小バカにしていた人間に自分がなったような気がして。
638
しかし、竹中氏の主張する世の動きは、決して必然ではない。人の世のことだからだ。人の世のことは、人が決められる。竹中氏はそれを知っていて、世の流れを変えようとし、そして成功させたのだろう。労働者の賃金を減らし、外国人投資家が儲かる社会の実現を達成した。見事。
639
以後、「問いかけ」と「能動性が起きた『奇跡』に驚く」のを、学生だけでなくスタッフや子どもたちに適用してみると、みんな能動性と意欲が高まり、楽しそうに取り組むようになることに気がついた。
640
私が驚く様子を見て、息子は「数字のことなら親を驚かせられる」と思ったようで、ますますのめり込んだ。私が「先回り」せず、「後回り」して驚いたから、興味関心が湧いたのだろう。
親の先回りはまあ、残念なことになることが多い、という話。
641
最近、「教育虐待」という言葉が広がっている様子。親が熱心に子どもを指導し、「上昇」させようとして子どもを潰してしまう事例が目立ってきているのだろう。私も複数見てきている。問題は、ものすごく「こじれる」ことが多いことだ。
bunshun.jp/articles/-/639…
642
その人だけだった。京大落ちて残念だったね、ではなく、大学の名前なんかどうでもよく、私が家事から逃げなかったこと、母が倒れた後、家族の危機を支えようとしたことを見てくれていた。そしてそのことを何より認めてくれた。家族も含めて、そうした反応を示してくれたのはその人だけ。嬉しかった。
643
けれど営業マンも、仕事から離れると、自分が驚くのではなくて、相手を驚かせたくなるらしく、関係をこじらせる人もいる。人間関係はまず相手に驚くことから始めるものだ、と、仕事で学んでいるはずなのに。
644
私が雇用問題を訴えるのもそのため。働く場所があり、社会に貢献できているという感覚は「居場所」につながる。雇用するのは高くつくから子ども食堂やフードバンクへの支援でお茶を濁す、というのは、政治家が「居場所」の深刻さを理解できていない証。居場所を減らせば社会は不安定化する。
645
日本はバブル前後で圧倒的な力を有していた。その時、西欧諸国は日本農芸化学会強さに恐怖した。何とかこれを弱体化したい。それがプラザ合意やBIS規制、半導体規制、株の持ち合い規制、大店法改正など、多岐にわたるルール改正だった。それらが日本の強みを削いでいった。
646
まとめました。
「教える」のではなく「教えてもらう」|shinshinohara #note note.com/shinshinohara/…
647
まとめました。
「子どもっぽい説教」と「大人の説教」|shinshinohara #note note.com/shinshinohara/…
648
竹中氏の弁舌は、日本の労働者を苦境に陥れ、外国人投資家に利をもたらす上で、素晴らしい触媒になったと思う。竹中氏の意見が受け入れられる素地が社会にあったとは言え、竹中氏でなければここまで加速しただろうか。そのくらい、竹中氏の弁舌は触媒として優れていたように思う。
649
企業が農業をする場合、最低賃金以上を保証しなければならない。しかしそうすると、農家が作る栗より高くなってしまう。なぜそうなってしまうのか。農家は自分の人件費のことを考慮しないで安く売っているから。つまり、今の農産物価格は農家の自己犠牲のおかげで安く済んでいる。