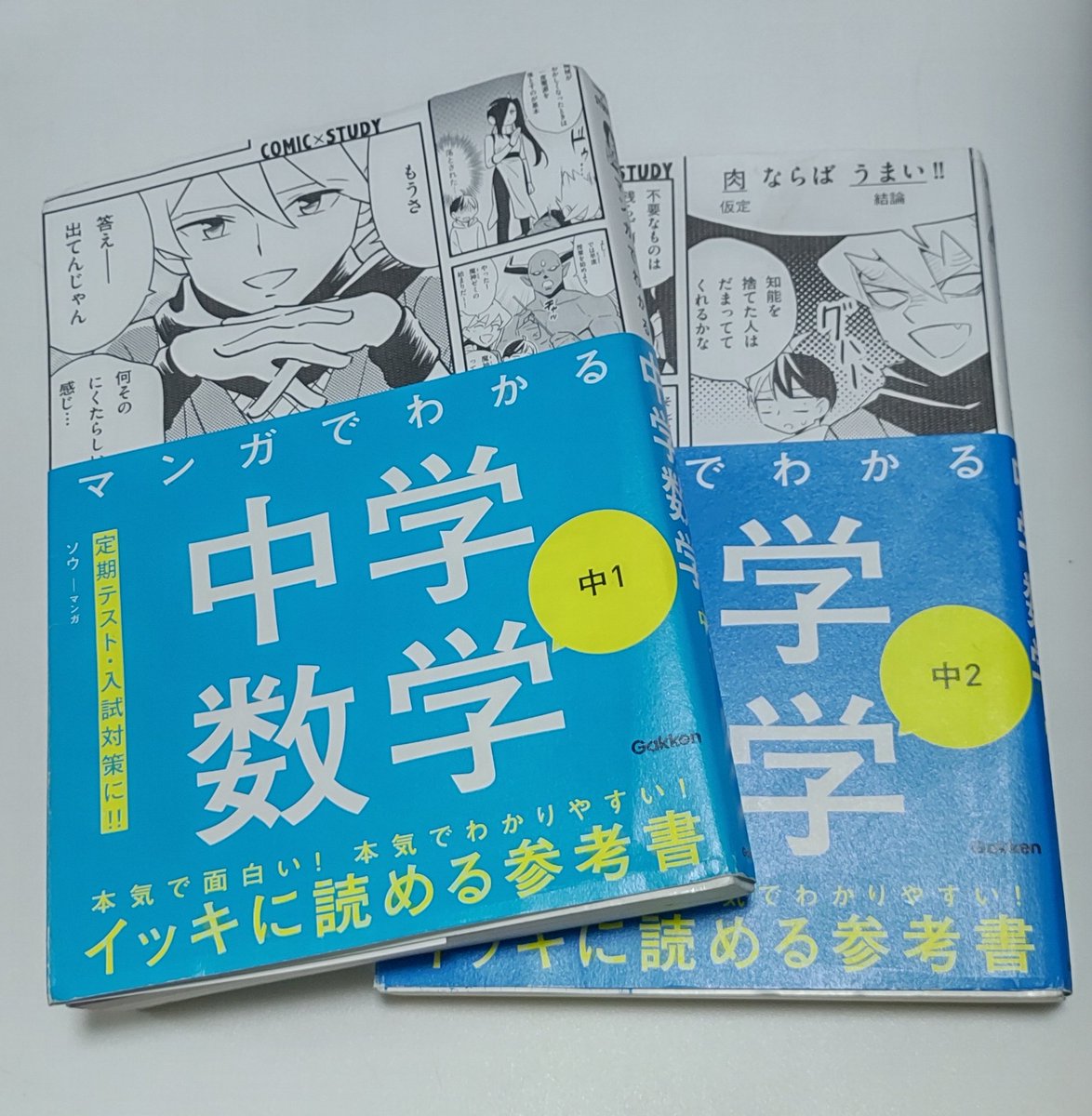526
レイチェル・カーソン「沈黙の春」が警告を発した頃の化学農薬には、二つの問題があった。水に溶けにくく、油に馴染みやすい性質(脂溶性)であったこと。そして、非常に分解しづらい化学構造だったこと。この二つの性質があると、体内に蓄積しやすい。生物濃縮が起きやすくなる。
527
多くの街が「ただ寝る場所」になっている。人間関係のネットワークは、電車で何駅も離れた場所の会社にあって、住んでる家は寝るだけの場所。ご近所との人間関係は希薄という人が多い。会社の人間関係が切れると、孤独に陥りやすい。
528
誰やこんなスカポンタンな記事を書いた奴は!死亡者のピークは感染者のピークの三週間後に来るねん!今の感染者で現在の死亡者の数を割り算したら小さい数字になるの決まっとるわ!ほんまに恐いのは感染者ピークの3週間後!小学校の算数からやり直せ!
news.yahoo.co.jp/articles/bc393…
529
私が思うに、人間は「居場所」を強く求める生き物のように思う。そして居場所とは、自分という存在を認めてくれ、自分を必要とし、自分のやるべきことがある場所であるらしい。別にいても構わない、いなくても構わないけど、という場所は居場所にならない。多分、必要とされることが大切。
530
遺伝子で才能の大半が決まる、という考えは根強い。遺伝子は重要だとは思う。けれど、あくまで「環境と遺伝子」のバランスで決まるものだと思う。
私はある酵素を大腸菌に大量に作らせようと、遺伝子を導入したことがある(大量発現系)。その実験はうまくいった。酵素を大量に作り出した。しかし。
531
なるべく孤独を感じずに済む社会を再構築できるだろうか?怒鳴り込みにくる高齢者の話をしたら、排除すればよい、というご意見も多かった。しかし排除すればますます孤独は深まる。孤独が深まれば、さらに精神が不安定化し、突飛な行動をとる人が現れる確率は高くなるだろう。
533
聞くと、そこにある大きな樽は、大メーカーに買い取られ、混ぜられて大メーカーの名前を冠したお酒として販売されるという。こんな美味しい飲み物があんなに不味いお酒にされてしまうの?と衝撃を受けた。
少し瓶に分けて頂き、ボランティアたちで飲んでみた。みんな一様に感動していた。
534
まあ、私も農学部卒業だと言ったら、「今時、畑を耕すのか」なんて言われたから、農学部がとても遅れた分野だと誤解している人は多い。しかし農学部は医学部、薬学部と並んでバイオサイエンスの研究で最先端を走っており、特に食品や飲料メーカーに就職がとても強い。
535
シングルマザー支援を中心に貧困問題に取り組んでいる辻由起子さんが、現場からの声を届けておられました。許可を得たのでここでシェアします。お米を配るという政策の問題点について。
では、次のツイートから始めます。
536
まとめました。
農学部はクワの振り方とトラクターの運転しか学ばない?という誤解・・・実は就職に強い|shinshinohara #note note.com/shinshinohara/…
537
「教えねばならない」という呪縛からいかに離れ、子どもたちが自ら動き出す能動性が生まれるようにするか。そこに意識をシフトすると、子どもの心が動き出す。指導者が能動的になっても仕方ない。子どもが能動的になることこそ、指導者の目的のはずだから。
538
結果、竹中氏はものの見事に労働者の分断に成功し、労働組合はボロボロになって機能しなくなり、労働者の賃金は下がり、経営者と株主が漁夫の利を得る構造ができるよう手助けをした。竹中氏がいなければ、ここまで巧みに社会が変わらなかったかもしれない。竹中氏の弁舌の力はとても大きい。
539
「まさか」と思いつつも、もしかしたら日本で「競争原理」を流行させ、正社員と非正規社員とに分断し、いがみ合わせ、労働者がまとまらないように仕向けたのも、日本の活力を奪い、その間に漁夫の利を得る「統治者」による現代的な「分割して統治せよ」なのかもしれない、という気がする。
540
当然のことを言うようですが、農家は農作物を作って売り、その収入によって老父母の病院代、子どもの学資を得ています。もし購買力のある市民にタダで配られたら、その人たちのお腹はそれで満たされますから、売り物の農作物はその分売れなくなります。すると、農家は自分の家族を支えられません。
541
欧米や中国は大陸性の気候。ざっくり言うと、湿度が低く気温も低め。すると、虫がそもそも少ない。農作物をダメにする病原菌も少ない。湿度が低く気温が低い条件は、有機農業が容易。だって、虫や病気の発生が少ないから。
542
昔の祭りはそうした装置だったのだろう。引っ越してきた人に「だんじりを引けるか?」などと誘い、街のイベントに巻き込んで、孤独を感じずに済むように、街のネットワークの中で自分の座標を感じられるようにしていたのだろう。しかし今は。
543
窓も何もない、完全閉鎖され、年中同じ気温で保たれた実験室で、植物の細胞培養してる方からの話。季節によって実験の成功率が変わるという。日も差さないのに!温度も一定なのに!植物の細胞は何かを感じて、反応しやすさが変わるのだという。原因は不明。
544
部下が自分の頭で考えて行動してくれない、とお嘆きの方は多いように思う。いわゆる指示待ちばかりで、自分で状況をよく観察し、何をすべきかを考えてほしいのに思考を停止し、指示が出るまで待ってる部下の多いこと、とお嘆きの上司をよく見る。
545
まとめました。
先回りすると興味を失う、後回りして驚くと興味を示す|shinshinohara #note note.com/shinshinohara/…
546
阪神大震災で、中古の毛布だったのだけれど、未使用品よりも人気の毛布があった。それには手紙が添えられていた。「使用済みのもので申し訳ないのですが、洗濯し、3日間日に干しました。こんなものでよろしければお使いください」。その毛布からは、人情のぬくもりを感じることができた。
547
驚き、面白がる、というのは、人間関係を最初につむぎ出すのに大切な様式のように思う。文化人類学の研究者が、見知らぬ民族を調査する場合もこの姿勢。これは、人間心理に寄り添ったアプローチなのかもしれない。
548
母には申し訳ないが、親の成績良かった自慢は、子育てにおいて不要だと思う。特にあまりにも良すぎる成績は、とてもマネできなさすぎてしんどい。それよりは、「子どもの頃の親なら勝てるかも」くらいの話の方が、子どもは負けるまいと思うようになるらしい。
549
昔、ビッグデータ解析の専門家が来て。水耕栽培でビッグデータ解析を行い、植物の生育を最大化する条件を見つけたい、と言ってきた。私は無駄だからやめておいた方がよい、と言った。私がビッグデータ解析や深層学習のことを知らないと思って、いろいろ説明してくれた。一応ひととおり聞いたうえで。
550
日本はそうはいかない。代表的なのは梅雨の時期。雨がずーっと降る。しかもそこそこ高温。高温多湿は虫とカビにとってパラダイス。虫がいくらでも湧く。カビがいくらでも繁殖する。無農薬でやろうと思うと、虫とカビをどうやって抑えるかが大きな課題になる。