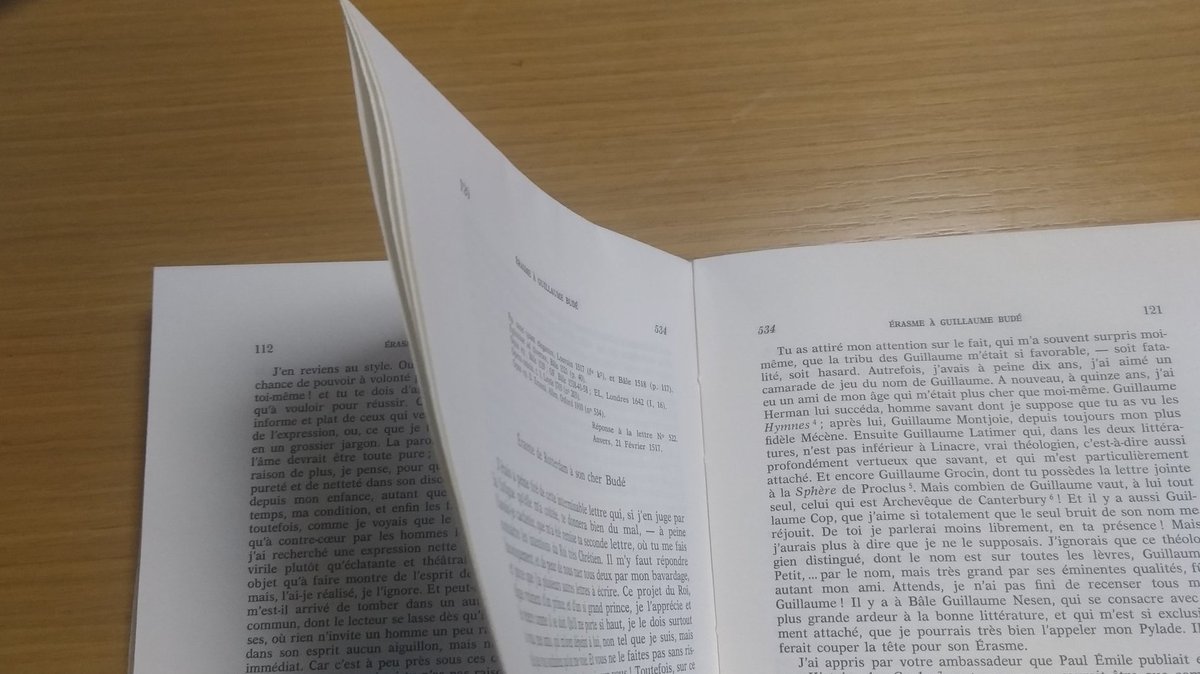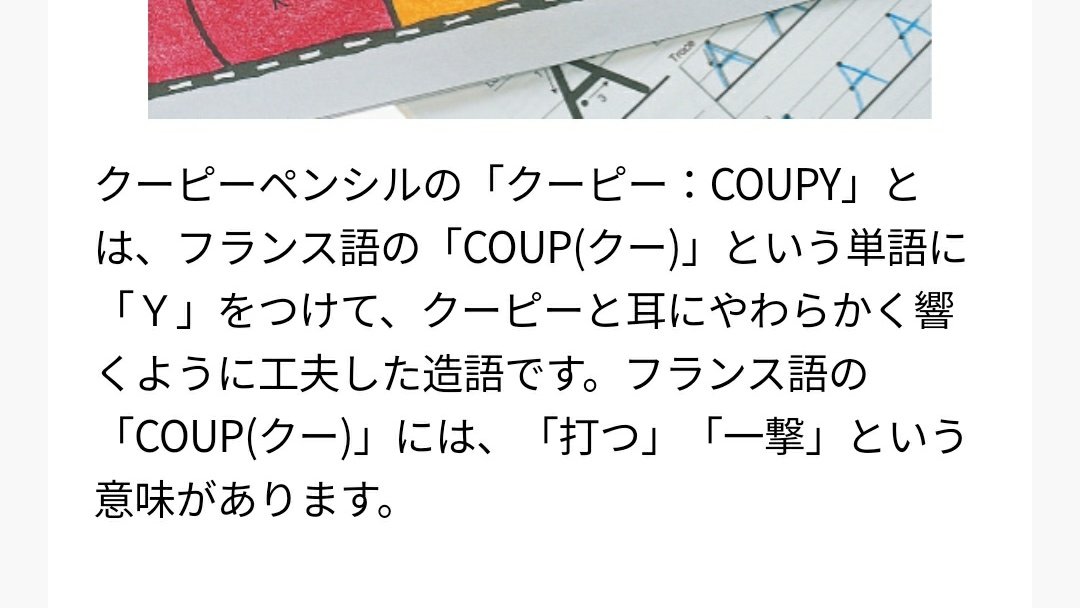1452
1453
1454
1455
legendに「伝説」や「図の説明文」という意味があるのは、語源のラテン語が「読まれるべき物(legenda)」だからです。伝説も読まれるべきだし、図の説明文も図を理解するには読まなくてはいけません。
-nd-は「されるべき」という意味なので、例えばアマンダさん(Amanda)も語源は"愛されるべき人"です。 twitter.com/monmon_bio/sta…
1457
1458
たまに耳にする「エウレカ」「ユリイカ」「ヘウレーカ」という言葉は古典ギリシャ語εὕρηκα(heúrēka)「私は発見した」が元で、これは動詞εὑρίσκω(heurískō)「発見する」の現在完了形です。
アルキメデスが浮力の原理を発見した際、この言葉を叫んで外を走り回ったと伝えられています。
1459
調味料入れや油入れだと考えられている、古代ローマ時代のガラスの容器です。魚の醤油差しと通ずるものを感じます。 twitter.com/OptimoPrincipi…
1462
サカバンバスピス(Sacabambaspis)という学名の元は、化石が発見されたボリビアのサカバンバ(Sacabamba)という地名と、古典ギリシャ語の「盾 (aspís)」です。サカバンバスピスの学名の成り立ち(サカバンバの盾)はかっこいいです。 twitter.com/epinesis/statu…
1463
「現実から目をそらす」は、ドイツ語では「頭を砂に突っ込む (den Kopf in den Sand stecken)」と言います。この豪快な感じ好きです。
1464
1465
また、「英語のsoy sauce(醤油)はsoybeanから作られるからsoy sauceと呼ばれる」のではなく、「soy(醤油)の原料だから大豆がsoybeanと呼ばれる」のです。soyの語源は日本語の「しょうゆ」です。 twitter.com/latina_sama/st…
1466
1467
「ローズマリー」の「ローズ」は「バラ」ではないです。
ローズマリーという名前の元はこの植物のラテン語名rōs marīnus(ロース マリーヌス、意味は「海のしずく」)で、これが縮まってさらに変化して英語でローズマリー(rosemary)と呼ばれるようになりました。
1468
1469
「ノーブレス・オブリージュ」は「位の高い人はその身分にふさわしい振る舞いをしなければいけない」という意味で使われますが、これはフランス語の文"Noblesse oblige."「貴族という身分は、義務を負わせる。」が元です。これだけで文になっているのです。
1470
ビスケットの語源は、ラテン語で「2度焼かれた (bis coctus)」です。
ちなみにパンナコッタ (イタリア語でpanna cotta、文字通りには「火が通ったクリーム」) の"cotta"の部分もラテン語のcoctusが元なので、ビスケットの「ケット」とパンナコッタの「コッタ」は元が同じなのです。
1472
1473
「ウルトラマリン」という顔料の語源は、中世ラテン語ultramarinus「海を越えた」です。
ウルトラマリンの原料であるラピスラズリはヨーロッパの近くではアフガニスタンのあたりでしか産出せず、それが海路でヨーロッパに運ばれたからです。
1474
「クーピーペンシル」の「クー」と、「クーデター (coup d'État, "国家への一撃")」の「クー」は同じです。 craypas.co.jp/products/picku…
1475
英語のdebt「借金」には"b"があるのに、「デット」と"b"を読まない理由はラテン語にあります。
中世の英語では"dette"という綴りでbは入ってないのですが、その後「detteの綴りは語源のラテン語debitum(負債)に近づけるべきだ」という理由でbを入れました。"doubt"「疑う」にbがあるのも同じ理由です。