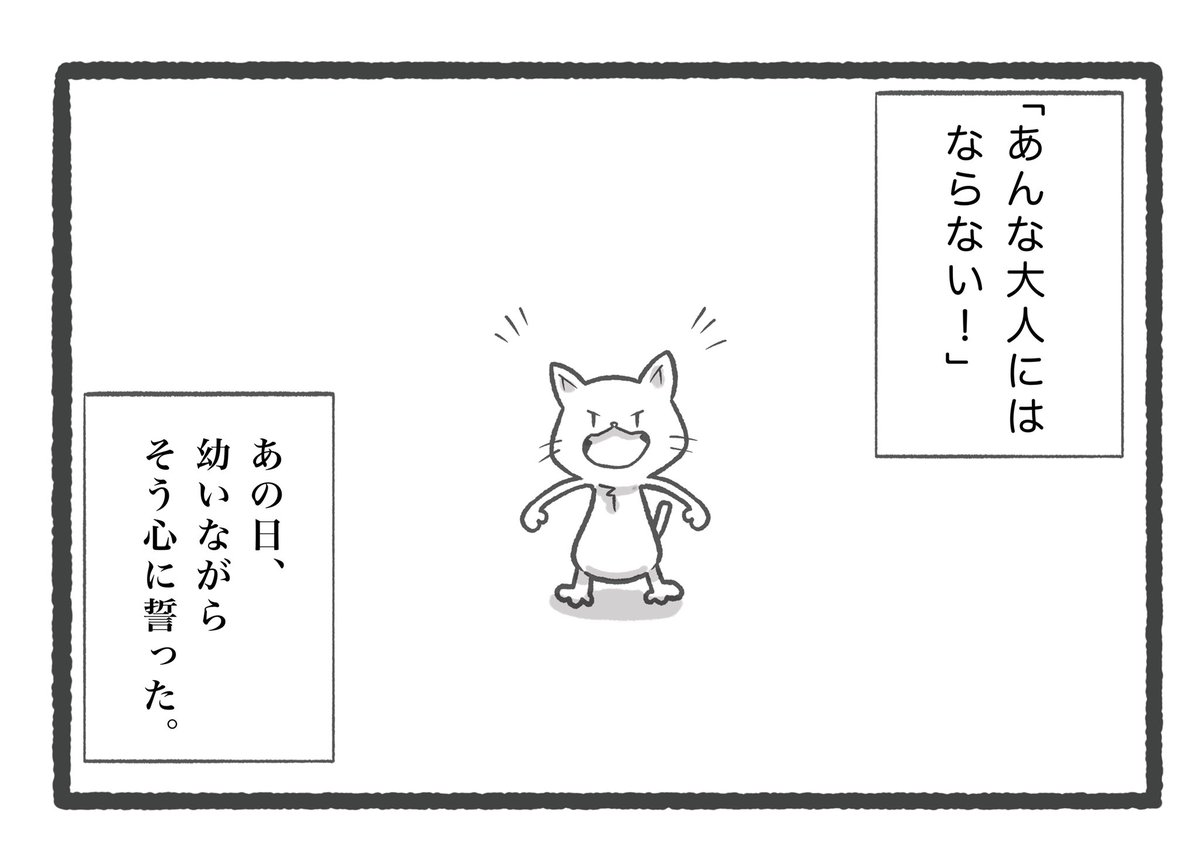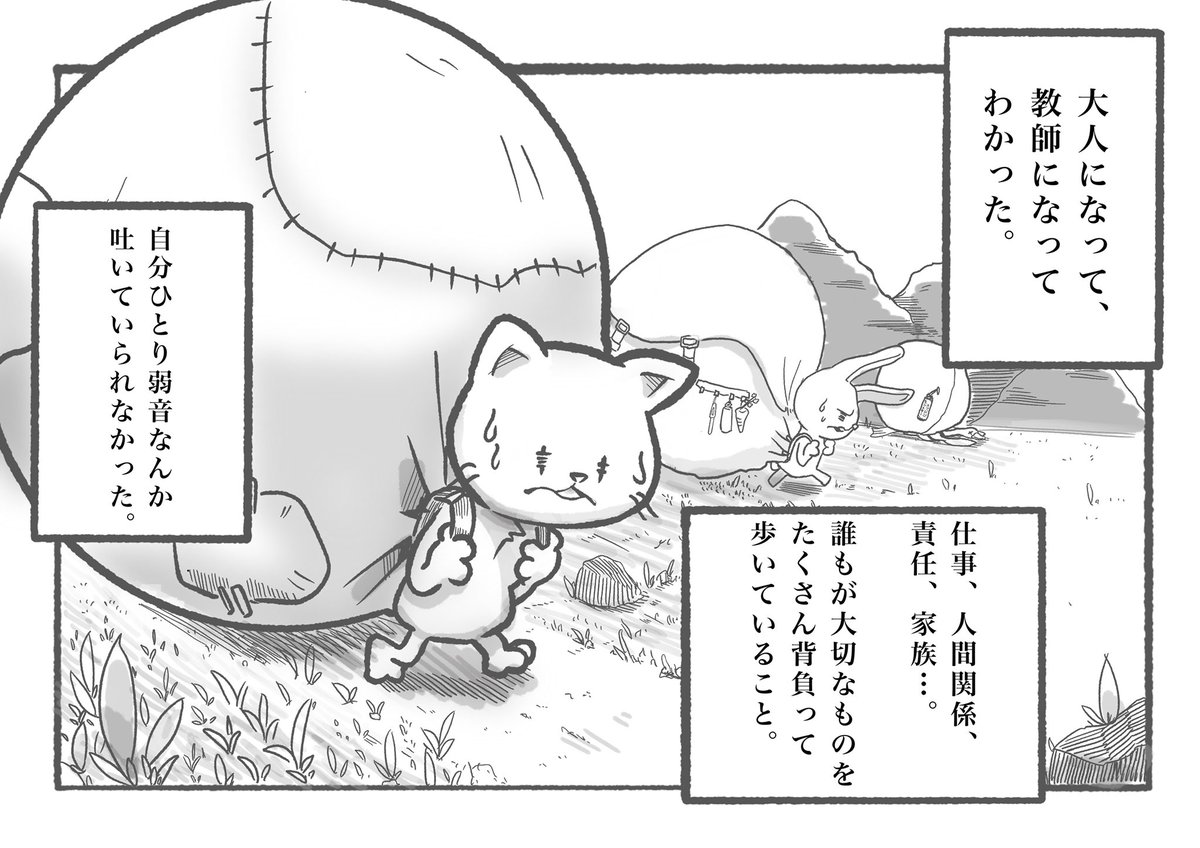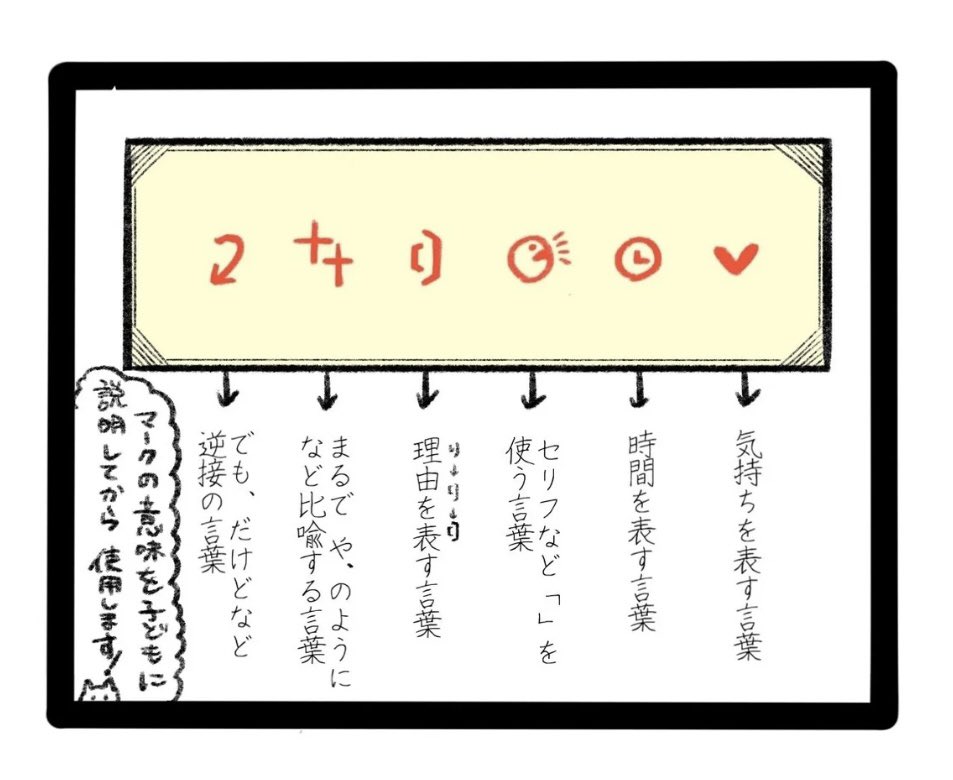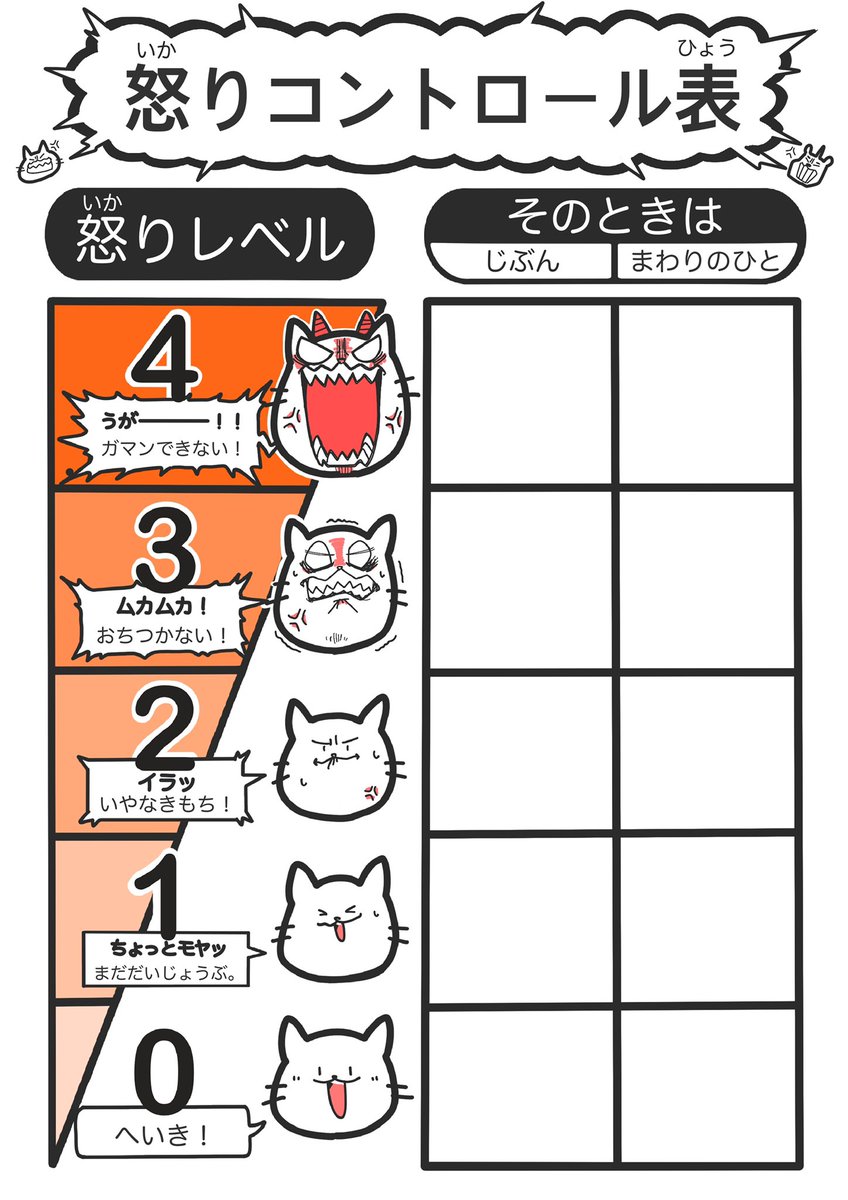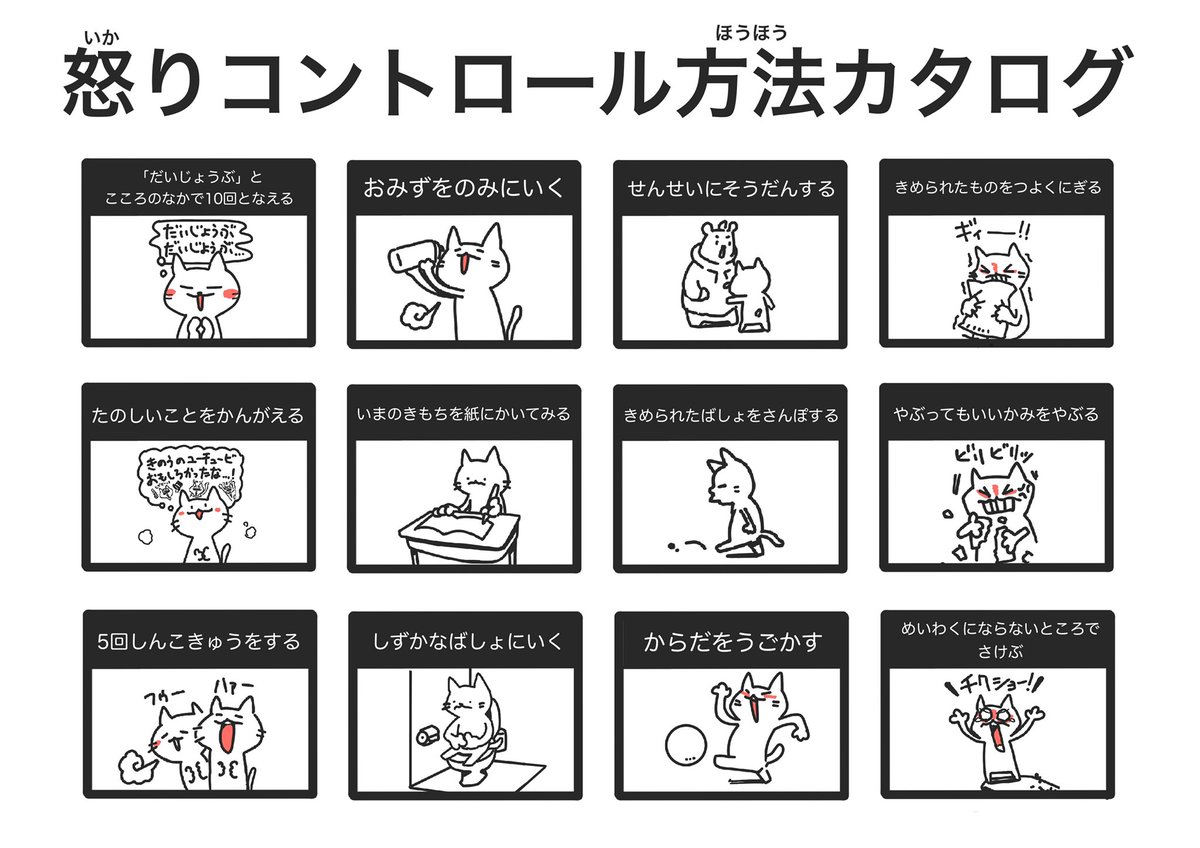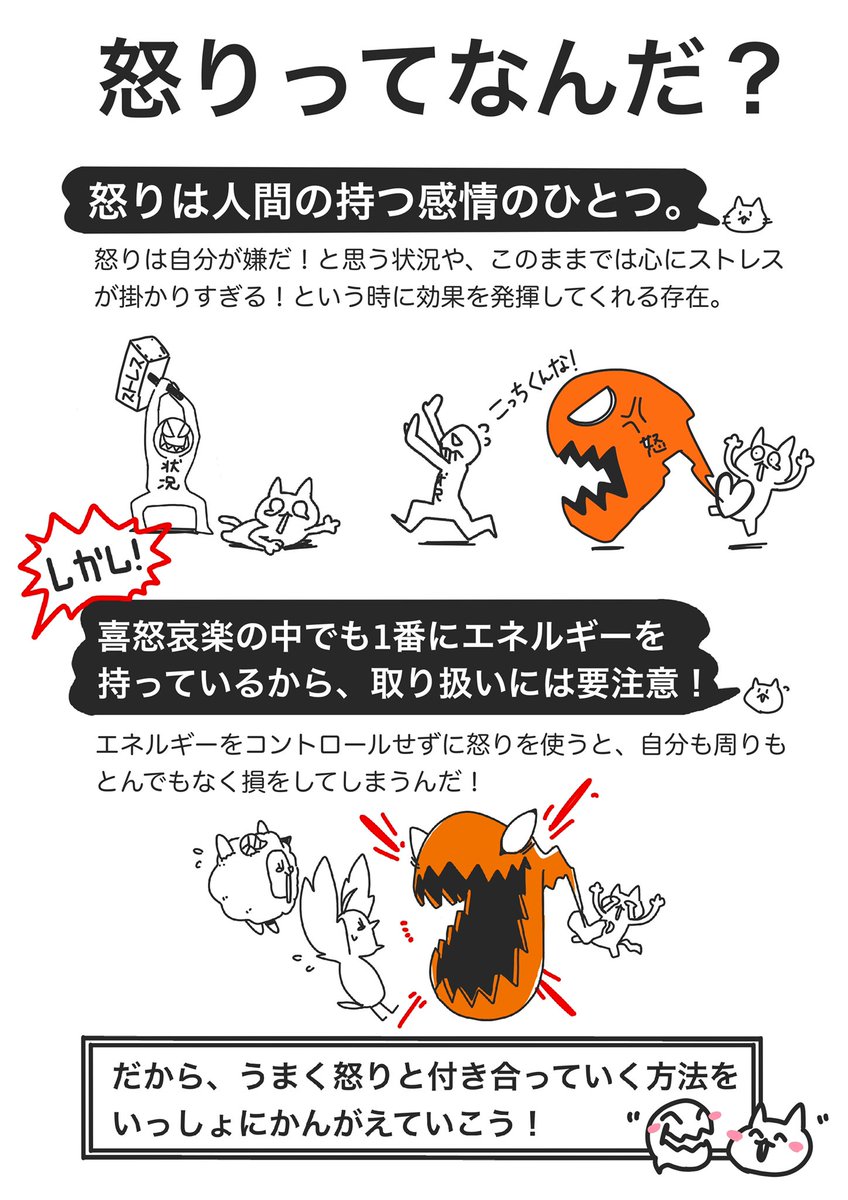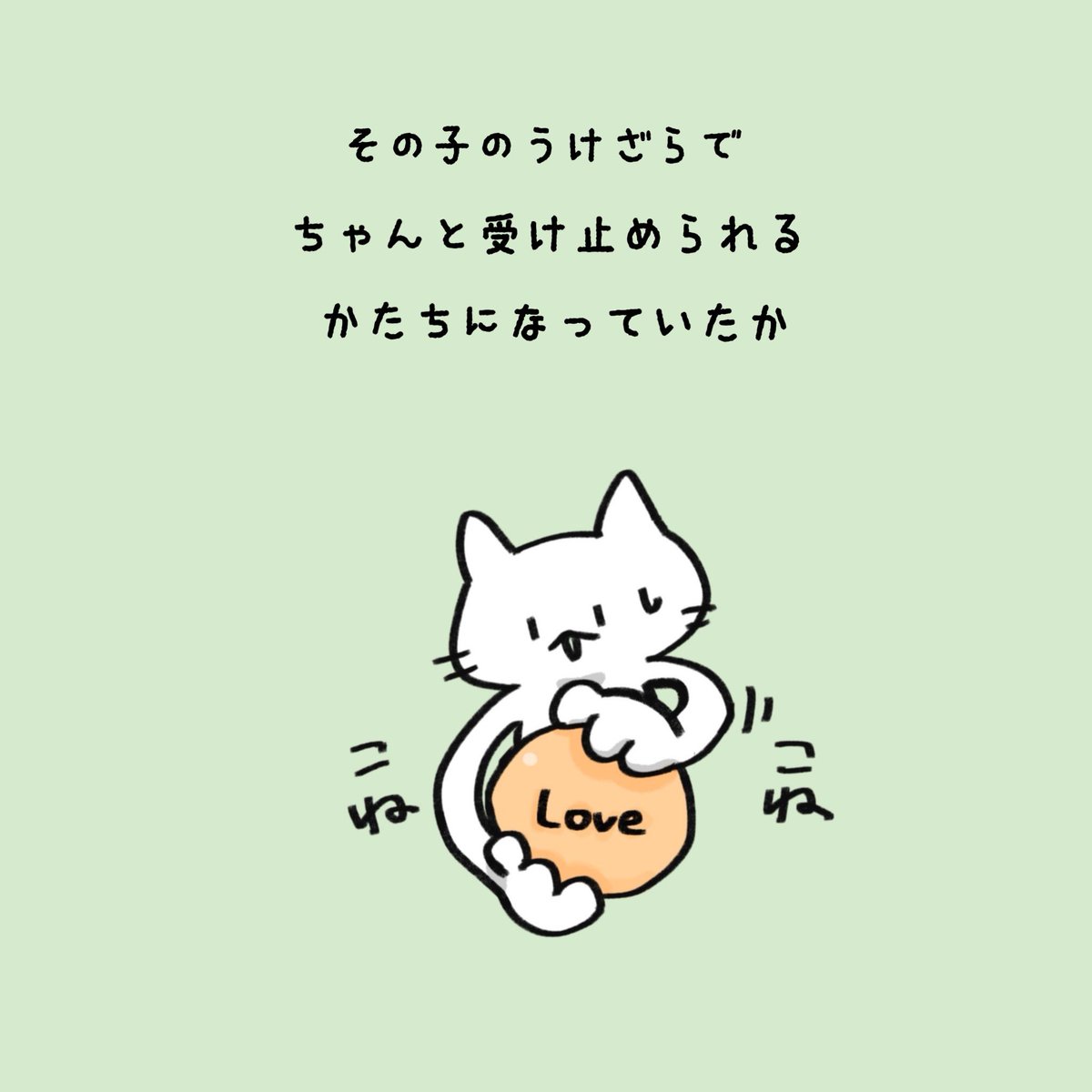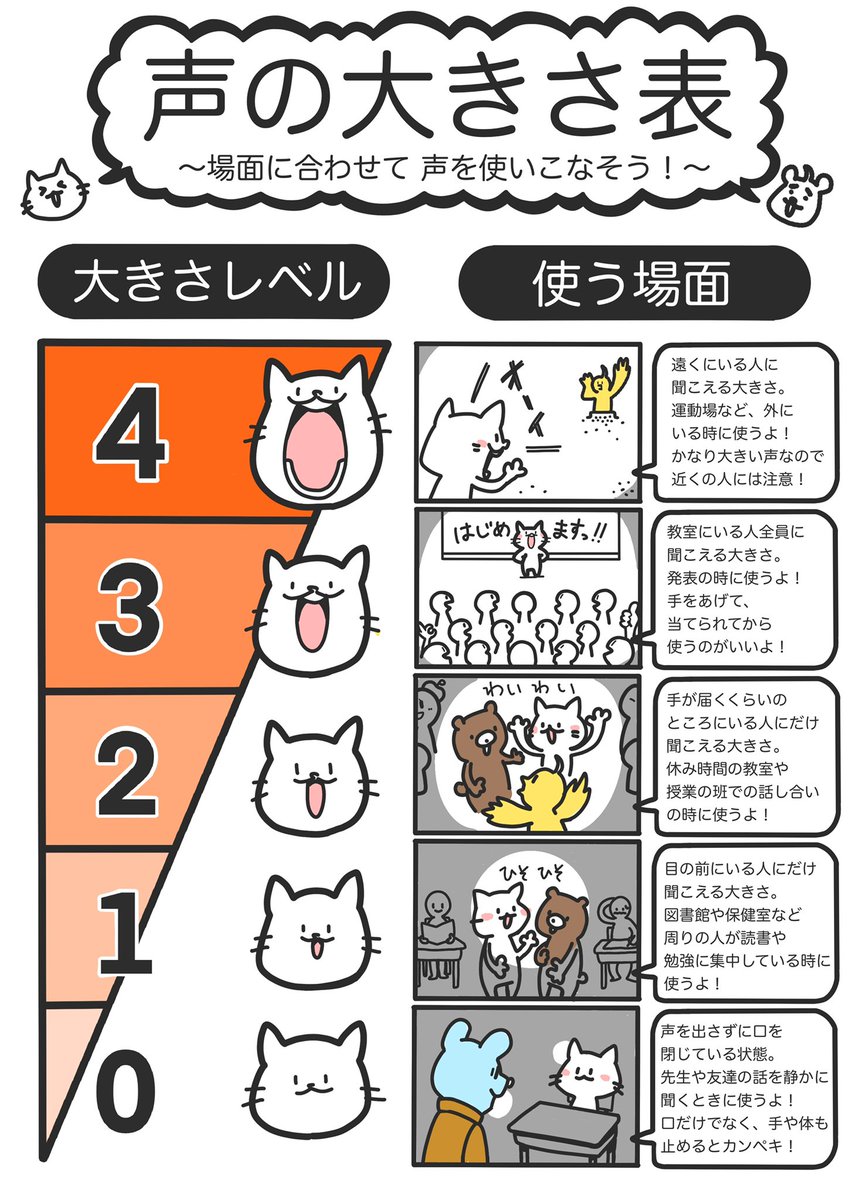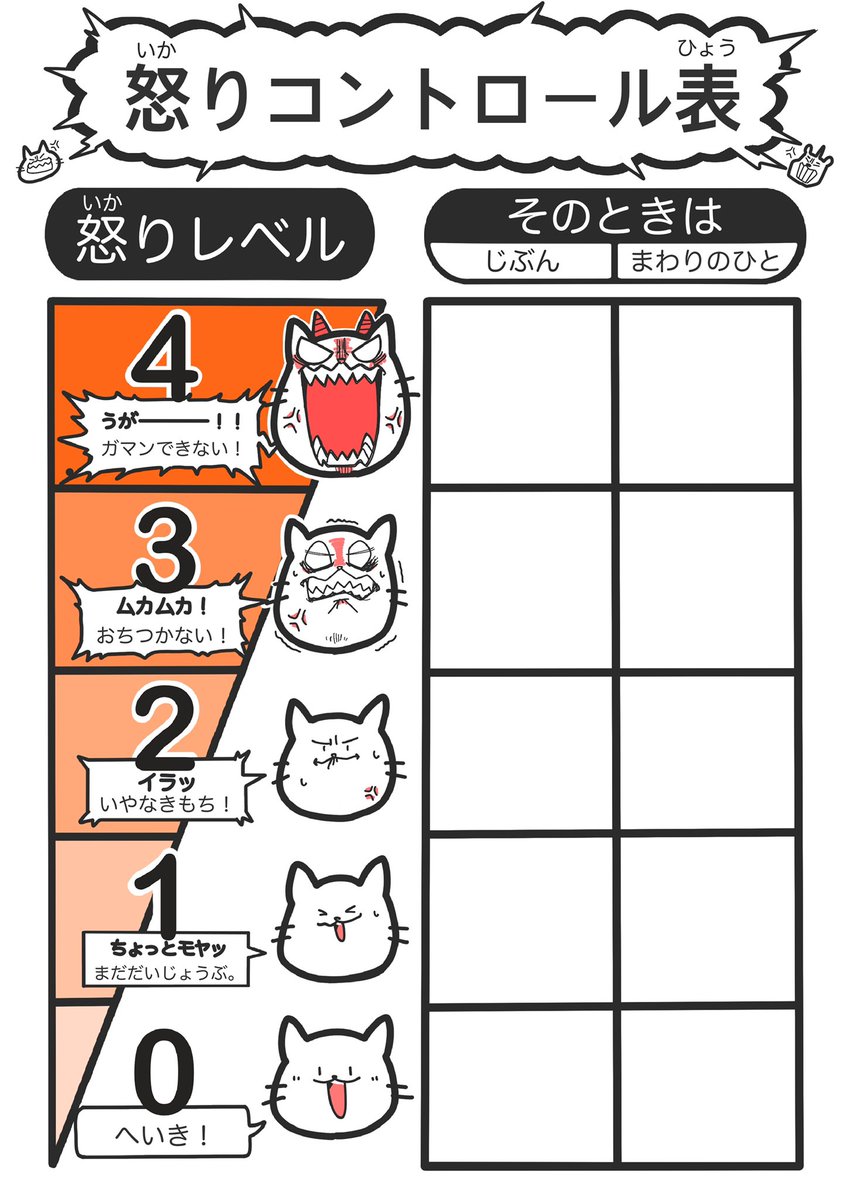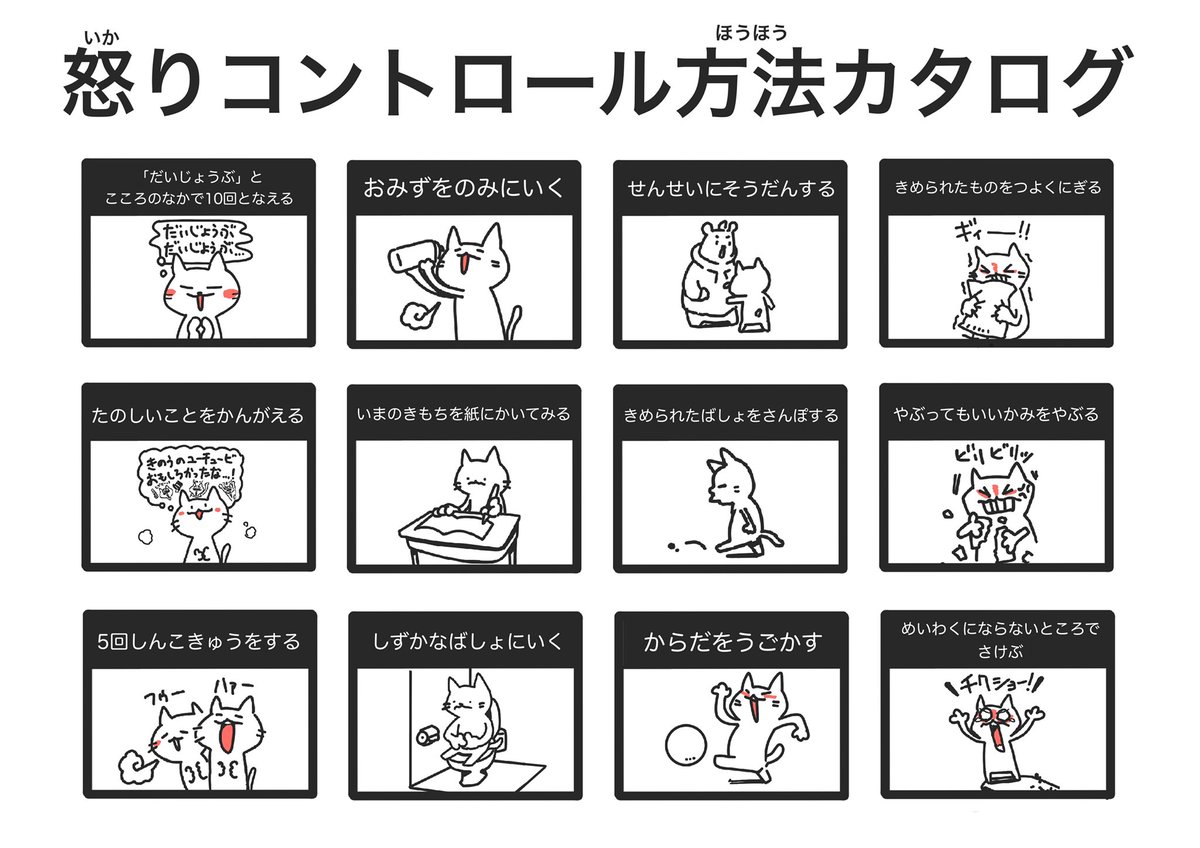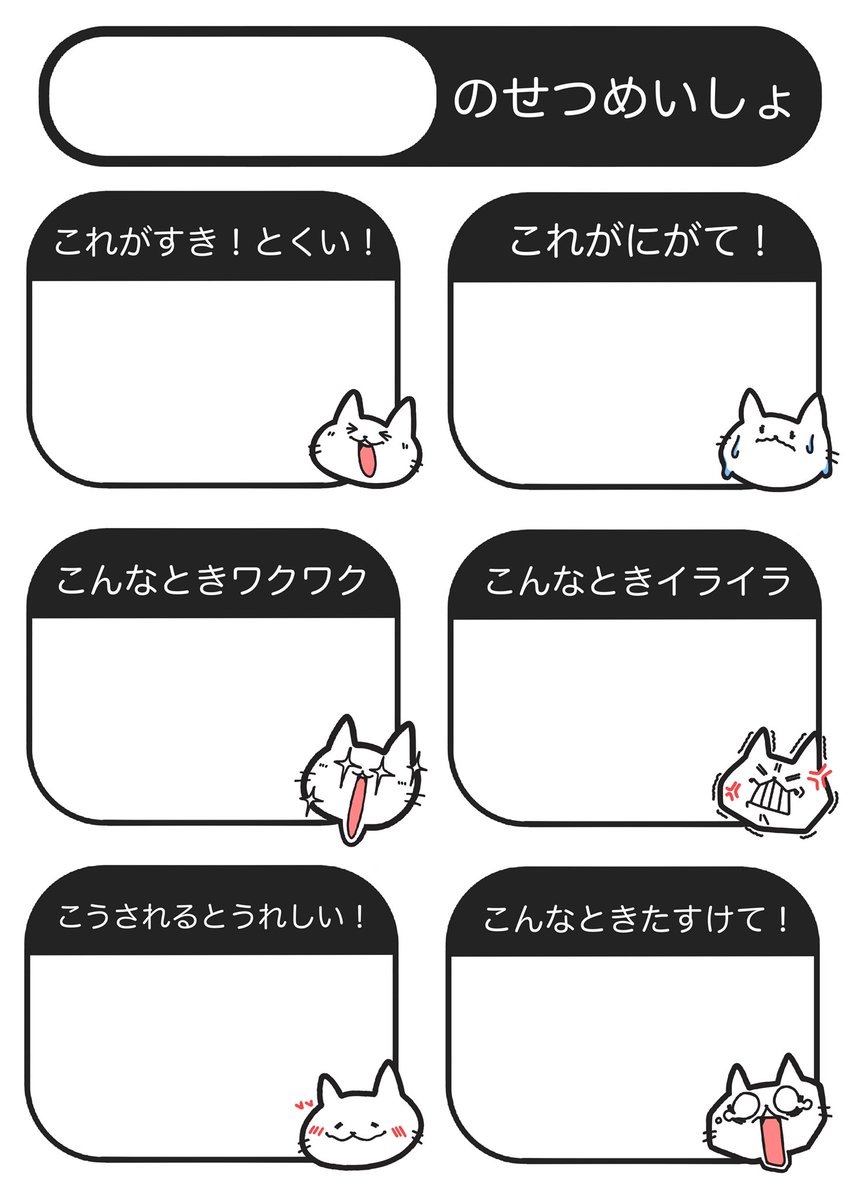26
27
#教師のバトン
誰かに託すには、このバトンは重すぎる。
子どもと教師に、十分に向き合える余白を。
28
国と国の衝突が起きて、学校や色んな場所でその話をする事が増えると思う。
その際に、主語を「あの国が」とすると子どもに「あの国に住む人みんなが」と思わせてしまう可能性がある。
それは子がこの先に見出す平和への妨げにしかならない。
教育者である以上、こんな時こそ言葉に気をつけたい。
32
34
中学の頃の担任の先生の言葉。
「テストで100点を取った時
試合で誰かに勝った時
描いた絵が誰かより評価された時
その結果を使って誰かを見下したり
貶めたりしてはいけない。
誇れる能力は、他者を思いやる心と両輪で
はじめて前へ進んでいく。
心も育てなさい。
大きな力に見合う、広い心を。」
35
中学の頃に言われた担任の言葉。
「腕立て伏せそのものを
試合中に使う人はいないでしょう。
腕立て伏せで鍛えられているものが
何かを探れば、その本質は見えてくる。
今あなたたちが『意味がない』と思う
『勉強』は、その腕立て伏せの本質を
探りきれていないからじゃない?」
本質を考えた日。
37
38
冷えたグラスに熱々のお湯を入れると
割れてしまうように。
心が衰弱して落ち込んでいるひとに、熱々のポジティブを送り続けると、
壊れて元に戻らなくなります。
39
43
46
とある教頭の言葉。
「子どもに黙って掃除させたり、黙ってなにかをさせることを強いる『黙○○』。あれは良くない。子どもは本来喋るし、コントロールできない生き物。それを強いるのは支配で教育じゃない。教えるなら『没頭』です。没頭は集中の境地。言葉が削ぎ落とされ、結果、静寂が生まれる。」
47
48
50