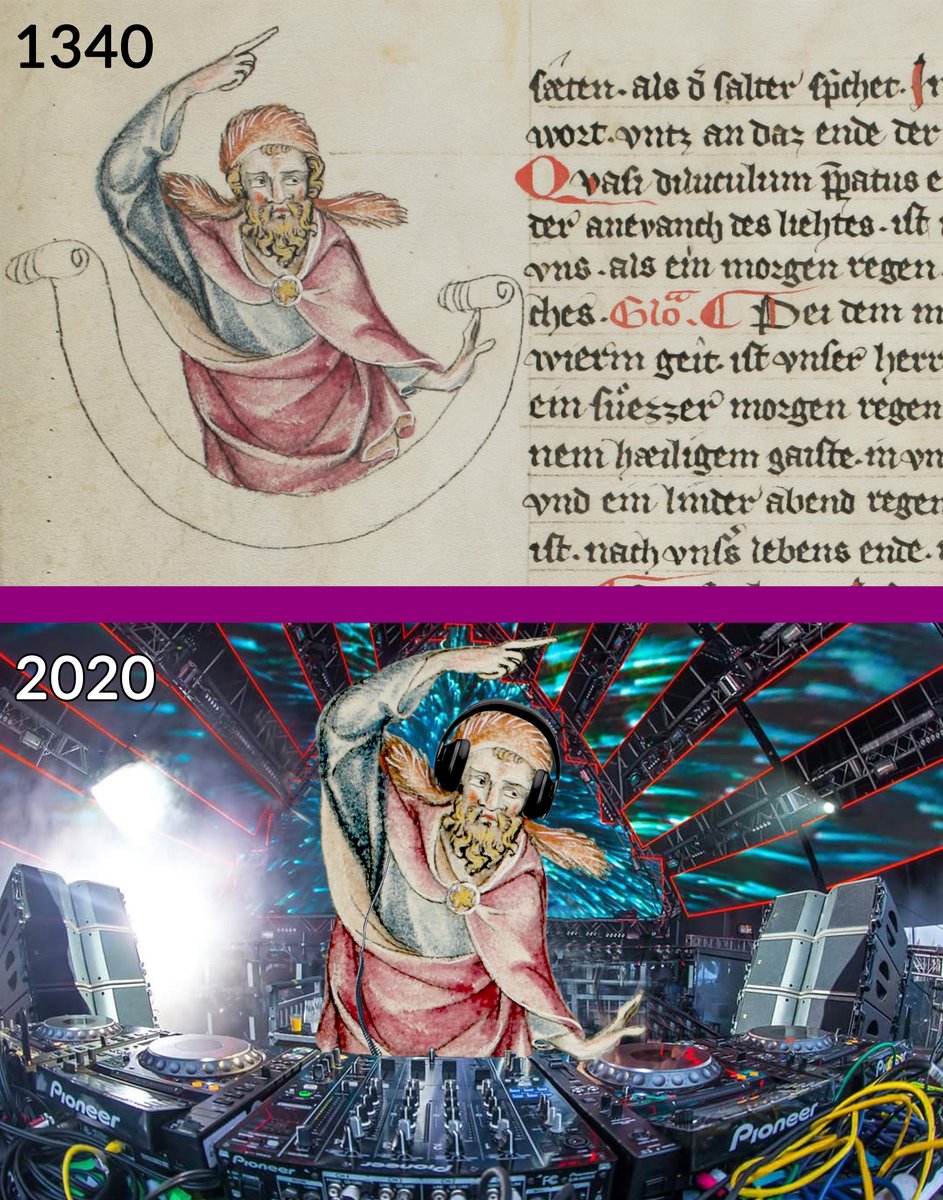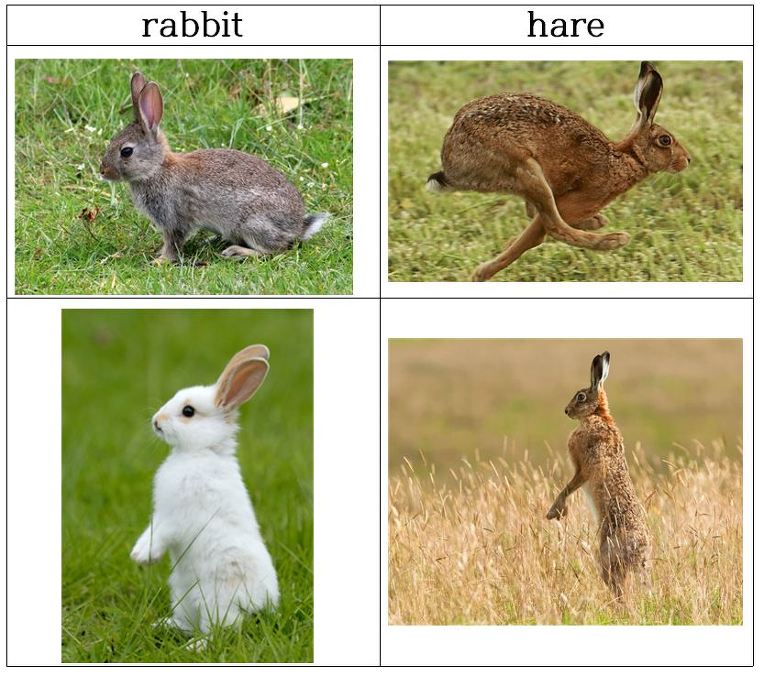126
「大学を職業訓練校に」や「三角関数より金融経済を学べ」という言説に接すると、我が国は抜き差しならないところまで貧しくなってしまったのかと思う。
127
「1人が木の高さを測ればいい。残りの99人は、木の高ささえ知っていればいい」という主張は「選ばれた人間だけが教育を受ければ良い」という意味なのだろうか。「教育を受ける権利」の否定だろうか。
129
130
義経の首は美酒に浸して黒漆塗りの櫃に収められ、鎌倉に送られた。首実検が和田義盛と梶原景時らによって行われたが「見る者皆涙を流した」という。
#鎌倉殿の13人
131
藤原泰衡を討った家人、河田次郎を頼朝は許さず斬罪に処した。頼朝はたとえ敵将であってもその家人が主殺しをすることを許さなかった。これは、父義朝が家人長田忠致に騙し討ちにされた記憶があったためだともされる。
#鎌倉殿の13人
132
オン バザラ アラタンノウ オンタラク ソワカ
虚空蔵菩薩の真言。知恵を司る菩薩であり、真言を繰り返し唱えることであらゆる経典を記憶し理解できるとされる。
#鎌倉殿の13人
133
大姫、インターネット創世記ならハンドルネームに「†」を付けそう。
#鎌倉殿の13人
134
伊東の八重姫について残る伝説
・頼朝との間に千鶴丸を生む
・千鶴丸は父祐親に殺害され、八重姫は入水して果てる
・八重姫は北条義時と結ばれ、泰時を生む
全てを回収して去っていく八重。切ないがお見事でした。
#鎌倉殿の13人
136
スピリチュアル界隈では、以前から縄文時代を称揚し弥生時代以降を人工的で邪悪な時代と見なす風潮が存在しているように思う。仕事の合間にポツポツ考えてみたい。
137
縄文時代の理想化には、「争いのない社会」や「環境に優しい狩猟採集社会」という上部だけ見た憧憬、現代資本主義や私有財産制、都市文明に対する反発があるのだろう。原始共産主義への無邪気な憧憬であり、また過去を善、現代を悪と捉える単純な二元論にも思える。
138
さらに縄文理想論を深掘りしていくと「世界文明は日本の縄文文化が原点である」や「縄文人は渡来した弥生人に駆逐された」「カタカムナと呼ばれる超古代文明が存在した」と、一気にオカルトの要素が強くなる。過去の安易な理想化は、容易に民族主義や陰謀論に付け込まれやすい。
139
「平和」や「地球環境」など、現代人に響くワードで安易な過去への憧憬、称揚に飛びつくのはリスクが高い。またそれらの安易な言説は往々にして古ぼけた説が根拠となっているケースもあるため、時々は歴史に興味を持ち折に触れては調べてみる態度も必要ではないだろうか。
140
先日の「一億総株主」で、20世紀末アルバニアのネズミ講による経済破綻を連想した人はそれなりにいると思う。
142
今の小学生はとても賢明だと思う。自分が小学生だった頃は、帰り道に皆でじゃんけんして負けた人間に全員のランドセルを背負わせることしか考えていなかった。
143
先日逮捕された神奈川の43歳暴走族リーダーがメンバーから毎月3000円の「会費」を取り立てていた件は、どう考えてもリーダーの総取りではなく「ケツ持ち」の組織への上納金に充てられていたのだろうと思う。全国ネットで報道されたということで、金の流れについても徹底的に追求されるのではないか。
144
昭和の時代から不良漫画や暴走族漫画は一定の人気があるものの、それは描かれているのが徹頭徹尾「あり得ない」ファンタジーだからだろうと思う。現実の不良は金と暴力、本能しかない世界。
145
安達盛長の嫡子、弥九郎。後の安達景盛。北条泰時の盟友であり、北条氏と緊密な関係を築く人物である。
#鎌倉殿の13人
146
「リンクを踏む前にドメインのチェック」は古来よりのインターネットしぐさである。
ホテルを予約しようとGoogleで「楽天トラベル」と検索して一番上のリンクをクリックしたら明らかに偽サイトだった togetter.com/li/1899504 #Togetter
147