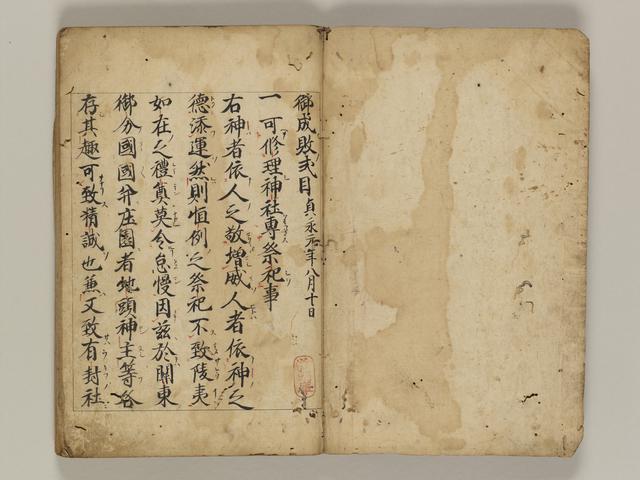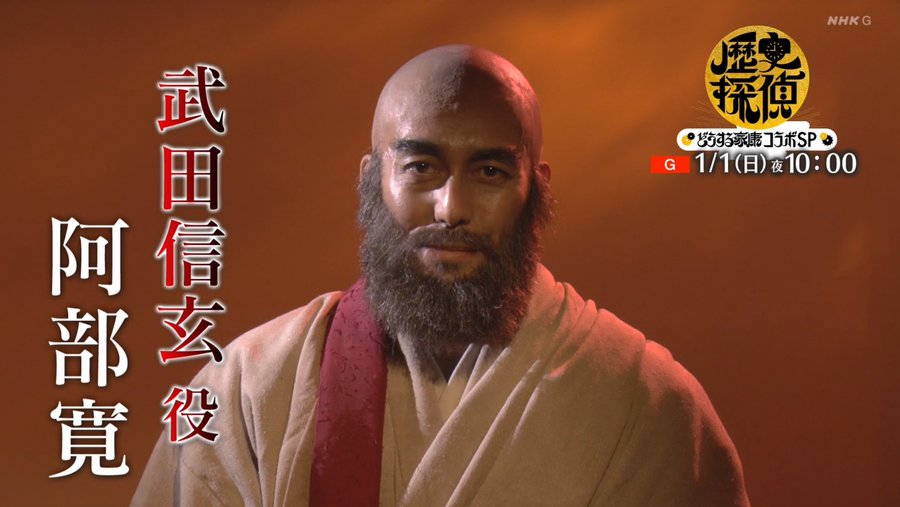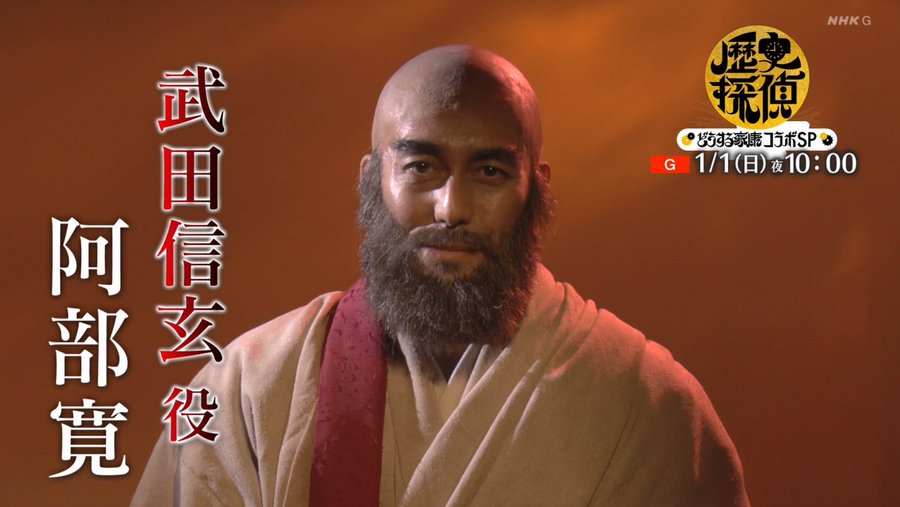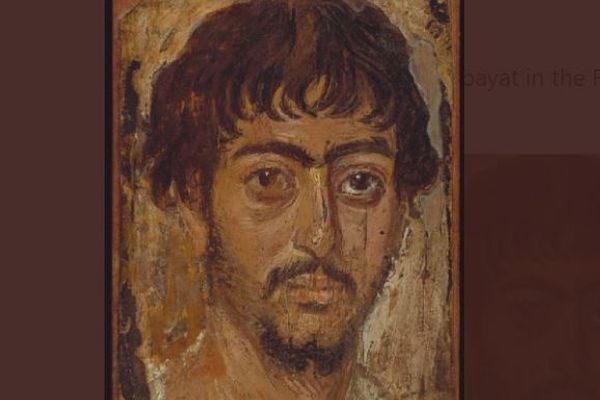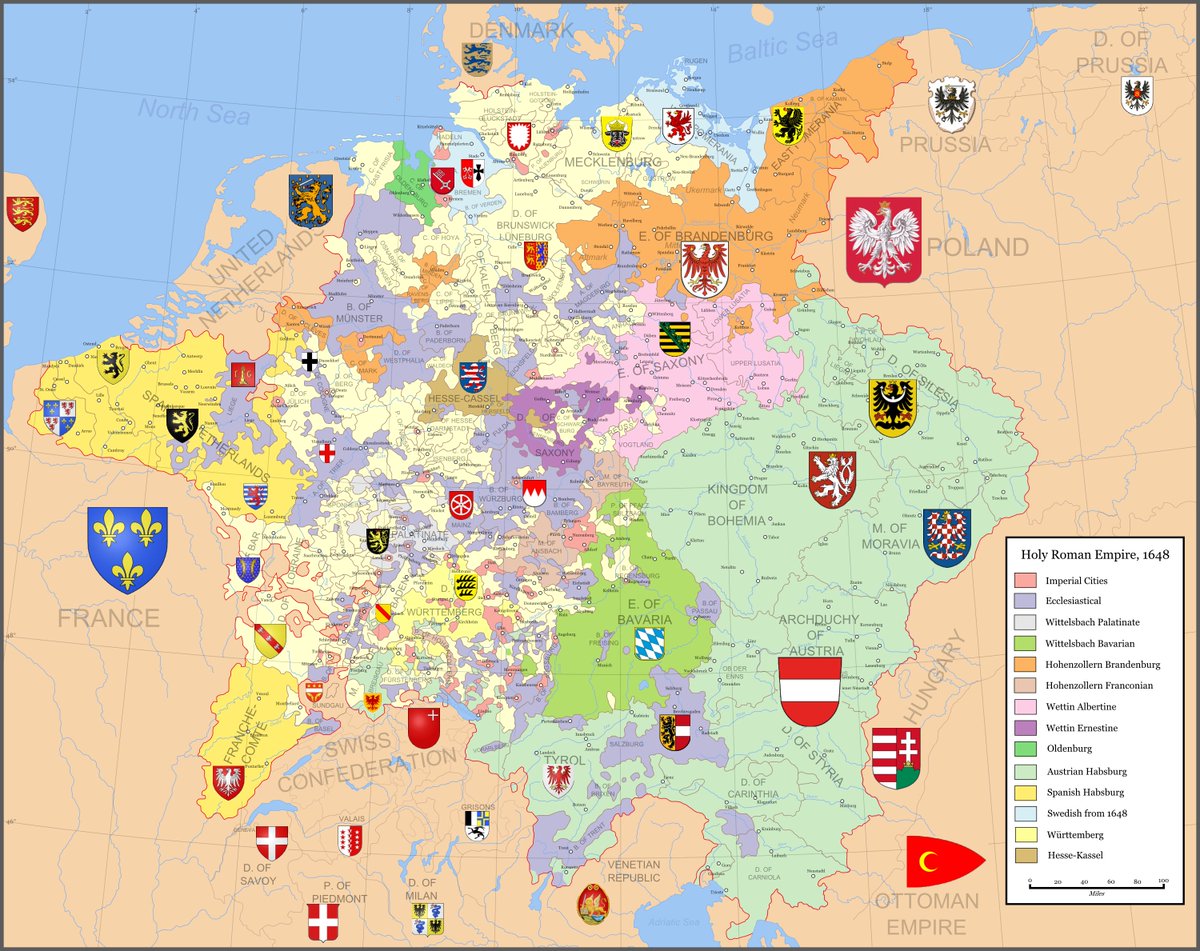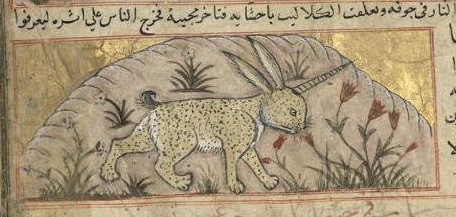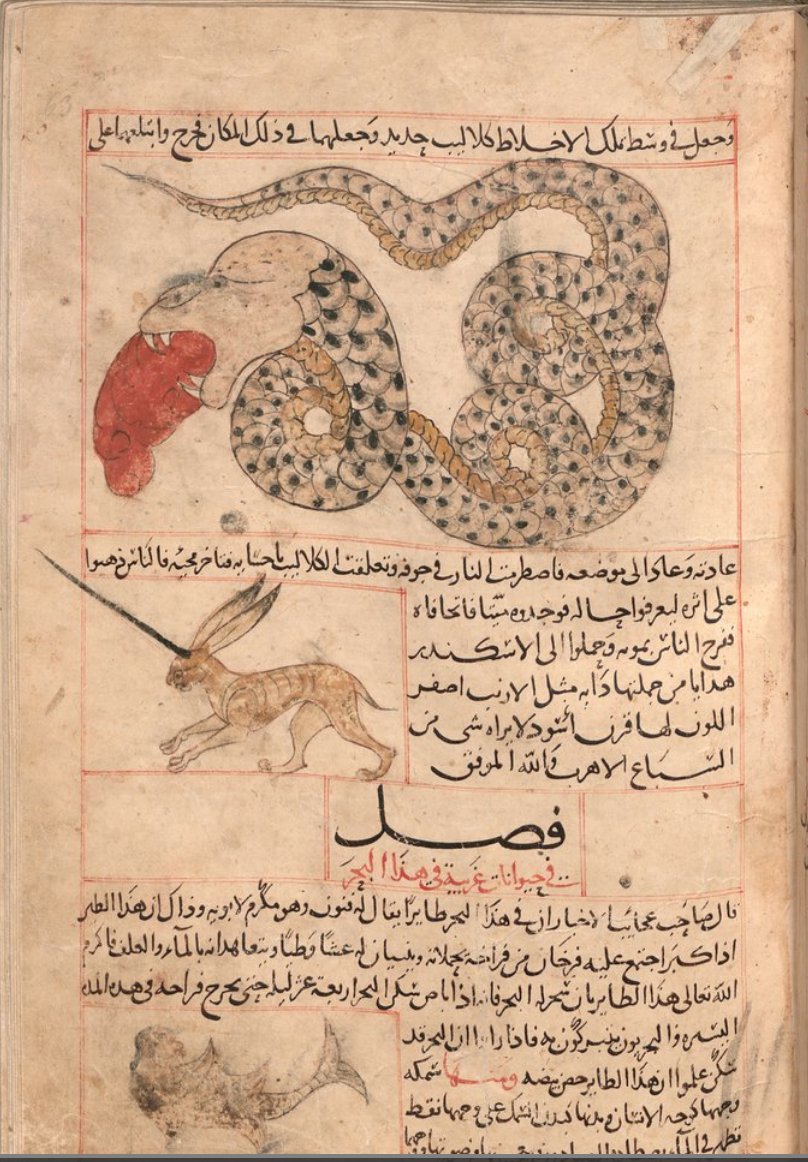276
277
御成敗式目は鎌倉幕府滅亡後も有効な武家法であり続け、室町幕府の各種法令や戦国大名の分国法も御成敗式目に準じた内容であった。なお御成敗式目は女性が御家人になることを認める項目が存在し、戦国時代の女領主はこれを根拠としている。
278
のえ(伊賀の方)毒殺説を採りつつ、背後に三浦義村の存在を匂わせる鬼脚本。
#鎌倉殿の13人
279
先ほど「平六は今回脱がなかったが心の褌を脱いだ」というリプライをいただいたが、その通りのシーン。
#鎌倉殿の13人
280
なお泰時の死後は
#鎌倉殿の13人
281
「粛清したのは全部で13人」
「ちょっと待って何で頼家が」
#鎌倉殿の13人
282
「この世の怒りと呪いを全て引き受け、私が地獄に持っていく。太郎のためです」
真に私心のない男の、だからこそ業の深い言葉。
#鎌倉殿の13人
283
「寂しい思いはさせません」
義時が没した翌年、政子と大江広元も相次いで没している。
#鎌倉殿の13人
284
ここで義時が胸を押さえる仕草、脚気衝心の症状にも見えて史実とも整合性が繋がる。
#鎌倉殿の13人
285
286
ツイートにインプレッション数が表示されるようになった。これは古の風習「キリ番ゲット」を復活させるときではないか。踏み逃げ禁止、リプライにカキコしていってね!
287
昨今の「○○は社会に出て何の役にも立たない」論は、実学主義というよりはただの反教養主義のようにも思える。
288
289
292
293
294
295
296
298
299
自分は「ごんぎつね」を見ると悲しくなってしまうので、同じ新美南吉作品では「このお手々にちょうどいい手袋下さい」の「手袋を買いに」が好きです。
300