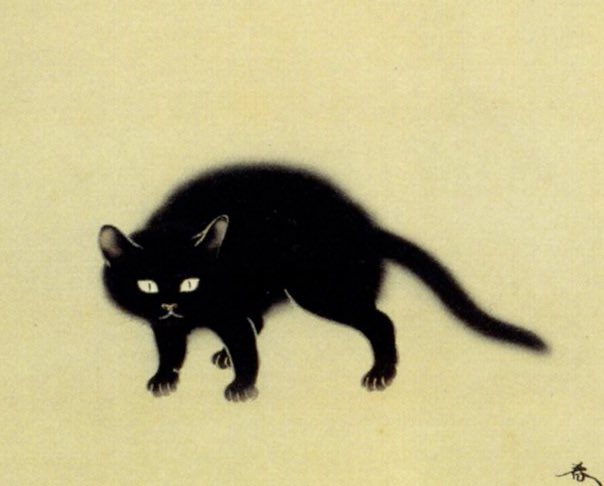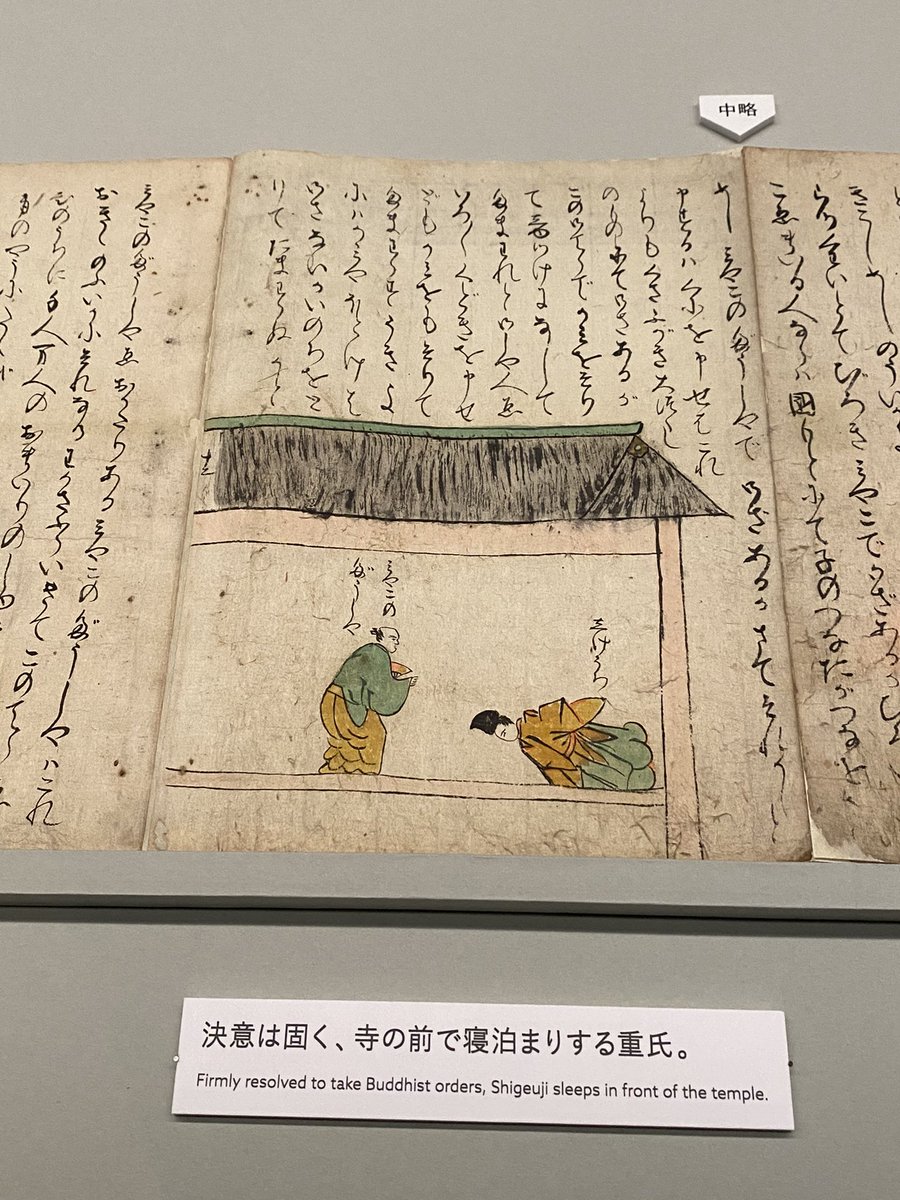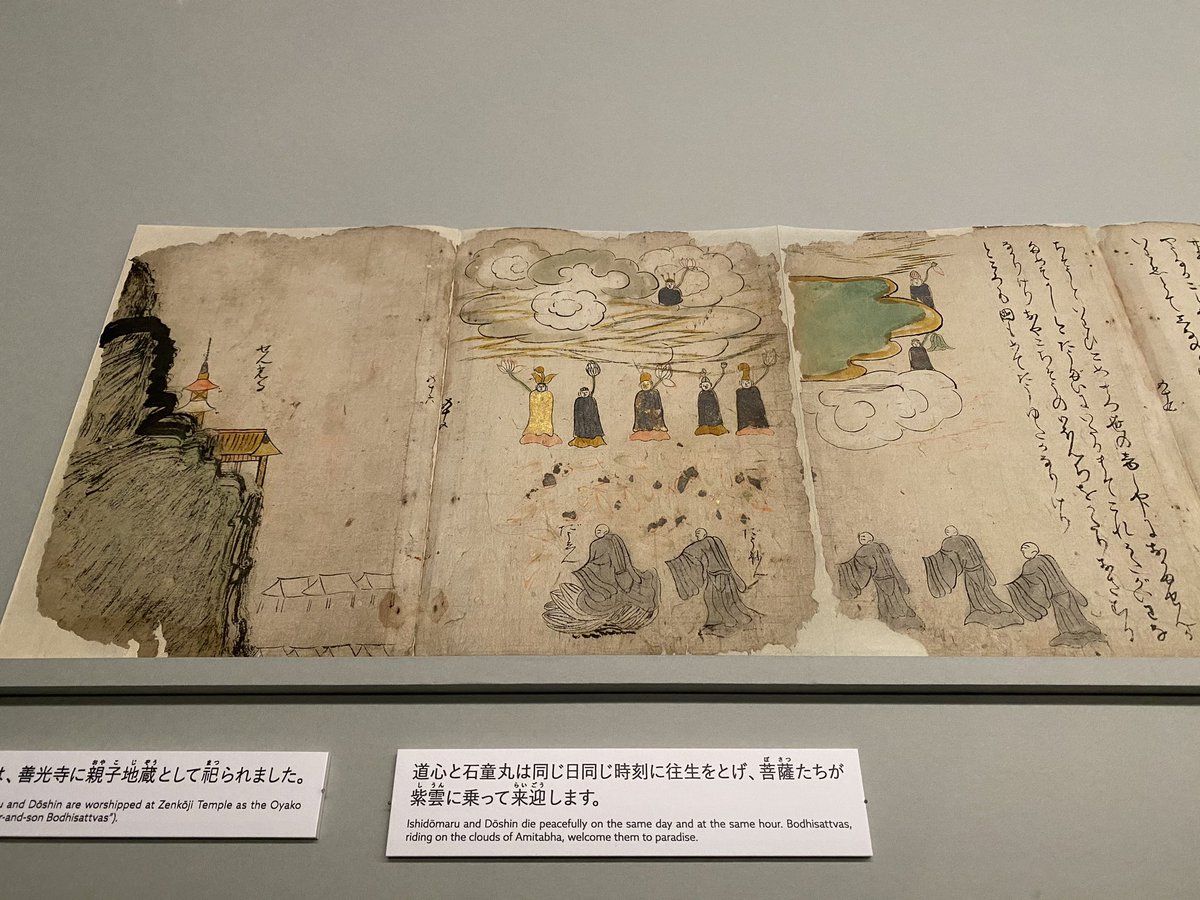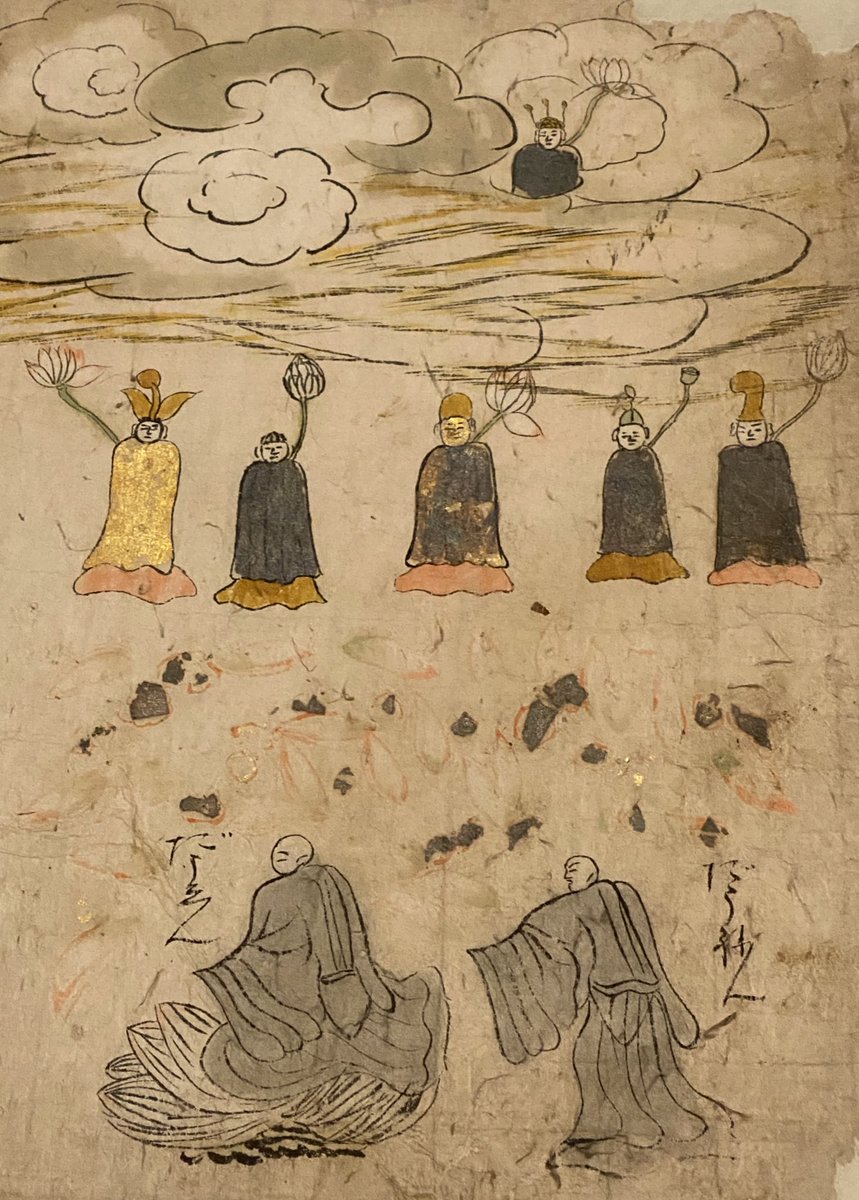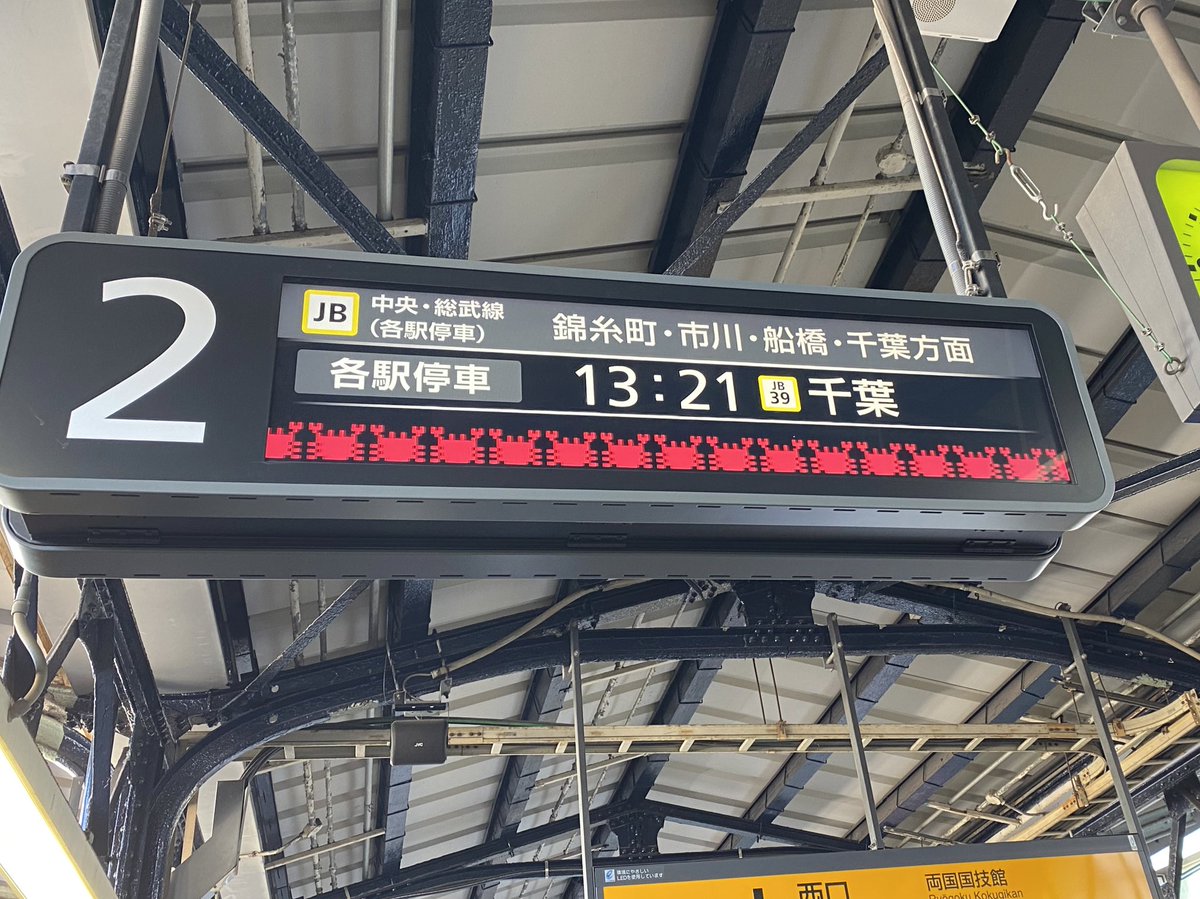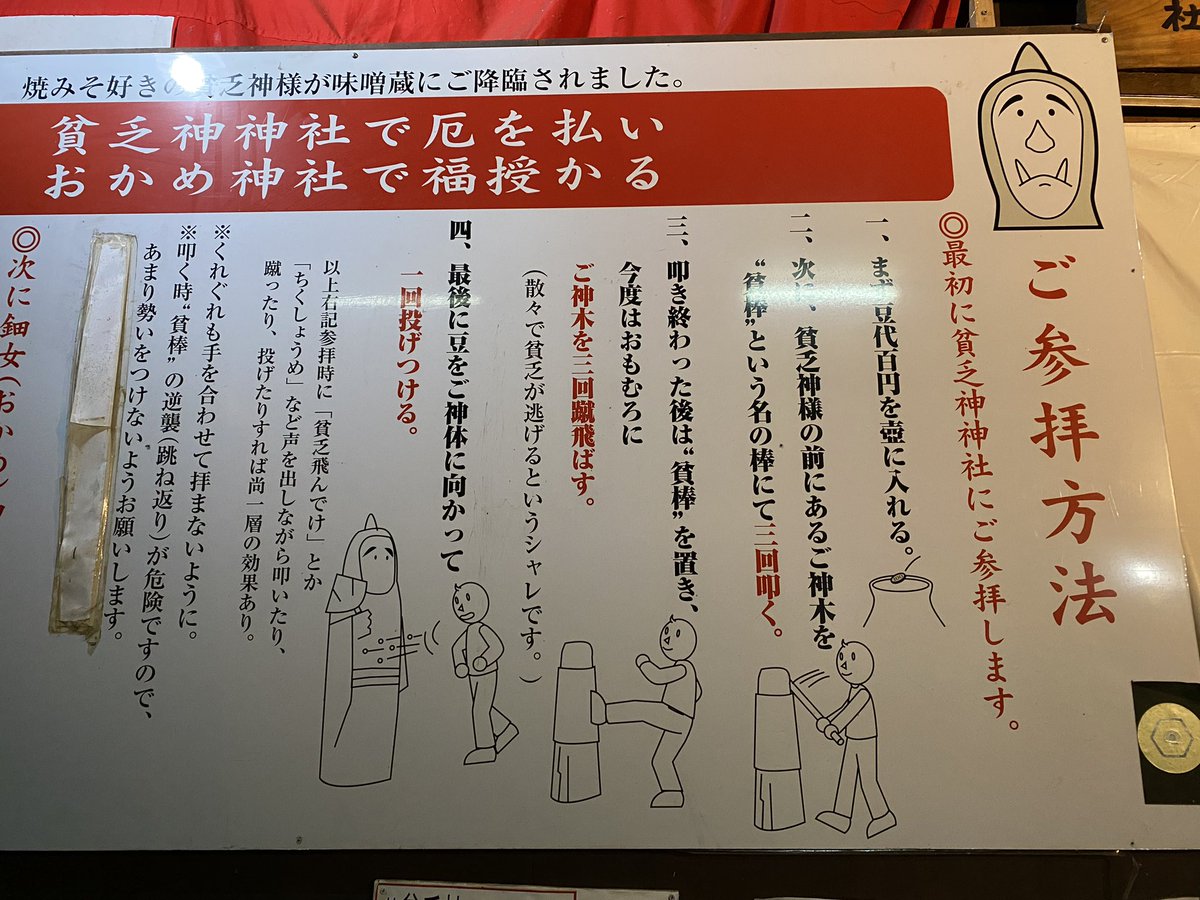26
平知盛が碇を担いでとか、二領の鎧を重ね着して入水したというのは、理にかなったことだとわかる。
「見るべきほどのことは見つ」と言い放ったあと、波間にプカプカ浮いてたらサマにならないもんね。
27
津軽にはカミサマと呼ばれる民間の巫者がいる。以前にもツイートしたので前からのフォロワーさんはご存知かもだが、うちの母方の大伯母は「カミサマ」だった。
イタコと違い、普段はごく普通の農家のオバサンで人に頼まれると祈祷などを行っていたという。
32
どうして奈良の鹿は、そこに鹿せんべいがあるとわかっていながら、せんべい屋を襲撃しないのだろうか?
33
いわゆる「憑きもの」に関する本を読んでるんだけど、憑きもの筋の家に女児が生まれるごとに75匹ずつ増えるなど、「75」という数が頻繁に出てくる。
そういえば他でも「75」という数に覚えがあるなぁと考えたら、かつて諏訪大社の御頭祭で献じられた鹿の頭も75頭なんだよな
37
書名は忘れてしまったが、「源義経」の演出だった吉田直哉氏の著書にあり、とても印象に残っているエピソード。
39
大河ドラマ「源義経」は総集編が保存されていて、この女官たちの入水シーンも映像が残っている。水の中、ゆらゆらと衣をなびかせ漂うように沈んでいく姿は美しく幻想的でした。
43
46
地理地学への知見を拓く良番組だったのになあ。スピ入ってきて、いっきにガッカリ感が。
ああいうレイラインとか見ると、前に話題になった名古屋のコメダ珈琲六芒星を思い出しちゃうんだけどなw
#ブラタモリ
48
RT 江戸時代、菅江真澄の記録だったが、木曽の御嶽山近くの村で、子供が疱瘡にかかると山に捨てに行く。すると乞食たちが集まってきてその子供を看病し、治ったら家に連れて行き家族から謝礼をもらう風習があったという。
50
先日の鎌倉殿での頼家暗殺のシーン、大河ドラマ「太平記」の妖霊星を思い出した。
で、もってついつい「太平記」見直してるんだが、このシーン、何度見てもすごい。真田広之もすごいが、馬が賢すぎて、すごい(語彙力)