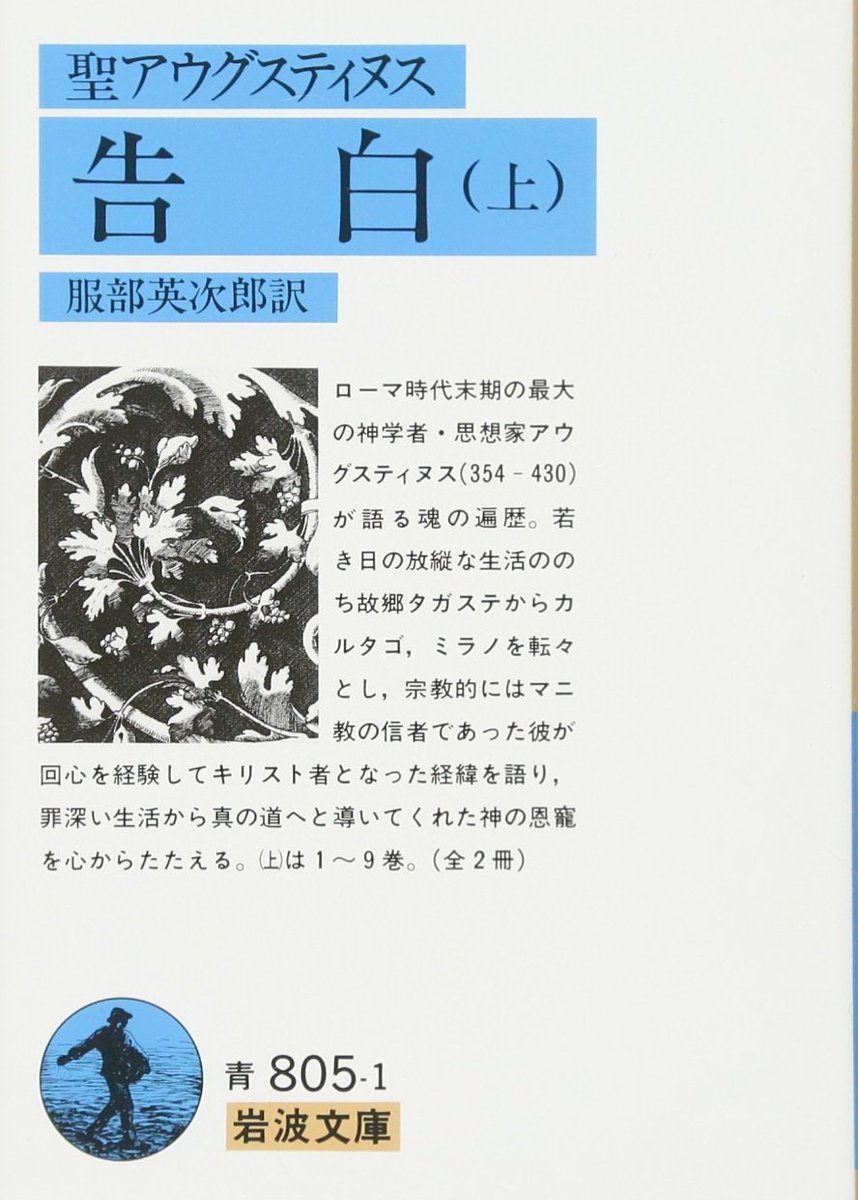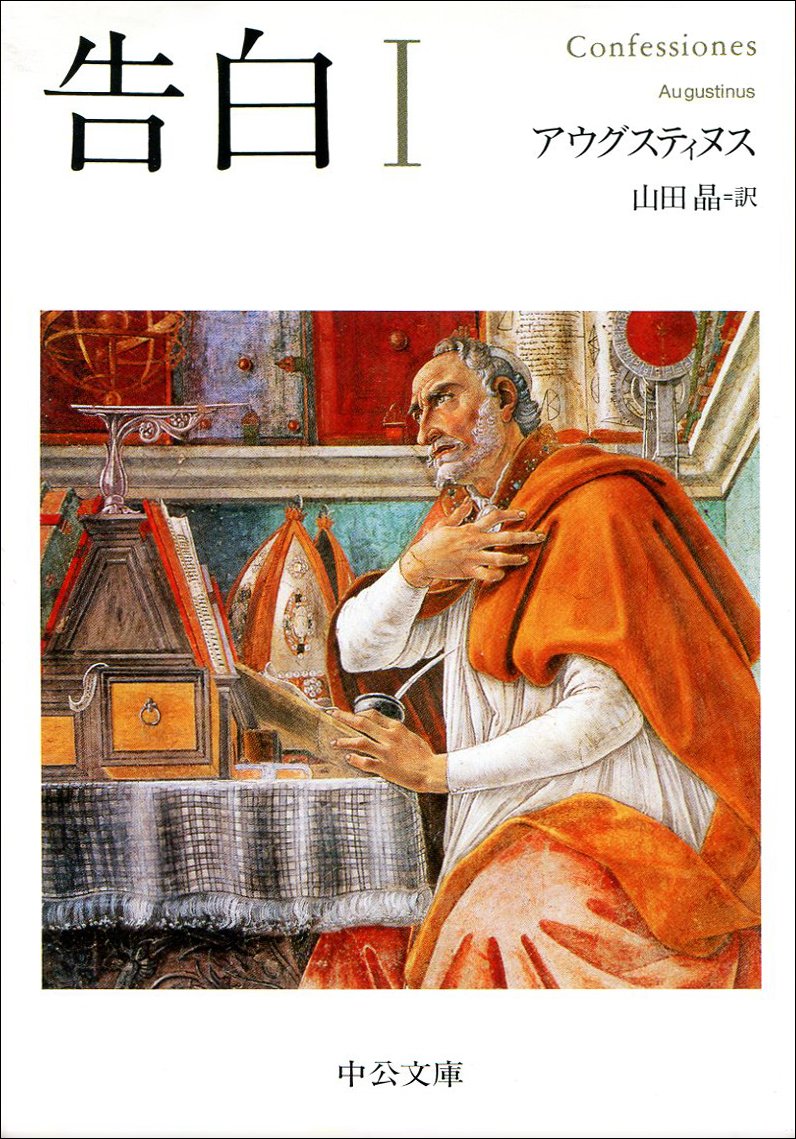26
イエスは「宗教」を語らない。彼が語るのは「神」のことだ。そしてイエスは「神」についての手垢のついた「概念」を語りはしない。彼が語るのは、そうした「概念」の手前にあり向う側にある、むき出しのままの「神」のリアリティーだ。聖書を読むとは、そうした神のリアリティーに触れることだ。
27
『世界は善に満ちている: トマス・アクィナス哲学講義』を一月に刊行します。「哲学者」と「学生」の対話形式で、トマス哲学の本質を解き明かします。これまでに刊行したトマス入門書の手前から、より平易に話を始めつつ、一歩先のより本格的なところまで話を展開しています。amazon.co.jp/gp/product/410…
28
拙著『世界は善に満ちている:トマス・アクィナス哲学講義』(新潮選書)の「まえがき」全文が、ネット上で読めるようになりました。一冊の書物との出会いが与えてくれる「ほんの少しの変化」が人生全体において持ちうる大きな意味について述べています。
kangaeruhito.jp/trial/43956
29
明日から来日する教皇フランシスコの思想について、クーリエ・ジャポンから受けたインタビューが公開されました。明日から始まる一連の出来事を理解するための補助線としてお読みください。日本語では他にあまりない、教皇の思想についての本格的な紹介になっています。
bit.ly/2O7rBQ2
30
一冊の書物を繰り返し徹底的に読み込むことによって、百冊・千冊の書物を眺めるよりも多くの洞察を得ることができるということは一面の真実だが、一冊の書物を真に徹底的に読み込むことができる為には、その書物だけではなく、百冊・千冊の他の書物にも目を通さなければならないということもまた真実だ
31
『トマス・アクィナス 理性と神秘』(岩波新書)が、サントリー学芸賞(思想・歴史部門)を受賞しました。「善は自らを伝達する」を根本思想としているトマスの思想がより多くの方々に伝達される機会となれば幸いです。
読んでくださる皆様に支えられつつこれからも活発に書いていきたいと思います。
32
創文社の解散が間近に迫った今、ぜひ見て頂きたい動画がある。1960年から2012年まで、半世紀をかけて完成したトマス・アクィナスの『神学大全』の日本語訳の歩みについての実に貴重な映像が満載で、一冊の書物の翻訳に生涯を捧げた人々の情熱が実にしみじみと伝わってくる。
bit.ly/2tE455z
33
「締切が原稿を完成させる」とよく言われるが、実は、似たことは「読む」ことにもあてはまる。読まなければならない期限が決まっていると、自ずと読みにメリハリと集中力が出てくるし、結びつけて読むべき他の本なども念頭に浮かんできて、漫然と読んでいるよりも遥かに深い「読み」につながりやすい。
34
5月の100分de名著のテキスト『アリストテレス『ニコマコス倫理学』』は本日発売です。現代でも現役の古典中の古典を、できる限り分かり易く解読していますので、手に取って頂けますと幸いです。『ニコマコス倫理学』は、一生を通じて出会いを深め続けていく事のできる書物ですamzn.to/37A9m2t
35
キリスト教の入門書として、群を抜いて優れているのは、『ナルニア国物語』の作者C.S.ルイスによる『キリスト教の精髄』です。9月29日(土)の13時から開講の「キリスト教入門 基礎の基礎」の一回目は、『キリスト教の精髄』を手がかりに、極めて基本的なところからキリスト教の本質に迫っていきます twitter.com/201yos1/status…
36
バイデン大統領は、就任演説で、アウグスティヌスの言葉を引用しました。「私が属する教会の聖人である聖アウグスティヌスは、人々は愛を注ぐ共通の対象によって特徴づけられると説いた」と(読売新聞)。この言葉は、アウグスティヌスの『神の国』第19巻第24章からの引用です。
37
坂口ふみ先生の『<個>の誕生:キリスト教教理をつくった人びと』の文庫版がいよいよ刊行されました。凡百の専門書や入門書を超えて、キリスト教神学や中世哲学の本質に「触れる」経験を与えてくれる名著です。四半世紀前に初めて読んだ時の興奮がありありと甦ってきました。amzn.to/3IVezlx
38
トマス・アクィナスを研究していると言うと、「宗教ですか?」と言われることがあるが、実はトマスには「宗教」という概念自体が存在しない。古典を読む面白さはこういうところにこそある。我々が当たり前に使っている概念が存在すらしないようなものの見方に触れ、世界観・人間観が根底から刷新される
39
私は、新しい発想が必要な時こそ、読み慣れた本を読み直すことにしている。歩み慣れた散歩道においてこそ新たな発見や驚きが見出されるように、馴染みの書物だからこそ与えてくれる新たな気づきがあるからだ。馴染むことそのものが、状況に応じた新たな気づきを生んでくれると言ってもいいかもしれない
40
今週末は「復活祭」ですが、世界中で、公開のミサは行われません。史上最も静かな復活祭になるかもしれません。ですが、考えてみれば、キリストが「復活」した日は、とても静かな日でした。ほとんど誰もそのことに気づかなかったからです。その意味では最も復活祭らしい復活祭になるかもしれません。
41
「悪魔は堕天使だ」というキリスト教の説明は、一見荒唐無稽な神話に見えるが、示唆するものが多い。最も優れた天使が、最も優れているからこそ、自分を受け入れることができず、「神に取って代わる」という野望の虜になってしまう。それは自己受容の失敗という意味であらゆる罪の原点になっているのだ
42
よい本は、読むたびに新たな謎を与える。問いを与えることこそ、よい本の特徴だからだ。そして、読むたびに読む速度が落ちることも多い。ほんの少し読むだけでも、心の中から様々な思いが触発されて湧き上がってくるので、そのまま読み続けることができなくなるからだ。
43
いよいよ創文社解散まで秒読み段階に入りました。『神学大全』は今後、一部分が文庫などで手に入ることはあっても、現在の創文社版以外の形で全体が入手可能になることは、今世紀中にはないかもしれません。古書でもさほど流通していないので、今月中に入手しておくことを強くおすすめしたいと思います twitter.com/junkuike_jinbu…
44
45
すぐには読めそうにない本ほど、すぐに読む必要がある。とにかく読んでみないと、なぜ今の自分にその本が解読できないのか、その原因をつかむことができない。読めない原因が分かれば、その原因を克服することが可能になる。敬遠して触れないでいると、いつまでも読めるようになる手がかりをつかめない
46
本を読めば読むほど、読むべき本が減るどころか、面白い本が更にあることが分かり、いつか読み返そうと思っていた多くの書籍を、おそらくはもう読み返す機会がないだろうということに改めて気づく。そういう思いを持ちながらもう最後と思って読み返すと、不思議なほどに全ての言葉が心に沁み渡ってくる
47
教皇フランシスコの思想と活動のキーワードは、「橋を架ける」です。困難のうちにいる人々、周縁化された人々、異質な人々に橋を架けていく実践のうちにこそキリスト教の本質が見出されるという教皇の思想が、明日からの数日間でどう表現されていくか、注視したいと思います。
bit.ly/2ObCDUp
48
簡単に読みこなすことのできない書物を読みこなしていくためのコツは、簡単には読みこなせないと自覚しながら、地道に読み進めていくことのうちにある。わからない部分をわからないままに抱え込みながら読み続けていくうちに出会うふとした一つの言葉、一つの文章が、全てを解読する為の鍵を与えていく
49
読書の醍醐味の一つは、繋がるはずのないと思っていた二つの書物が読者の心の中で繋がることによって、作者も思っていなかったような新たな言語宇宙が誕生することのうちにある。無数の読者の心の中で無数に日々誕生するこうした無限の言語宇宙の連鎖こそ、この世界に意味を与えているものに他ならない
50
「本を読んでも解決しない」ということが分かるのは、本を読むことの大きな意義の一つだ。自分が抱いている問いが、書物を読むことによって解決する問いなのか否かということ自体、書物を読まずにははっきりしない。「読書では解決しない」と思いこんでいた問題が、読書だけで解決することも意外に多い