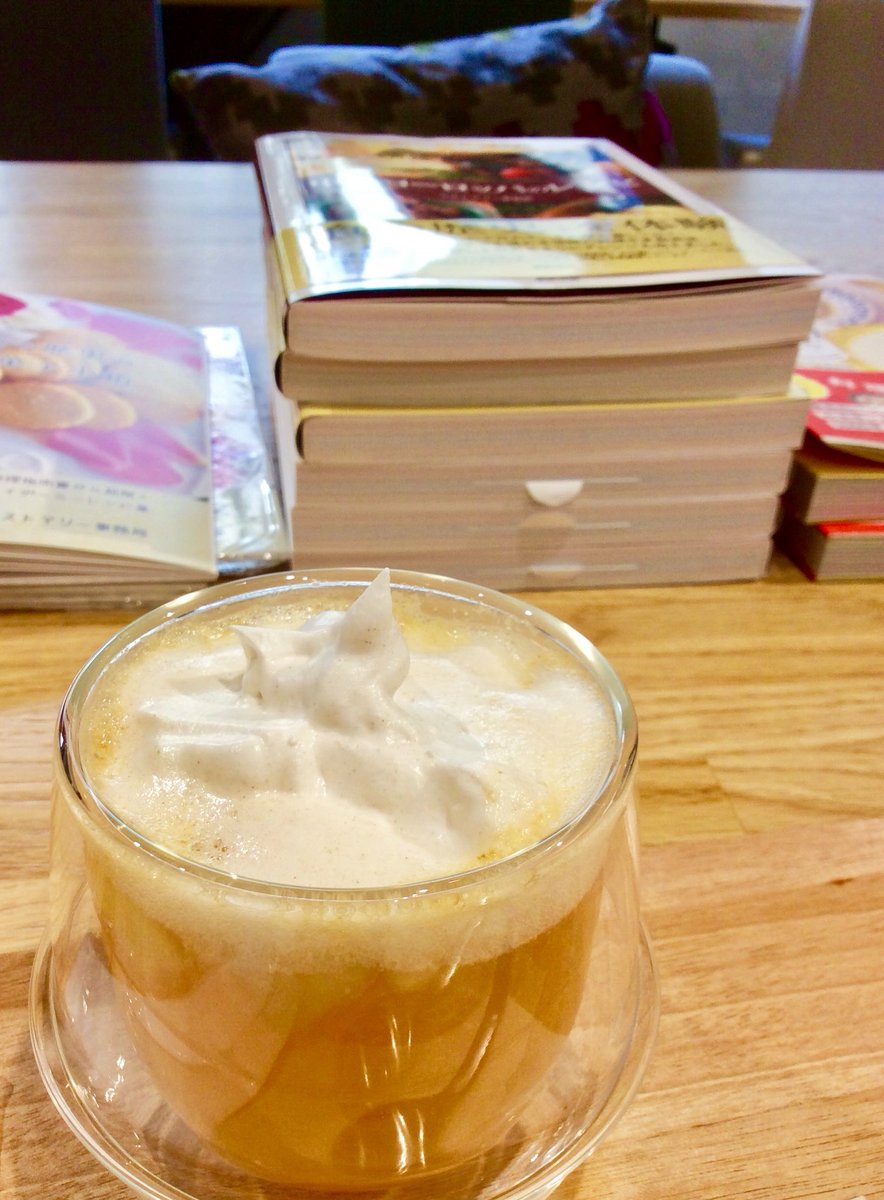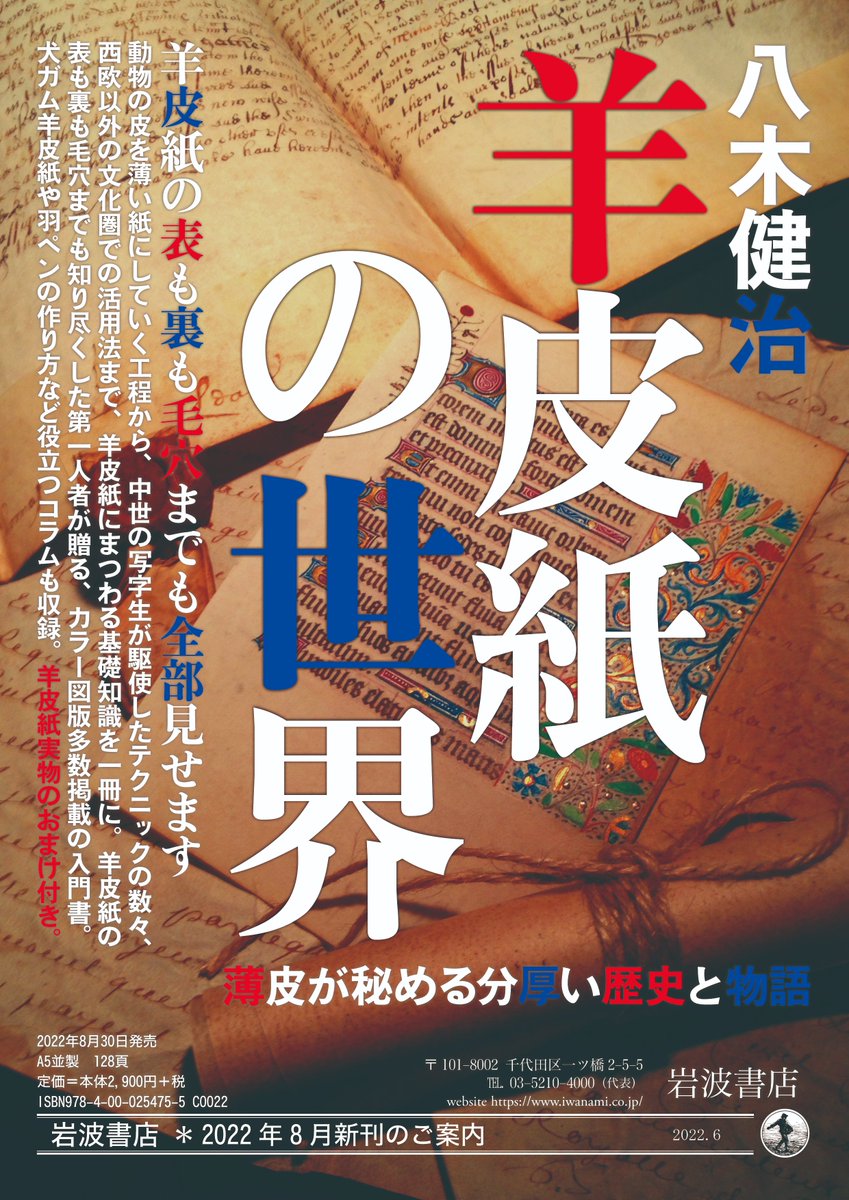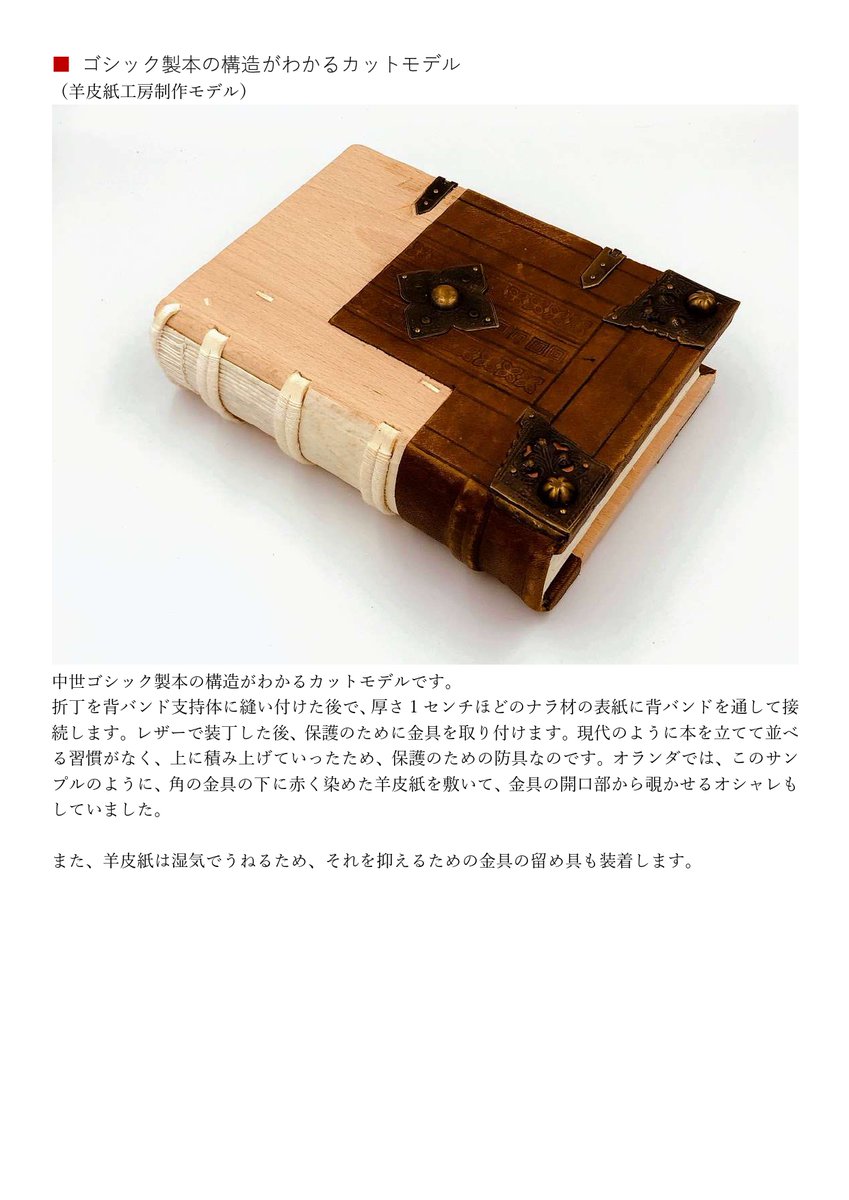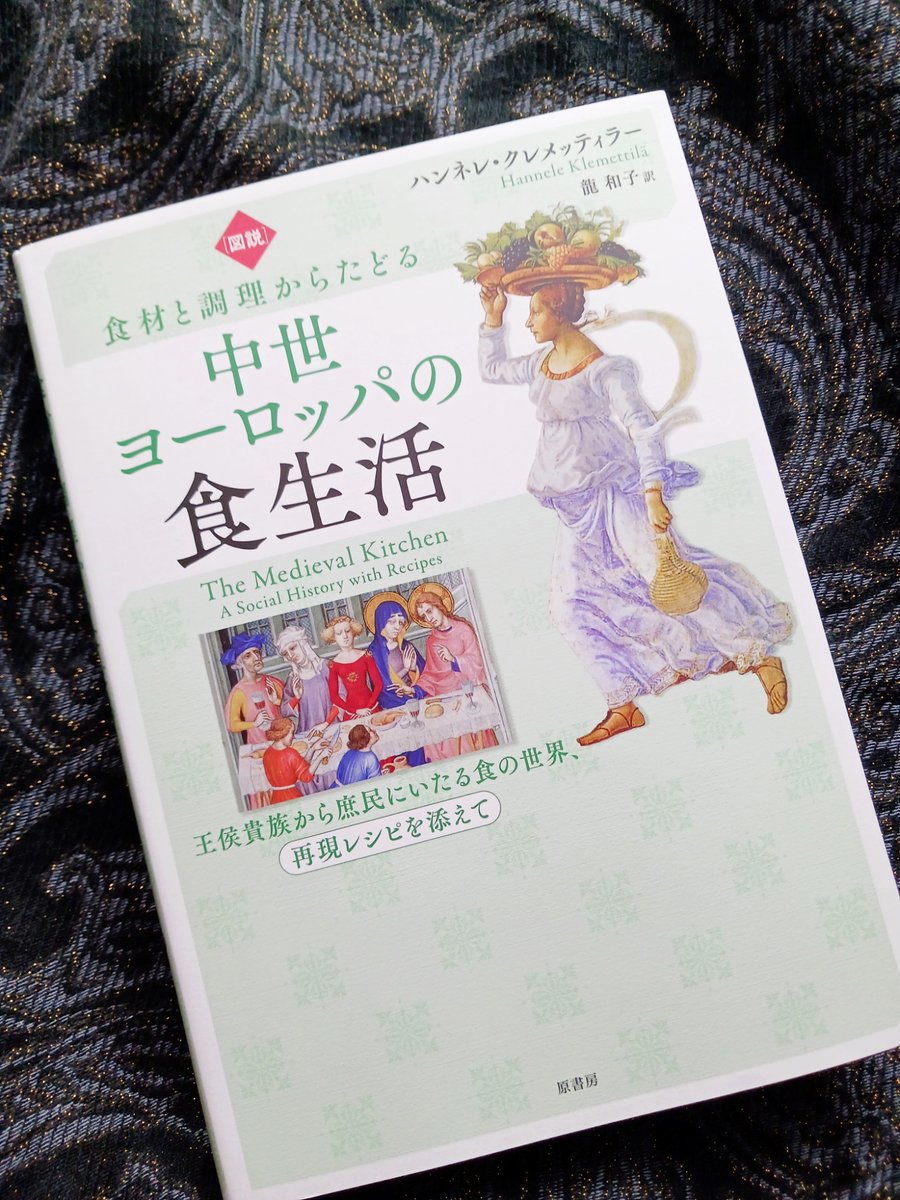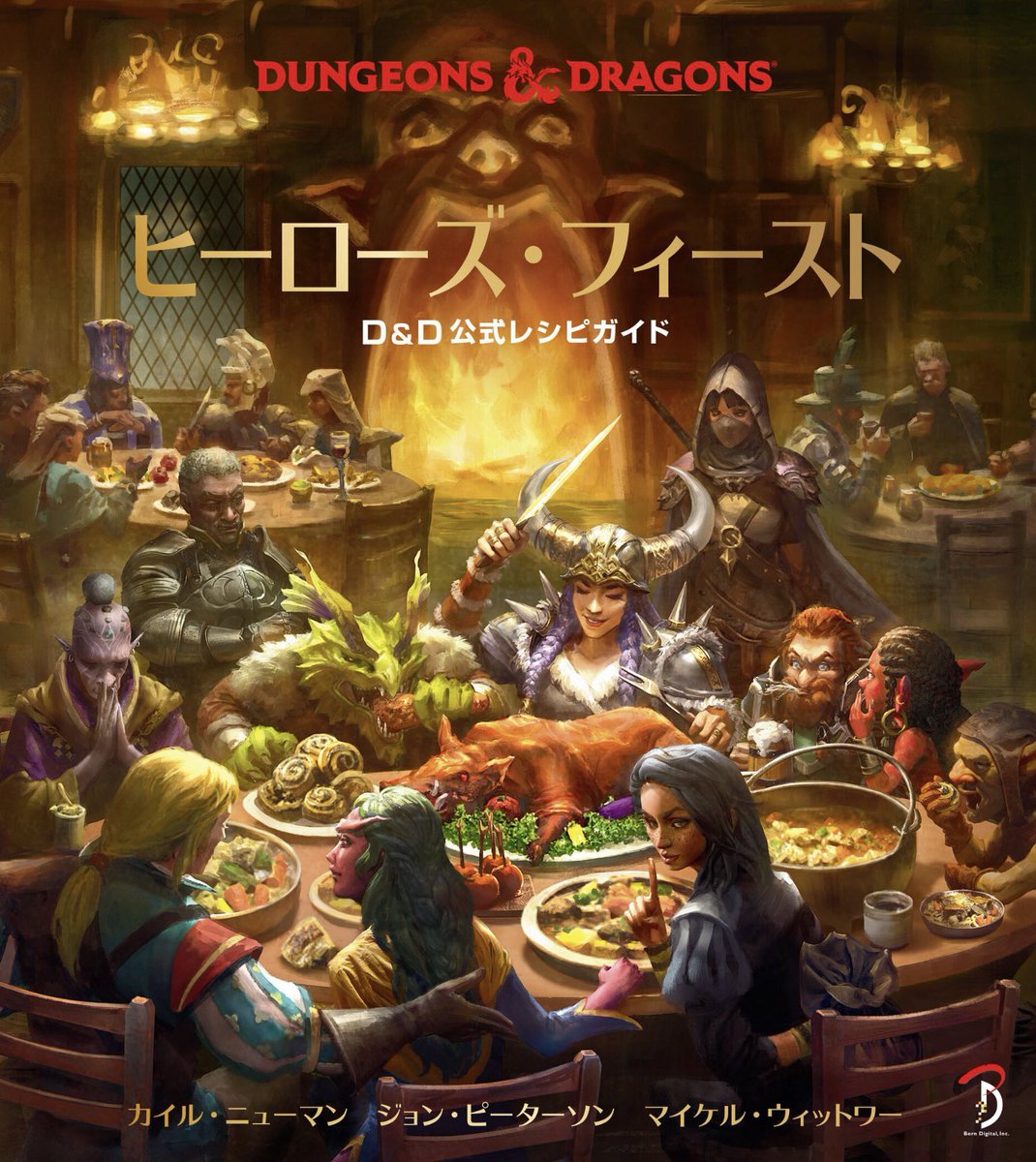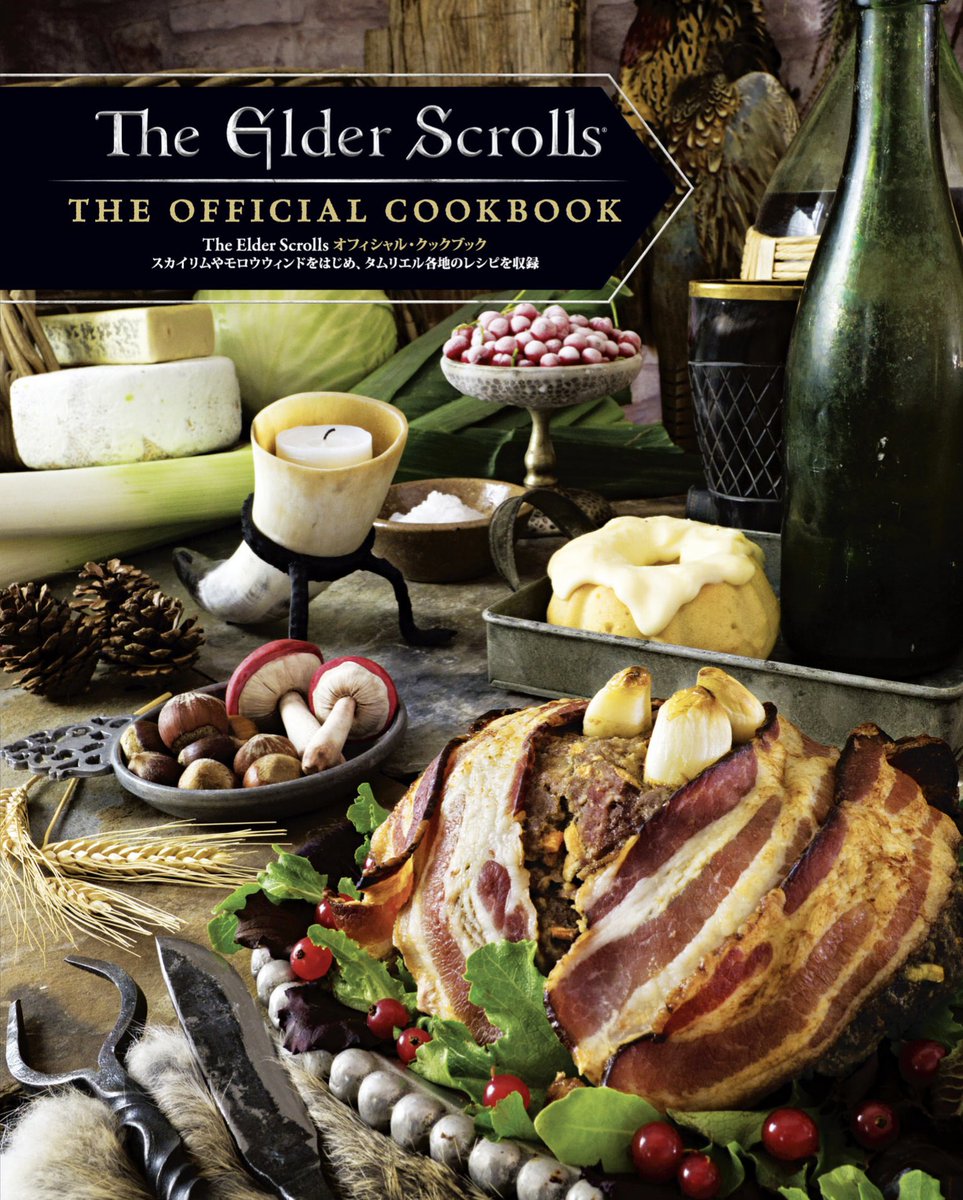1
2
3
タペストリー集「貴婦人と一角獣」が所蔵されているフランス・クリュニー中世美術館が、改装工事などのながーいお休みを経て5/12から再開するそうです(超絶行きたい)。公式アカウントの賑やかさもすんごいんですけど、一角獣とかもウエーイって感じで、なんか見ていて楽しいです(*^_^*)↓。 twitter.com/museecluny/sta…
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
世界はアレなコレで大変ですが、今年もガッツリやりますこの「行事」。超絶本気モードで「例のご一行様」をレーダーで追跡していきます。現在おうちを出て北欧の上、北グリーンランド海あたりにいるみたいでっす。「使用年数」なんぞ、もう歴史クラスタ歓喜じゃないかとコレ(*^-^*)↓ twitter.com/shuhohka/statu…
15
16
17
18
戴冠式の招待状。改めてよぉーく見ると、5月を象徴するグリーンマンや野いちご・矢車菊・テューダーローズ・アザミ・ブルーベル・魔を退けるオークやサンザシ、ローズマリーの枝などがギュギュッと詰められていて、ほぼ中世にもあったシリーズやーん!と、1人でテンションダダ上がり中です(//∇//)。 twitter.com/royalfamily/st…
19
20
21
22
23
24
25