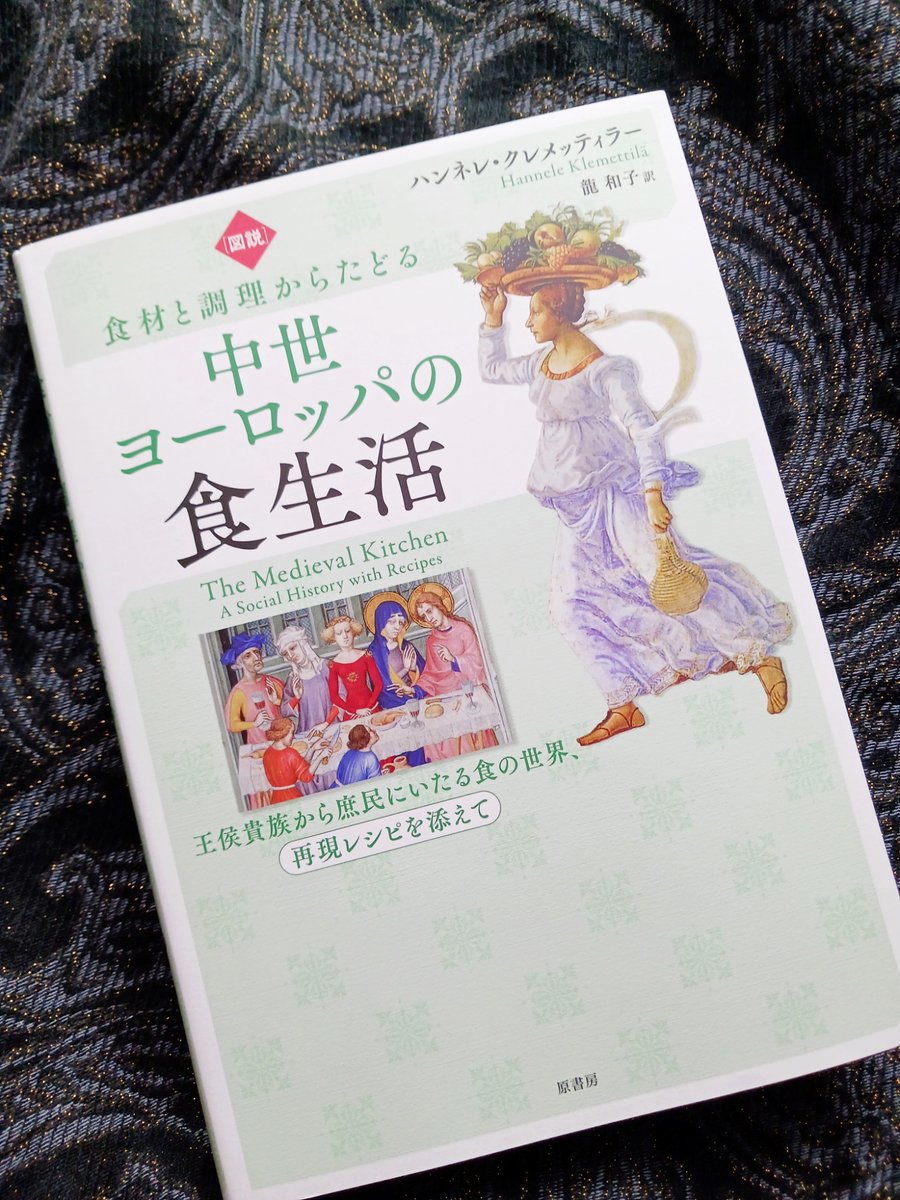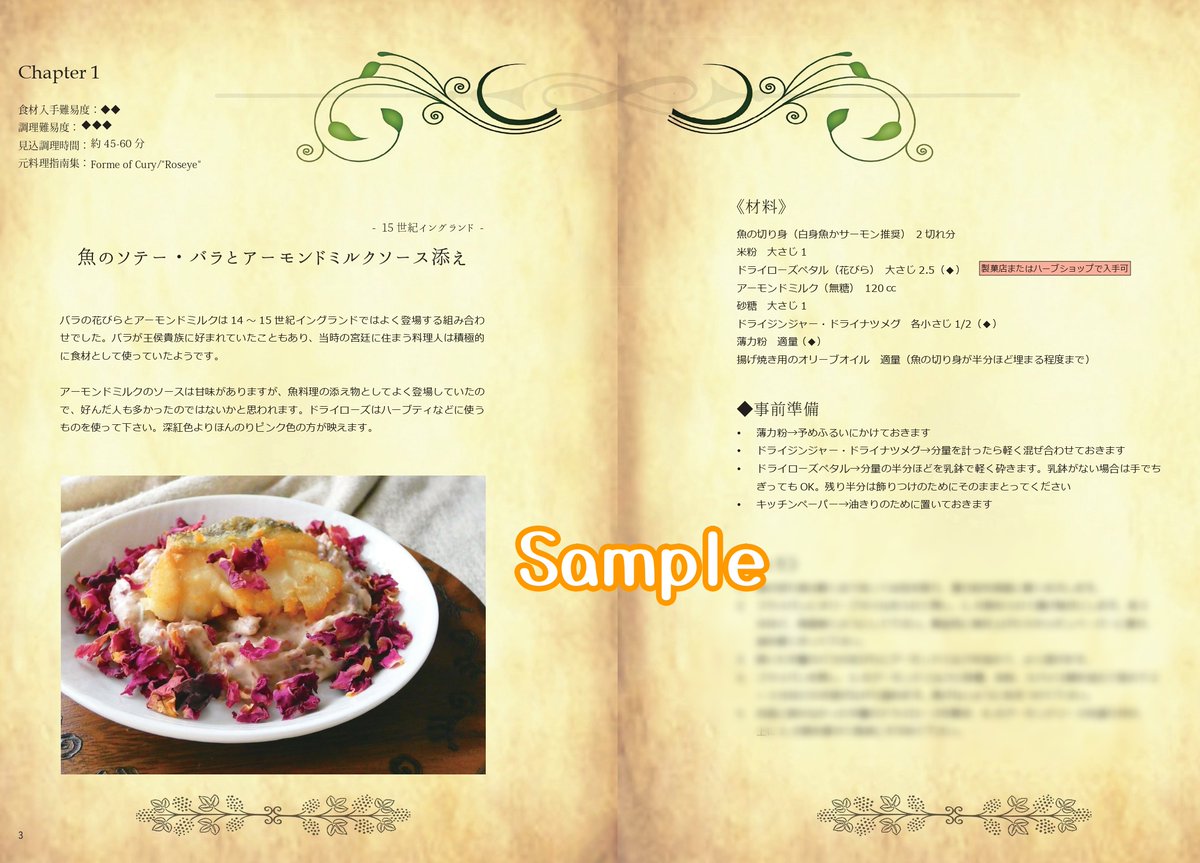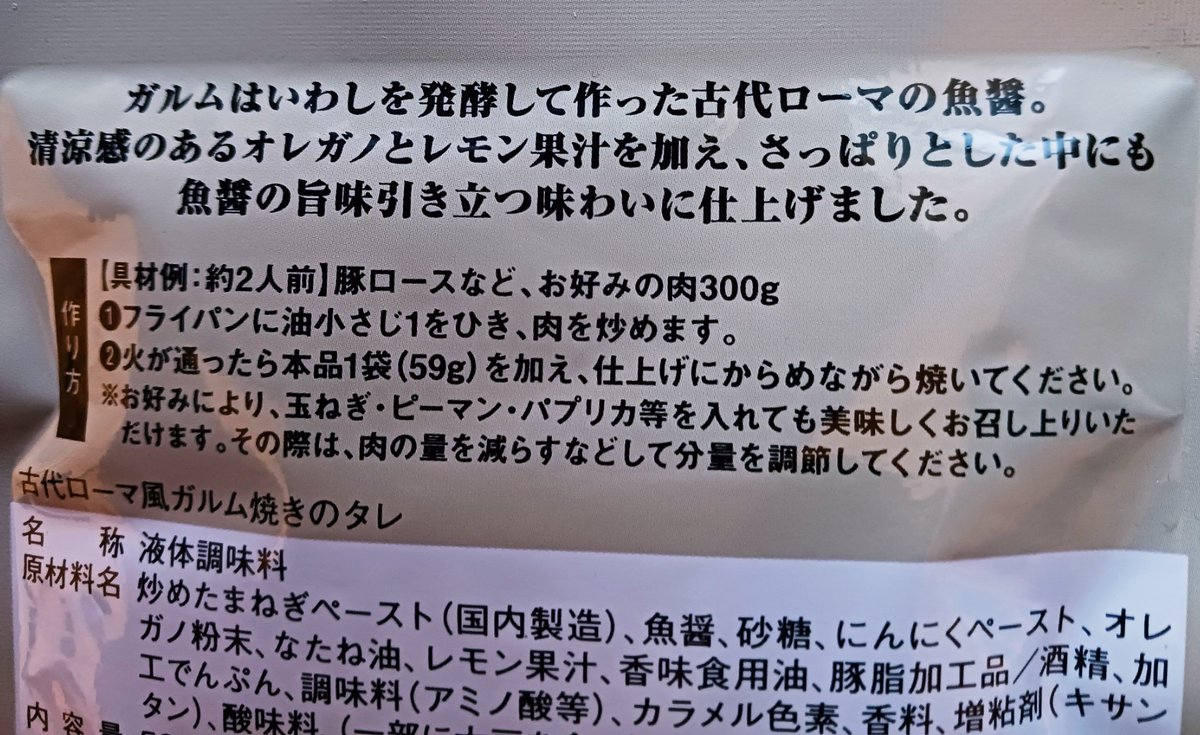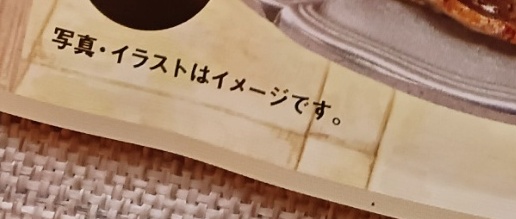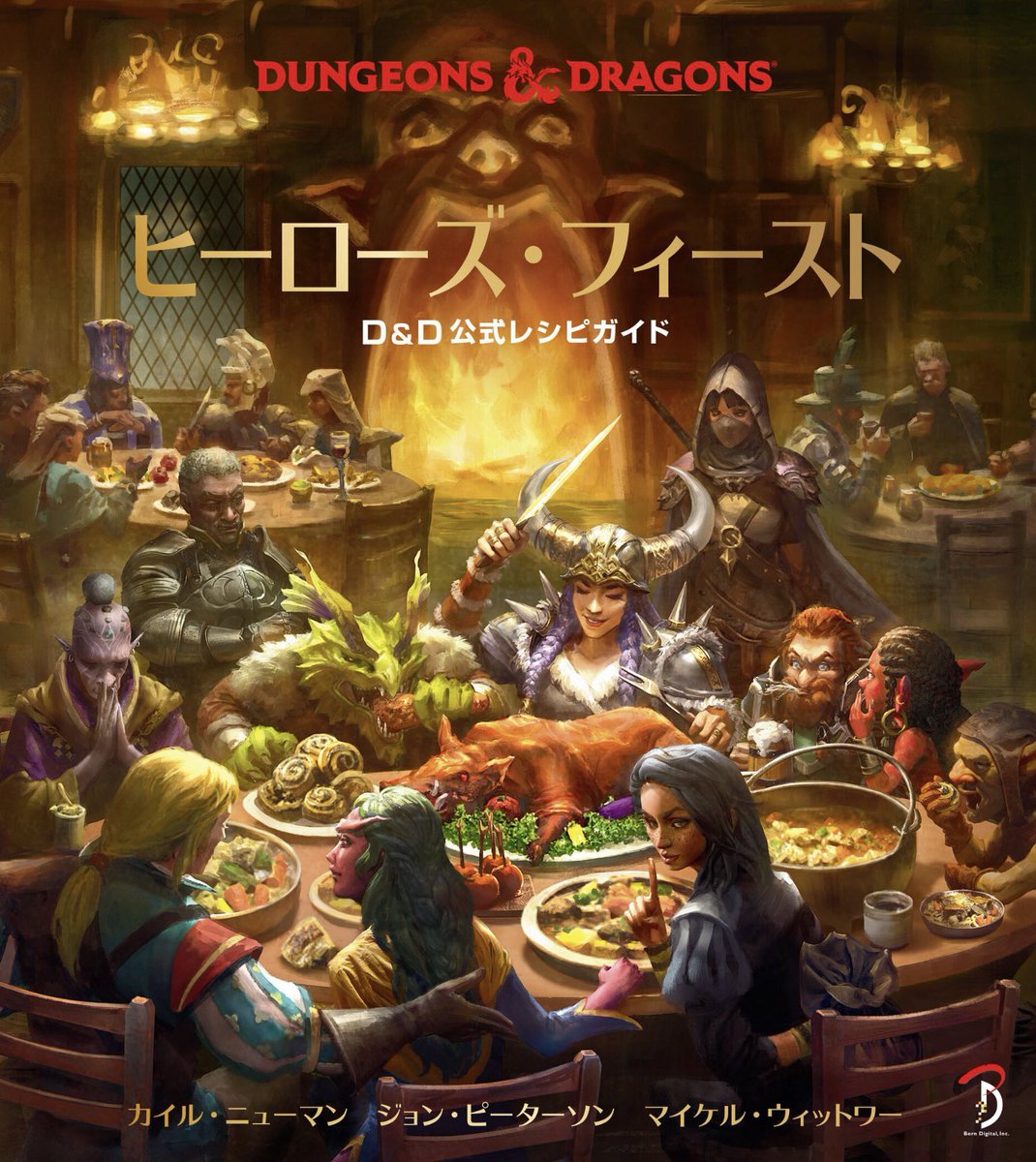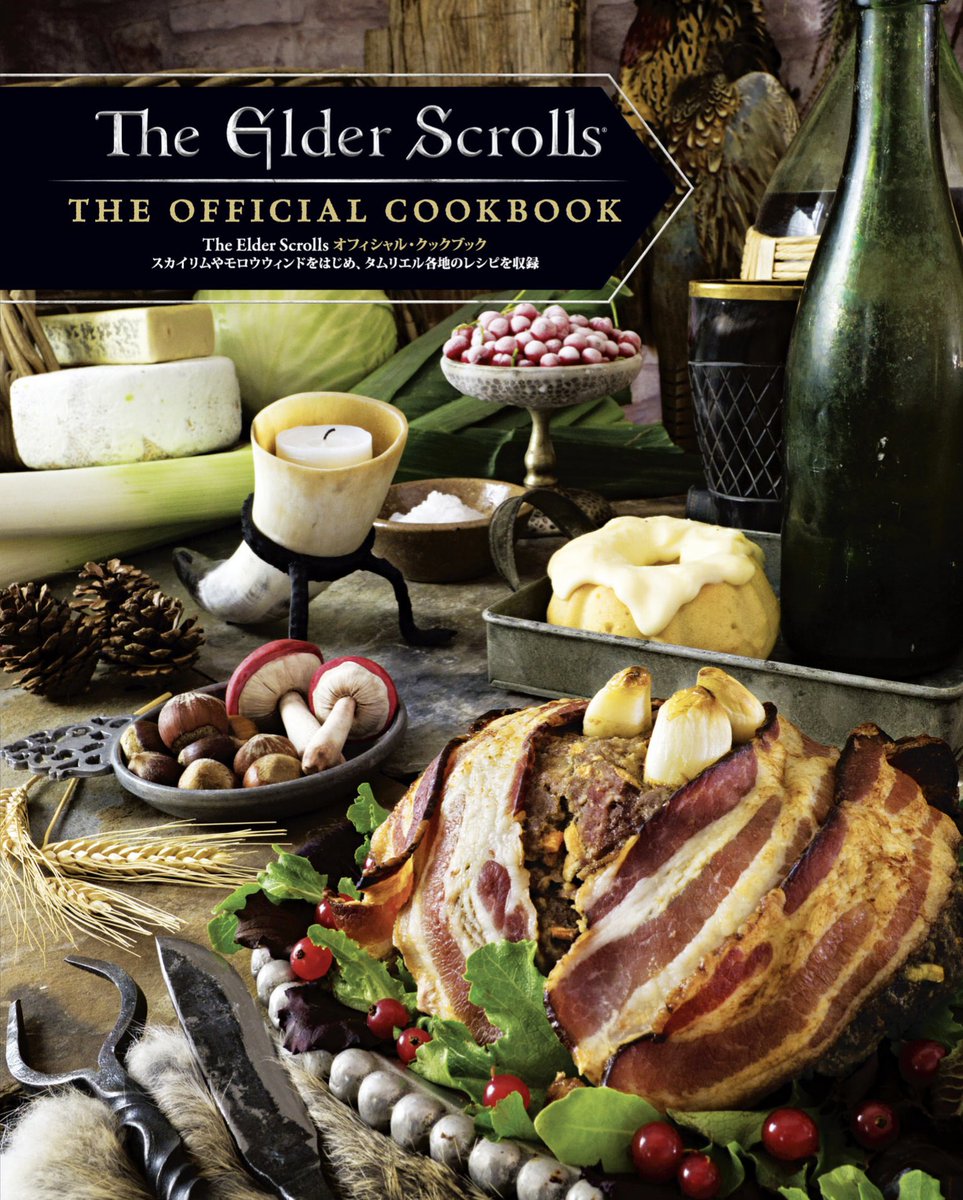1
2
3
明日6/21は太陽の力が最も強くなるといわれる夏至。イギリス・ストーンヘンジでは、毎度恒例夏至のお祭り(?)として、多くの人がパワーをもらうべく訪れます。一部ヒャッハーな方もいると思いますが、日本時間の12:00頃からライブ配信もしますのでご興味あればぜひ。晴れるといいんですけどねー。 twitter.com/EnglishHeritag…
4
5/6の戴冠式で使われる植物一式が届いたそうで、素敵なお写真ツイートを引用ペタリ。イギリス国内で採集したものがメインだそうですが、北アイルランドやスコットランドのスカイ島から採った植物もあるのは意外でした。戴冠式を飾った花々は、終了後すべて慈善施設へ寄付されるそうです。 twitter.com/RMRussell29/st…
5
6
戴冠式の招待状。改めてよぉーく見ると、5月を象徴するグリーンマンや野いちご・矢車菊・テューダーローズ・アザミ・ブルーベル・魔を退けるオークやサンザシ、ローズマリーの枝などがギュギュッと詰められていて、ほぼ中世にもあったシリーズやーん!と、1人でテンションダダ上がり中です(//∇//)。 twitter.com/royalfamily/st…
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
なんで行かない方がいいの?という理由のひとつはフェアリードクターが解説しておりますのでこちらもご参照下さいませ。美しい花たるもの、遠くからそっと愛でるのが一番よきかと存じます('▽')。
twitter.com/bardoffairyhil…
22
23
24
25