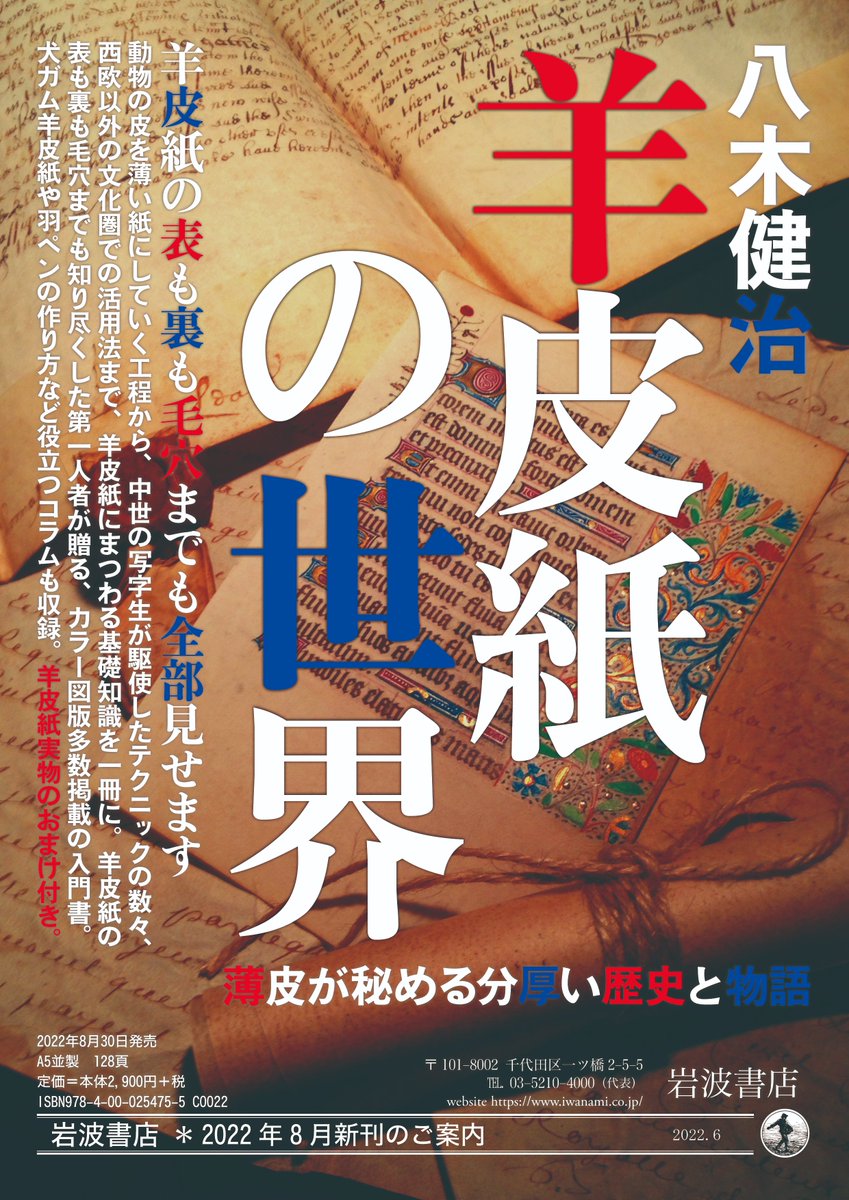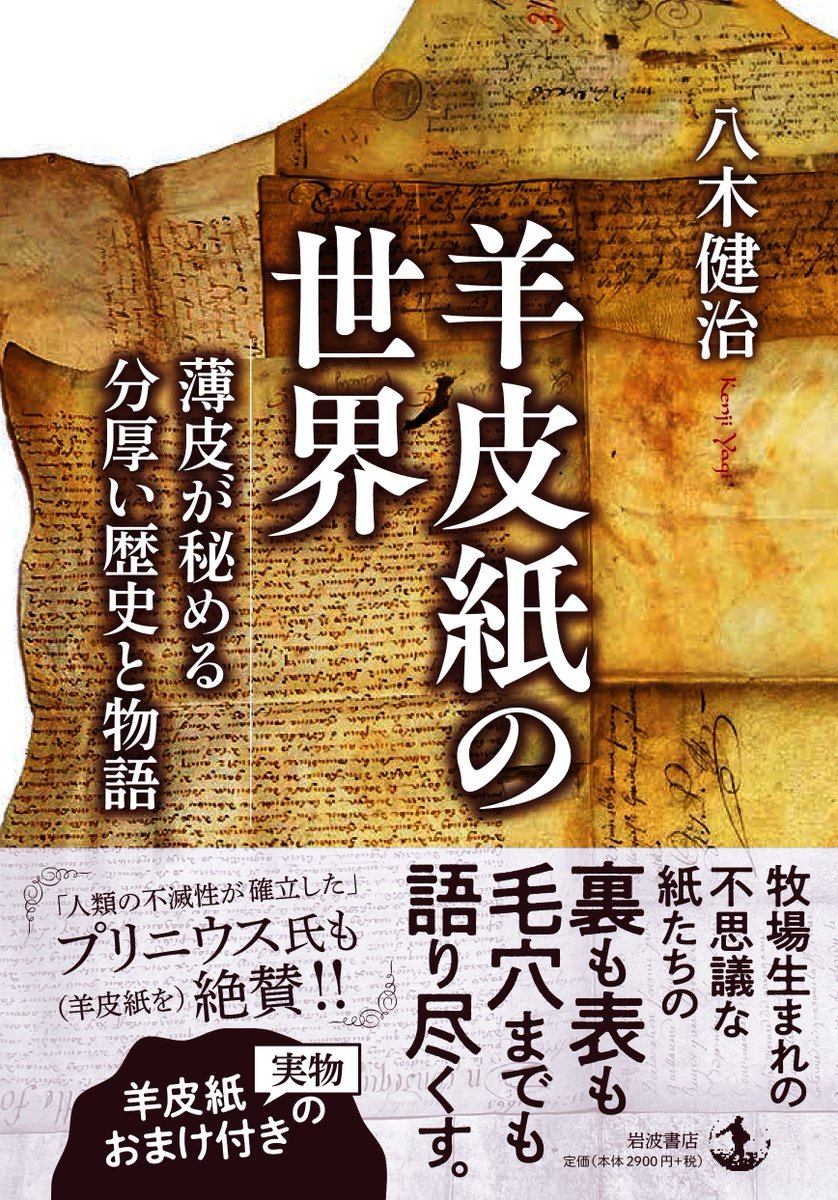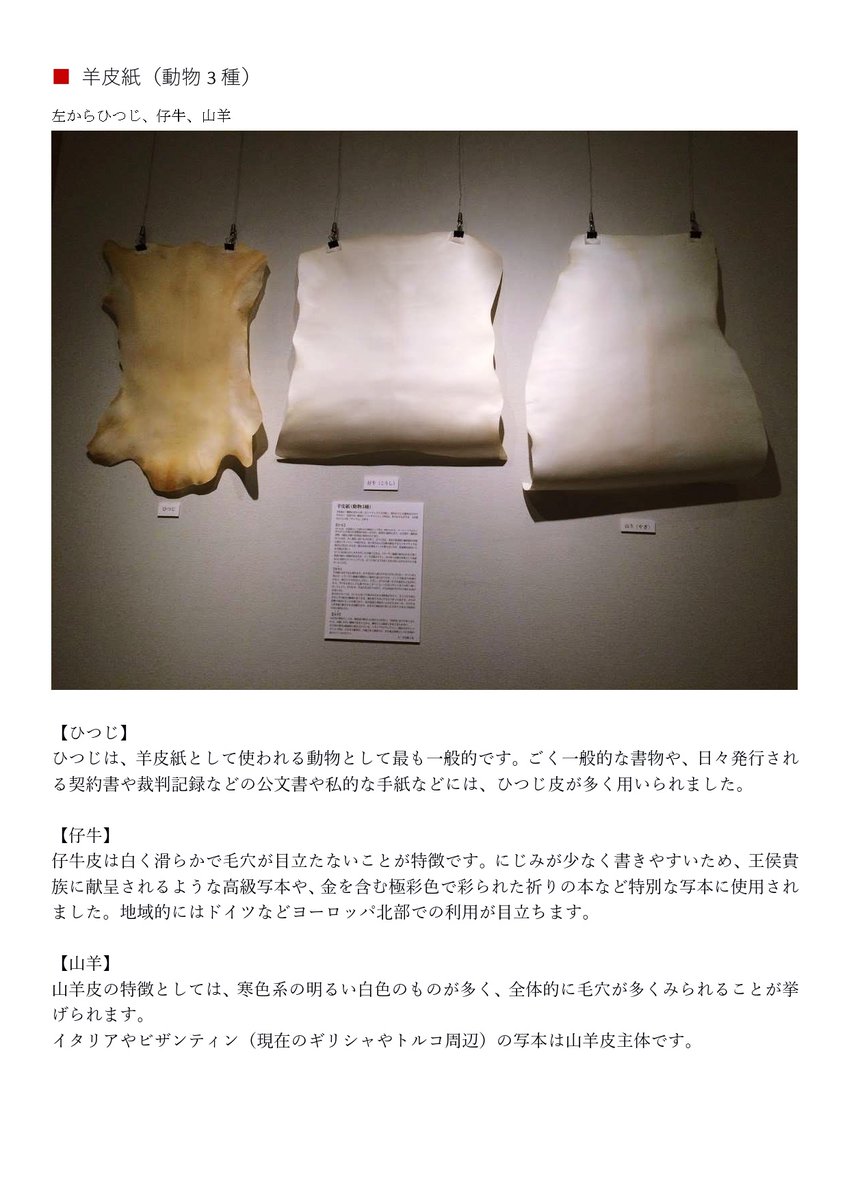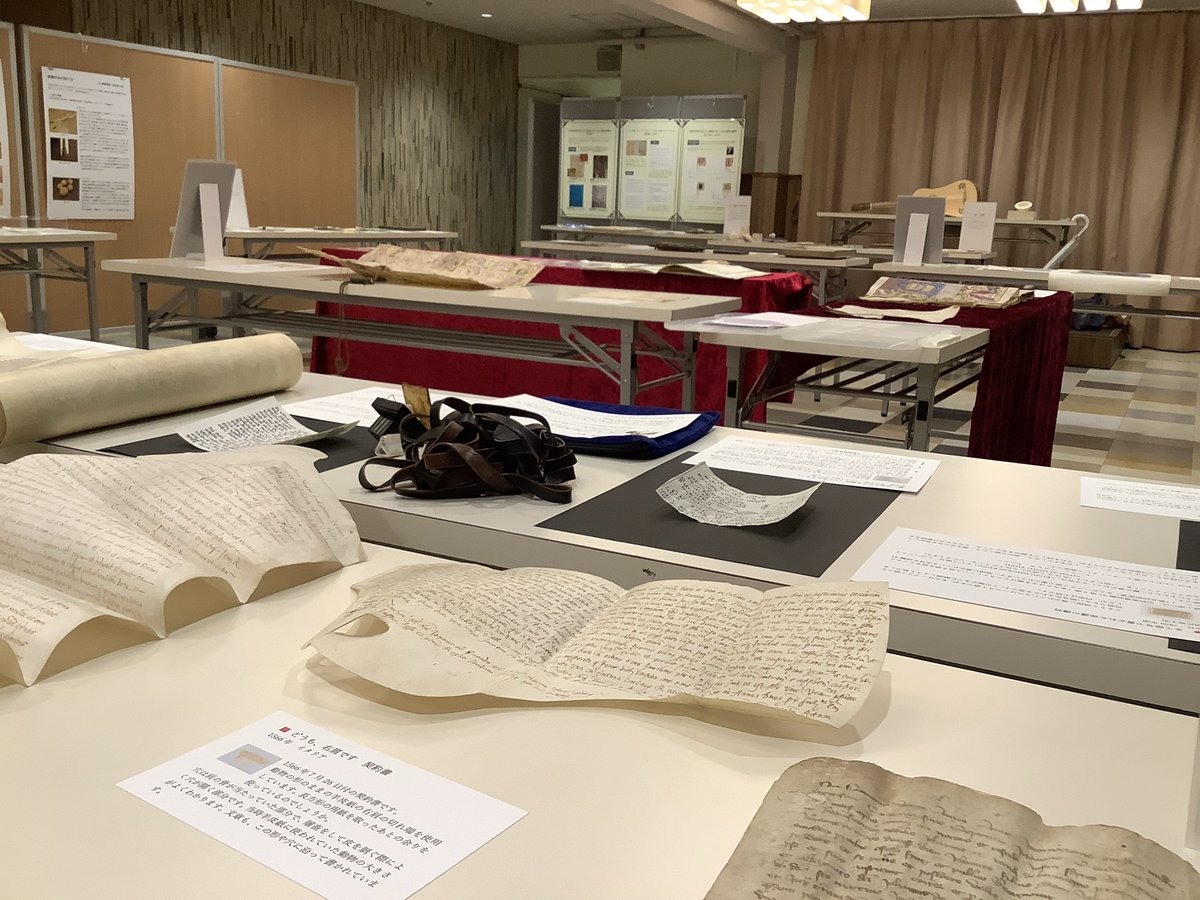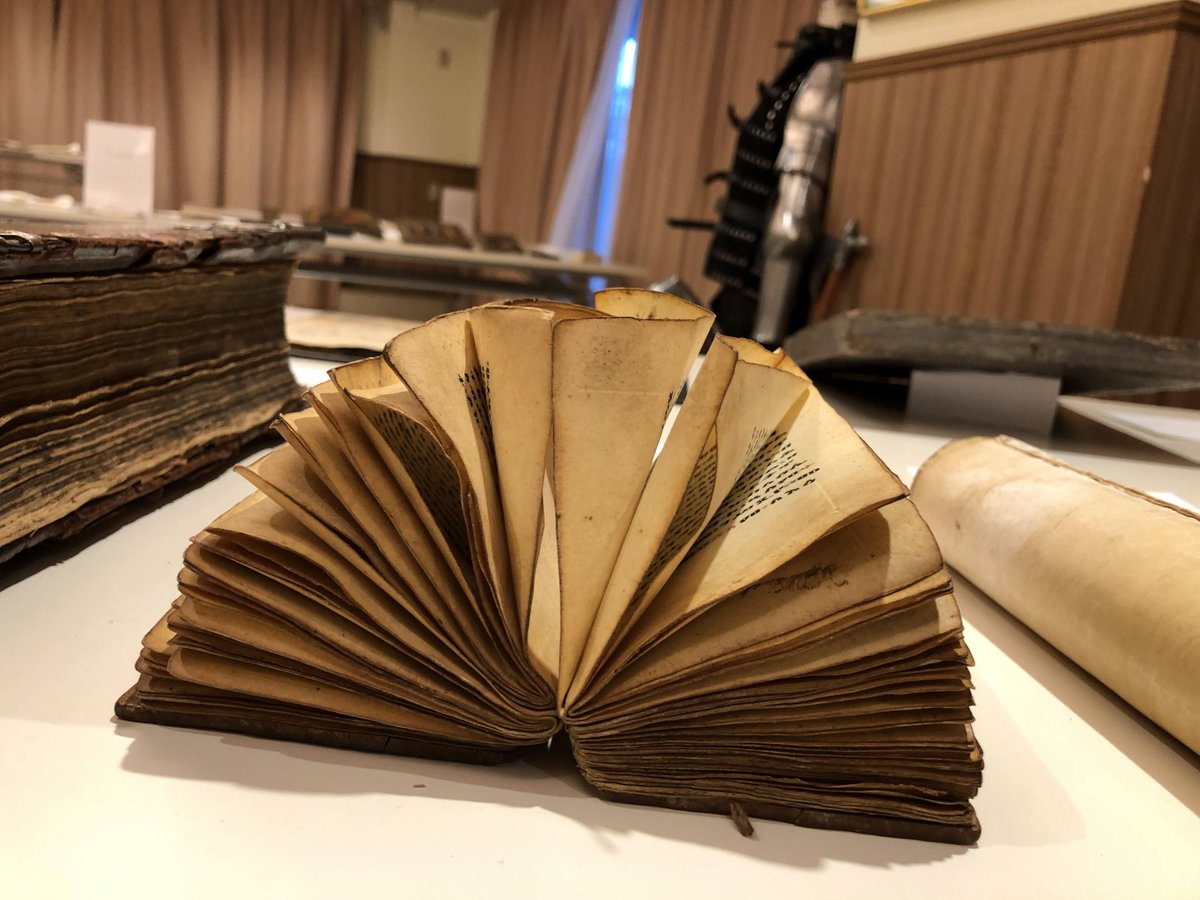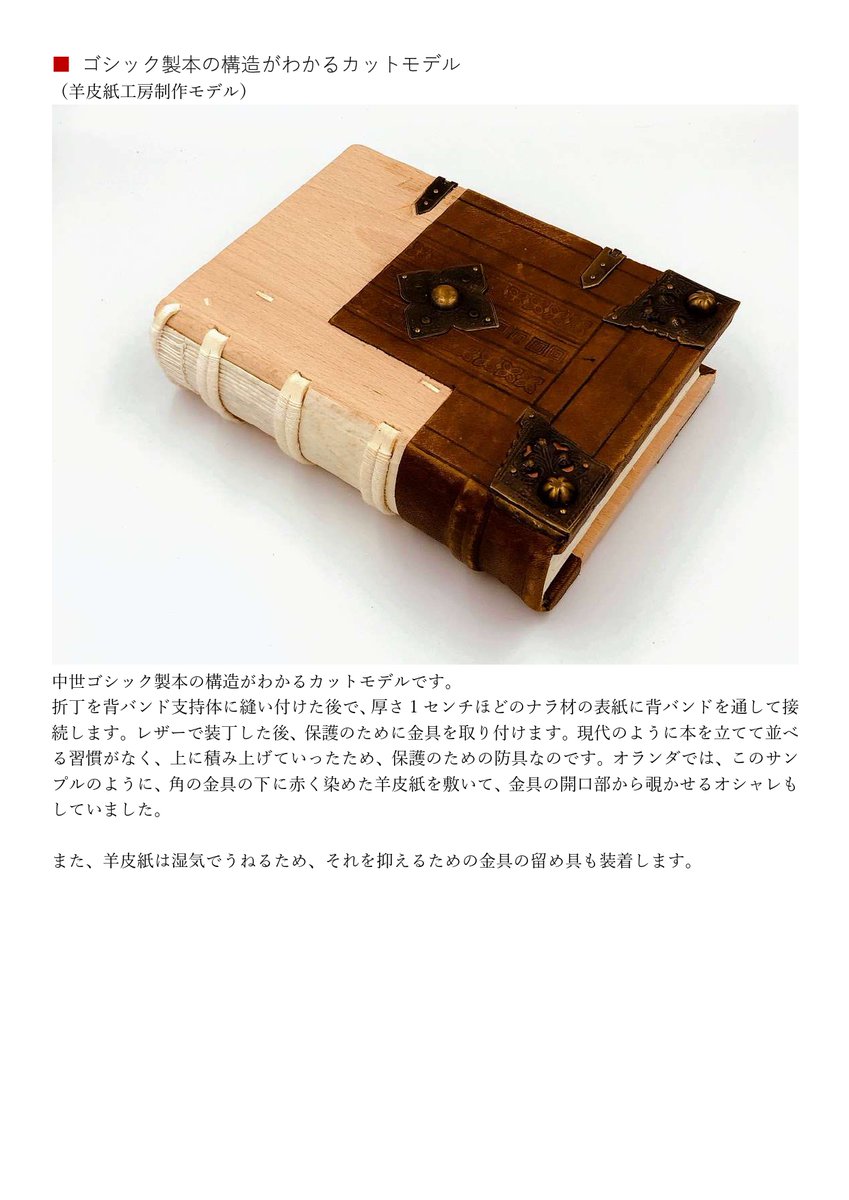26
27
28
29
30
【#C100 新刊のご案内】
今のところ参加予定の夏コミ新刊「中世欧州のお魚本」、なんとか発行できそうです。お魚文化圏は意外と範囲が広いので、中世前後の時代モノも一部取り扱います。レシピはパイ・ソテー・スープなど。8/1(月)~期間限定で自前通販も行います。ご興味ございましたらぜひにどぞ♪
31
32
33
今回の新作同人誌『中世欧州の魚料理』でも少し触れている「ガルム」という調味料に関する記事をこれペタリ。古代ローマ料理には欠かせない逸品だったんですが、中世ヨーロッパの料理指南書にはほぼ登場しません。歴史的背景が色濃く影響しているのも要因だったりしますです。
natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/0…
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
魔を退けるローズマリー、一途の愛の象徴マートル、古の神木といわれるオーク。他の花々も含め、永遠の旅路にふさわしい、大変美しいリースだと思いました。 twitter.com/RoyalFamily/st…
44
45
46
遥か昔に絶滅したと思われる幻の食材「シルフィウム」に関するレポートをペタリ。これ、前からめっちゃ気になっていたんですが(断定はできないものの)、解析研究の一端になるだけでも有難い情報でございます。シルフィウムを使った古代ローマ料理検証もありますです。
natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/22/0…
47
48
49
50