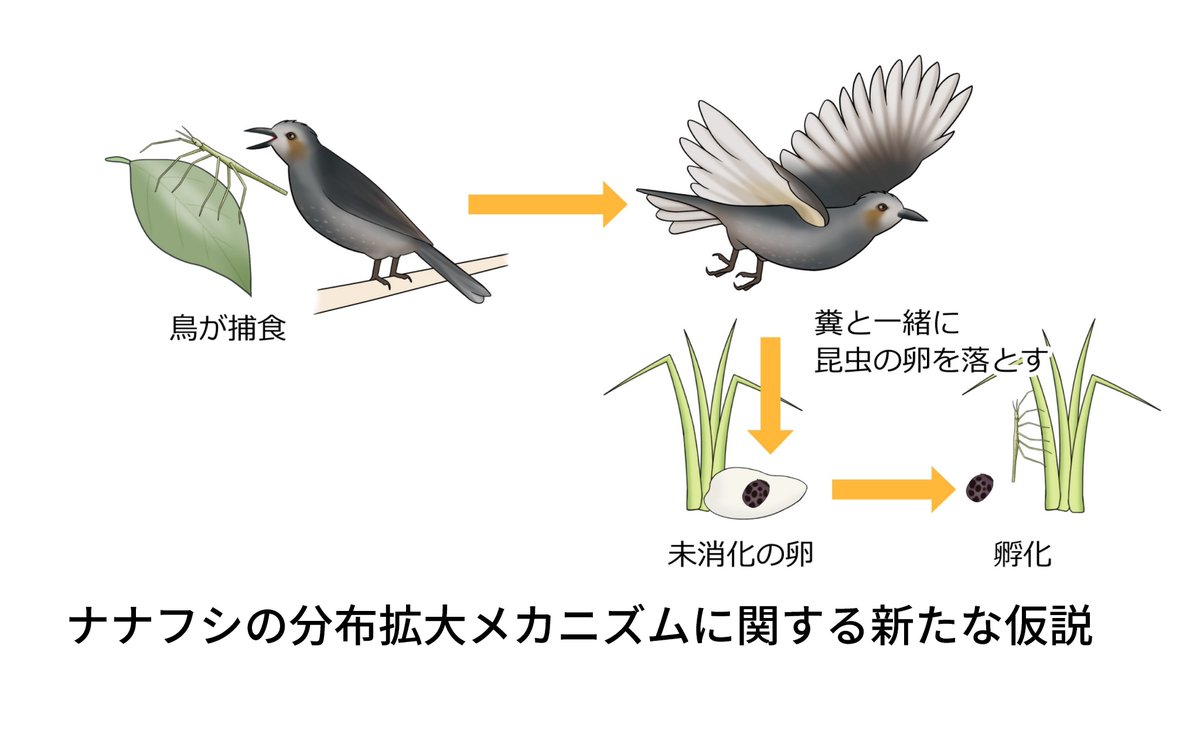76
77
78
79
80
81
83
84
85
兵庫県立大の中浜さんたちと,美しい花を咲かせるラン科植物「サギソウ」の自生地とされるいくつかの集団で、栽培品種もしくは栽培品種との交雑個体が混じっていることを明らかにしました。つまりサギソウ野生集団で遺伝的撹乱 (遺伝子汚染) が起きていたことを解明しました。doi.org/10.1007/s10531…
86
87
88
89
90
91
この表紙の『植物』をやめた植物について、光合成をやめた植物をそもそも聞いたことがなかった人用に解説します。「キノコ」や「イソギンチャク」と思う人もいるかもしれませんが、実はれっきとした植物なんです(キノコはむしろ動物に近い)。表紙の植物は、とろろなどに使用する山芋の親戚です。 twitter.com/tugutuguk/stat…
92
山田孝之の植物番組、第4弾!シュールな演出と本格的な生態解説で熱狂的な支持を集めてきた異色の植物番組。今回も山田孝之が3つの植物の奇妙な生態と生存戦略を語る。
1.独自の道を歩む孤高の植物
2.妖しく誘惑する日陰の植物
3.裏の顔を持つ可愛い白花
ご期待下さい!
nhk.or.jp/d-garage-mov/m…
93
94
95
96
日経サイエンスや日経新聞の記事で、光合成をやめた植物に関心を持ってくださった方は、ちょうど明日の菌学会(熊本&youtube)で一般向けシンポジウムで、もう少し詳しい話をお聞きいただけます!無料・誰でも可というのはなかなかない機会だと思います。ぜひぜひどうぞ! twitter.com/tugutuguk/stat…
97
>RT「草木のこと」さんのツイート,植物の啓蒙に貢献しているとは思うのですが,ほとんど全部ネット上から取ってきた写真なのは,あんまりよくないなあという感じですね.左のヤクノヒナホシは発見者の山下さんのもので,右は私の以前の写真ですね...
98
99
100