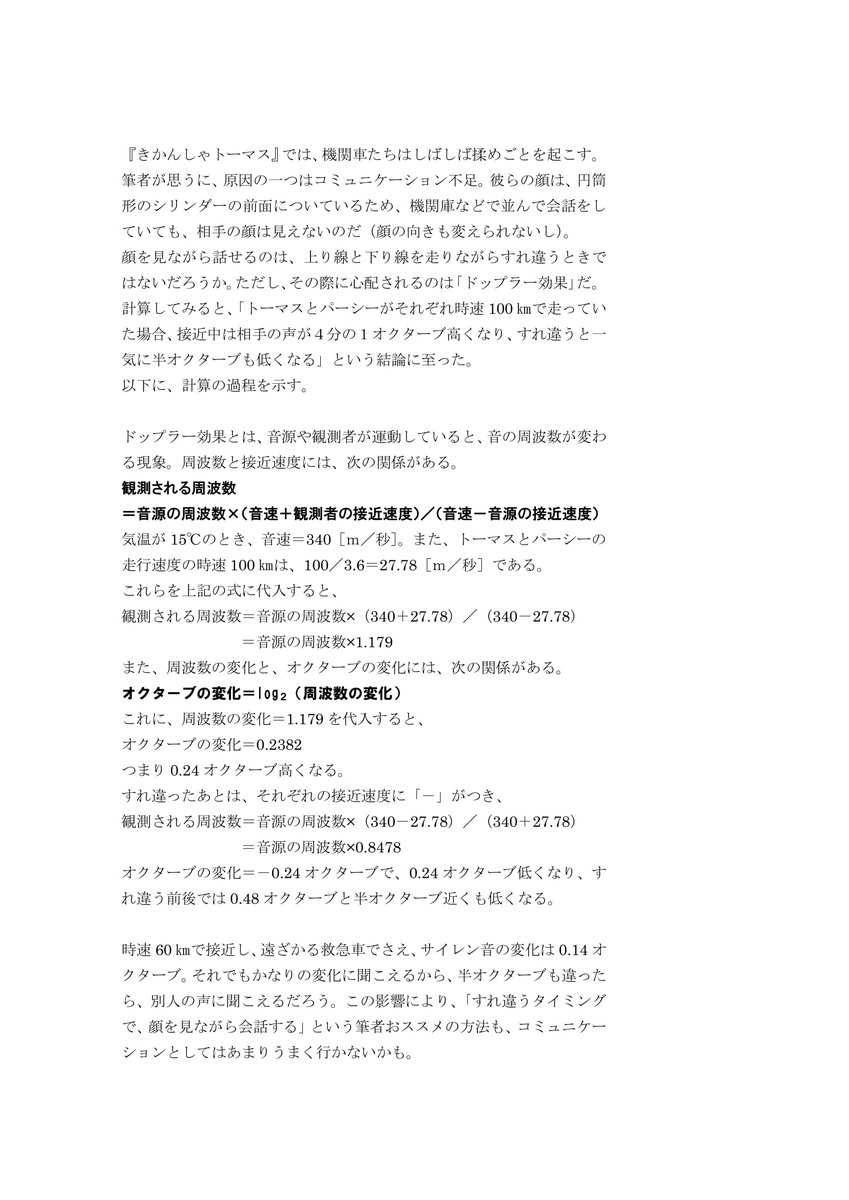176
『アンパンマン』で、バタコさんが「新しい顔よ」とパンを投げると、新しい顔と入れ替わり、古い顔が飛んでいく。これ物理的に言うと「新旧パンの反発係数は1」。だが反発係数1のパンは、まったく変形しない硬さを持つ。アンパンマンは空腹の人に自分の顔をあげるけど、硬くて食べられない!(柳田)
177
植物で最も伸びるのが速いのは若い竹、つまりタケノコだ。1日に1mも伸びることがある。普通の植物は、茎のいちばん上だけが伸びる(成長点)。ところが竹には約60の「節」があり、その1つ1つに成長点がある。タケノコは節のあいだが広がって成長するが、それが60ヵ所で起こるから伸びが速い。(柳田)
178
『ビルド』も驚きの展開になってきたが、驚いたといえば『仮面ライダーゴースト』だ。敵の眼魔が街一つを浮上させ、落下させた。推定重量3億3千万t。落下時間は1分49秒で、自由落下なら高度59㎞から落下。これを受け止めたゴーストの斥力(反発し合う力)は180億t。驚きすぎて忘れられん。(柳田)
179
今年もあと2日しかないないと思うと、なぜか妙に焦ります。そんな年の瀬、『空想科学読本WEB』更新しました~。「『おそ松さん』の十四松は、やることが人間離れしているけど、ホントに人間なの!?」 です。web.kusokagaku.co.jp/articles/814
180
『三国志』において、孔明を劉備に推薦したのは、徐庶という人。彼も実績ある兵家だったが、孔明について「拙者が蛍とすれば 孔明は月のようなもの」とまで言った。すごい。光の明るさを比べると、月はホタルの1垓6千京倍。数字で書けば160000000000000000000000倍。さすが日経電子のばーん!(柳田)
181
フランスパンの一種「バゲット」が細長いのはなぜ? かつてフランスでは、パン職人は暗いうちから働いて、丸いパンを焼いていた。そこで「午前4時より早くから働いてはいけない」という法律ができた。丸いよりも細長いほうが、発酵も焼けるのも早いため、バゲットが作られるようになった。(柳田)
182
海や嵐の神ルギアvs大雨を降らせて海を広げたカイオーガ。海は44億年前から降った大雨で生まれたから、カイオーガの実績はすごい。ルギアが嵐を起こせるのも、海の水蒸気がエネルギーを供給するから。つまり両者は協調関係にあり、仲よくなる可能性が高いと思う。共闘されたら、困るのはグラードン…?
183
『#塔の上のラプンツェル』の原作はグリム童話で、ラプンツェルの歌声に魅せられた王子が、彼女の髪を使って塔に登る。そんなこと可能か…と、毛根1本が耐えられる力を実験で調べたら、なんと150g。髪が10万本なら15tに耐えられる! おらおら、ヨーロッパ中の王子ども、まとめて登ってこい!(柳田)
184
『アメトーーク!』の仮面ライダー話、面白かったですね。紹介された『鎧武』の大玉スイカ攻撃、スイカの直径は3mほどもあった。これが転がって時速100㎞を出すには、毎秒2.9回転が必要だ。で、鎧武には52Gの遠心力がかかる!人間は10Gしか耐えられないから、やっぱ鎧武すごい。(柳田)
185
186
医師は次の基準によって、死亡と診断する。①心拍動の停止 ②自発呼吸の停止 ③瞳孔の光反射の消失
だが『宇宙戦艦ヤマト』最終回で、佐渡先生は艦長室に入るや、その場で敬礼しただけ。基準を確認した様子がない。後日、沖田艦長は甦り、理由は「佐渡先生の誤診」とされるが、当然な気が…。(柳田)
187
『きかんしゃトーマス』の機関車たちは喧嘩が多いが、なぜか? 彼らは顔が車体の前面にあり、顔を見ながらコミュニケーションする機会が少ない。走行中には顔が見えるが、すれ違う100m前から話し始めても、双方が時速100㎞なら、1.8秒で通過! しかもドップラー効果で声が変わる。悩ましい。(柳田)
188
眠らせ対決。プリンは相手が眠くなる波長で歌う。息継ぎをしないから、相手が寝ないと命がけになる。スリーパーは振り子を使い、起きたばかりの人も3秒で眠らせる。スリーパー有利に思えるが、プリンが目を閉じて歌えばいいのに対し、振り子を持つスリーパーは両耳を塞げない。プリンの勝ちか?
189
『ドラゴンボール』で悟空は、人工重力装置で重力を100倍にして特訓していたが、恐るべきことだ。そこではあらゆる重さが100倍になる。250gのスマホが25㎏になり、体重60㎏の人は6tに。また落下の衝撃も100倍増。高さ20㎝の段差を降りると、高度20mから落ちたのと同じ衝撃を受ける。めちゃ危険!
190
『名探偵コナン』コナンと毛利探偵はかなり身長差がある。マンガで測ると、毛利探偵はコナンの2.27倍。文科省調査では、小1生男子の平均は116.83㎝、38歳男性は171.79㎝。コナンを基準にすると毛利探偵は265.5㎝になり、毛利探偵が基準だとコナンは75.8㎝だ。1歳児(平均77.8㎝)より小さい!(柳田)
191
ドードリオとダグトリオは、どちらも頭が3つ。ドードリオの3つの頭は喜び、悲しみ、怒りの感情を表す。ダグトリオは一つの体から生まれた3つ子なので、考えることは同じ。なんか逆のような気もするが、戦いとなったら、3つの感情に揺れるドードリオより、気持ちが一つのダグトリオが有利か。(柳田)
192
『ウルトラセブン』最終回。正体を告げたダンにアンヌが「人間だろうと宇宙人だろうと、ダンはダンに変わりないじゃないの。たとえウルトラセブンでも」。感動の場面だけど、ダンは仮の姿である。「バカ殿だろうと志村けんだろうと、バカ殿はバカ殿に変わりない」と言うのと同じような気が…。(柳田)
193
とっても久しぶりに『あるある空想科学』の新作発表だよ!
これは「登場人物が、自分たちの行為を科学的に理解している」マンガ。
このたび、西園寺と東郷が登場するシリーズに『超竜剛拳GO』というタイトルがつきました(今ごろ…)。
マンガを描いてくれたのは、黒城ろこさん。
#あるある空想科学
194
『ウルトラマン』18話には、にせウルトラマンが登場した。目の形が違うのに、なぜ騙される!? と不思議だったが、ウルトラマン登場はそれ以前に17回。しかも現れるや格闘し、3分以内に慌ただしく去る。スマホのなかった時代、ウルトラマンの姿は劇中の人々に正しく認識されてなかったのかも。(柳田)
195
196
最弱のコイキング⇒凶暴なギャラドス。ヒレがボロボロで醜いヒンバス⇒最も美しいポケモン・ミロカロス。どちらの進化がすごいか。コイキングも昔はそれなりに強かったというから、嬉しいV字回復だ。一方、誰からも無視されたヒンバスが、憎しみの心を癒すミロカロスに進化するのは胸を打つ。引分け!
197
壁などに貼ったシールをはがしたいときは、熱を加える。シールの糊はデンプンでできていることが多いので、熱で軟らかくなる。ぬるま湯につけたり、ドライヤーの熱風を当てよう。熱ではがれない場合は、台所洗剤や消毒用のアルコールを垂らして、乾かないようラップをかぶせてしばらく置く。(柳田)
198
『ウルトラマン』全39話で、ウルトラマンは怪獣26匹に対してスペシウム光線を放った。だが26戦のうち、1発の光線で倒したのは12回だけ(46%)。それ以外は、別の技5回、スペシウム2~3発4回、科特隊の力3回、外れ1回、自分の敗北1回。あの光線が意外と効かないのか、怪獣が予想外に強いのか。(柳田)
199
ゼットンの1兆℃の火球が直径1mで、1秒間燃えた場合、発生したγ線の影響で、半径402光年以内の生物は全滅する。ジャミラの回によれば『ウルトラマン』の舞台は1993年。γ線は光速で広がるから、たとえば地球から27光年離れた織姫星=こと座のベガに達するのは、2020年。えっ、今年!? わ~織姫さま~。
200