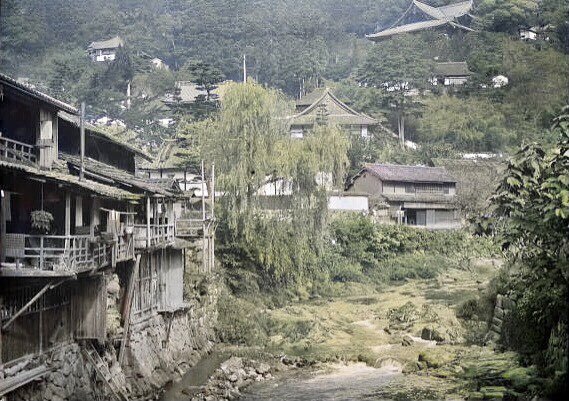76
77
78
阿野全成の娘が公家に嫁ぎ、阿野の名字と領地を相続したことで阿野家は公家として残り、全成の血は天皇家にと繋がります。
養子を挟みながら昭和まで続くも、戦争で当主と後継ぎが戦死し断絶。
阿野家の墓は今も谷中霊園にひっそりと建っています。
#鎌倉殿の13人
79
83
84
姉川の戦いが起きた時の登場人物の年齢(満年齢)
徳川家康 27歳
瀬名 28歳前後
浅井長政 25歳
お市 20歳前後
酒井忠次 43歳
石川数正 37歳
本多忠勝 22歳
榊原康政 22歳
平岩親吉 28歳
織田信長 36歳
木下藤吉郎 33歳
明智光秀 54歳
井伊直政 9歳
#どうする家康
87
89
90
92
1945年8月15日、終戦を迎えた人々の様子
#終戦記念日
93
94
比奈は、義時と離縁した後に、京都の貴族で歌人としても有名な源具親に再婚します。
具親との間に、輔通、輔時という2人の子をもうけ、輔時はのちに、比奈と義時の間に生まれた北条朝時の養子となります。
輔通も、幕府の後押しで官位の任官を受けるなど、北条氏との縁は続きました。
#鎌倉殿の13人
96
98
99
100