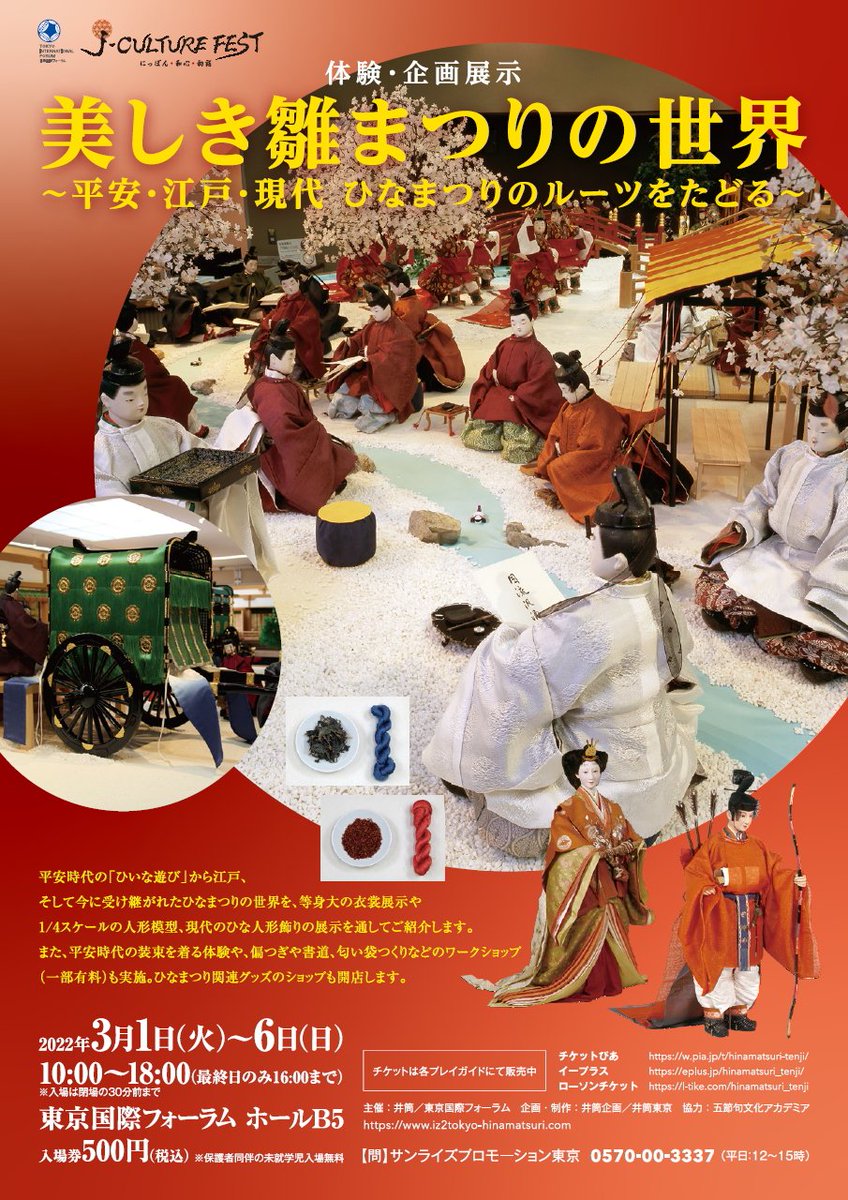401
403
407
408
409
このたびの重版決定につきましては、robin様はじめ、ツイッターご利用の皆さまに大変お世話になりました。心よりお礼申し上げます。
411
後ろに長く引く下襲(したがさね)の裾(きょ)。天皇は襟下2丈1尺5寸。皇太子は襟下1丈9尺6寸。臣下は官位が上がると長くするので、裾を下襲とは別パーツにした「別裾(べつきょ)」ですが、天皇・皇太子は下襲から続いた「続裾(つづききょ)」なので、襟下の寸法表記になります。
412
414
皇后陛下の御小袿はの上文は窠中浜茄子。洲浜形との比翼文?
今上陛下の立太子でも皇后陛下(現上皇后陛下)が比翼文でしたが、小袿で比翼文というのは新しき故実ですね。
415
416
417
江戸時代まで装束の衣更えは「旧暦4月1日と10月1日」でしたが、明治以降は「立冬立夏」です。
今年の立冬は明後日11月7日なので、今日は夏服、立皇嗣の礼の8日は冬服ということになります。
419
『有職の色彩図鑑』(淡交社)
四季折々の植物を見たとき、それをわたくしたちの先祖が、どのように見て、どう表現してきたかを知る、良きリファレンスガイドになるのではないかと考えております。そしてクリエイターの方にこういう形で使って頂けますことは、望外の喜びでございます。 twitter.com/_suga613_81941…
421
422
田の畦に植えられ、その毒性を利用してモグラの侵入を防いだ(エサになるミミズがいなくなる)とも言われています。同様の目的で墓地にも植えられたため、「死びと花」などという別名も有ります。
423
今日の「らんまん」の徳永助教授は、多くの皆さまに感動を与えてくれたようです。自分と同じ感慨を持つ方がたくさんおいでになることは、何よりも嬉しく心強いものでございます。 twitter.com/yosinotennin/s…
424
椿の葉のおかげで、餅が手に付きません。スポーツ時のフィンガーフードとしては最適だったのも頷けます。
425
基本的には事前予約ですが、「和菓子の日」である本日は、店頭でもわずかながら販売されています。それぞれの菓銘は、真上より時計回りに、武蔵野・源氏籬(げんじませ)・桔梗餅・伊賀餅・味噌松風・朝路飴・豊岡の里(中央)です。