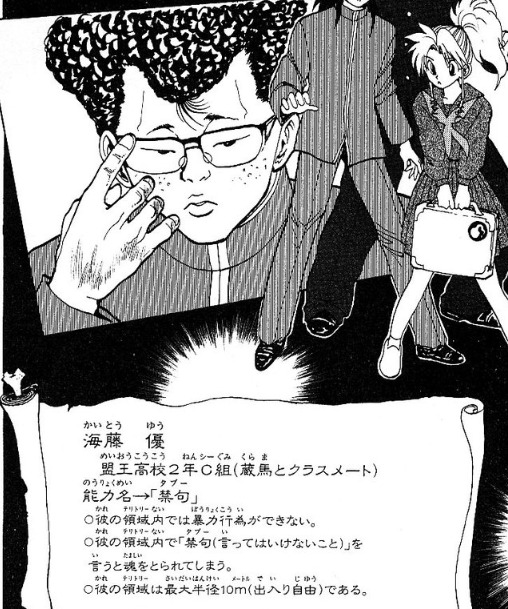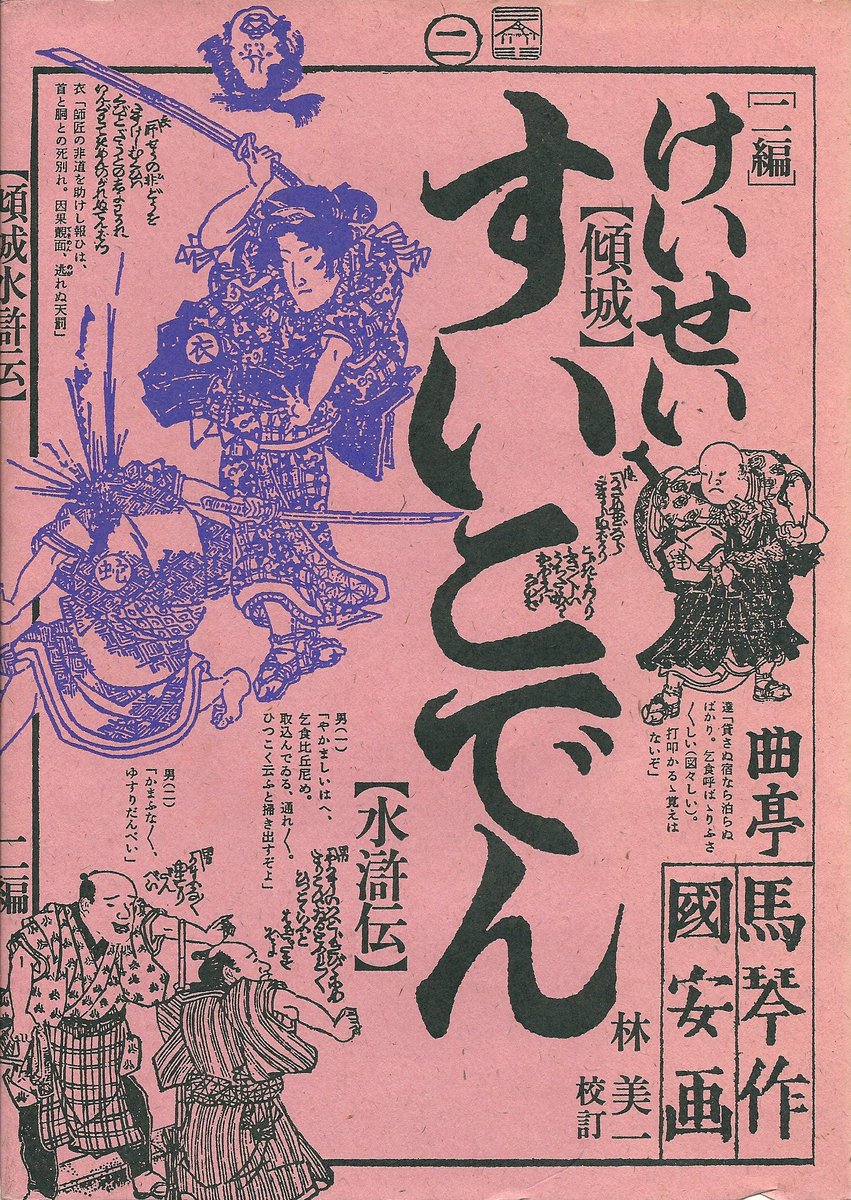926
「結婚式の加害性」まで言い出したら、さすがに自他境界線が崩れているので、マジでメンタルカウンセリング案件だと思う。
いやホントマジで。
私も思い当たるところあるから。
927
正直、やばい状態の人間って、「自分以外のポジティブなもの」全てが、「ポジティブでない自分を責めている」と思うようになるの。
例えば、桜の花が咲いているだけで、「自分をバカにしている!」って思うようになるの。
928
929
まぁでもネタ抜きでね、わかるでしょ? このおかしさ。いや、人間性のおかしさでなくてね?
同じ「不思議な能力を得られるなら」の「もしも」の発想が、「自分を幸せにする」ではなく、「他人を自分と同レベルに落とす」になっている。
これは、自他境界線の歪みですよ。
930
他人の幸不幸は他人の勝手です。
自分の幸不幸に関わりません。
これが自罰に向かう人もいます。
それこそ、「こんなご時世でみんな大変なのに自分だけ幸せになってはいけないと思う」みたいに言う人です。
一見善人ですが、誰も幸せにしません。
ついでに言えば不幸な人も救われません。
931
まず、自分と他人の間に、れっきとした境界線を引きましょう。他人は他人、自分は自分。
その上で、祝福したいなら祝福する。
したくないならほっとく。
できるのはそれだけです。
他人の不幸であなたが幸福にならないように、他人の幸福であなたは不幸になりません。
932
そして同時に、他人の不幸であなたも不幸になるわけでないからこそ、人は不幸な人に同情し手を差し伸べられる。
また、他人の幸福で幸福にならないからこそ、他者の幸福を無責任に、そして打算抜きに祝えるのです。
933
だから実は、人間は精神の均衡を保つためにも、時に大げさなくらい、他人の幸福を祝うくらいの方が良かったりするんですよ。そこで自身の線を引き直せる。
「他人に引っ張られずに」済む。
この均衡を取り戻せた状態を得られることが、「幸せのおすそ分け」状態なのかも知れませんね。
934
935
936
桃井さん「塚原卜伝と武蔵のように、俺に襲いかかってみろ」
ジロウ「ドリフのコントで有名なあれですね!」
桃井さん「発想が古すぎる」
#ドンブラザーズ
937
なんだぁ? 21世紀にもなって「優生思想」なんて非科学的な話をしたやつが現れたのか? んなモン、条件付次第でいくらでも前提が変わるのに、限定された実験室じゃあるまいに、なにをもって「優秀かそうでないか」を定めるのが不可能ってので、全部終わりなんだよw
938
「実力主義」「成果主義」信仰の異種みたいなモンなんだが、これらを邁進した結果、常に確実に問われるのが「それを判断する者の正当性を如何に立証するか」なのよ。日本が成果主義評価主義に切り替えて、ことごとく失敗してんのも、それが原因。
939
そも生物の進化ってのは、様々な見方がある。大型化すれば繁殖力が下がるため滅びやすい。単体では死にやすいが大量に生み増やすことで絶滅のリスクが少ないものもいる。サーベルタイガーは滅んだが、ゴキブリは生きているようなものだ。
940
魚にしても、マグロは「人間の視点」で言えば、優秀な生物に見えるが、逆に言えば「人間に常に食べられるリスクを背負った」とも言える。そのせいで滅びる可能性も持ってしまった。
941
逆にシーラカンスなんておもしろいんだ。「生きた化石」と称されるほど、他の生物が化石でしか残っていないほどの古代から生態を変えていない。
その理由の一つに、「汽水域」が挙げられる。
海水の中にある淡水溜まりの中で生息する生物なのだ。
942
大型の海水魚は汽水域に入れない。
小型の淡水魚ではシーラカンスは捕食できない。
結果として、「誰にも脅かされない」生活が可能となった。だがそこに新たな脅威が現れる。
「道具を使って他の動物では干渉できない水域の魚を取って食う陸上生物」人間である。
943
だがシーラカンスはそれすらも乗り越えた。
如何にしてか。
答えは「不味かった」w
シーラカンスって、マズイの。
煮ても焼いても食えない、人間にとって「価値のない」魚だった。
結果として、最大の天敵たる人間からも、捕食されずに済んだ。
944
こいう言う話を聞くと、思い出すのが古の賢者『莊子』の一説、「無用の用」である。
ある日、とある大工が旅をしていると、ずいぶん立派な神木を目にした。
人々に崇め奉られている巨木だが、ひと目見て、大工は「これは使えぬ」と断じる。
945
「この木で家具を作れば壊れ、舟を作れば沈み、棺桶を作れば腐る。なんの用途もない。それゆえに誰にも見向きされず、他の『使える木』が切り倒される中、こいつは生き延びて、神木と崇められるようになったのだ」と。
946
すなわち、人間の視点からすれば「無用」だが、生物の意義、すなわち「より長く生き延びる」という条件では「用」を成している。視点によって様々変わるという話なのだが、この話はさらにもうちょい続きがある。
947
その翌日、大嵐が起こり、地盤が緩み、あちこちで土砂崩れが発生。中には村一つが飲み込まれるなど大被害を及ぼす。だが、神木のある一帯は、神木が何百年もかけて地中に張った木の根のお陰で地盤が固まり、災厄を免れたのだ。
948
その光景を目の当たりにし、大工は改めて、自分の見識の狭さを痛感する。
「使えない使えるの判断だけでは及ばぬ場所がある」
「使えないという選択をすることで生き延びることもできる」
という、「判断」すら一面のものであり、「『無用の用』の用」足り得る事態もある。
949
天然自然の千変万化する世界の営みの中、常に絶対に正しく一切間違いのない「優秀」など存在しない。もしそんなものがあるとしたら、神様くらいなものだ。
神を前程とした条件など、ナンセンス極まりない。
だから、「優生思想」は「非科学的」なのだ。
950
もっと言うなれば、「自分が神様のように絶対に間違いのない常に正解を選択できる」と勘違いした愚か者が陥るのが、「優生思想」と言っても良いかもしれん。
まぁ、そういうことです。