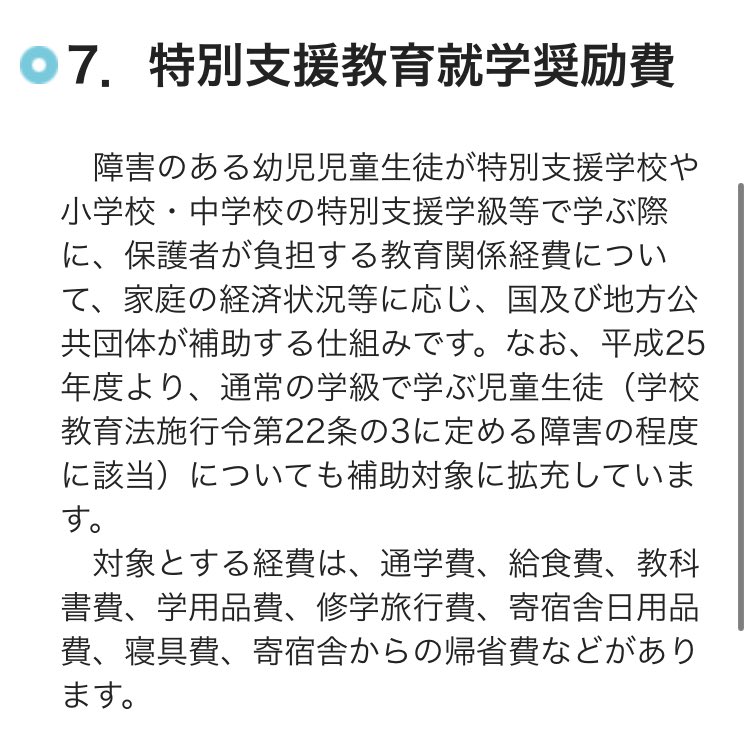26
学校なんてのは子どもにとって「逃げられない場」だからこそ「母の日」をテーマにした授業はしない。感謝の手紙も書かないし、カーネーションの工作もしない。みんなにお母さんがいるわけじゃないし、いても良好かなんて知らないし。「逃げられない場」での傷をできる限り小さくするのも先生の仕事だよ
27
「恐怖で子どもをコントロールする先生」は百害あって一利なし。それに慣れてしまった子どもたちは「こわいかどうか」が話(指示)を聞く基準になってしまう。しかもそんな先生に限って「あなた方の指導は甘いから子どもにナメられる!」とか言い出して白目。負の遺産でしかない。ご退場くださいませ。
29
子ども用ハーネスみたいな一昔前にはなかったあれこれに文句いう人いるけど、あなたに被害があるわけでもなく、ましてやあなたがその子を守ってくれるわけでもないのにね。ヘルメットとなにがちがうの?ライフジャケットとなにがちがうの?手は出さず口だけ出す格好悪い大人にだけはならないでいたいよ
30
「障害」は「生きづらさ」と近い。言い変えると「生きづらさ」が“ない”なら「障害」では“ない”。社会に適応して自立するためのスキルを学ぶことも、社会の理解や受容が深まることもおなじだけ大事。「双方から」障害を薄めて弱めていきたいね。障害のある人にいい社会は、障害のない人にもいいんだよ。
31
土曜に吸収された祝日が月曜に振替えられないのはどう考えても狂ってる。
32
「いじられた」か「いじめられた」か決めるのは「いじった」あなたじゃないからね。ここ、テストに出ます。
33
いろんな物の値段が上がるのに給料が上がらないと「たのしいことにお金を使う」が削られる。これはほんとに良くないよ。みんなの機嫌が悪くなる。
34
仕事の愚痴を書けば「辞めろよ」、配偶者の愚痴には「別れろよ」なんて、最も強い解決法を外野は簡単に提示する。でもそうじゃないでしょう。ここに書く愚痴なんてのは、大抵がしんどい現実を誤魔化しながら、どうにか前を向くための息抜きだ。
おはようございます。
折り合いつけられるのが大人だよ
35
いろんな大人が「かわいいね、かわいいね」って自分のいろんなことを犠牲にして赤ちゃんから大きく大きく育ててくれた子どもたちが、容姿で苦しむことのない社会になりますように。みんなちがって、みんなかわいい。
36
生きててよかった夜は、死にたい夜を越えてきたからあるんだよ。
このむつかしい話わかる?
37
「発達ゆっくり」ってことば。揚げ足取るつもりはないけど、まわりと比べての表現だよね。でも、その子なりには全然ゆっくりじゃないかもよ。たしかに速く走るウサギは格好いいけど、大事なのは完走できるカメになること。ウサギにはウサギの、カメにはカメのゴールがある。カメは自分を遅いと思う?🐢
38
保護者のみなさんは「自閉症の子どもを育てる◯つのポイント」みたいな記事を鵜呑みにしないでね。特別支援学校の先生として、ひとりの子どもを「自閉症だから◯◯の指導」なんて接してない。「◯◯くんだから◯◯の指導」と思ってやってるよ。参考にするのはいいけど、盲信するのは良くないぞー!!
39
子どもを怒る理由が「こっちの思うようにいかない」になってないか気をつけようね。
鳥に海の泳ぎ方を教えませんように。
魚に空の飛び方を教えませんように。
40
特別支援学校、支援学級、普通級に通う障害のある子どもには「特別支援教育就学奨励費」があるよ。支援学校の入学説明会で説明されると思うけど、とりあえず先にいちばん大事なことだけ!子ども関連の買い物はなんであれ
レシート捨てるな
レシート捨てるな
レシート捨てるな
mext.go.jp/a_menu/shotou/…
41
元・明石市長の泉房穂さんが子育て政策や障害者支援に力を入れてる理由を「障害者や貧乏人に冷たい社会への復讐心」と答えてるのめちゃくちゃいいな。めちゃくちゃいい。
42
足りないのは教員免許じゃなくて教員なんだよ。
このむつかしい話わかる?
43
支援学級で友だち関係に悩み、支援学校へと転入した男子。始業してすぐ、同級生で発語のない自閉症男子にくっつくように。「なんでその子が好きになったの?」と聞くと
「絶対ぼくをバカにしたり悪口を言ったりしないし、いつも笑顔だから」
否定も肯定もせず「そこにいる」ことで救われる人がいる。
44
ポジティブでいることより、ネガティブを受け入れられるほうが大事だよ。
このむつかしい話わかる?
45
特別支援学校に通う子どもの多くは
「大丈夫?」と聞くと「大丈夫」
「わかった?」と聞くと「わかった」
と答えちゃうから「やってみて」「説明してみて」と、“子ども本人”に実践しもらうほうがいいよー。おうむ返しラリーで「お、わかってんな!」なんて大人が勘違いしないように気をつけようね。
46
投票に行く理由は「ユポ紙」を触るため。ユポはすごい。名前もかわいい。木材パルプの紙じゃないから、軽い筆圧でもしっかり書き込める。そして破れにくく形状変化も起こりづらい。折り曲げて投票しても、箱の中で元通り。あとなんたって手触りが最高。すべすべツルツル。あぁ触りたい触りたいよユポ。
47
教育が時代に合わせてアップデートされるなら、校訓もそうしなきゃいけないよ。小学校や特別支援学校にありがちな「明るく」なんてワードはもう撤廃しないとね。明るい子どもが暗い子どもより優れてるわけでもなんでもない。明るい子と超明るい子を比べたら前者は暗い子なの?もうやめましょ令和だよ
48
「適応障害に気をつけよう」なんて簡単にいうけど、気をつけるのは(適応障害になりそうな)「当事者」だけでいいの?異動してきた人、あたらしい人にやさしく声をかけたり、強引にでも無理させず休息を与えたりして「まわりの人」が防いであげられる環境をつくろうよ。これは“みんなの”問題でしょ?
49
そこそこのストレスと引き換えに、衣食住と健康を維持できる給与がもらえてるのに「これは天職だろうか」と必要以上に「やりがい」に目を向けて悩むのは脳みそのバグだから覚えといてね。自己実現や自己肯定感は、仕事以外でも育める。
おはようございます。
天職かどうかより、食えるかどうか。
50
障害のある子どもを産んだお母さんや育てる家族は「特別に強い人間」でもなければましてや「神様に選ばれた人間」でもない。大変なあれこれは「あなたなら乗り越えられる壁」なんて綺麗事じゃない。ふつうのお母さんとふつうの家族に産まれたこの子が、社会で生きてけるようにふつうの先生が手伝うぞ。