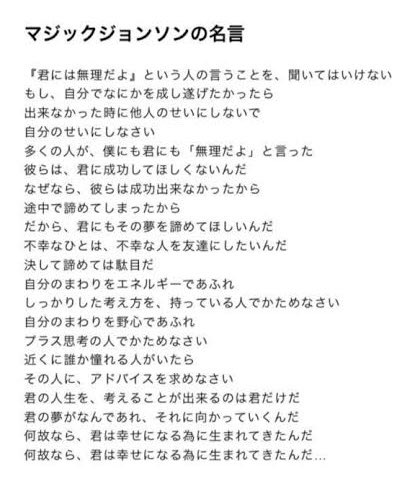51
52
サタデーステーションのスポーツコーナーを見ていた。まず紹介されたのは大谷選手の活躍。そして今日行われたプロ野球。さあ来るぞーと思っていたけど、そこでスポーツコーナーは終わり。さっき終わったばかりのホカホカのJリーグが放送されることはなかった。忘れていたけど、これが今のJリーグの現実
53
この世代の頂点を決めるオリンピック決勝。そしてブラジル対スペインの好カード。それがライブではなく、ディレイでの追いかけ放送。これがいまの日本におけるサッカーの立ち位置なんだろうな。まず向き合わないといけないのは、ここだろう。日本人にとってのサッカーはどれほどのものか。
54
56
先日J1初ゴールを決めた小泉佳穂選手@30_YOSHIO も新人一年目はメンバーに入ることができず、運営のサポートをしてくれていた時もあった。そこでも腐らず、内なる闘志を燃やし、ピッチ上で表現し続けた先に今の姿がある。沖縄に愛された彼の活躍を誰しもが喜び、誇りに思っている。
57
Jリーグを見ていて、何がきっかけでサッカーにハマるかわからない。うちの息子なんかは選手はあんまりわかってないけど、チャントやコールを口ずさんでいる。ゴール裏の住人たちがスタジアムに作り出す雰囲気は、子供がスタジアムに行く理由のひとつであり、選手同様に夢を見させる存在である。
58
部下に「営業取ってこい」っていうのは簡単だけど、それって監督がFWに「シーズンで30点取れ!」って言ってるのと同じだなって気づいた。上司が監督と同じだとすると、やっぱり戦略を練って、勝たせ方を考えないといけない。ゴールを決めるのは、選手だけど、監督には監督の役割がある。
59
「サッカーが強いから、街に応援される」とはならないかもしれないが、「街に応援されるから、サッカーが強くなる」は大いに当てはまると思う。
60
昨日、三ツ沢で見た鹿島アントラーズのゴール裏はすごかった。昔、天皇杯で鹿島と筑波大学が試合したときに感じた地鳴りのような応援を思い出した。鹿島のファンはサッカーを見たいだけじゃなく、鹿島アントラーズそのものを見たいんだなと痛感した。
61
「サッカーが強いから、街に応援される」とはならないかもしれないが、「街に応援されるから、サッカーが強くなる」は大いに当てはまると思う。
62
ファンサポーターの心が離れるのは、負けた時でも降格した時でもなく、「ガッカリした時」なんだと思う。たとえ負けても鬼気迫る表情で次に向かう選手たちにガッカリすることはない。ファンサポーターは本当によく見ている。
63
無観客をやってわかったこと。Jリーグは見るものではない。正確に言うと、映画や小説のようにエンディングが決まっているものを静かに見ているものではないという意味。見るものではなく、参加するもの。ホームゲームという作品はプレーする選手だけではなく、多くのファンサポーターの参加で成立する
64
65
Jリーグを見ていて、何がきっかけでサッカーにハマるかわからない。うちの息子なんかは選手はあんまりわかってないけど、チャントやコールを口ずさんでいる。ゴール裏の住人たちがスタジアムに作り出す雰囲気は、子供がスタジアムに行く理由のひとつであり、選手同様に夢を見させる存在である。
66
やべっちFCとスパサカの終焉を見て、自分たちの育ってきた日本サッカーが変わっていくのを感じる。海外やアジアに目を向けるのは大事かもしれないけど、今こそ「日本人に愛されるJリーグ」を見つめ直さなければならない。
67
Jリーグで検証してみたい仮説「毎年ユニフォームを購入し、ほぼ全ての試合を観戦するコアサポーター層が、顧客の紹介つまりスタジアムに人を連れてくることに貢献できていない」一方でクラブが満足度を上げようとしているのは、コアサポーター層。ここでギャップが生まれているのではないかと見ている
68
平日の観客動員数が一気に減るJリーグと比べて、平日も休日も動員数はほとんど変わらないプロ野球。この違いはエンタメの楽しみ方にあると思う。仕事の都合で開始時間に間に合わなかったとしても、野球はそこまで見逃した感覚になることはないけど、サッカーは一気に置いてかれた感じがある。
69
清水エスパルスに加入したGK権田修一は試合前に審判の名前と年齢を必ず確認する。昨年までプレーしていたポルトガルリーグで、選手たちは審判を「レフェリー」ではなく、名前で呼んでいた。「『さん』付けして呼ぶだけで印象は違う。審判も人間なので感じ方が変わるはず」asahi.com/articles/ASP3K…
70
好きなスポーツだから、給料は安くても、長時間働いても、休日がなくても問題ない。こんな情熱の搾取が、この業界で起きていては夢の仕事になりません。いつか子供たちの目指す夢の仕事に、スポーツ選手だけではなく、スポーツクラブで働くフロントスタッフがノミネートする日を夢見ています。
71
本当にファンになってくれる人を集客する。プロスポーツにおいて、無料招待券という劇薬がまかれた土壌で芽を育てることは並大抵のことではない。目先の数を追うことで、失う未来が大きすぎると感じている。そして招待券に慣れてしまったお客様は全体の雰囲気と質を下げてしまう傾向にある。
72
無観客をやってわかったこと。Jリーグは見るものではない。正確に言うと、映画や小説のようにエンディングが決まっているものを静かに見ているものではないという意味。見るものではなく、参加するもの。ホームゲームという作品はプレーする選手だけではなく、多くのファンサポーターの参加で成立する
73
74
「周りの環境やチームメイトは一切関係ないです。全部自分にベクトルを向けてください。そうすれば、その気持ちを持って1日1日頑張れば、必ず道は拓けます。そして、周りが助けてくれます。」
この感覚をチームで一番上手い選手が持っていることで、チームの哲学に浸透していく。組織は上が引っ張る。
75
中村憲剛選手の言葉に凝縮される哲学。「Jリーガーというのは、お金を稼いで、いい車に乗って、いいものを買って、サッカーをすればいいと、入る前に思っていました。けれども、このクラブに入って、そうではないことに気づかせてもらえました。『川崎市の皆さんを笑顔に、元気にする』という合言葉。