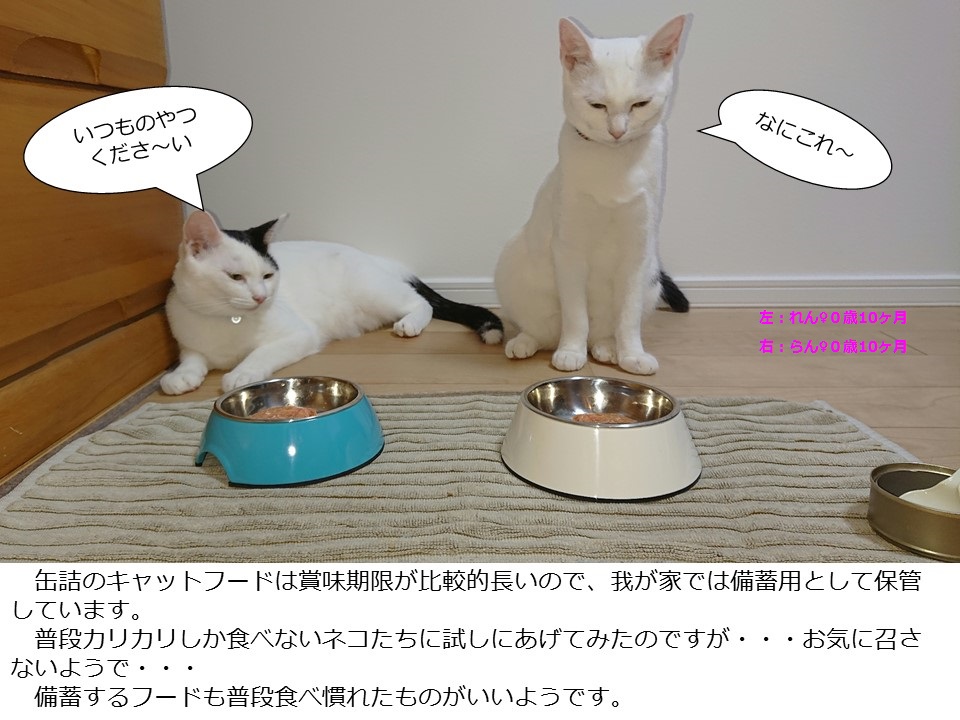1351
台風が複数発生したのを見て、ふと「合体して大きくなって近づいてきたらどうしよう」と心配になり調べました。結論から言うと基本的には合体しないとのこと。ただし、お互いの回転速度で反発や干渉をしあうので複雑な動きになり、進路の予測が難しくなるようです。こまめな情報収集が重要になります。
1352
夏の時期、火気を使用せず簡単に温水ができる方法を紹介します。ペットボトルに水を入れて黒色のビニール袋等で包み、陽があたる場所に置いておくだけで水が温水になります。調理やシャワー等に使えるので、災害時、電気・ガスが使用できないとき役に立つと思いますので参考にしてください。
1353
#逃げなきゃコール をご存知ですか。大切な人が暮らす郷里等を登録しておくと、災害の危険が迫った時に通知が届くというもので、離れた家族に直接電話で避難を呼びかけることができるアプリです。コロナ禍で帰省できなくても、離れて暮らす大切な家族をあなたの一言で守ることができます。
1354
今年も大雨等による災害が各地で相次いでいます。地球温暖化の影響で災害が激甚化していると言われており、大雨の発生頻度は増加傾向にあるそうです。「今まで大丈夫だった。」といった経験則を過信することなく、状況によっては、避難指示を待つことなく早めの避難を心掛けてください。
1355
今年も各地で大雨が続いています。大雨の時、冠水場所を車で走行するとエンジン吸気口への浸水等が理由で車が止まってしまいます。更に水嵩が増すと水圧で車から出られなくなり危険です。大雨に遭遇したときは、冠水しやすいアンダーパスや高架下等周囲より低い場所には進入しないようにしましょう。
1356
1357
私は、非常用持出袋に虫除けグッズを入れています。この暑さで蚊も少なくなりましたが、種類によっては11月頃まで活動します。蚊は水溜まりやジメジメした場所を好むため災害現場や避難所等で注意が必要です。シールやリング等様々な虫除けグッズがありますので、備蓄品に加えてみてはいかがですか。
1358
小学生の娘が「和式トイレで用を済ませる事ができなかった。」と言うので自宅で練習してみました。避難所となる都の公立小中学校のトイレは、約70%が洋式トイレではあるものの膝が悪い人等の需要があり、避難者で列になってしまうことも予想されます。和式トイレも使用することが出来れば安心です。
1359
最近よく新聞、ニュースで「観測史上最も」というキーワードを聞きます。気象庁では1951年から降水量、風速等を約1300カ所で観測しているそうです。このキーワードが出るということは、今までに経験したことのない大雨や大雪が降る可能性がありますので、早め早めの避難を心掛けてください。
1360
1361
1362
毎年8月30日から9月5日は「防災週間」(9月1日は「防災の日」)です。本週間中は、固定電話や携帯電話はもちろん、公衆電話からも「災害用伝言ダイヤル171」を体験することができます。皆さんもこの機会に是非、ご家族と一緒に使用方法を確認してみてください。
1363
てるてる坊主で晴れを祈る風習は、中国から伝わったそうです。本来なら顔はのっぺらぼうで、願いが叶ったら必勝ダルマのように顔を描き入れるそうです。雨が降ってほしいときは、逆さに吊るすか黒くするのだとか。これ以上大雨が降らないよう、てるてる坊主に願掛けしようかと思う、今日この頃です。
1364
1365
1366
先日、息子(小4)のガ〇ダムのプラモデル作りに、カッターを使わせました。最近「ナイフで鉛筆が削れない人が増えている」と聞きますが、災害など困ったときに役立つ重要アイテム。小さい頃から、大人の目が届く範囲で正しい使い方の練習をさせたいですね。
1367
1368
1369
休日に息子と気象科学館へ見学に行ってきました。波浪と津波を模擬的に発生させる津波シミュレーターや気象現象のメカニズムなどが体験できる体感シアターなど、楽しみながら防災について学ぶことができました。みなさんもご家族と一緒に、命を守る行動を確認してみてはいかがでしょうか。
1370
1371
今日は「マッチの日」だそうです。そこで災害時におけるマッチの活用方法について、ご紹介したいと思います。マッチは擦った時の臭いが強いので、災害時にトイレの水が流せなくなり、不快な臭いが、気になった時にマッチを擦ることにより不快な臭いを軽減することができますので、参考にしてください。
1372
災害時にも使用する乾電池。実は使用済み乾電池にもまだ電気が残っており、電極同士の接触で電気が一気に流れ、短時間のわずかな電流でも破裂や出火の危険があります。捨てるときは電極を完全に塞ぐようにテープを貼り、二次災害を防ぎましょう(捨てるときは自治体のルールを確認してください。)。
1373
1374
7年前(平成26年)の今日、長野県御嶽山が噴火しました。土曜日の昼食時、見晴らしのいい山頂付近に集まっていた多くの登山者が被災しました。登山時は、もしもに備えて天候だけでなく火山情報・避難ルートの確認や防災用品の準備などを忘れずに。過去の災害の記憶を風化させないようにしましょう。
1375
日頃の備えや訓練が、いかに減災に大切か!災害の疑似体験で部屋の明かりを消し、懐中電灯で着替えや非常持出袋を背負い、渋る家族をなだめながら雨の夜道を指定避難所まで歩きました。体験すると家族も真剣に物事を考えるようになり、不足品の準備など我が家の避難ルールがより現実的になりました。