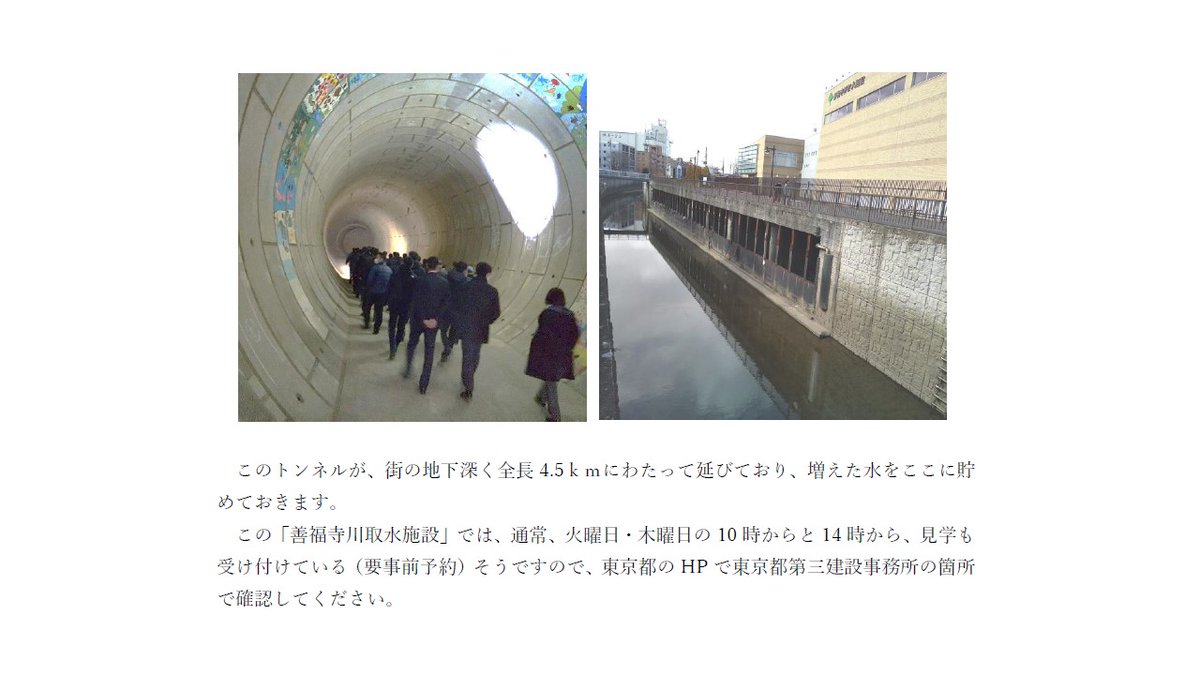1026
寒さで体が震えて、歯がカチカチとなる現象をシバリングと呼びます。これは脳が無意識に行わせる防衛本能の一種で、下がった体温を上昇させるために平常時の数倍の熱量を一時的に産出できるそうです。冬の避難所等、シバリングの起きる前にこれまでご紹介してきた防寒対策を実践していただければ。
1027
1028
1029
1030
1031
津波被害が多い三陸地方で「津波起きたら命てんでんこだ」と伝えられてきました。これは「津波が起きたら家族が一緒にいなくても気にせず、てんでばらばらに高所に逃げ、まずは自分の命を守れ」という意味です。今日で東日本大震災から9年を迎えました。この教訓に基づき命を守る行動を取りましょう。
1032
1033
新年度が近づき、引っ越し等で今までとは違う場所でスタートを切る方も多いかと思います。入居の手続きと合わせて、是非、家具の転倒防止など屋内の危険防止措置を早いうちに行い、新居周辺の避難場所や給水拠点、ハザードマップを市区町村のHPなどで確認するなど災害に備えましょう。
1034
1035
水道水は塩素の効果で雑菌等の繁殖を抑え、常温で3日、冷蔵庫で10日程度(飲用)保存できます。また浄水器を通した水や白湯は塩素の効果が弱まるため長期保存(飲用)には不向きです。災害時の飲用水は長期保存が可能な市販のもの、生活用水は水道水の汲み置きを利用する等、備蓄の参考にして下さい。
1036
1037
1038
気象庁から発表される警報のうち大雨警報と洪水警報の違いをご存じですか。大雨警報は大雨により土砂災害や住宅等への浸水のおそれがある場合。洪水警報は河川の増水・氾濫や堤防の決壊等のおそれがある場合に発表されます。警報の種類に応じて注意すべき事を理解し、早目の対応を心掛けましょう。
1039
1040
1041
東京都の公式動画サイト「東京動画」内で紹介された、当課のツイート動画8本を「YouTube警視庁公式チャンネル」にアップしました。10円玉を使った袋の開け方等、災害時などに役に立つ動画ですので、ぜひご覧ください。youtube.com/playlist?list=…
1042
1043
1044
1045
予報で耳にする「時々雨」と「一時雨」。違いが曖昧だったので気象庁HPで調べると、「時々」は断続的な雨で降雨時間の合計が予報期間の1/2未満、「一時」は連続的な雨で降雨時間の合計が同じく1/4未満だそうです。いまいちピンときませんが、「時々」の方が長く降るようです…jma.go.jp/jma/kishou/kno…
1046
今年は花見の自粛を求められましたが、川沿いに桜が多い理由を知っていますか?江戸時代には、大雨が降り、川が氾濫することもしばしば。そこで、土手に桜を植えることにより、毎年多くの人が花見に訪れ、自然と土手を踏み固め増水に耐えられる土壌を作ったそうです。先人の知恵には感心させられます。
1047
1048
緊急事態宣言が発令され、私たちは、かつて経験したことのない脅威にさらされていることを再認識しなければなりません。新型コロナウイルスの脅威も様々な災害の脅威も、一番大切なことは命を守ることです。今何をしなければならないかを考え、力を合わせてこの難局を乗り越えていきましょう。
1049
緊急事態宣言の発令により、これまで以上に自宅で過ごす時間が増えることと思います。在宅中に災害が発生した場合への備えは万全ですか。家具の倒壊やガラスの飛散、停電への対応など、事前の準備によって被害を減らすことも可能です。自宅にいる機会に災害への備えも進めていただきたいと思います。
1050
⚡️ "警視庁災害対策課ツイートまとめ⑤(在宅中の災害の発生に備えて自宅でできること〔パート1〕をまとめてみました。)"
twitter.com/i/moments/1247…