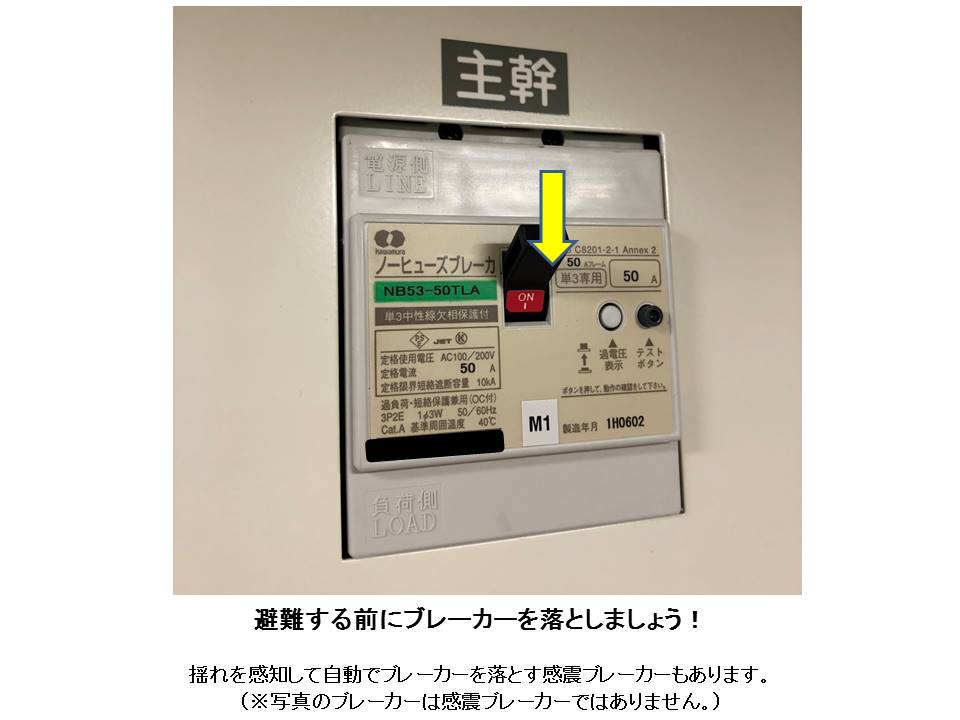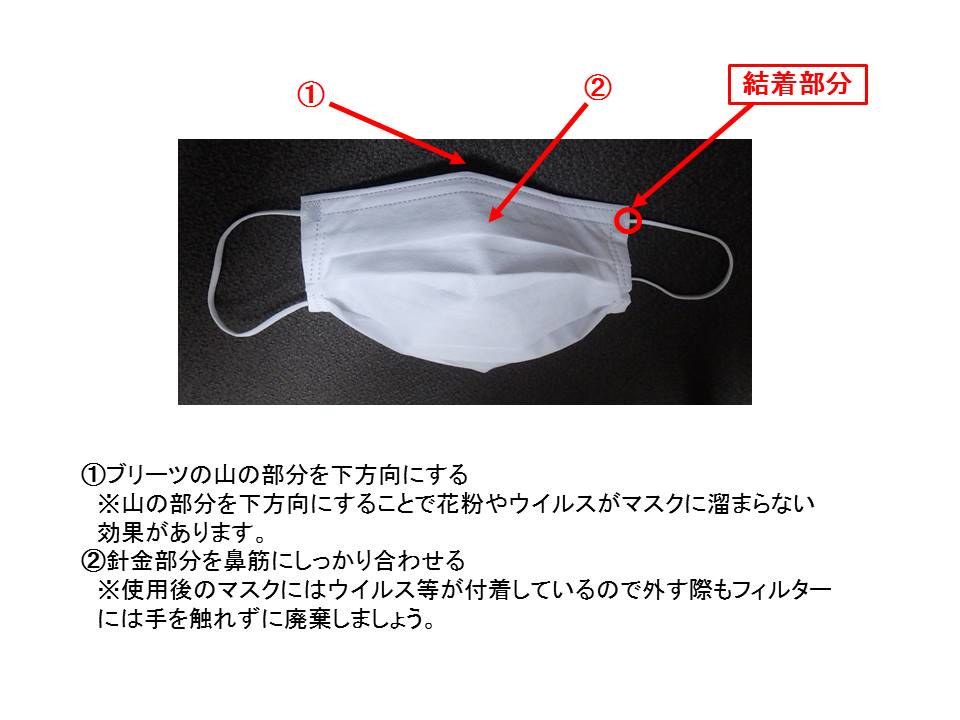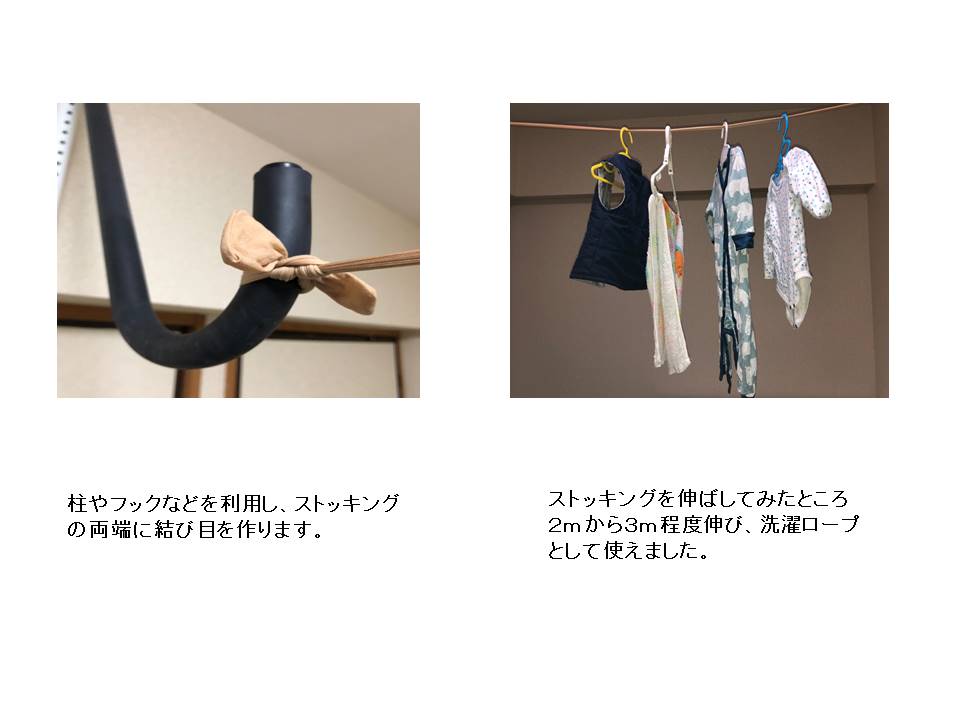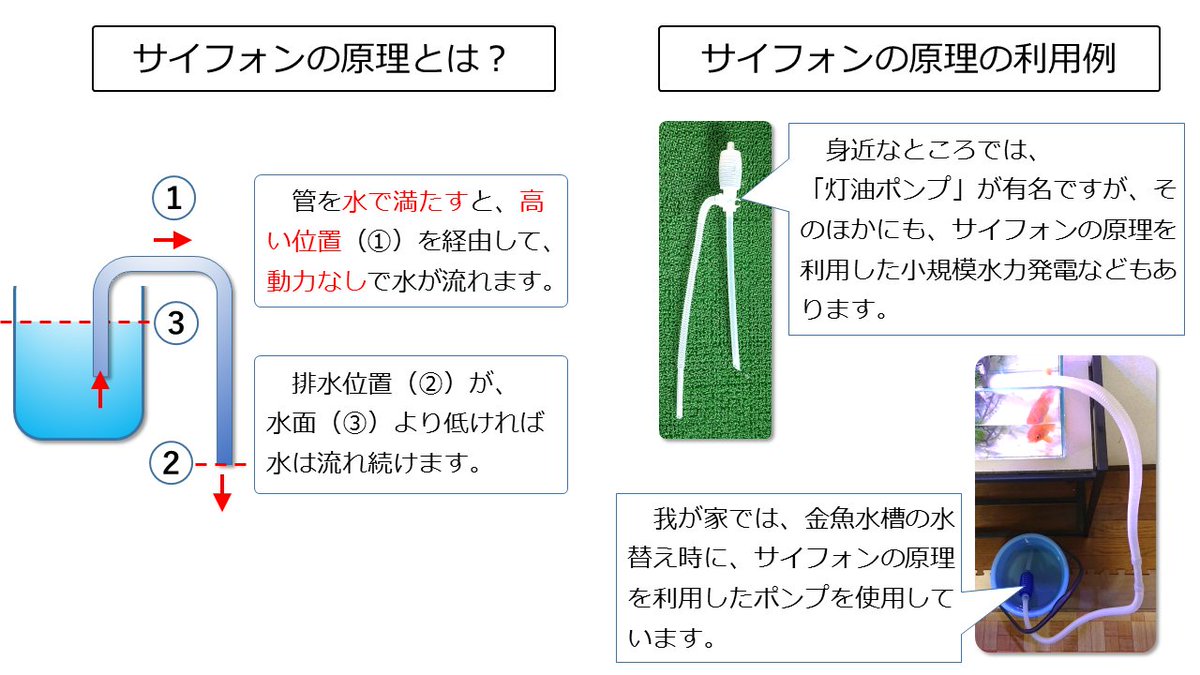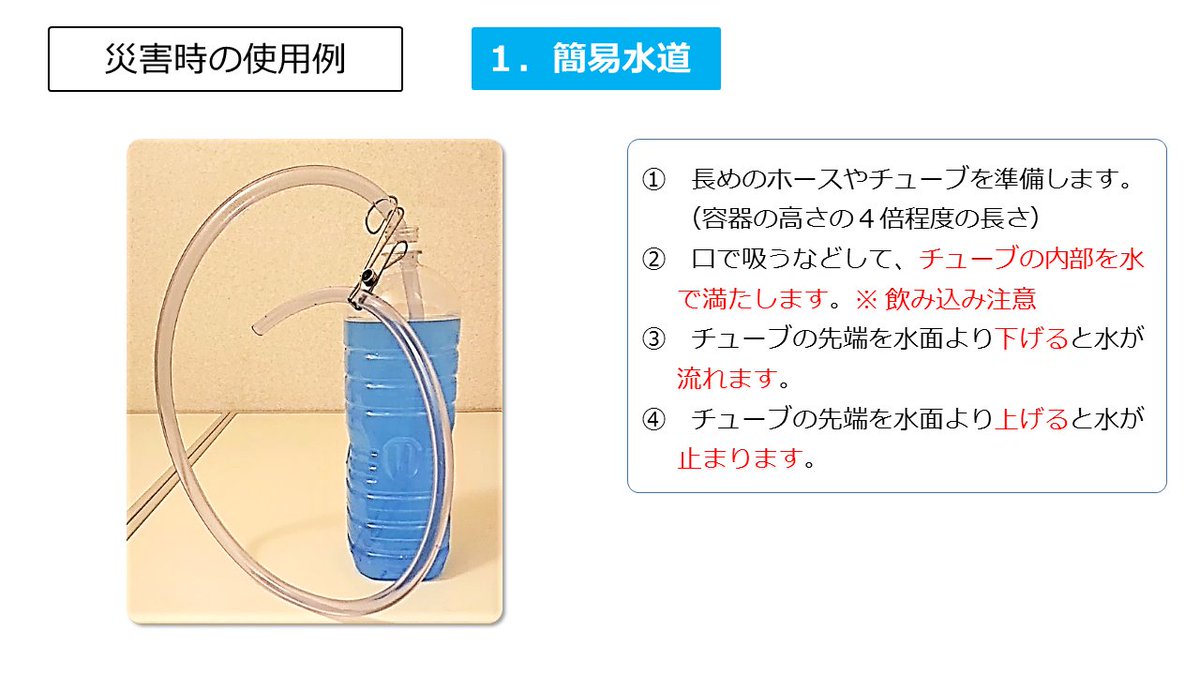376
377
378
379
380
381
警視庁広域緊急援助隊の部隊は、7月10日(土)から熱海市の土石流被害現場において、救出救助活動を行っています。降雨状況はないものの、強い日差しの中で、暑さと戦いながらの活動となっています。安否不明となっている方々の一刻も早い発見のため、部隊員一同、力を合わせていきます。
382
383
384
先日、晴天で空気が乾燥した日に非常持ち出し袋内の衣類を薄手のものに入れ替えました。雨天時や湿気の多い日に入れ替えると、湿気も一緒にしまい込みカビの原因になると言われています。入れ替えのタイミングは、天候の善し悪しがポイントですので、是非梅雨入り前に行っておいてください。
385
386
阪神淡路大震災の発生から25年。就寝中の方が多い早朝の時間帯での発生であったため、亡くなられた方々の死因の多くが家屋等の倒壊による窒息死・圧死でした。また、負傷原因の多くは家具の転倒や割れたガラスによるものです。家具の固定やガラスの飛散防止等、減災に向けた事前対策をお願いします。
387
388
我が家では、非常用の保存水と一緒に水で溶ける粉末ドリンクを備蓄しています。粉末ドリンクは、お茶、コーヒー、スポーツドリンクなど種類が豊富で、水さえあれば手軽にいろいろ味を楽しむことができます。また、不規則な生活で不足しがちな栄養素を補給できるものもあるので参考としてください。
389
390
391
赤ちゃんがいる家庭に必ずある赤ちゃん用のお尻拭きシート。赤ちゃん用に作られているため肌に優しくシートは厚手で沢山入っています。お風呂になかなか入れず、温水洗浄便座も使用できない避難所等でとても役に立つと思います。災害備蓄用品として加えてみてはいかがでしょうか。
392
393
394
395
#国際緊急援助隊 として、トルコ共和国において捜索救助活動に従事した災害対策課特殊救助隊員8名と警備第二課員5名(警備犬4頭)、通信職員1名については、昨夜、無事に帰国しました。数多くの応援メッセージ、本当にありがとうございました。派遣者・関係者一同、心から御礼申し上げます。
396
防災グッズの一品にぜひ入れてほしいものがあります。それはビニール袋です。大小のレジ袋やゴミ袋など、種類の違う袋があると、用途に応じて使い分けができるので便利です。例えば調理や雨具(防寒具)などに利用できるだけでなく、ケガをしたときの応急手当にも活用できますよ。
397
災害時、給水所から水を運ぶ容器などを準備していますか?通常、ポリタンクなどの容器に入れて運ぶと思いますが、容器がない場合の知恵として、阪神・淡路大震災で被災された方の経験から、バケツの中にビニール袋を入れ、その中に水を入れた後、袋の口を結べば水がこぼれることなく運べたそうです。
398
以前、災害時の食品用ラップの活用について紹介をしましたが、「アルミホイル」もまた有能です。重ねて使用すれば火にかけられるフライパン代わりになりますし、食器にもなります。また、丸めて使用すればたわしにもなります。様々な活用方法がありますので、ぜひ災害への備えの参考にしてください。
399
400
使わなくなったオムツを処分しようとしていた矢先に、妻が防災講習会でオムツを使った簡易トイレの作り方を教わってきました。作り方はレジ袋の中に開いたオムツを入れれば完成!災害時やゴールデンウィークでの渋滞中の車内などでも使えそうです。オムツの代わりにペット用のシーツでも代用可能です。