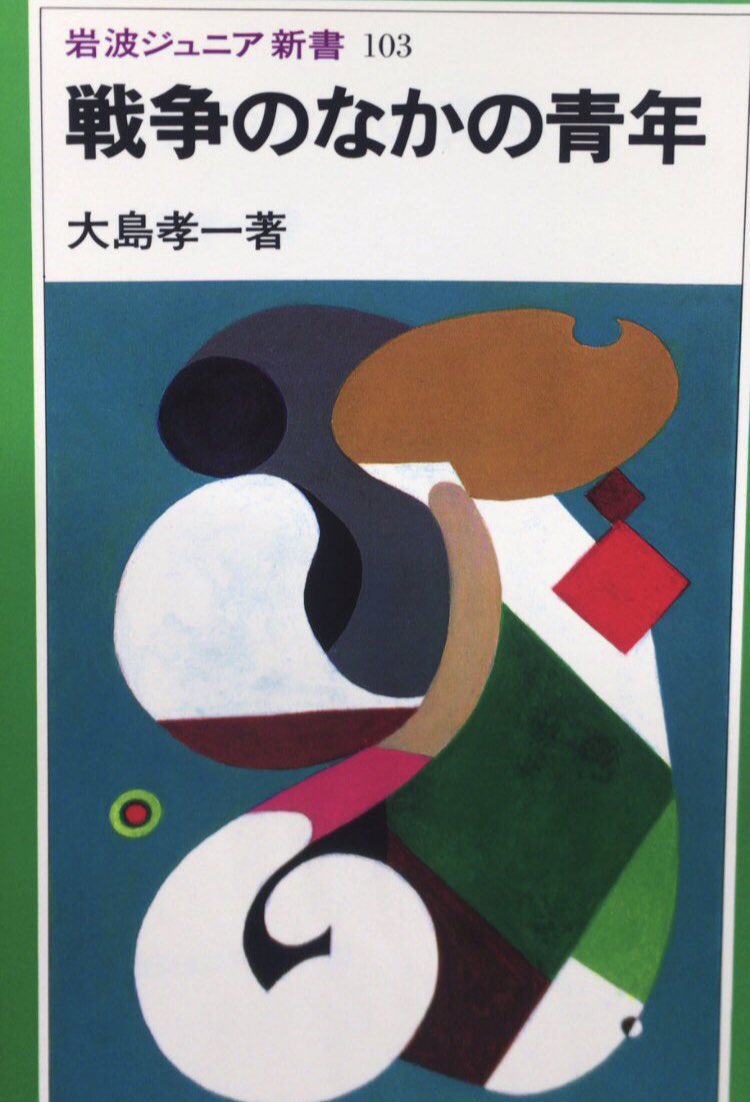801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
「人生って無理せず自然でいいんですよ。自分の立ち位置ってものもそうだよ。人との出会いを大事にして、流れに身をまかせていれば、きっといい巡りあわせがあるんじゃないかな」(文春オンライン、2018/9/2)
関連作品:『高木ブー画集 ドリフターズとともに』↓
amzn.to/3yUKxsh
815
816
817
「いったん戦争がおこってしまうと、戦争に異議をとなえることはたいへんむずかしく、戦争に協力するしか道は残されていない。そして、戦争に協力しているうちに、やがてみずから率先して積極的に戦争を推進するようにもなってゆくのである。」(『戦争のなかの青年』岩波書店、P5)
#国際反戦デー
818
819
820
821
822
823
824
825