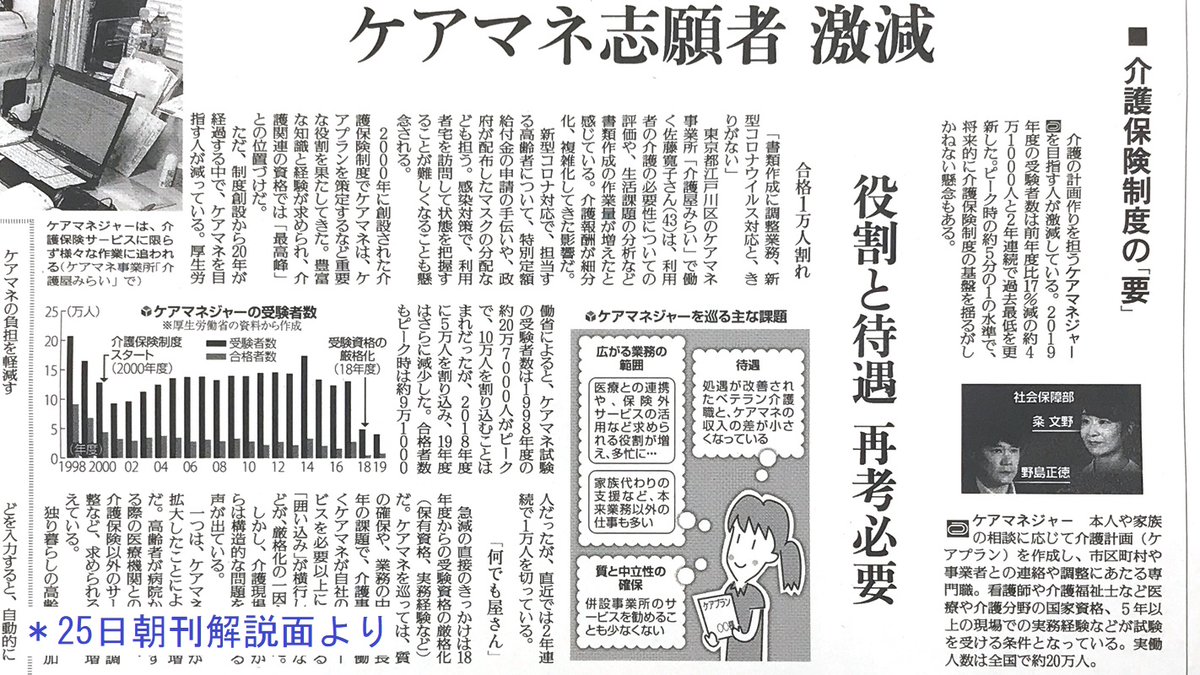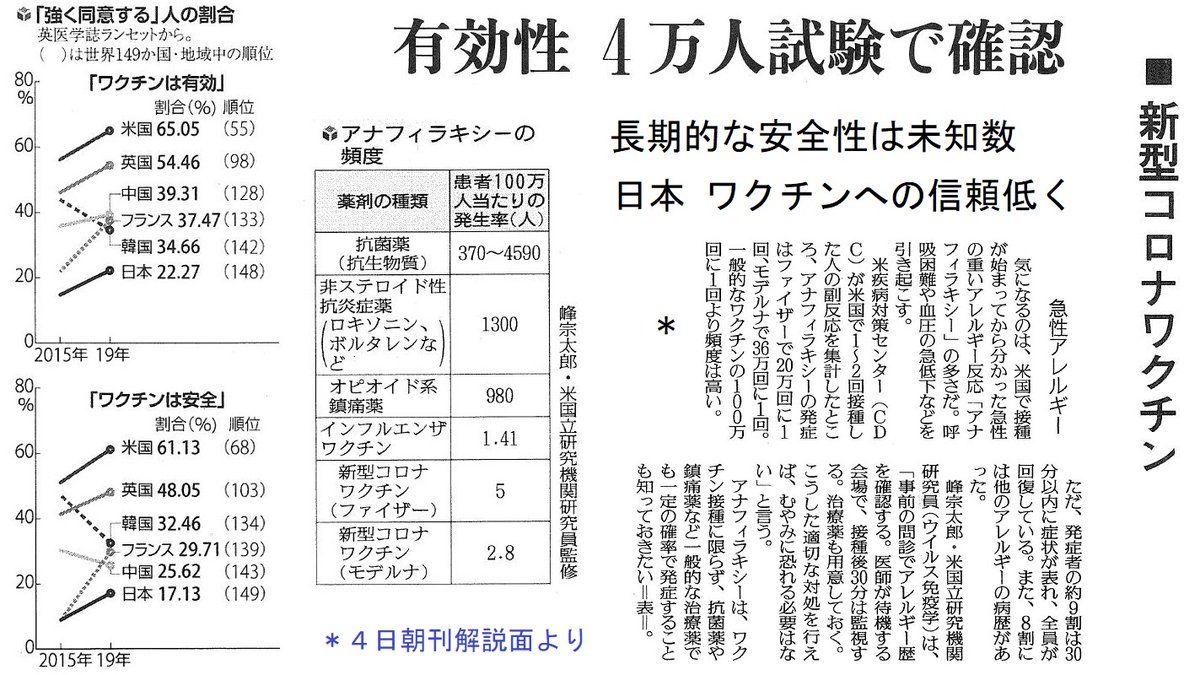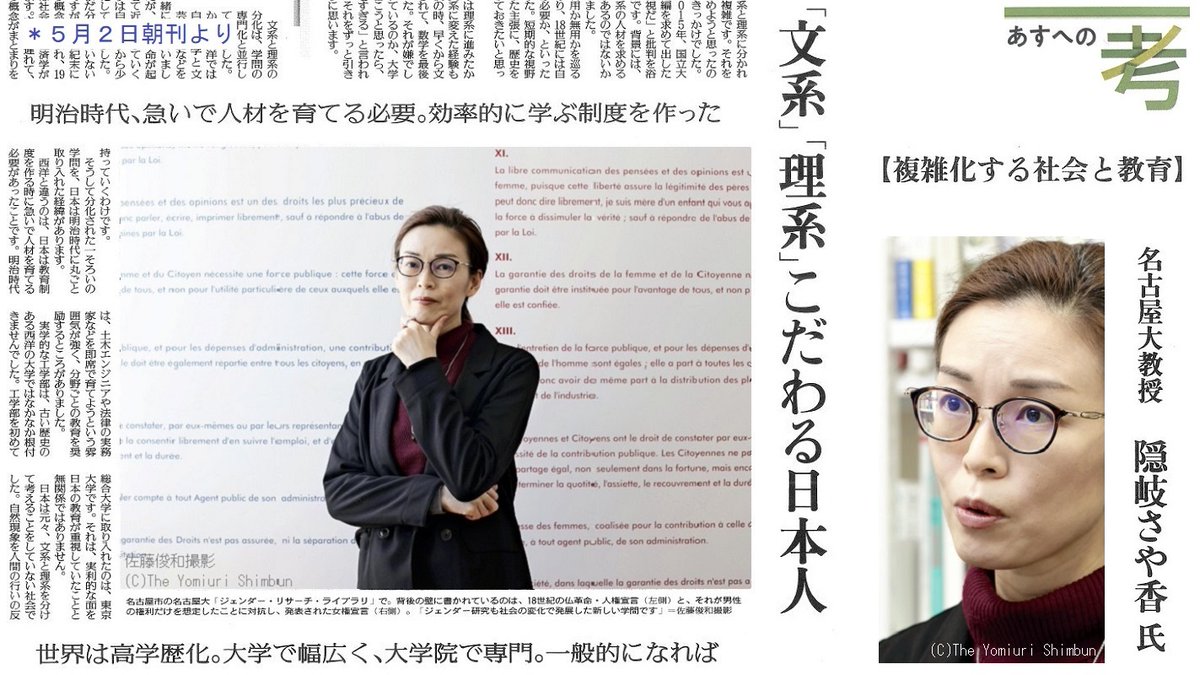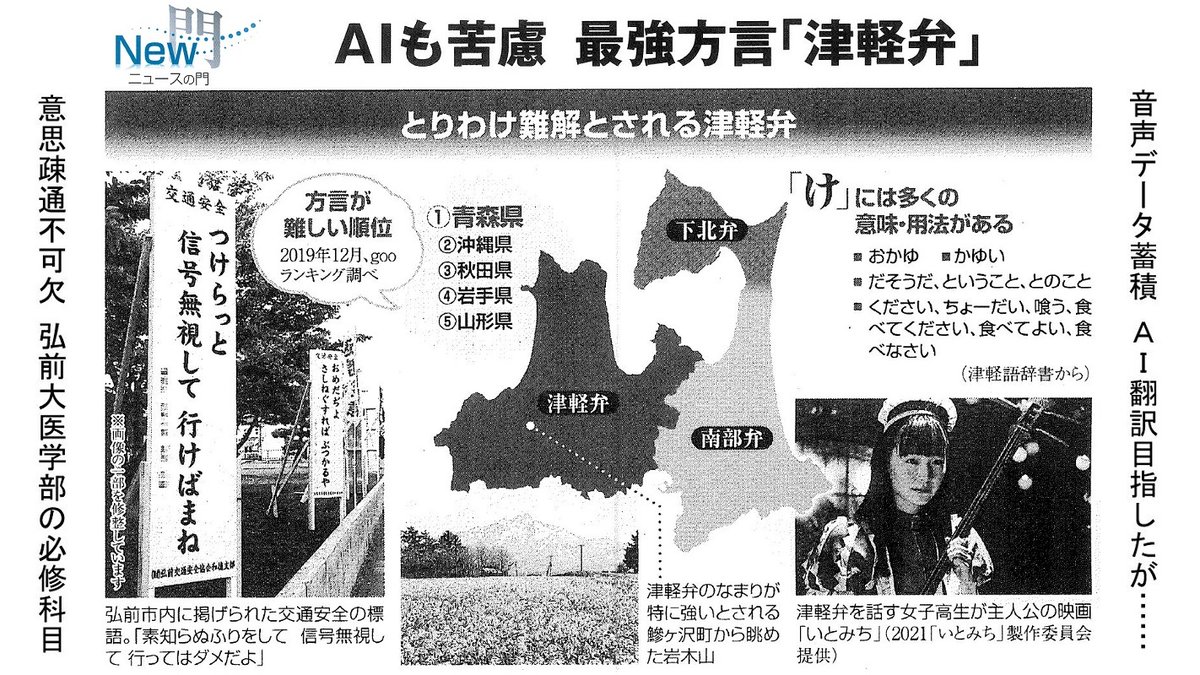26
27
28
29
本日朝刊「デジライフ面」でも紹介していますが、初音ミクと、声優・歌手の小倉唯さんが、読売新聞のコラム「編集手帳」を朗読する動画が、本日27日早朝にアップされました。下のURLをタップして、ご視聴ください。(東)
youtube.com/user/YomiuriOs…
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50