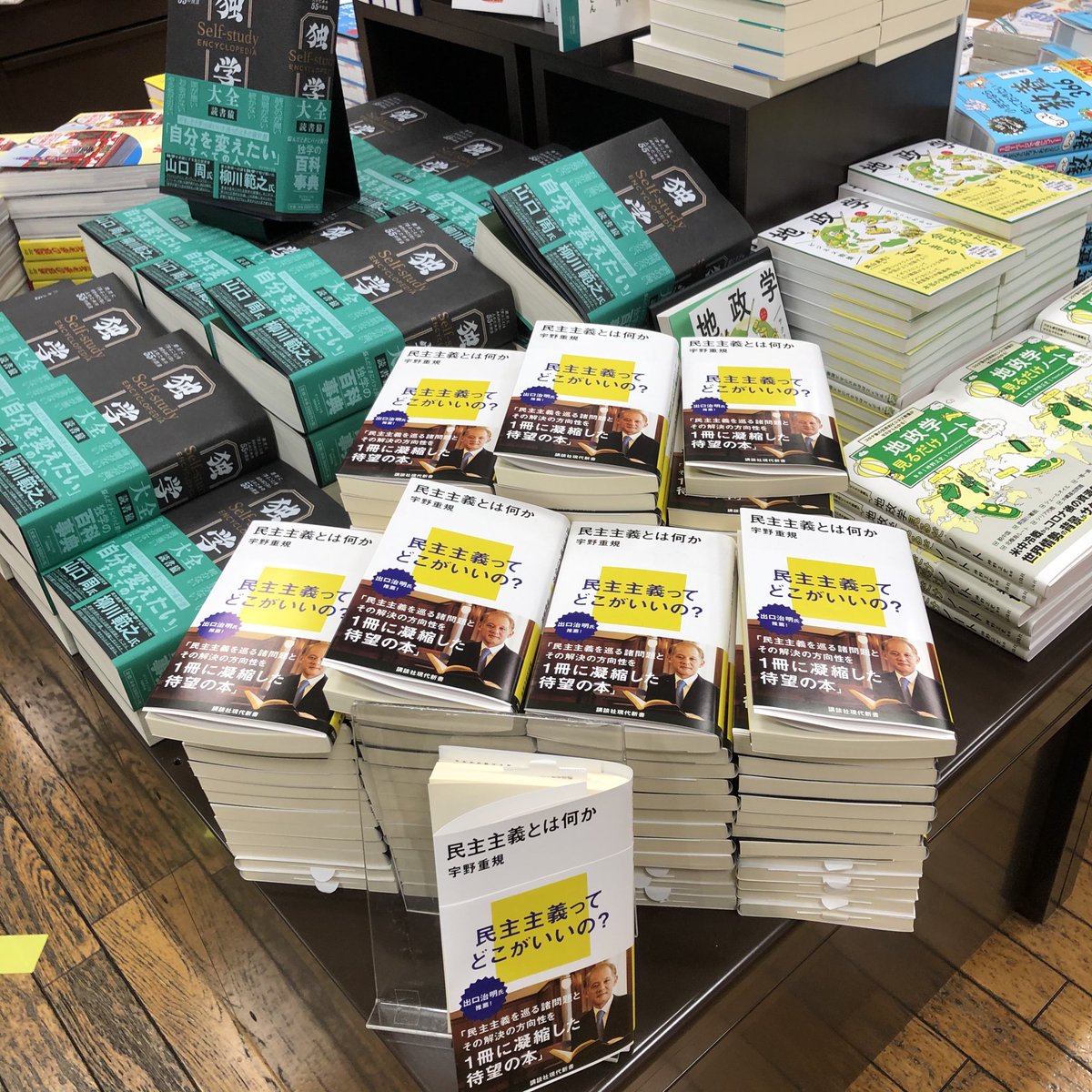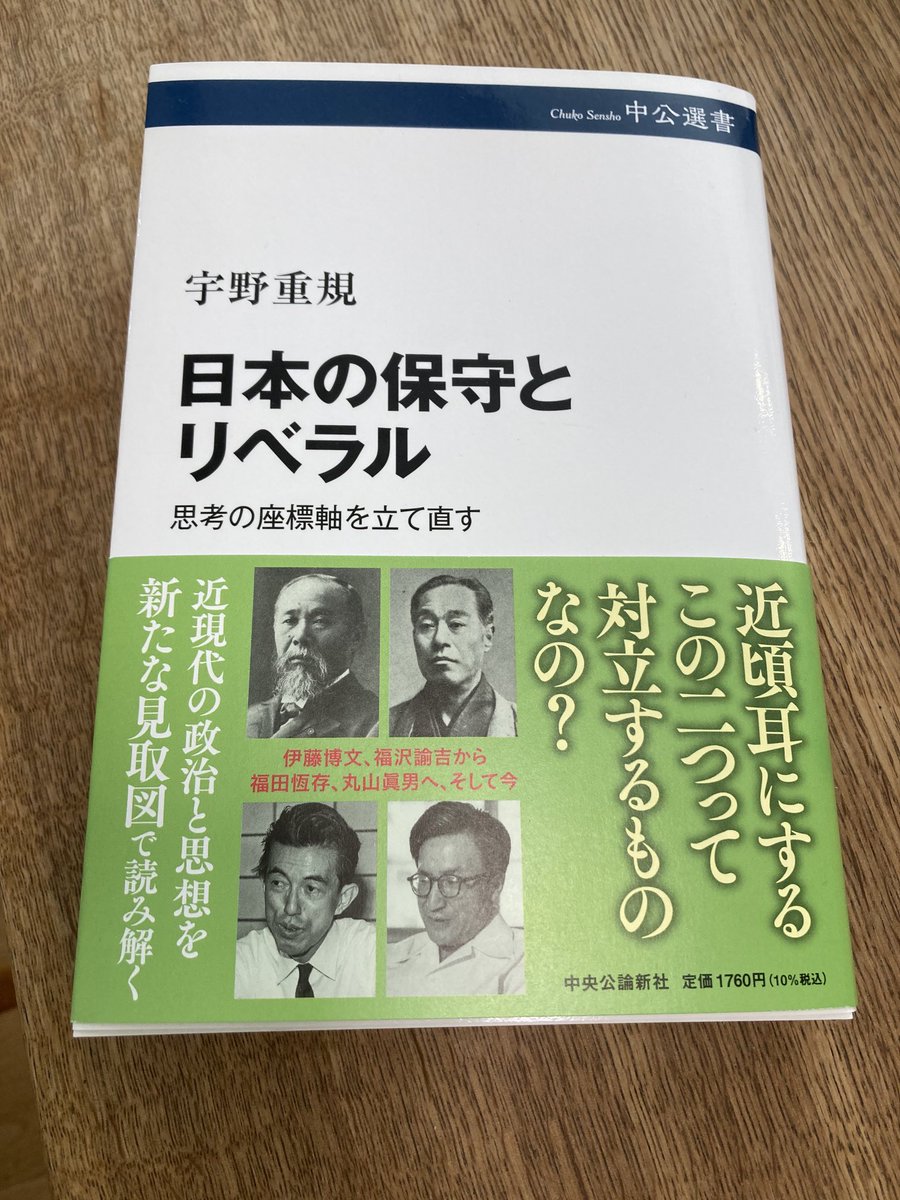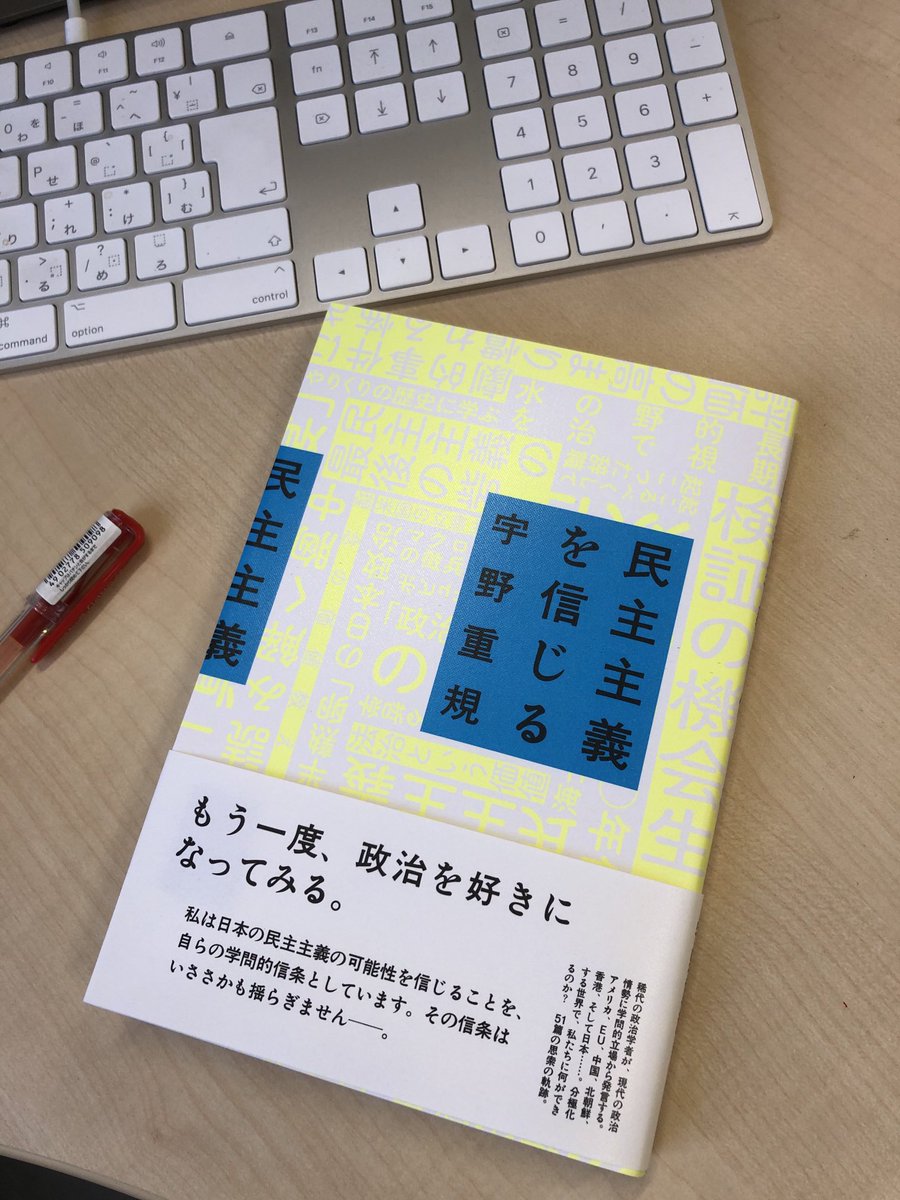1
先ほどいただいたメールに「お変死をいただき、ありがとうございます」とあった。昨年の「いつも大変になっております」と並ぶ大ヒットだ。
2
自分が信じていた何かが音を立てて崩れる瞬間がある。そういうときに「みんな嘘だった」と投げやりにならず、どう立て直していくかを冷静に考えるのも知性の底力だろう。
3
今日いただいたメールの冒頭に「いつも大変になっております」とあった。いや、わかります。いつも大変ですよね。
4
いまさらかもしれないけど、選挙に行こう。
現在の仕組みがベストではないことはわかっている。
それでもここを乗り越えないとどうにもならない。
みんなで前に進もう。
5
人に「そろそろ出してもらわないと困るんですよねー」というメールを書いた30秒後に、今度は自分に来た催促メールに「出せないものは出せないんだな、これが」と居直っている自分をたいへん罪深く思います。人間は矛盾に満ちた存在です。
6
憲法12条はとても面白い。憲法の人権の規定は本来、国家によっておかされてはならない個人の人権を規定しているはずだ。が、この条文では「不断の努力によって保持しなければならない」と国民の努力を促す。ぼおっとしていたらいけないよ、と言っているようだ。
7
仕事納めというけれど、メールを見ていると、「1月4日提出」「1月5日正午厳守」「必ず連絡を」といった言葉が並ぶ。日本から正月休みという観念はなくなってしまったのだろうか(泣)。
9
菅首相の退陣についていろいろ思うところはあるが、政党政治の原則からすれば、それまで政権を担った首相の下で、その間の業績について国民の審判を受けるのが筋だったと思う。
11
民主主義とは何か (講談社現代新書) 宇野 重規 amazon.co.jp/dp/4065212952/… @AmazonJP
12
フランスの哲学者ジャン=リュック・ナンシーが亡くなった。最近では言及することが少なくなったが、昔とても影響を受けた思想家の一人だ。人が共同体を作るのは、何かあらかじめ共通の属性や本質があるからではない。共有するものが何もない人々がそれでも共にいることーーその意味を考えていきたい。
13
朝日の朝井リョウさんの文章がいい。「同性婚合法化は少子化に拍車をかけるなんて根拠のない論を振りかざす前に、性的指向によって人生の選択肢が増減しない社会の構築を目指したい。そんなに育休をとられたら迷惑だと訴える前に、誰が欠けても補い合える働き方を構築したい」digital.asahi.com/articles/DA3S1…
14
ドイツの学生と丸山眞男の「超国家主義者の論理と心理」を読んだ。結論として、彼らは丸山の議論に対して極めて批判的であった。彼らに言わせると「抑圧の移譲」も「無責任の体系」も特に日本に固有の現象ではないし、近代国家の価値中立性という理解も極めてあやしい。とても今日深いやりとりだった。
15
柄にもなく、シェイクスピアの本を書評しました。深く考えさせられる本だと思います。book.asahi.com/article/139279…
16
僕は何度でも言うよ。国民の代表を選ぶ選挙戦で候補者やその応援者を暴力で襲うのは民主主義への挑戦だ。「民主主義への挑戦」という言葉がどれだけ手垢にまみれ、凡庸で、政治的な言葉だとしても。
17
オルテガ・イ・ガゼットの『大衆の反逆』が岩波文庫に入るということで、解説を書きました。エリートによる大衆批判ではなく、現代人の自己批判の書として読もうとしています。 twitter.com/BaddieBeagle/s…
18
オンラインで講義をしていると、時々、受講者がミュートにするのを忘れていて、その生活音が聞こえてくることがある。今日はなんとATMの自動音声が聞こえてきた(「硬貨を入金する場合は、、、」とか言っていた)。う〜む、あなた、いったい、どこで講義を聞いているんだよ?
19
政治家に限らないけど、近くで接してがっかりする人がいる。江田さんはその逆で、イメージ通りの人だった。まじめで、良い意味で書生っぽい人だった。がらんとした参議院議長公邸で、「男所帯だからねえ」と笑っていたのを思い出す。 news.ksb.co.jp/article/144049…
21
あまり、こういうことを繰り返し書くのはいかがかと思うけど、発売一月をまたず5刷とのこと。発売前にちょっと野心的に思っていた部数をあっという間に超えてしまった。多くの皆さまの励ましとして、感謝している。でも、瞬間的に読まれるのではなく、ずっと少しずつ読まれる本になって欲しい。
23
「一切を棄つるの覚悟」があるのか。ワシントン会議を前に、小日本主義を唱えた石橋湛山の言葉である。小欲にかられて「失敗に失敗を重ねる」より、自らの権益を放棄してでも、国際世論に訴えるべきではないか。石橋の言葉が、五輪を中止できずに苦しむ今の日本に響くという話を今朝の東京新聞に書いた
24
国際政治学者・宇野重昭さん死去 成蹊大元学長:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASK45…
25
しかも、後段には「公共の福祉」が出てくる。これが拡大解釈されれば、個人の権利も制限されかねない。何が「公共の福祉」なのか、議論してしっかり歯止めをかけることを促している。