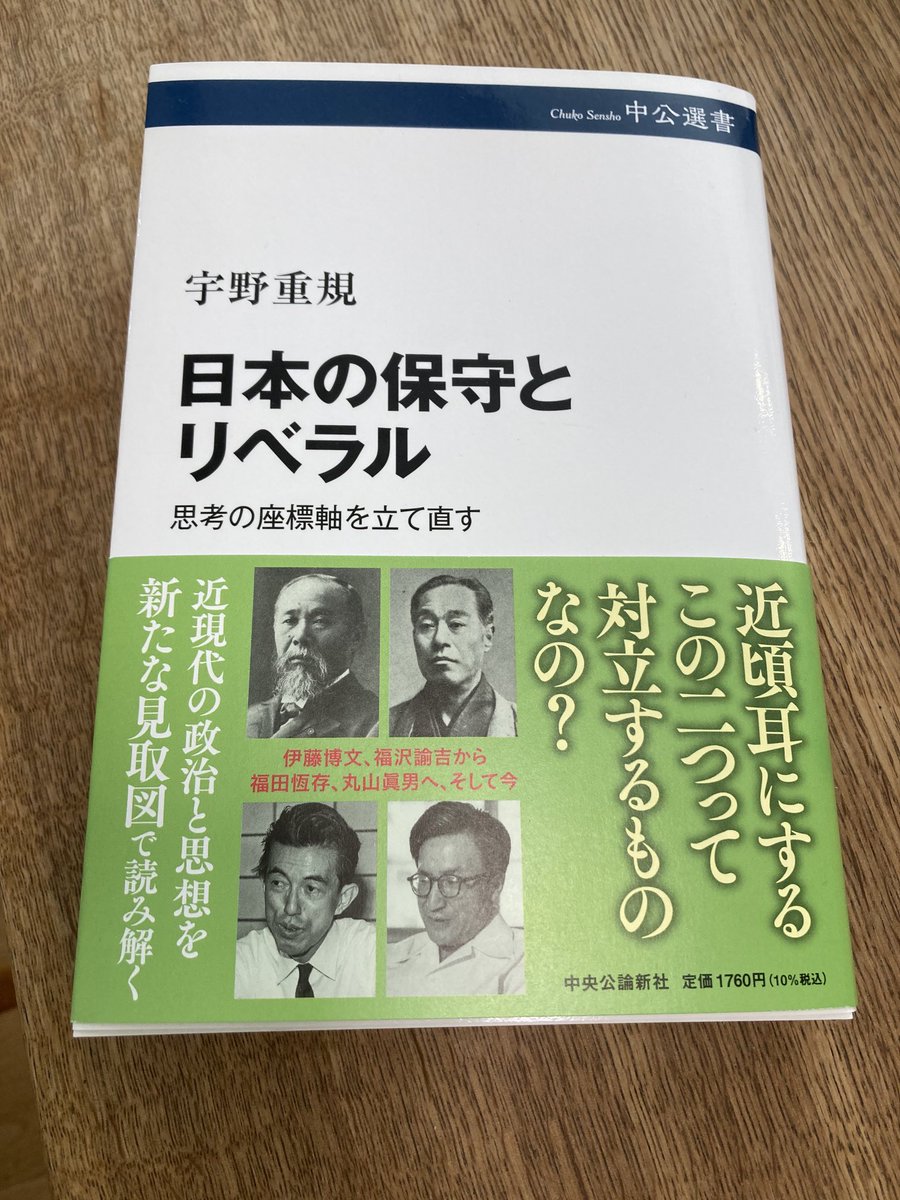1
いろいろなデータを見ていて思うけど、このままでも日本は5年はもつと思う。ひょっとしたら10年もつかもしれない。でも15年はもたない。最後の余力がある今こそ未来のために投資すべきだと思う。これからのためにやるなら今だ。
2
人生の基本は本を読むことだと思っている。仕事はその合間にするものだ(本を読むのは仕事ではない)。なのに仕事が多くなり過ぎると、本が読めなくなる。僕がいらついているのはそういうときだから、「あー、本が読めていないんだな」と優しくスルーして下さい。
3
今日、人と話していて、現在の小説の黄金パターンは、それぞれに傷ついた人たちが何かの事情で同じ空間に居合わせ、共に何かを行動するが、一瞬の感情の交錯を経て、しかしそれも何かの錯覚だったのかと思いながら解散していく、というもの。そうなのか、と納得してしまった。
4
僕は何度でも言うよ。国民の代表を選ぶ選挙戦で候補者やその応援者を暴力で襲うのは民主主義への挑戦だ。「民主主義への挑戦」という言葉がどれだけ手垢にまみれ、凡庸で、政治的な言葉だとしても。
5
今、多くの人が、「この組織に自分がコミットするだけの意味があるのか」と思っている。自分が無理して、犠牲を払って、そこまでして関わる意義があるのか、迷っている。それだけの意味があると反論できるのか。この問いは「日本社会ははたしてコミットするに値するのか」という問いにもつながる。
6
水田洋先生というと、歴史上の人物だと思っていた。ところが、社会思想史学会に行くと、総会では後ろからよく通る声で発言され、懇親会ではいの一番に挨拶される。しかも、つねにスミスのテキストで新たに見つけられたことを話す。尋常でない方といつも思っていた。ついに。 nordot.app/99493589576405…
7
学問とはある時期まで、過去から継承された古典をきちんと読みこなせることであった。いつしかそれはまともなデータをきちんと処理できることに変わった。どちらがいいとは言わない。両者を適切に結び付けられたらと思う。
8
今日話していて思ったけど、ヨーロッパ語の「コレクティブ」は「みんなで力を合わせなさいと、どーにもならないからね」、「ソーシャル」は「お互い様だから、しゃーないね」と訳すべきだと思った。
10
やる気があるときは時間がない。時間があるときはやる気がない。
11
人生で、早いうちから自分の及びもしない「すんげー頭のいい人」がいることを知ったのは幸せだったと思う。同時に、世の中で意味のある仕事をするのに、「すんげー頭のいい人」である必要は必ずしもないとずっと感じてきた。
13
葬儀というのは本来、故人を偲ぶ人たちが行えばいい。国家が主催する葬儀、特に民主主義国家があえて行う国葬とは何なのだろうか、考えてみた。しかし、岸本さんはかっこいいな。 twitter.com/tokyonewsroom/…
14
東京新聞の社説で新著を取り上げていただきました。民主主義が「参加と責任のシステム」であること、しかしこのまま投票率低下が続くなら「民主主義返上」になってしまうこと、だからお任せにせず、投票に行くことを訴えています。今回の参院選の意味はとても大きいと思います tokyo-np.co.jp/article/188687
15
安倍晋三元首相のご逝去について書きました。webronza.asahi.com/politics/artic…
17
話している内容の割に、楽しそうだ。 tokyo-np.co.jp/article/183366
18
昔、長男や次男を迎えに行った保育園での夕刻の風景を思い出す。彼らがいつまでも園庭を走り回る姿を見て、この時間、同僚たちは研究や仕事をしているんだよなという焦りの思いと、まあ、これは自分の人生のゴールデンタイムだよな、という思いと。
19
ついに出ます。他の先生方とはだいぶ雰囲気の違う対話調。それでも大切なメッセージは伝えたと思います。粘り強く考えていきたい内容です。 twitter.com/Iwanami_Shinsh…
20
両大戦間期の国際危機を描いたカーの『危機の二十年』(1939)を読むと、マンハイムの『イデオロギーとユートピア』(1929)、ニーバーの『道徳的人間と非道徳的社会』(1932)が参考文献に出てくる。個人の思いを踏みにじる国家や社会の暴力性、コントロールの難しさを描いた3冊。いま読むべき。
21
コロナ禍において、あるいは有能な専制体制の方が危機によりよく対応できるのではないかという言説が力を持ったとすれば、今日、世界はあらためて暴走する独裁者の恐ろしさを痛感している。今回の悲惨な出来事を契機に、民主主義への動きが再び加速することを願う。
22
とてもよく考えられた演説だと思った。印象に残ったのは、「人々は、これまで暮らしていた場所に戻らなければならない。彼らが育った場所に。彼らが、そこが自分の家だと感じる場所に。自分の小さなふるさとに。私は、あなた方はこの感覚を理解していると確信している」という一節。 twitter.com/Ukrinform_JP/s…
23
まあ、SNSの世界では「ディスらず」「ディスり返さず」「スルーする」の非ディス3原則で行くしかないね。
24
自分が信じていた何かが音を立てて崩れる瞬間がある。そういうときに「みんな嘘だった」と投げやりにならず、どう立て直していくかを冷静に考えるのも知性の底力だろう。
25
仕事納めというけれど、メールを見ていると、「1月4日提出」「1月5日正午厳守」「必ず連絡を」といった言葉が並ぶ。日本から正月休みという観念はなくなってしまったのだろうか(泣)。