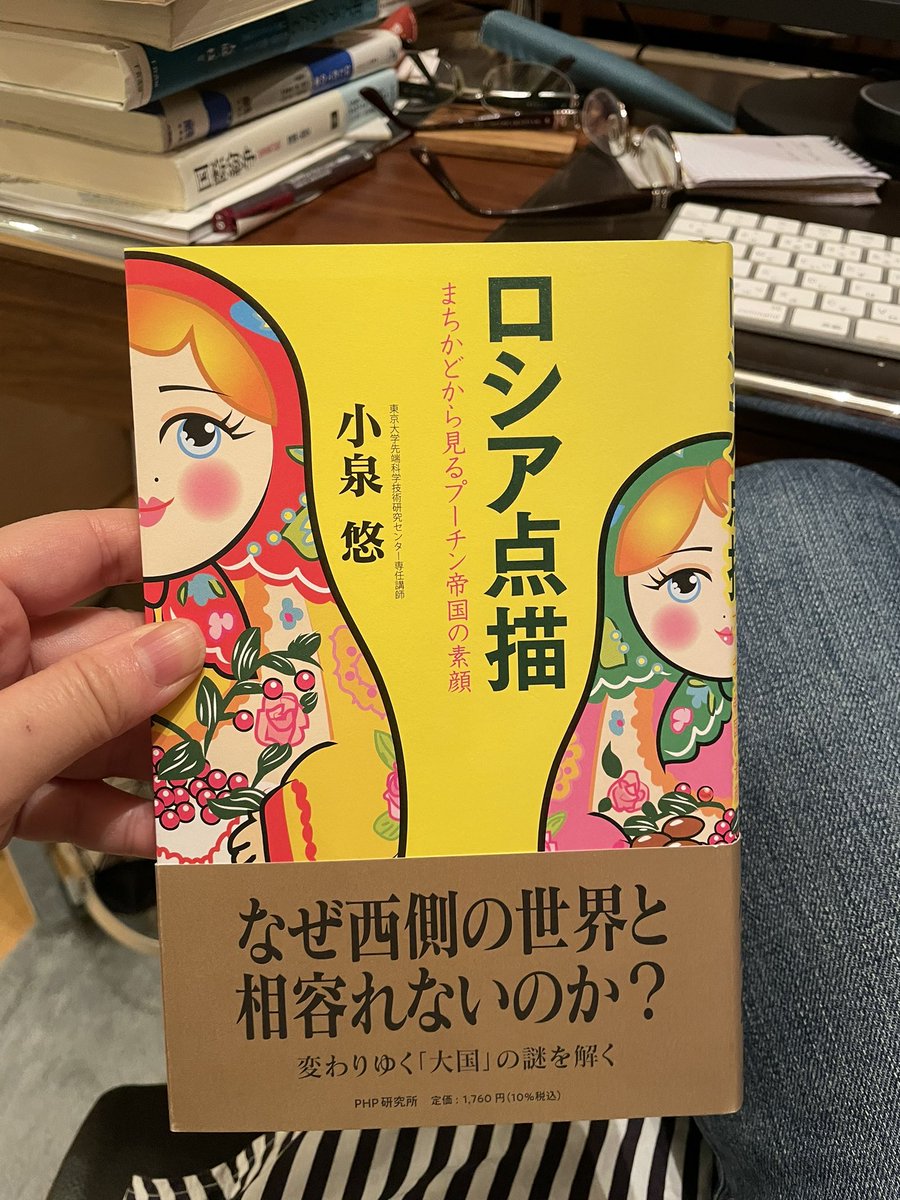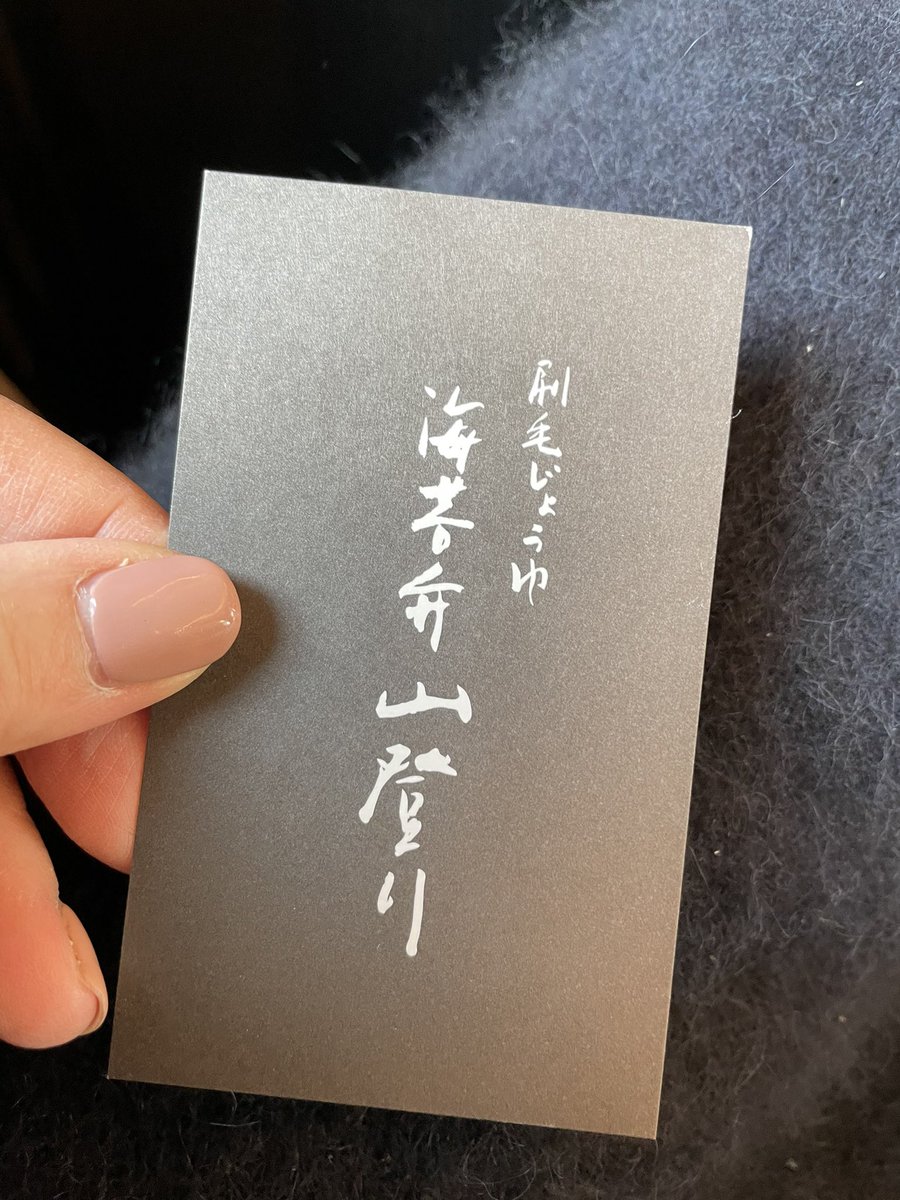26
ロにもウにも言い分はあるでしょう。しかしどちらが今の国際社会におけるルールに則した行動、反した行動をとっているか。国境侵犯し侵略行為を行い、国際人道法違反をも厭わない。こうした行動から判断するとロに理はなく、彼らの言い分をウと同等の重みと正当性を持つものとは見做せない
27
28
真の優しさ、フェアネスを絵に描いたような方でした。一緒に仕事した、飲んだ、Appleのガジェット話で盛り上がった、思い出はつきません。そして今後の日本にとって多大な損失。彼の穴は誰も埋められない。
国際政治学者で慶大教授の中山俊宏さん死去 55歳:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQ59…
29
この小川氏という方、経済的相互依存が深いからこそそれを断ち切ることが相手に打撃を与える「兵器」になる、ということをご存じないのだろうか。今の状況見れば明らかではないですか。相互依存を論じた古典ナイとコヘインの『力と相互依存』で相互依存=平和なんて論じてないのでは。むしろ(続く) twitter.com/kazzubc/status…
30
31
ブチャでのロ軍の所業にも触れないで早期の停戦よしとするのはどうなのか。その後のウの人々の人権は守られる保証あるのか。江川紹子さんのコメントの方がバランスとれている。抗戦ウクライナへの称賛、そして続く人間の破壊 寄稿・豊永郁子さん:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQ89…
32
終戦の日が近づいて特番が組まれてるけど、みんな日本人の被害者の視点を強調しがち。それはそれで事実ではあるが、日本が東南アジアで何をしたのか、加害者としての日本という視点がすっぽり抜けがち。今、NHKでやってる「太平洋戦争1942」はそこをクローズアップ。
33
戦時下の日本人の辛さみたいなのは事実ではあるけど、日本が先の戦争で特にアジアに対しては加害者でもあったのを忘れてはいけないのにその視点が薄れてると感じる。それは兵士としてあの時代を生きた世代が多くお亡くなりになってるということもあるのだろう。
34
なんでアメリカ(政府)が全てをコントロールできた、できると考えてる人が多いんだろう。ちょっと驚く。歴史認識の話だけではなくて、今回のロシアのウクライナ侵攻についてもそうですよね。日本の中に根深い対米怨念が存在するのをつくづく感じます。
35
中華民国の下で既に中国は満州を除いて統一され、中華民国政府のもとで経済成長も遂げつつありました。かつ東南アジアには日本がやってくる前から既に独立運動が活発化、フィリピンは既に独立が約束されてました。日本は流れを結果的に促進したかもですが、独立が日本のおかげというのは違う。 twitter.com/iasikevoli/sta…
36
日本がアジアの脱植民地化をもたらしたのではと考えている方、手っ取り早く各地の脱植民地化過程について学べるこの本をお勧めします。
アジアの脱植民地化と体制変動:民主制と独裁の歴史的起源 amzn.asia/d/fZtxlrm
37
第一次世界大戦を経て国際規範は戦争違法化と民族自決原則の承認、の方向に舵を切りつつあった。日本ではこの一次大戦のもたらしたインパクトについての認識が弱い。満州事変以降の日本の行動が時代に逆行していたことを認めず、近衛文麿の世界観のままの人がいるのだなと改めてわかった。
38
1930年には中華民国は満州除き統一されてて一定の経済発展も遂げてたってこと、どうしてここまで知られてないんだろう。その時代に日本と欧米が仲良く中国分割なんかできるわけない。日本の行為の是非以前に、アジアの近現代史が本当に知られてないと改めて思う。
39
ほんと誤解を生んでいるようで驚愕していますが、この本は、日本が東南アジア諸国の独立を助けたなどということを書いている本ではありません。各国の独立とその後の過程を各国内の政治に焦点当てて論じているもの。ここまで東南アジアの独立は日本がもたらしたと考えてる人がいるとは思わなかった。 twitter.com/mie_oba/status…
40
国際政治の分野は、女性活躍について比較的風通しの良いところだとずっと思ってた。世間で思われてるよりも女性研究者の数も多いし。だけど今回の戦争以降、女性が全面に立って発言することについて相当抵抗感を持つ同業の方も相当いるのだな、と悲しい気持ちになる。 twitter.com/chutoislam/sta…
41
続き。女性研究者がきっちり論理的に反論することに抵抗感を覚える人が相当数いる一方で、池内さんのようにそうした女性研究者の発言内容を評価した上で、応援する姿勢を明確に示す人もいる。そのことは見ててすごく嬉しいこと。
42
「あちら側」と「こちら側」に単純に二分できない複雑な国際社会を象徴するの存在。しかし戦略を持って世界を翻弄しているというより、自らが抱える危うさに対する対応を重ねているように見受けられる。インドがロシア原油「爆買い」 安さだけでは語れぬ事情: 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
43
これのもと記事、NATOの拡大を米の政策のみに帰するのはおかしいのでは?加盟した当の東欧諸国が、皆ロシアを信用できず、その脅威から逃れるためにNATO加盟を希望したという側面無視では。なんでも大国の意図通り動くという見方は本当の意味での「現実主義=リアリスト」ではない。 twitter.com/KS_1013/status…
44
根拠については既に別のとツイートで明確に書いてます。NATOの拡大を促したのは米の戦略もあるでしょうが何より東欧諸国が望んだということ。そしてそれはソ連、ロシアが近隣諸国からの信頼を得られないほどの行動をとってきたからであり、責められるべきことではないということです。
45
かつては日本中に米軍基地があり、しかし各地での激しい反米軍基地闘争を経て、本土では縮小返還された所が多い。戦略的に私は沖縄に基地は必要だと思う。しかし反対運動が沖縄で存在するのはある意味当たり前だし、それが過激さを伴う場合があるのは沖縄に限ったことではなかったんじゃないかと。
46
特に学部時代まで、国際政治学に興味があると話すとトクトクと自分の見解を述べてこれ知ってる?とマウントかけてくる男性はめちゃくちゃ多かったですね。その頃は元気だったので全て10倍返しで論駁、撃退させていただきました。大学院に入ってからも数は減ったけどありましたね。
47
48
49
いろんな人がいていろんな意見があることは理解しますが「研究者はこうあるべき」とか「〇〇(ある学問分野)はこうあるべき」とかいう原理主義的発想って超苦手。これ、摩擦と分裂しか産まないよ。特に正義感と原理主義が結びつくとよろしくない。
50
むしろロシアのウクライナ侵攻以降、TVで国際問題を扱う際、その問題領域や地域を研究してきた研究者が起用されるようになったんではないかと。その前の方が、全く関係ないタレントさんなんかにコメントさせてお茶濁してたのでは。専門家の情報発信という点で、今の方が状況良いのでは。