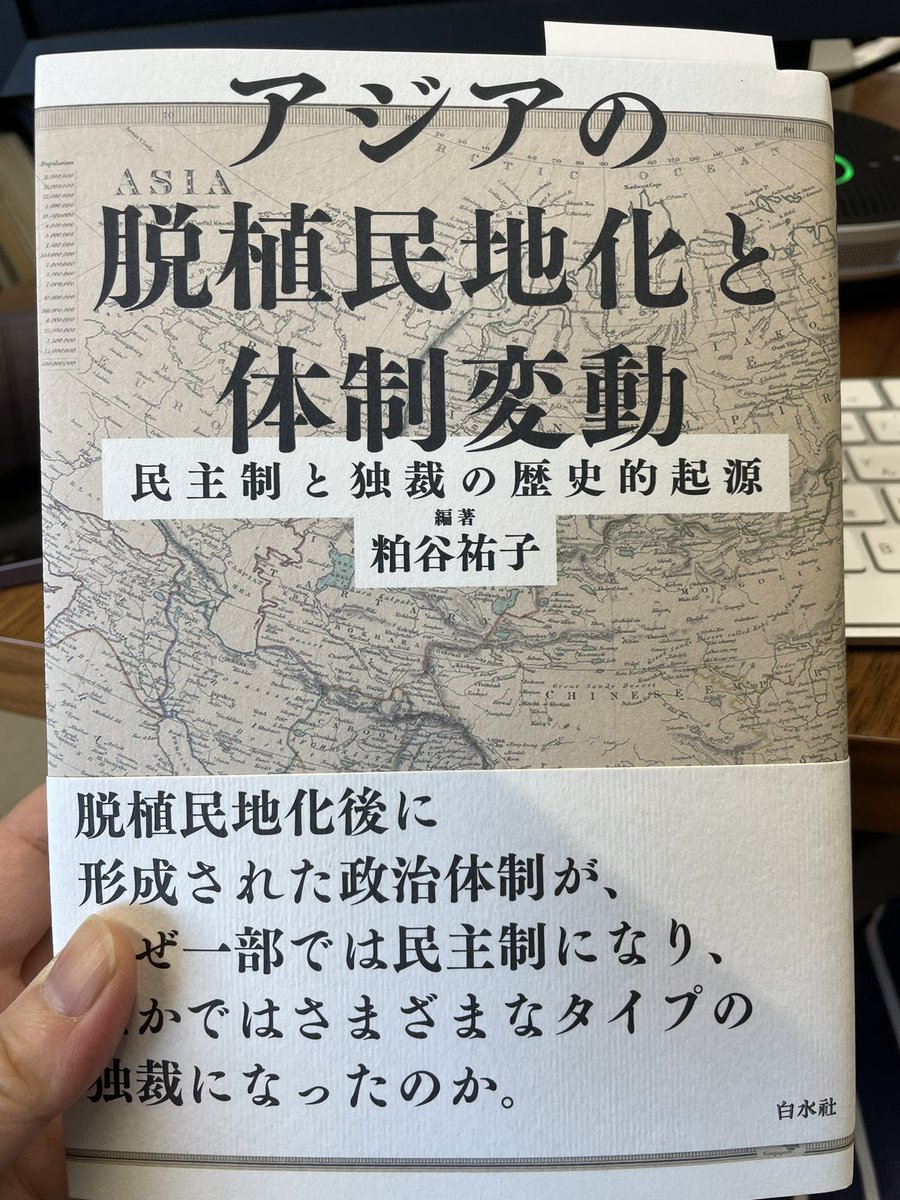1
私自身、前は、女性だから選ぶというのではダメで実力で判断すべきと思ってた。でも、その実力なるものを図る尺度が極度に歪んでる中、それをいえばいうほど世の中変わらない。とにかくトップに立つ立場の女性の数増やさないとダメ。
2
非常に興味深く腑に落ちる論考。私は個人的には、少人数のゼミは対面、大人数の座学型の授業はオンラインて割り切って決めてしまえばいいと思ってる。
対面授業再開、キャンパスに来るけど教室に来ない学生たち どうすべきか悩む教員 globe.asahi.com/article/145077…
3
ウクライナ情勢先が見えませんが、取り締まりが厳しいにもかかわらずロシア内で反戦デモが収まらないというところに冷戦時代との違いを感じる。この30年は全くの無駄ではなかったということか。
4
AFPによると、中国のいくつかの公営銀行が、ロシアからの資源買付のためのファイナンスに制限をかけるそう。欧米からの制裁措置を回避したいからとのこと。中国も、今回の事態を引き起こしたロシアをあからさまに手厚く支援するのは厳しいかも。
5
万が一、ロシアがいうようにNATOを東方拡大させない密約があったとしても、当事者であるウクライナをはじめとする国々不在の、大国間のみのまるで勢力圏を固定するかのような合意が、21世紀の今守られるべきだと考えること自体に問題がある。
6
NHK9時のニュースで小泉悠さんがウクライナ情勢、ロシアの軍事作戦の甘さについて解説。きちんとした専門知識に裏打ちされたプロの説明。報道番組はこうあるべき。
7
今回のロシアのウクライナ侵攻を封じるための経済制裁は、直で我々市民の生活にも影響がある。でも痛みを覚悟しないといけないのだろう。この暴挙がそのまま許されたら、武力を用いて現状変更してもOKということになってしまう。東アジア含む世界への負の影響が大きすぎる。
8
同感。ことの経緯をすっ飛ばして、何でもかんでもとにかく戦わないことが善、と刷り込まれた結果がこうなる。そして丸腰ならば相手は攻撃しないという妙に固い信仰。非武装中立論を彷彿とさせる。 twitter.com/atsukohigashin…
9
これ大事。国連とかアジアだとARFとかっていうのは、潜在的な敵国とか問題のある国であっても包摂、場やルールを共有し、問題があれば皆で対処するという論理で成立。で、like-minded な国で集まって困った国に対峙するのは同盟。両者は似て非なるもの。 twitter.com/KS_1013/status…
10
ウクライナの勝利を心から願ってるし何としてもロシアの今回の無理筋を通すのはダメだと思ってる。だけど仮にロシアが敗北しても殲滅したり地球から追放したりはできないんだから、その時にはロシアの国際社会への再包摂が必要で、その際には国連の活用が一つの選択肢かと。
11
プーチンが主張するNATOの東方拡大に今回の事態の責任を負わせる議論がいかに正しくないかを証拠を示して論じたマクフォール論文が日本語訳でNippon.comに
ついに登場!竹中先生、お疲れ様でした!大変参考になります。今期ゼミで学生さんにも読んでもらいます。 twitter.com/westlinen/stat…
12
プーチンのみならずミアシャイマーへの反論論文です。私へも、ミアシャイマー先生はこう仰ってるというツィート来るんですが、私としては、彼の議論はわかった上で、それはかなり雑であると考えています。この論考は、事実に基づいてミアシャイマー的な議論の不正確さを論じてます。 twitter.com/westlinen/stat…
13
ほんとにマジに聞きたいんだけど、ウの中立化でことは収まると言ってる方々、もしウを日本に置き換えたらどう考えます?仮に米中で日米安保破棄で日本はバッファーね、これ俺たちで決めたから、て言われたら?私は自分の国の安保政策をここまで露骨に大国の都合で決められるのはまっぴらごめんです。
14
ロシアvs国際社会という図式を打ち出しすぎることにはあえて警鐘鳴らしたい。国際社会=先進国とみるとそうなのかもだが、新興国や途上国の目線は複雑。またそれは中ロや中印が結託する、とかいうのとも違う。中印は案外ロシアに寄り添ってないと思う。無碍にはできないが。
15
あと新興国や途上国はシリアやアフガンの時と今回との対応のダブスタぶりについて厳しい目を向けていることにも留意すべき。今このことを論じるのは安易にロシア側に加担しかねないので注意が必要ですが。繰り返しますが新興国らの立場は理解する、しかしロシアを正当化することは絶対にできない
16
安全保障に関する思考に単にブレーキをかけて、戦争や武力紛争のリアルや伝統的安全保障に蓋をする態度で乗り切るのはもともと限界があった。湾岸戦争が起こった時の日本の中の議論は目を覆うばかりだった。今回はそれよりも随分マシな現実的議論が展開されてると思う。
17
平和実現の議論をするのに戦争や戦略のリアルを知ることは必須、にもかかわらずこの国は戦後戦争研究や戦略研究を長い間封殺してきた。しかしその中でも、特に冷戦終結後にそうした研究に従事する研究者たちは増えていたし、リアルな議論も展開されるようになっていた。その流れが今回一気に表に出た
18
だから、今回この流れに危機感を覚え、戦争は兎にも角にも両方共に非があるという人々が出てくるのも理解できるが、申し訳ないけどもうそういう議論は説得力ないと思う。
19
ロシアにもウクライナにも実際に現地に足を運び、人脈を多層的に築いて情報をこれまで収集してきた人々のもつ説得力は大きいよ。そしてそうした交流や研究が冷戦終結がもたらした国際環境の変化でこそ可能になったことの皮肉を感じる。
20
日本の先の戦争についての真摯な反省はずっとこれからも必要で、今回のウクライナにかつての日本を重ね合わせるような議論は歴史の忘却か大誤解なので慎むべき。しかし世界で起こる武力紛争についてそれらが起こった文脈を無視してとにかく乱暴はいけません的な議論をしつづけるのはもうやめるべき。
21
戦略研究や戦争研究が日本の学界でずっと異端扱い、差別されてたことをどうもご存知ない人がいて、深追いしちゃったけどやはり見ようとしないようなので諦めた。こんなの国際政治や政治学の界隈にいたら常識だと思ってたけどね。勇気ある先達の存在には本当感謝だが。
22
今のロシアのウクライナ侵略をめぐる日本の国内のアカデミアでの意見対立は、分野の対立もあるけど世代間対立の側面もある気がする。「米帝」という言葉に条件反射的にスッと寄り添う世代と、「へ?」と反応してしまう世代。もちろん米もかなり悪いことしてきたんだけどこの条件反射感がキモのような
23
前の国連特別総会におけるロシア非難決議の焦点は国家主権の尊重と領土の一体性なので、多くの途上国も賛成票を投じたが、今回の国連人権理事会からのロシア除名案件の焦点は人権、この政治化に拒否反応を示す国は多い。人権という価値を強調すると国際社会はまとまらないことが改めて浮き彫りに。
24
25
ウクライナにもロシアにも正義があるという物言いは正確ではない。ロシアにはいい分はあるが、正直正義があるとは言えない。喧嘩両成敗的な見方は逆にそれぞれの国がこれまで何をしてきたのか、をきちんと踏まえて判断する努力を放棄しているのと同じ。