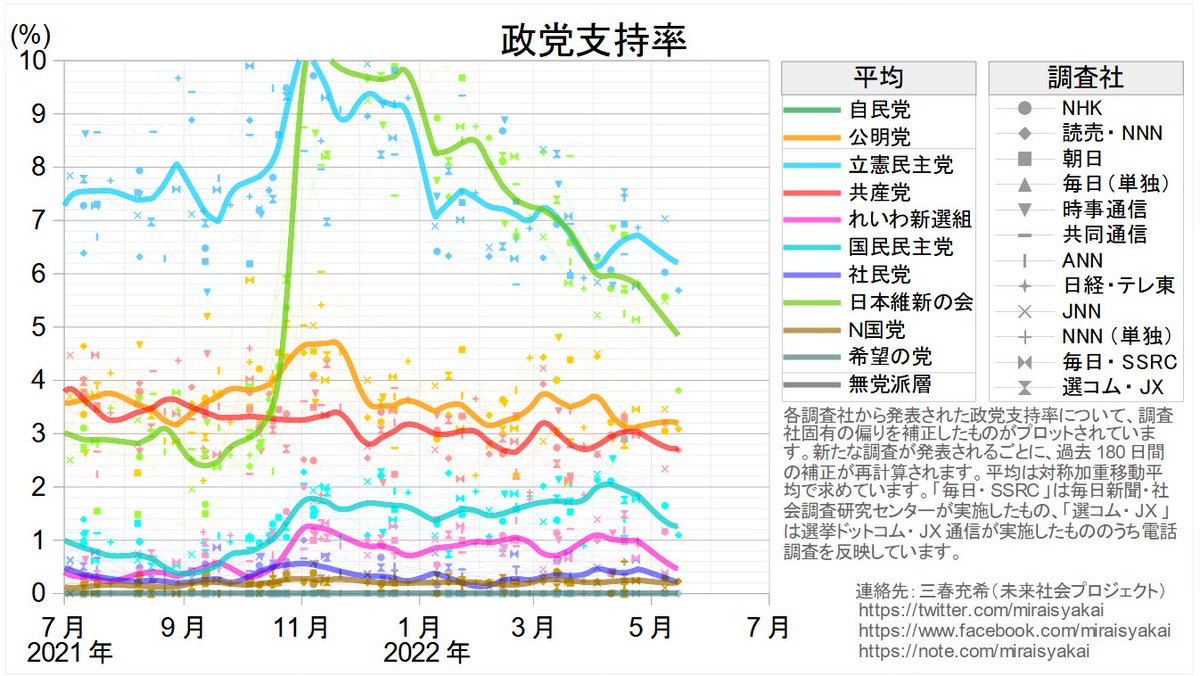1251
1252
1253
1254
ショック・ドクトリン(衝撃的な事件の後、人々が判断力を失くしている状況を利用して、なし崩しに政策を進めていくやり方)ですね。理性的に対峙する拠点を確保できなければ一方的にやられてしまうでしょう。
twitter.com/qhP9VYZ9hda1dF…
1255
そもそも平和のための軍備なんていう考えがまともに成り立つなら、世界最大の軍事大国であるアメリカはあんなに戦争を繰り返していません。そういう主張は戦争が起こる論理について大きな勘違いをしているということです。
1256
手厳しいですが、一面を抉っている指摘です。労働組合にも総評・同盟の頃から対立や切り崩しがありました。淀めば腐敗し、権力と癒着することにもなります。そして結局、大量の非正規労働者が取り残されているのが現実です。その辺の立て直しは重要なので近いうちに書きます。
twitter.com/yeqfc29t/statu…
1257
人々の連帯といっても、残念ながらそんな実感は若い世代からはほとんど失われてしまっている。労働組合は労働者の代表とはいいがたく、政治に失望した膨大な層が生み出されている。そうした状況を具体的にどうするかということが問題にされる必要がある。
1258
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」といっても、具体的にどのようにその努力を行うかということが教育からことごとく抜けてしまっている。そこからどうするのかという問題が常にある。
1259
比のゆくえ――憲法記念日によせて
note.com/miraisyakai/n/…
ロシアとウクライナの戦争を世論形成に利用して、軍備の拡大や統制の強化、人権の水準の切り下げを行おうとする動きが進められています。そうした動きに、どのような地点から対峙しうるのかということを書きました。
1260
日本がこれまで容認されてきた面があるのは、戦後、「共産圏への防波堤」や「資本主義のショーケース」としての利用価値を見出されてきたからだ。そしてその後は経済力に利用価値を見出されてきた。それが日本のパスポートの強さでもあった。その国が経済力を衰退させていくとしたら、どうなるかね。
1261
ヒトラーと一緒に昭和天皇の写真 ウクライナ政府が動画から削除、謝罪
mainichi.jp/articles/20220…
この件、議員と外務省が動いたというのが愚かすぎる。ドイツやイタリアがこれに抗議すると思うのか。抗議し、削除を求める態度こそ恥ずべきものじゃないか。そして日本は改めて敵国と認知されるわけだ。
1262
戦争の残忍さや悲惨さを見せつける事を通じて、新たな憎しみを掻き立てる動きには注意深くありたい。残忍さや悲惨さを受け止める土壌が十分になければ、写真や映像を広めること自体がそうした効果を持ってしまう。その恐ろしさを敏感に察知する人。それは正しい。それは少なくとも情報戦の一部をなす。
1263
大江健三郎が印象深い場面を書いています。「教頭が壇にあがっていった。みなさん、進駐軍が村へ入ってきたら、大きい声で《ハロー》といって迎えましょう」「その教頭は、つい一月ほど前まで、村で最も軍国主義的な男だった」(『厳粛な綱渡り』より『戦後世代のイメージ』)
twitter.com/Osaka_wombat/s…
1264
戦争が起きたとき、とたんに勇ましくなる人を、ぼくは決して信用しない。
1265
JR東日本 駅のロシア語案内板 覆い隠すも批判受けて元の状態に
www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
自覚していようがしていまいが、分断と差別への加担と言うほかない。ウクライナでは日常生活でロシア語を使う人も多いというのに。(Razumkov Centre世論調査で44.5%、FOM-Ukraine世論調査で52%など)
1266
ここから見える世界は――国家間の軍事的対立を乗り越えていく社会観のために
note.com/miraisyakai/n/…
国や権力に思考を委ねず、人々の側に立つのであれば、戦争を正当化する論理などどこにもありえません。国が強権的に人々を統制し、戦場へ駆り立てていくことが、まずもって許しがたいことなのです。
1267
改めてだけど、イギリス最大級の労組からこの水準の声明が出てくるのはさすが。
UNISON National Executive Council statement on Ukraine
stopwar.org.uk/article/unison…
twitter.com/miraisyakai/st…
1268
プーチン政権に抵抗してデモをする人たちがいるのと同じく、ゼレンスキー政権の行ってきた労働強化や軍拡に抵抗してきたウクライナの社会運動や労働運動があるということも見落とすわけにはいかない。労働者には共通の利害がある。そしてそれは、根底から、戦争という理不尽な事態を否定するものだ。
1269
ウクライナとロシアの労働者には共通の利害があるということを明らかにし、プーチン政権からもゼレンスキー政権からも独立して行動する労働者に連帯を表明している。
twitter.com/miraisyakai/st…
1270
UNISON National Executive Council statement on Ukraine
stopwar.org.uk/article/unison…
ウクライナに関してイギリスの労組が出した声明。この声明はさすがだ。
1271
自分とかけ離れたものに自分をゆだねないということが第一だと思います。国を自分に憑依させて語り始める人が多すぎます。
twitter.com/toktalk009/sta…
1272
やや気が重かったけれども、書きました。ぼくとしては、読んでくださる数少ない人たちに対して誠実に書くのみです。
twitter.com/miraisyakai/st…
1273
ここからはじめる平和――何もかもが戦争の論理に飲み込まれてしまう前に
note.com/miraisyakai/n/…
戦争をする国の側に立つのではなく、戦争で生活を破壊される人たちの側に立とう。東西の人たちが二つに分かれて世界の再分割戦を争うなどという悲劇を作り出さないために、ぼくたちはそこから始めよう。
1274
戦況を実況中継したり「プーチンが」「ゼレンスキーが」「NATOが」「バイデンが」というようなことばかり言っていたって傍観者にしかならない。それよりも声を上げたり、思い悩んだり、改めて読むべき本を手に取ったりする人の方が、ぼくは同時代を当事者として現実感をもって生きているように思う。
1275
考えるというのは、一つ一つ基盤を固め、それにのっとって論理を進めていくということであって、概念をもてあそぶということではありません。