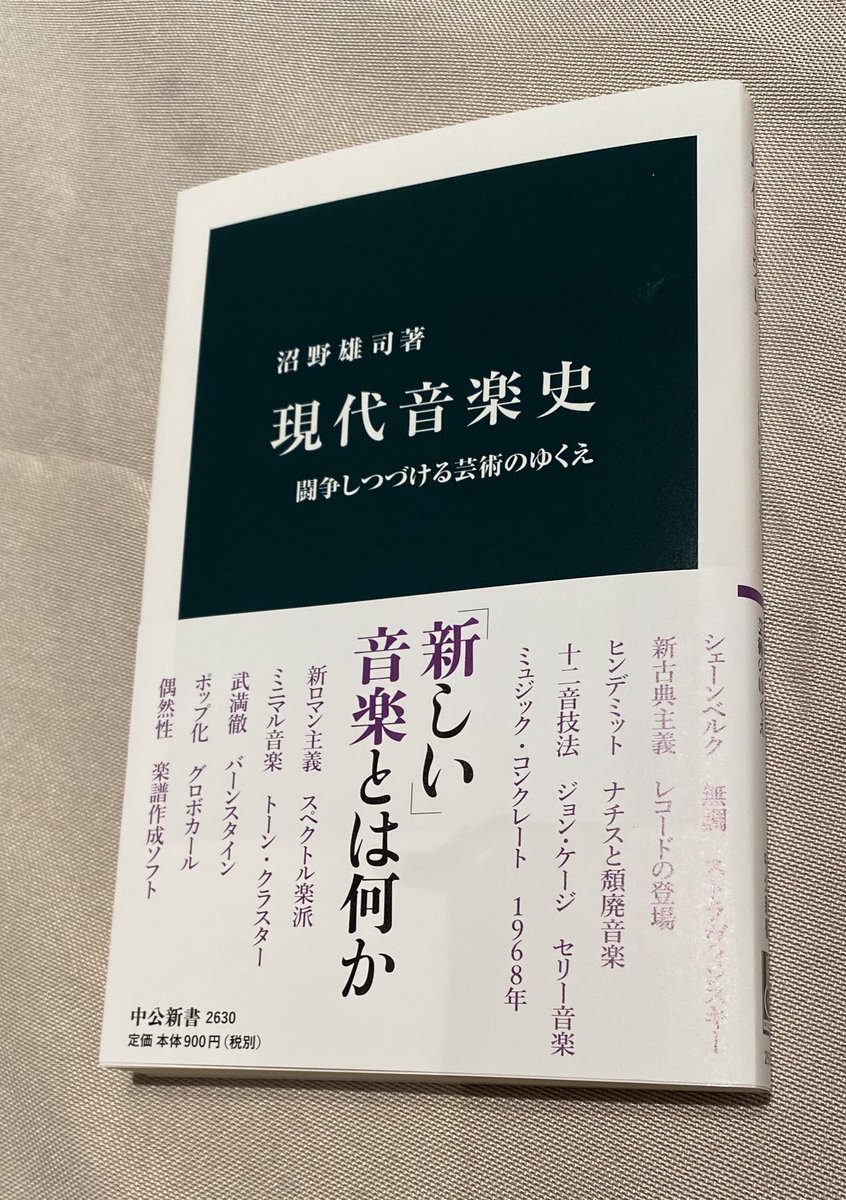26
YMOの最大の功績は、ポップミュージックに「教養」を持ち込んだことではないかな。それは3人が、とてつもない「教養人」だったからなのだろうけど
27
「ライヴハウスに関していえば、政府よりも一般の人たちの方が怖い。不謹慎厨的なものが怒鳴り込んできたり、何やってんだお前、みたいなことを言われるわけですよ」 storywriter.tokyo/2020/05/03/311…
28
29
音楽も、芸術も、役に立たないことを誇るべきである
30
どうしたら曲が作れるようになりますか?アレンジとかミックスとかできるようになりますか?と訊かれるたびに「耳コピー」と即答してる。真似。真似。真似すれば作り手の意図がわかる。だがそう言われても、ほとんどの人はやらない。ちゃんと真似するのは、ものすごくめんどくさい作業だから。
31
何かと報道姿勢を責められがちなNHKだけど、五輪のこの時期に『映像の世紀』をあえて再放送している事とか、国が民間人をないがしろにし続けた戦後補償問題を取り上げた番組 nhk.or.jp/special/plus/a… を今夜も再放送している事とか、何か言わんとしている「中の人」の存在を感じる
33
アマチュアとプロの大きな違いに、ダイナミックレンジや可動域の広さがある。プロの演奏家はアマよりずっとppが小さくffが大きい。プロのダンサーは完全な静止もできるし、あり得ないほどの跳躍もできる。そこに価値が生まれる。これは思考や文章にも言えることかもしれない。
34
ラブレターを書くときは恋の狂人になれ。だがポストに入れる前に正気に戻れ。作りながら自己批評すると何も作れなくなっちゃうから、作る時はひたすら吐き出し、後で仕分けするのだ。ロラン・バルトが言うように「恋する私は狂ってる、そう言える私は狂ってない」この2つの「私」を使い分けるのだ。
35
ある程度の歳をとったら、耳が痛い事や恥ずかしい事を指摘された時ほどうれしそうに「教えてくれてありがとう!」とふるまう演技力を身につけた方がいい。言われてムッとするような年長者には、鼻毛が伸びてることもジッパーが開いてることも、誰も教えてくれなくなる
36
「毎日特別おいしいものはいりません。おいしいものって、心乱すでしょ。作る人も食べる人も。ふつうでいいのです」「食べる家族は、作る家族を守ってください。ほんとうの豊かさは、料理して作るという暮らしです」日々の生活を肯定されたようで胸が熱くなった。料理ガイドを読んで泣いたのは初めてだ
37
友だちが少なくて悩む、みたいな記事が流れてきた。確かに子供の頃は誰しも友の多少や友人関係に悩むものだが、大人になると「仲間」が増えるので「友」という形にこだわらなくなる。仕事仲間、遊び仲間、飲み仲間…その時その場でつながり信頼できれば十分だ。「友」という概念に縛られる必要はない
38
赤子が生まれたら最初の三ヶ月は人として最低限の生活もできない無茶苦茶な時期に突入する。産んだ母親は身も心もグシャグシャだし、父も赤子対応&妻ケアでグシャグシャになる。「育休」っていう字ヅラには休めるイメージがあるが、現実は24時間稼働の赤子番なので「育働」とかに変えた方がいい
39
「コミュ障なのでフリーランスでやってきたい」っていう学生には「フリーはコミニュケーション能力がないと生き残れないから、組織に所属した方がいい」と助言する
40
「あなたの身体は君が食べたものでできているのです。だから食べものはあなたの未来の身体です」「自分で料理して食べることは何よりも自分を大切にすることです」こういう金言がレシピのあちこちに織り込まれている
41
作曲家が同業の曲を真似ても、画家が他人の絵柄を真似ても、パクリと呼ばれる。ならば音楽家は建築から盗めばいいし、画家は俳句から、役者は陶芸から、物書きは彫刻から…と別分野から盗めばパクリになりようがない。盗むと言う不純な目的を持った瞬間から、専門外のあらゆる分野は宝の山になる
42
「電子証明書は、市区町村の窓口でのみ更新できます(スマートフォン、パソコンによる申請はできません)」というパンチラインにクラクラっときました。電子とは。 twitter.com/h_mino/status/…
43
44
しばらく前から大学では、教員という「上の立場」から学生という「下の立場」を酒食に誘うのはハラスメントの温床としてご法度となっているが、だからといって「飲みに連れてってください!」と「下」から声をかける豪胆な学生などほとんどいないので、教員と学生の飲み会みたいなものは絶滅しつつある
45
46
ダンサーってよくあんな複雑な振り付けや段取りをおぼえるよね。どうやって記憶するの?という話をしていたら、「ソロで動くよりも、他の人がいる方が記憶しやすい」ときいた。「相手がこう動いたら自分はこう動く」みたいに、空間的な関係性がある方が記憶しやすいという
47
あなたがそこそこイイ歳だとして、年寄りに見られたくなかったら、まず「音を発しないこと」だ。「よっこらしょ」とか「フゥー」とか「ンアー」とか、年寄りは結構な頻度で何かしら音を漏らすんだよね(俺も
48
退屈だから本を読むし旅に出るし恋をする。退屈は作曲家にとっての無音の時間だ。絵描きにとっての白いキャンバスだ。退屈を恐れるな。他の誰かが提供するものだけで自分の時間を埋め尽くすな。
49
世の中には、新しい「型」を発明するのが得意な人と、既にある「型」を使って表現するのが得意な人がいる。「あ!大太鼓と小太鼓とシンバル組み合わせたら一人でリズム叩けんじゃね?」と思いつく人と、そうやってできあがったドラムセットを叩きこなせる人は、同一人物でなくていい。適材適所。
50
どんなに面白そうな話でも、リンク先が動画だと「ああ…数分間の動画を観なきゃならないのか」とげんなりしてスルーしてしまう。テキストで書いてくれたらパッとリンク先に飛んで読むんだけど。要は可処分時間の使い方。