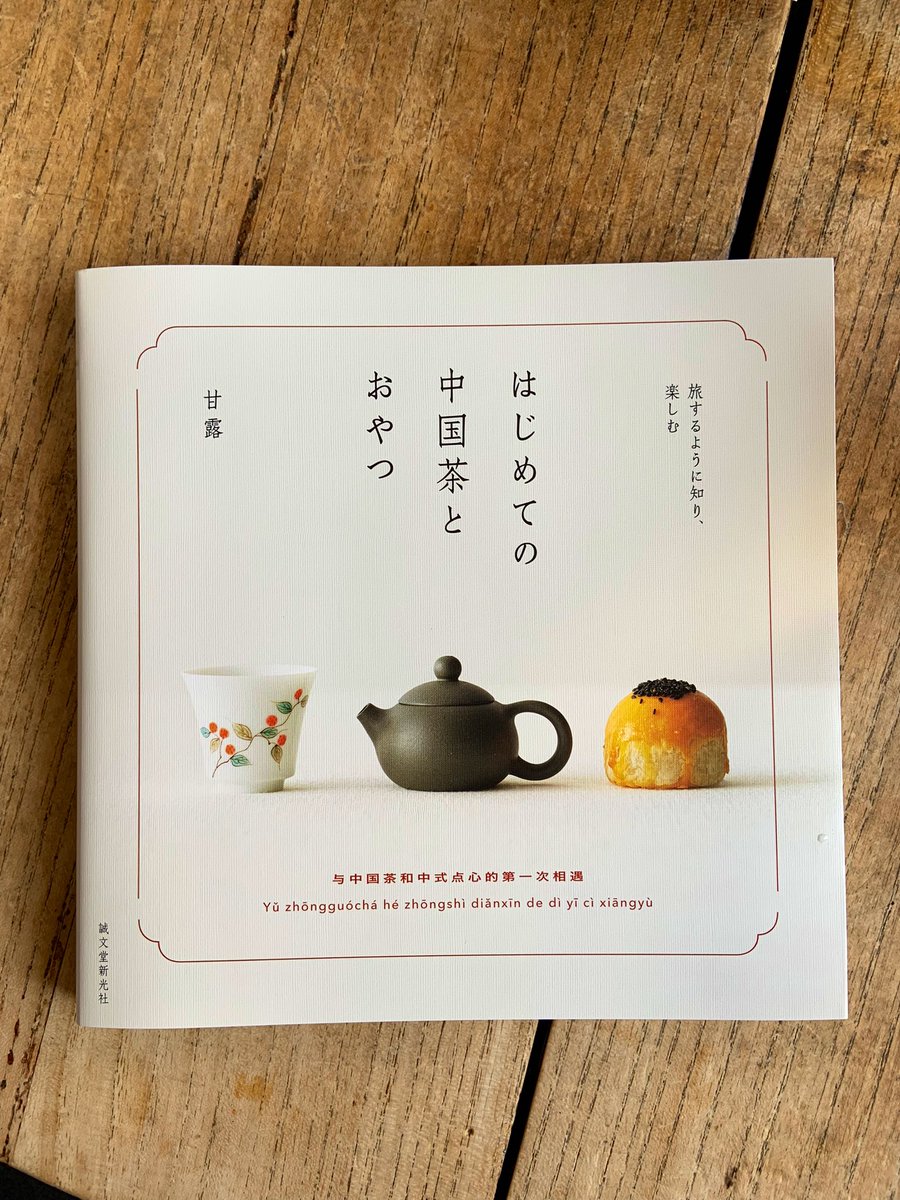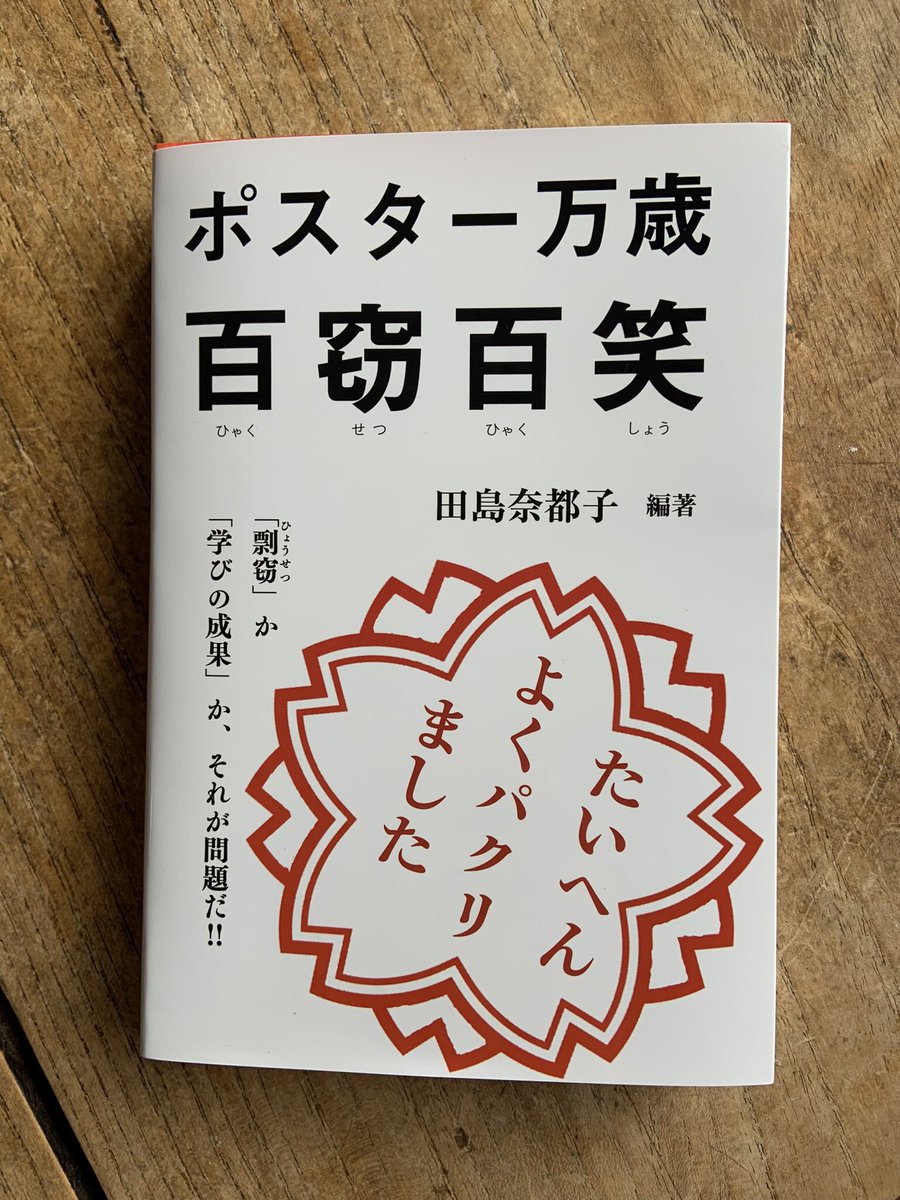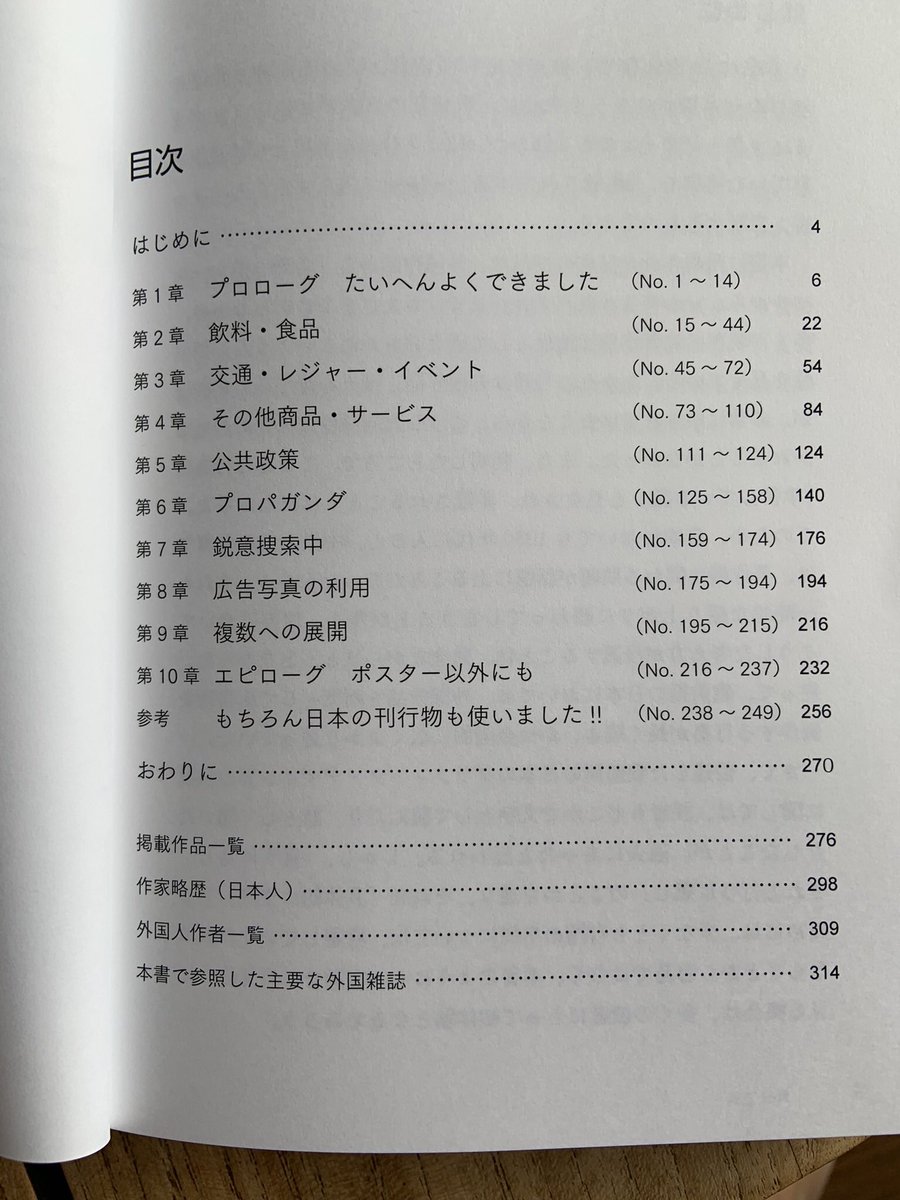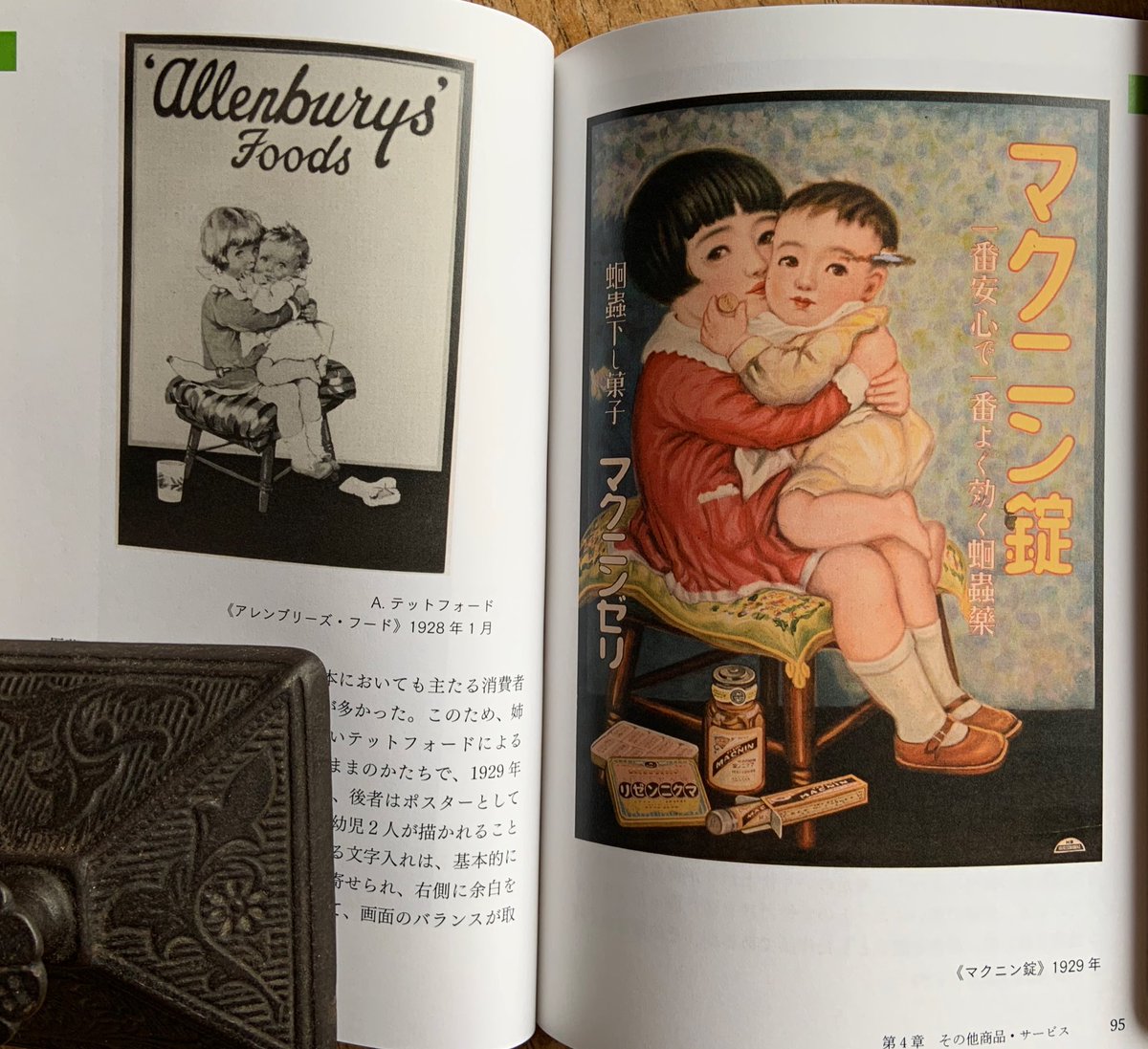26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ようやく五仁の回油(水分が生地に戻ってしっとりした状態)がいい感じになってきたので食べてみました。私は月餅屋になったほうがいいんじゃないかと思うくらい美味しいです。 #月餅
39
40
@wathymmm 今はほとんど見なくなりましたが、上海では白蘭花(バレイホ)といって、夏の風物詩です。ふたつワイヤーで束ねてボタンに引っ掛けられるようになっていて、一日限りの香りのブローチとしておばあちゃんが道端で売ってます。そちらの方では暖かいから夏限定ではないんですよね、羨ましい。
41
さらに言えば月餅は一個を一気食いするものではありません。今は小さな月餅が増えつつありますが、昔は150gクラスのを6分の1くらいの放射状にカットしてちびちびと食べるものです。生地に転化糖を使ったり油分を多くしたりするのはこうした食べ方を考慮し保存性を高めるためでもあるのです。
42
43
44
46
作り方もへったくれもないですがご参考まで。
1 砂糖(できれば氷砂糖)と水半々くらいで煮溶かし絞ったみかんの汁と薄皮剥いたみかんを入れ軽く温める。
2 白玉粉をで耳たぶくらいの固さに練って直径2cmくらいの小さな玉をいっぱい作って茹でる
3 器に1を注いで2を浮かす。熱いうちにどぞ。
49
50