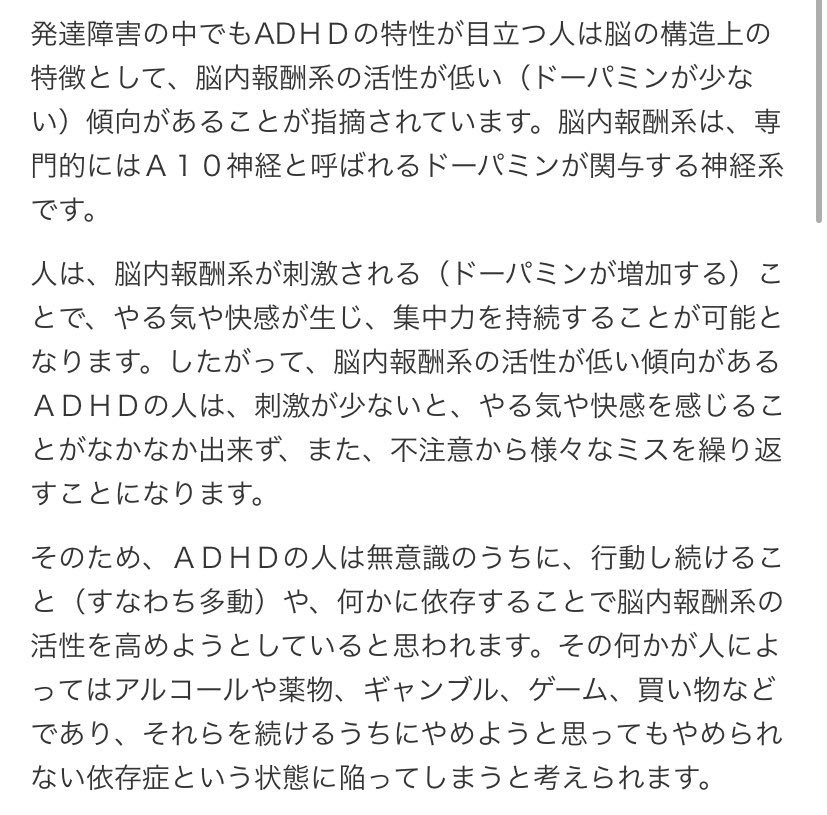26
「適応の才能がない」という単純な能力不足があまりに"自己責任"と相性が良すぎる、努力神話という世界観で生きてる人々が明日を生きるための酒の肴にされすぎてはしないかと、すごく卑屈な考えかもしれないけどそういう側面はあると思っている。「適応しない」努力不足でなく、「適応できない」んだよ
27
付き合いやすい人、付き合いやすい空気感を作れる人、一緒にいて安心する人というのはある種どこか諦めていて、目の前の相手に執着しないからこそ常に逃げ道を作ってあげられる人、嫌われたくない、とか好かれたい、とかモノにしたい、みたいなのがにじみ出ないから相手も自然と素直になれる。
28
「イキってます」というメタを持ちながら若さをやってる人たちすごくいいなって思って、若いうちにイキるのってなんというか社会機能の発達過程的なとこあると思ってて、変に逆張りせず受け入れてその時代にできることを素直にやってる感じ、楽しんでる感じが後々経験として活きるんだろうな、って思う
29
当然僕が神経質な部分も間違いなくあるし、視野も経験もクソ雑魚ゆえ、なんもわからないけど、今のところはそういう世界観に至ってしまって、自分ひとりで仕事を創り出す、自分自身で自分の価値を見つめて信用を積み重ねる方が結局手っ取り早いような気が今はしてしまうんだよな。どうしても
30
反出生主義、「自分が生まれてきたくなかったから」とか「これ以上自分のような人間を増やしてはいけない」みたいな"自分"を根拠として謳ってる人が一定数いる気がするんだけど、個人の生きづらさから「社会規模で子供を持たないべき」という主張に飛躍するのってたぶん"主義"ではないと思うんだよね。
31
自閉傾向の強い子ども、「どれだけかかってもいいから自分の納得いくまでやってみてね」をやらせてもらえるかどうかで自己肯定感の育ち方がまるで違う
32
“セルフコントロールができる人”というのは、「いつも冷静な人」ではなく「人の見ていないところで物に当たれる人」とかだったりする。
33
別にそういう人たちを今は恨んでるわけではなくて努力神話の向こう側にいる人たちも見方によっては被害者だし、結局その世界観の中で生きることに適性があった人たちで、然るべくしてその生き方をしている訳で、というところで過去も含め自分のために「赦す」段階に入っていけるといいなあと思っている
34
「ASDは共感ができない」というやつ、厳密には「感情の解像度が高すぎて、浅いところで共感を与え合うアレができない」というのが正しい気がする。冷たい機械のような言われ方をしてるけどむしろ逆、社会性の中で表現しきれない深い悲しみや、文脈が複雑に絡み合った喜びを知ってる。
35
36
「しあわせな人」を自分から憎みに行く時間はないけど、「なぜかすべての人に自分と同程度の環境が備わっていると思い込んでいて、自分の水準に達していない人を"努力が足りない"と説教しに来るしあわせな人」は完全に"敵"認識でいったほうがいいと思います。
37
「相手の見たくない部分を見ない」というのは決して”拒否”ではなく、むしろ距離感を適切に保つことで関係性を持続させようとする努力だと思うんですよ。「どんなところも愛する」というのは余程の覚悟がないとできなくて、一部をシャットアウトしつつも関係は続ける、という曖昧さはあって当然。
38
「すべてを見せてくれたように錯覚させてくる頭のいい人」というのはメチャクチャ多いので、「心開いてくれたから自分もちゃんとすべてを晒そう」みたいな安直な思考には至らない方がいいですよ、みんなその辺上手いので。
39
「ずる休み」が必要になってくる時点でなにかしらの限界を迎えているので、なにもずるいことはないのだよ。
40
それとは別にこういった感情を腹の底で抱え続けることが結局今の僕のモチベーションにも繋がっているわけで、怖い大人だなあとか結局奴隷だなあとか、あんまり変わらないよなあとか思うわけだけど、それも含めて仕方ない人間の姿として受け入れつつあるような気がする!もうみんな仕方ないんだよな実際
41
「発達障害を甘えということにしないと気が狂ってしまう健常者」が滅茶苦茶いると思うので、救済されるべきはあちら側なのかもしれないとも思っている
42
43
「基本的に他人は信用しない」からこそ信頼の価値が生まれるのであって、誰でも信じる人は誰も信じていないのと同じようなものだと思っている
44
できない人の気持ちがわからない人、「なんでできないの」じゃなく「なんでやらないの」になっちゃう。余裕がなく傲慢になっていて、「できる」に至る過程への想像力が失われている、「やるだけなのに、どうしてやらない」になってしまう。その先の解像度が存在せず、不誠実であるように見えている。
45
46
今って「わかりやすい幸せ」から「自分で幸せを定義する」へと移行する真っ只中の時代で、
「高身長・高収入・高学歴」「時計・車・マイホーム」という”正しい幸せ”が存在した時代を生き抜いた親たちは、子どもを想って「正解」を説いてくることもあるけれど、その時代はもう終わりつつあるんだよね。
47
発達障害、スペクトラムであるという肝心の部分が広まらず、特性だけが取り沙汰されて「自分も似たようなところあるのに、あいつは甘えてるな」の使い方をされてる場面が度々見られて、あまり良くない方向に向かってる感じがする。
48
「自分は気分屋だ」で思考停止せず、どういった環境・条件のもとでモチベーションが湧くのか、飽きてしまうのか、実験と検証を繰り返しながら自分に当て嵌められる法則を整理していくことで、少しずつ”最高の状態”を意図的に再現できるようになっていくと思う。気合いだけではどうにもならない。
49
マナーや礼儀、常識を身につけるということは社会性の奴隷になることではなく、むしろ自分をさらけ出すためのツールと捉えた方がいい気がする。型に則ってさえいれば逆にいろんなことが言えるようになるから、自分らしさを認めてもらうための土俵に上がる手段、と割り切って最速の習得を目指す。
50
人を嫌いになるということは「近づきすぎてしまった」ということでもあって、賢い人はそもそも嫌いになる前に自分から遠ざかるんですよね。嫌いにさせてしまう方にも責任はあるけど、なる方もコントロール不足ということがある。