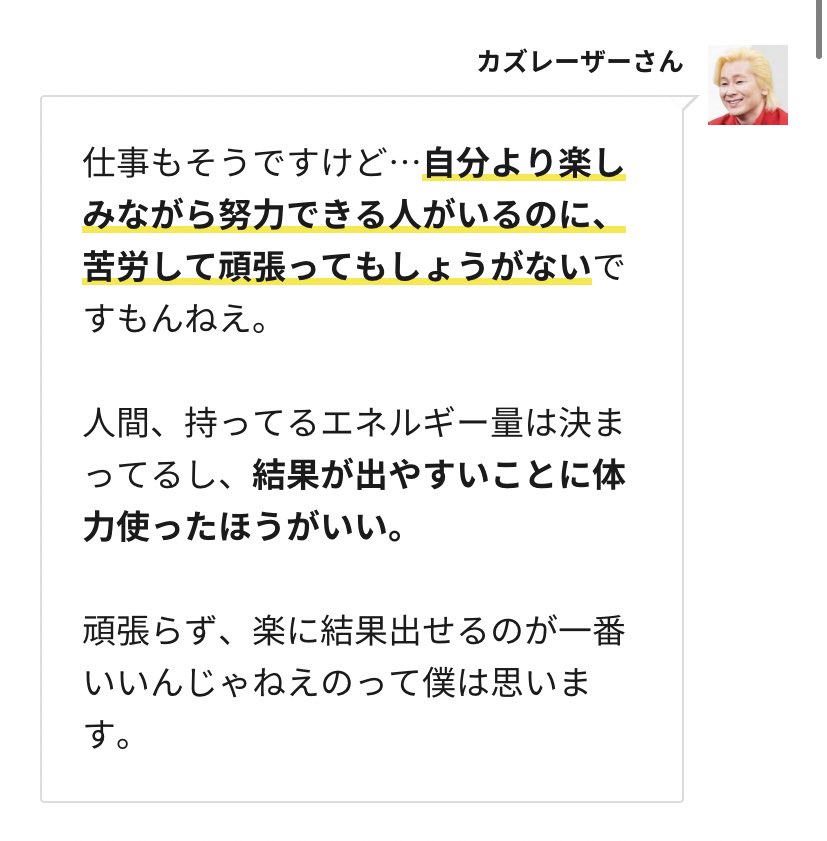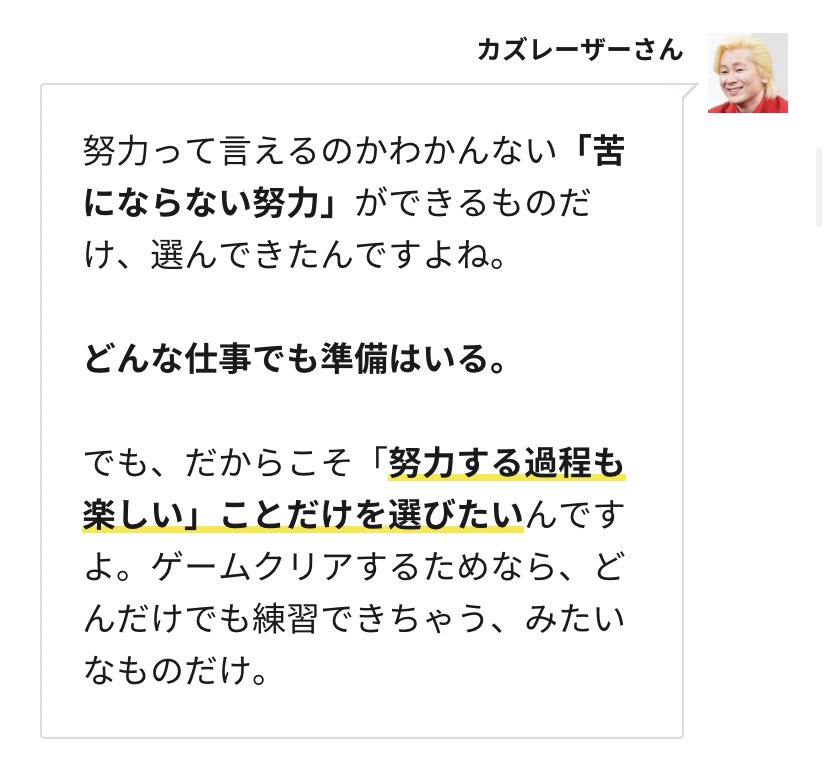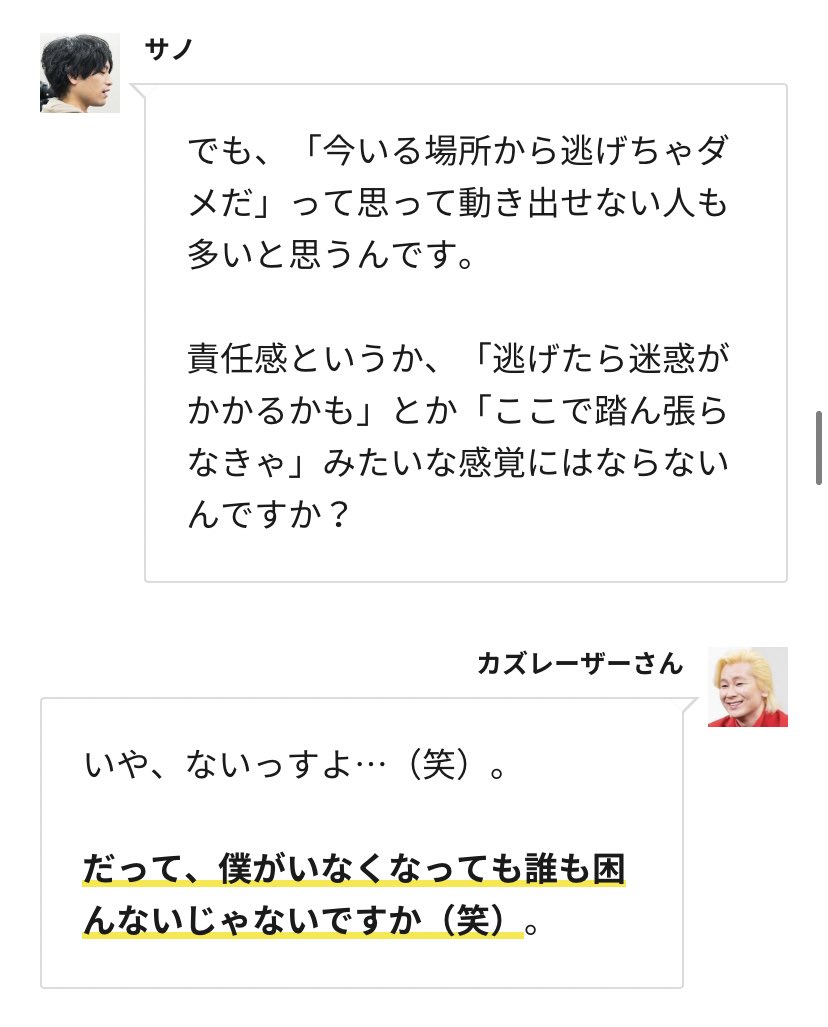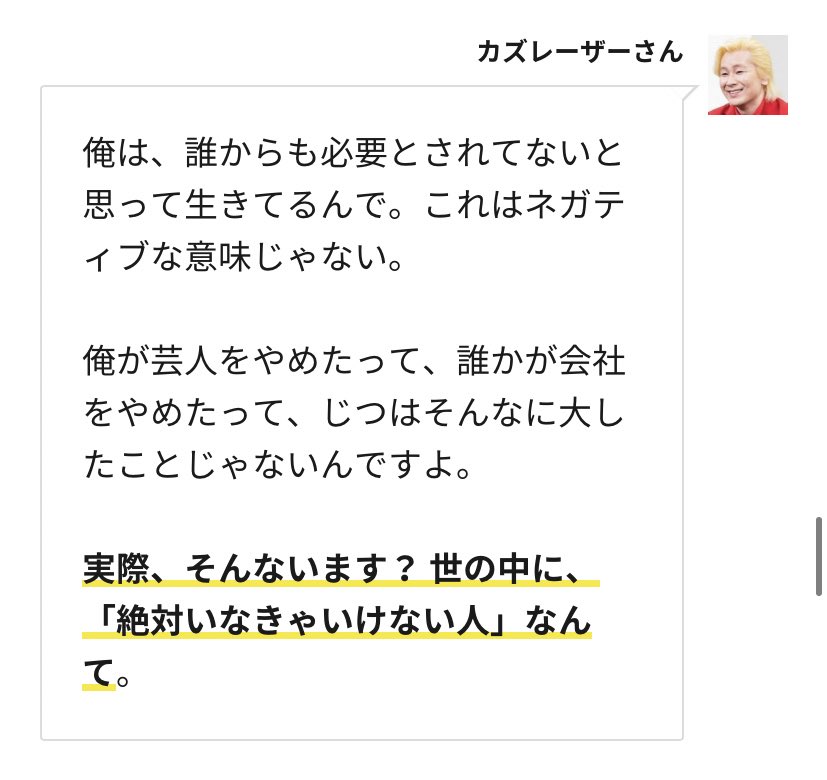1
中学生で自殺とかする人に「いくらでも道はあったのに」と言う人は多いけど、家と学校が世界のすべてで、寄り道すら背徳感を感じるような"ちいさな世界観"の中で、世界の半分を占める学校での居場所が無くなったら生きてる意味もわからなくなるよ。
「世界は広いんだ」って知るのは大人になってから。
2
嘘のような実話だけど、周りから「どこ見てんの?w」「はいまた自分の世界入った〜」と言われ続けていた高校時代、趣味のカメラで近所のお花を撮っていたら突然おっさんから「凄まじい集中力だ、俺にはできない、君は天才になる」と叫ばれて、訳わかんなかったけどそのおっさんの言葉だけが味方だった
3
ほんとうに舌が肥えてる人って、たとえばマクドナルドを食って「なるほど、これは万人が受け入れる合理的な味だ。」とか、めちゃくちゃ高いのを食って「これはもう自己満足の領域だけど、私にはわかるぞ。素晴らしい。」みたいな、どんな料理にも意図や良さを見出せる人のことなんじゃないかと。
4
「右利き用につくられた世界で左利きが暮らす」ような「死ぬほど困りはしないけど、毎日続くと膨大なストレスが蓄積していく」という”映えない生きづらさ”って実はものすごくしんどくて、困りごとを説明しても「がんばれば適応できるでしょ」で片付けられ、自尊心を削り続けるしかないという地獄がある
5
アスペルガー気質のある人とこれまでたくさん関わってきたけど、「すぐ本質を突くから周りから距離を置かれてしまう」とか「正しいことを言ってるのに相手が勝手に怒り出してしまう」みたいな認知になってる人は自分の在り方を見直した方がいいんじゃないかなと思ってる。原因はおそらくそこじゃない。
7
僕はアレ「社会性から一時的に解放される最高の贅沢」だと思って観てたんだけど、
「人と食べた方がたのしいのに、変わった趣味を持つ人の考えを知れるエンタメ」みたいに話してた人がいて、そうかふつうは「社会性がデフォルト状態」なんだなと思った覚えがあります。 twitter.com/lolicoro/statu…
8
「人間の能力には限界があるから、仕組みでなんとか解決しよう」という世界観で育ってきたのではじめてバイトしたとき「仕組みに期待するのは甘え」「努力次第で人は変われる」みたいな空気感があってめちゃくちゃ驚いたし普通にクビになった、仕組みに対する改善案ばかり語っていたら完全に嫌われた
9
「触らぬ神に祟りなし」をやられているのに「みんなが言いづらいことを代弁するダークヒーロー」みたいな自分の物語が頭の中で展開しちゃって、あらゆる認知がそのストーリーに整えられていってしまう。歳を重ねるごとに触れなさは加速する。だから早いところ疑えないと、行くところまで行ってしまう。
10
「モテたい」って男性から相談を受けたら「連れ込むには」「酔わせて」って言いながら「温かい関係がほしい」って言っててびっくりしちゃったんだけど、無意識の加害性というか、それでも真っ当に関係性やりたいという無邪気さみたいなものが恐ろしすぎて、これが社会人やってるのか、と思ってしまった
11
たしか1時間くらい同じお花を撮り続けていて、おっさんはほぼ最初から最後まで僕の姿を見ていたらしい。
正直恐怖もあったけど、なにより馬鹿にされるだけだった姿を「能力」と言ってもらえたことで初めて自己肯定という発想が生まれたし、その時からこの力を何かに使えないかと考えるようになった。
12
銭湯行ってたんだけど、横にいた日焼けにツーブロックで体格のいい"社会性"って感じのお兄ちゃんたちが、
「アイツ、ボーッとしてどん臭えしやる気ない奴だと思ってたけど、アスペルガーなんだって。なんかいろいろあんだなーって思ったわ。」って言ってて、これでいい、これでいいんだって思ってた。
13
マックとか牛丼を鼻で笑うようなのを舌が肥えてると思ってる人が多い気がするけど、ほんとうに価値がわかる人ってのはどんなところにも意味を見出せる人なんじゃないかなあと思う。どれだけの歴史や葛藤、選択の積み重ねでチェーン店の味が成り立っているのか、その想像力もないのが美食家なんて。
14
“グレーゾーン”は生きづらさを語っても金にならないんですよね、映画にならないから。
人々が共感したくなるような「ストーリー性」を持てない生きづらさには、見えない地獄があるんですよ。
15
「ひとりで過ごすのがデフォルトで、たまに人と会うと新鮮でたのしい」が僕の中の常識だったので、「みんなで過ごした方が楽しいから、1人であそぶ理由がわからない」という人たちが大多数だった当時のバイト先はカルチャーショックの嵐だった
16
「いま少しの時間をかけて仕組みを改善したら、追々の数十、数百倍の時間が節約できる」みたいなことをいくら説明しても目の前の実務に関係ない行動や議論に一切聞く耳を持ってもらえなくて、仮にそれを語れるようになるのは最低でも数年は無心で手を動かし続けて信頼を得てから、という世界観で
17
きわめて個人の自己責任、自立を促すように見せかけて実際は教育的責任の放棄、必要最低限の合理的な差し伸べすらできないほど社会全体に余裕がなく、ただ心を殺して理不尽に強いられる"努力"に耐えて這い上がってくる人だけが「仲間」として認識されて内輪で酒を酌み交わす、そういうのがあまりに
18
なんだろうな、「関係性を楽しみたい」という意識は僕もあって、その手段としてたとえばお酒が入るとかは全然あると思うけど、それって当然相手も楽しいというのが大前提で、「一緒に楽しみたい」ならわかるんだけど、「酔わせて連れ込みたい」の延長上になぜ「温かさ」が来るのかその時は意味不明で、
19
ろくに説明もしてくれない(僕の見る限りでは修行の一環でなく、あきらかに上の言語化力不足)ので見て学ぶとか、覚えられないのは努力不足だから教育やマニュアルにコストを割かないとか、目的に対する手段の選択、俯瞰的な意思決定が美しい努力の物語で塗り潰されていく様に流石に耐えられなかった
20
「ひとり焼肉」とか「ひとりカラオケ」みたいな言葉があるけど、僕はこれらに1人で行った回数の方が圧倒的に多くて、わざわざ"ひとり"と付けようとする社会の流れがあることに軽く恐怖を覚えているよ
21
後から考えたらたぶん、寂しいんだろうな、と思った。「一緒に楽しむ」の想像がそもそもできなくて、感情を共有するという感覚がないから「酔わせて」みたいな表現になってしまう、受け入れてもらえる自信がなくて、だから強引に操作することでしか感情を満たせない、と思っているのかな、とか。
22
キモすぎて、そういう努力神話、「努力してきた側であるという選民意識、自分たちの理想とする努力が(実際は能力的な課題で)できない者に対する異常な排他性とそれを餌に酒を飲んで明日も美しい努力を続けられる」みたいな構図が、ない環境を探す努力より適応する努力の方がコスパがいいという
23
「失礼な人には失礼な対応をする」を心がけるとかなり生きやすくなるのでオススメです。
24
努力ではどうにもならない壁があるから協働して仕組みを作って、個々人の資質を活かして働ける環境をつくろう、みたいのが社会性の理想的かつ合理的な在り方だと思っていた(机の上で勉強していた限りでは)のに、いくつかの環境でいわゆる"現場"を経験する度に実際は
25
表現の根底にある「楽しみたい」自体は大事にしてよくて、ただそれが加害性に変換されてしまうのを自覚して直していけば「モテる」もいつか達成できると思う。無自覚さは必ず滲み出て人に伝わる、社会性やりたいなら日々疑って素直に修正し続けるしかない。それが欲求の正しい使い方でもあるはず。