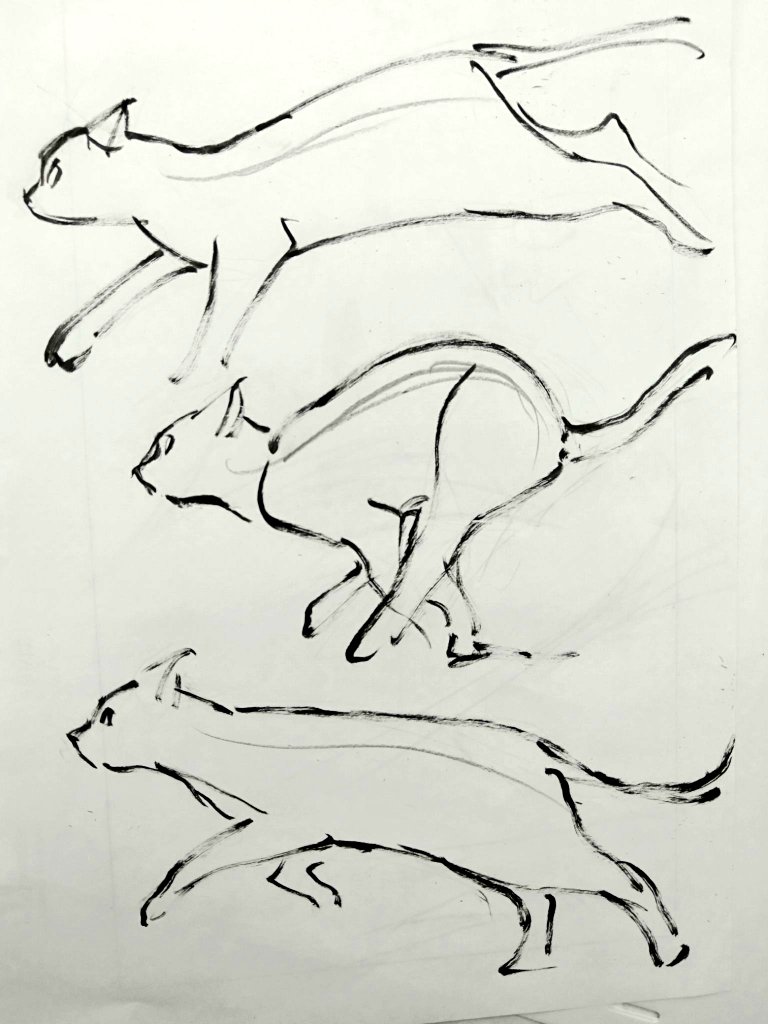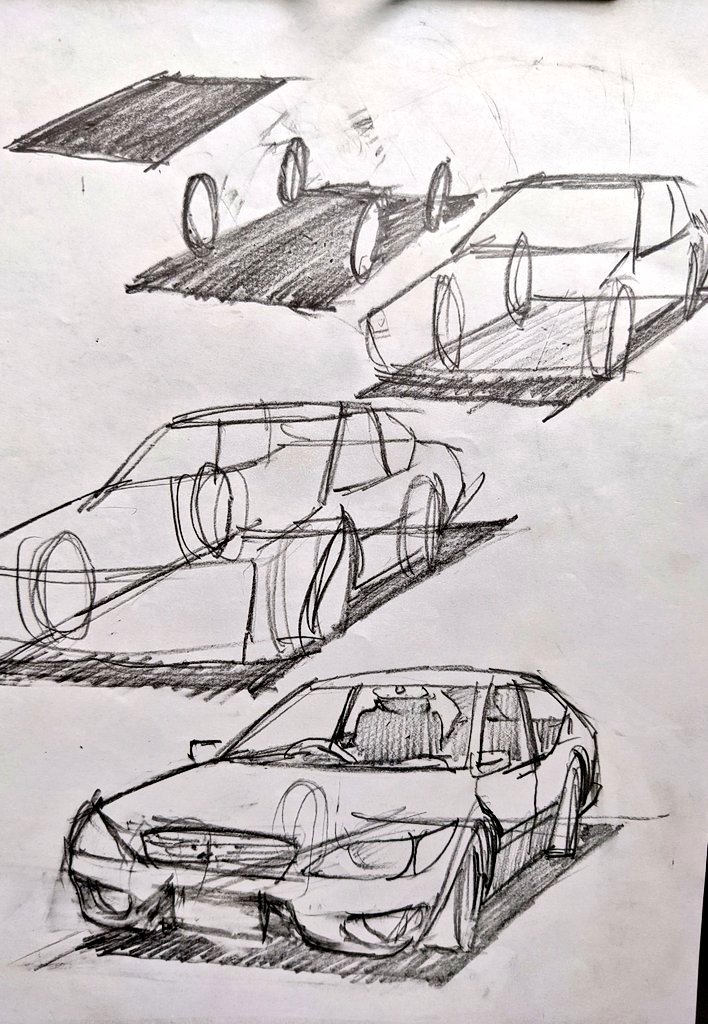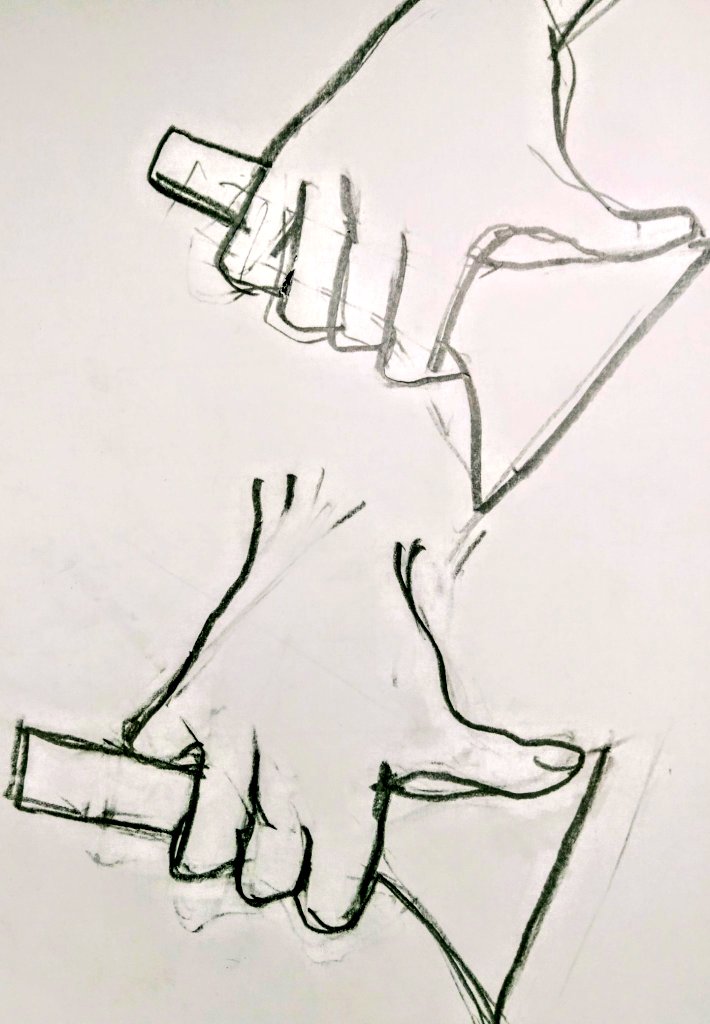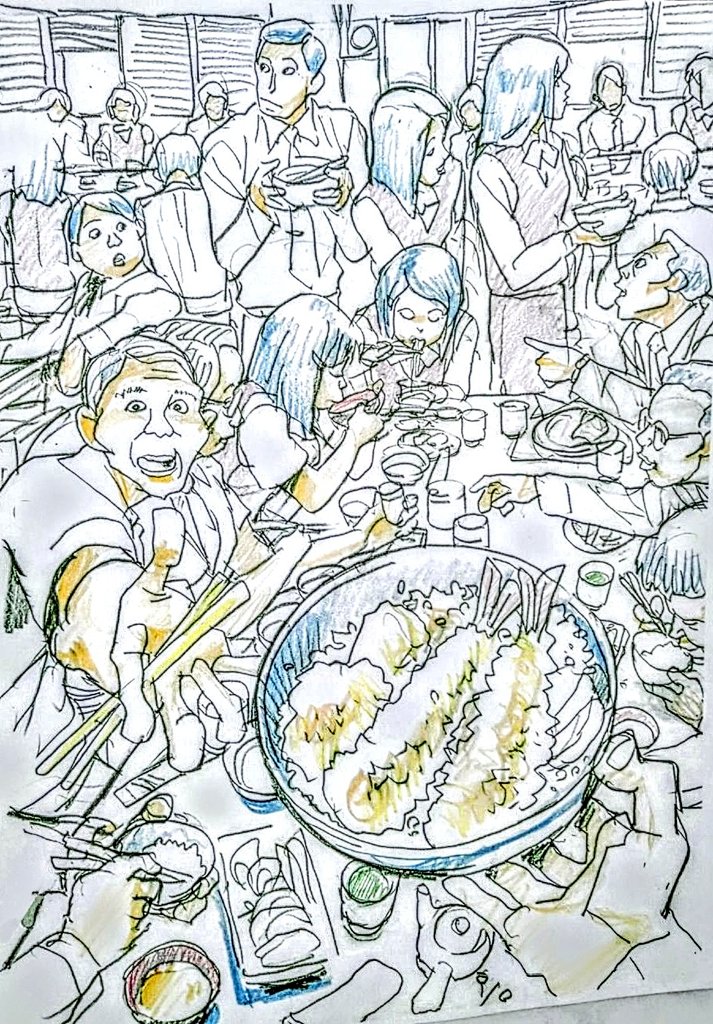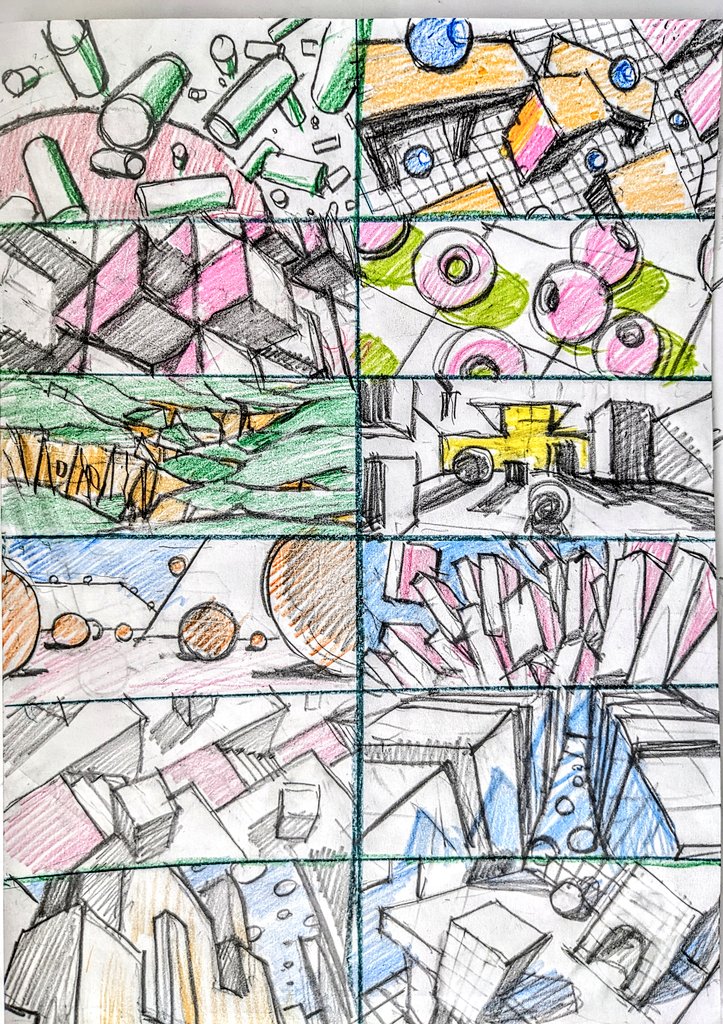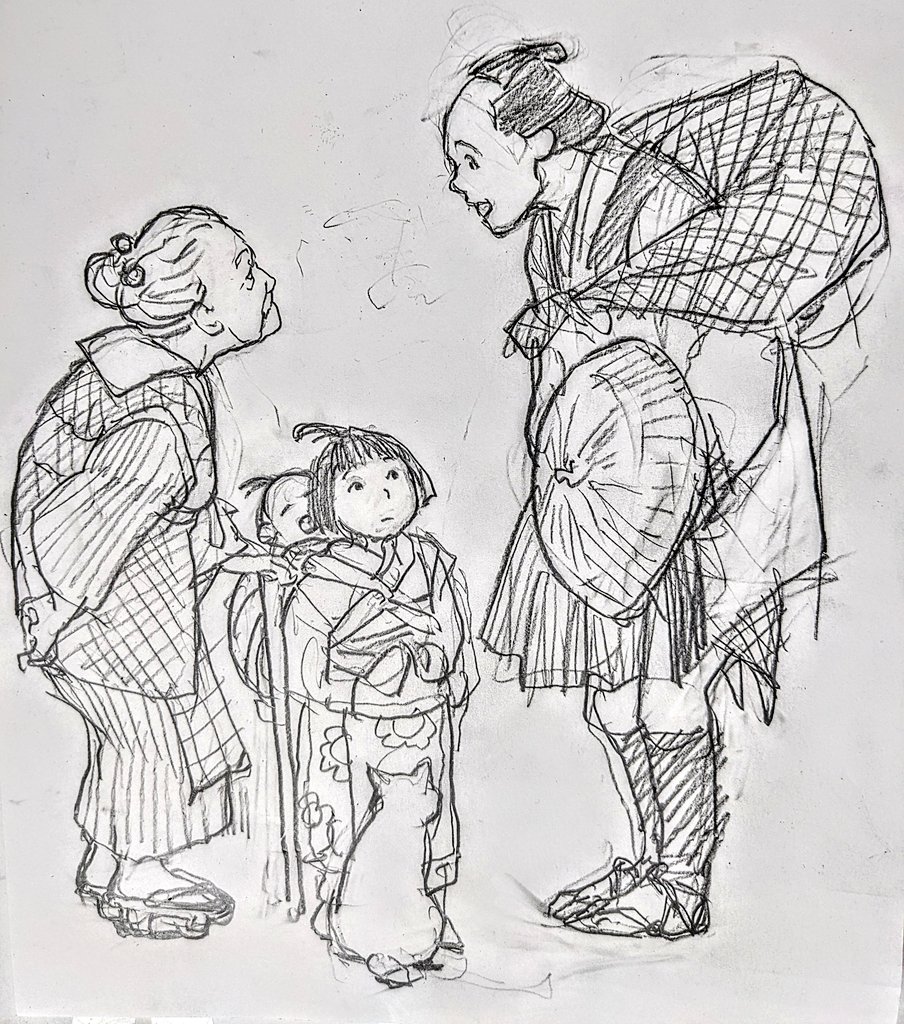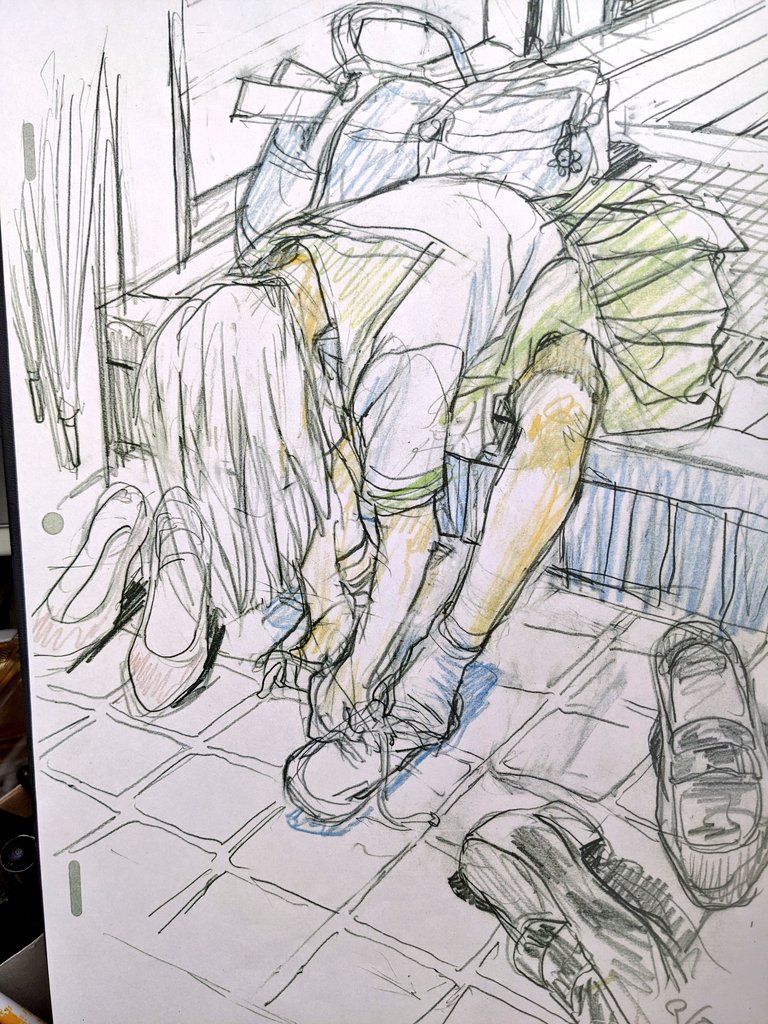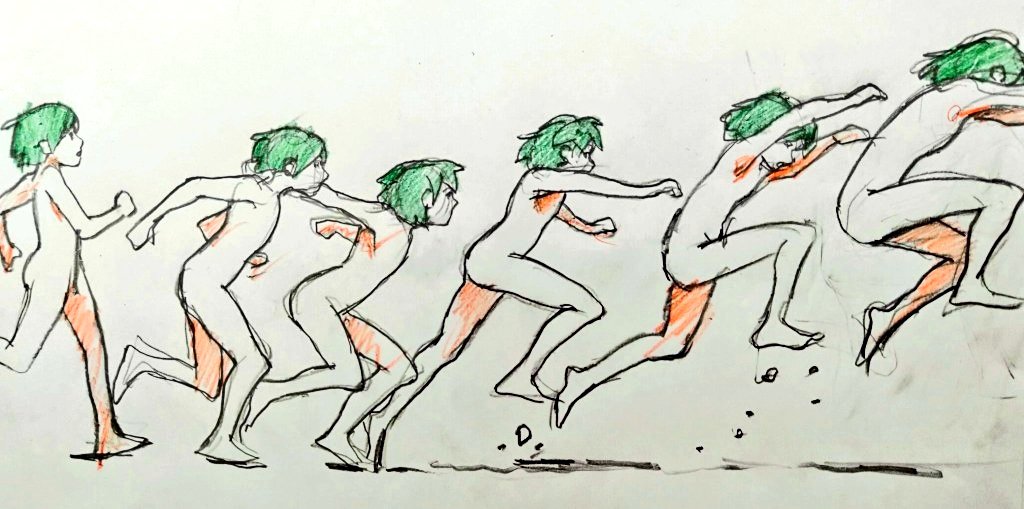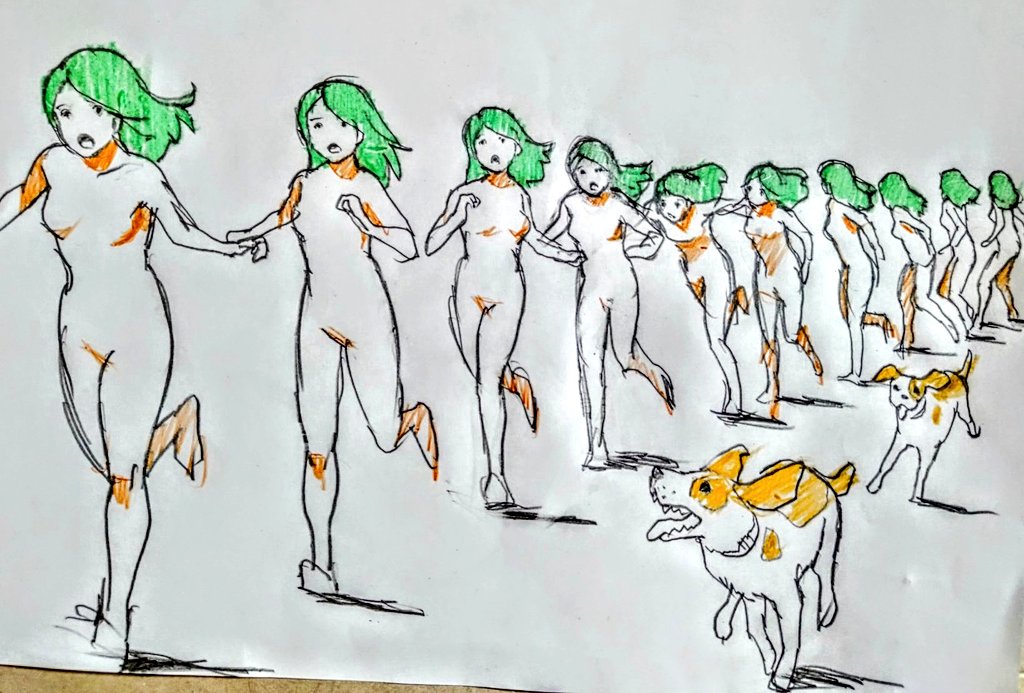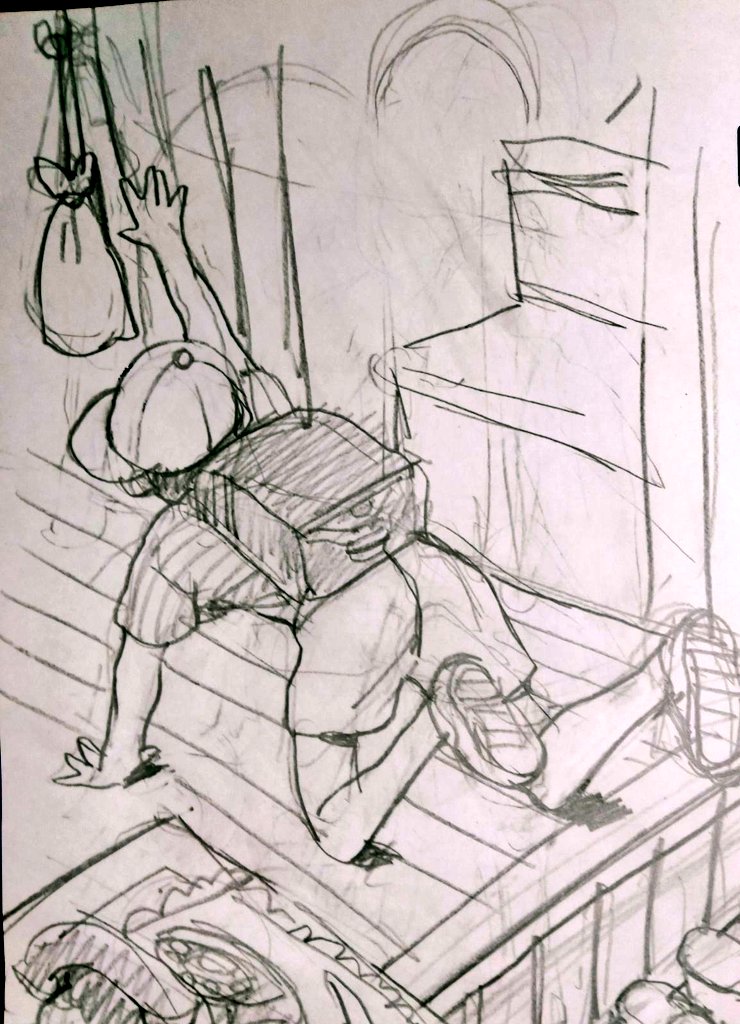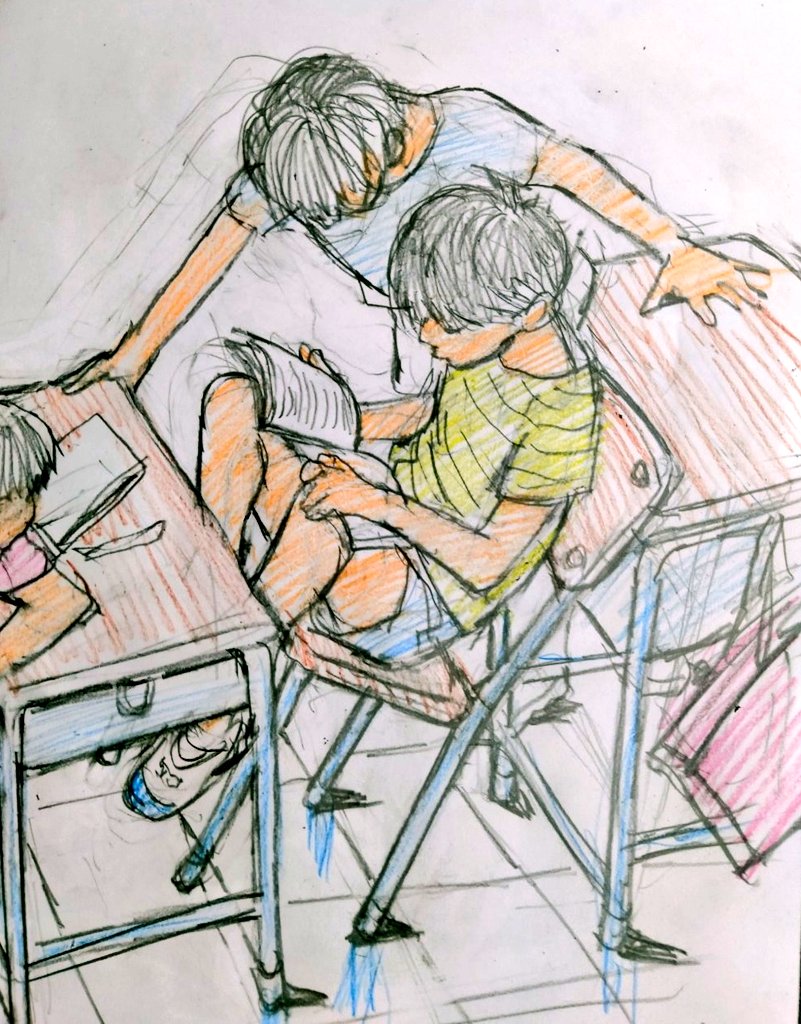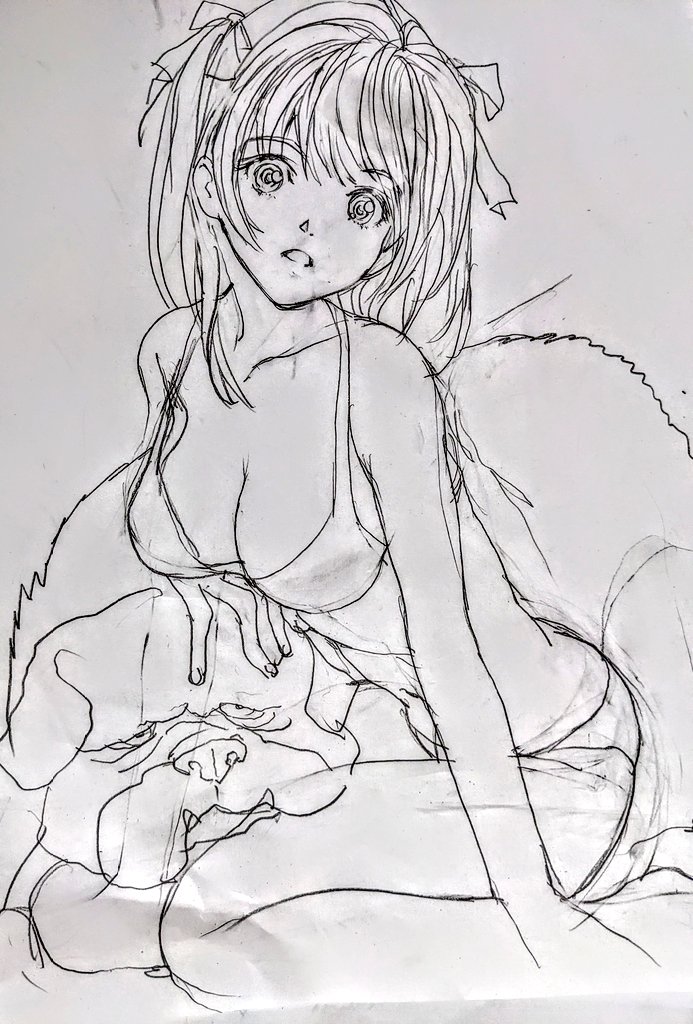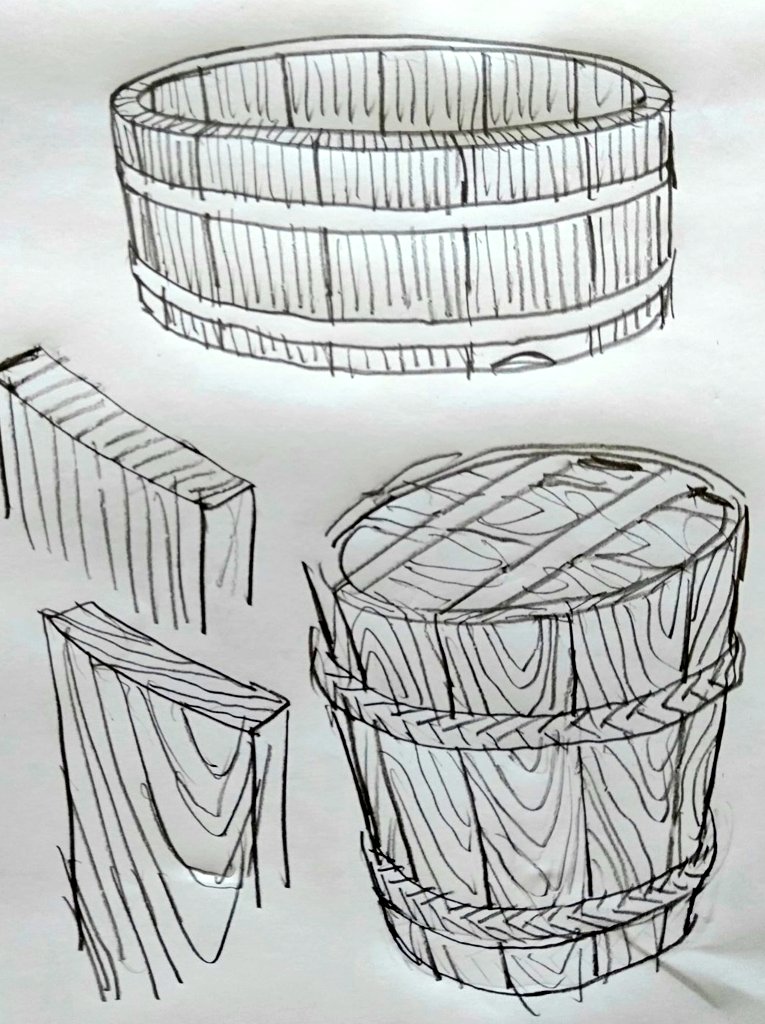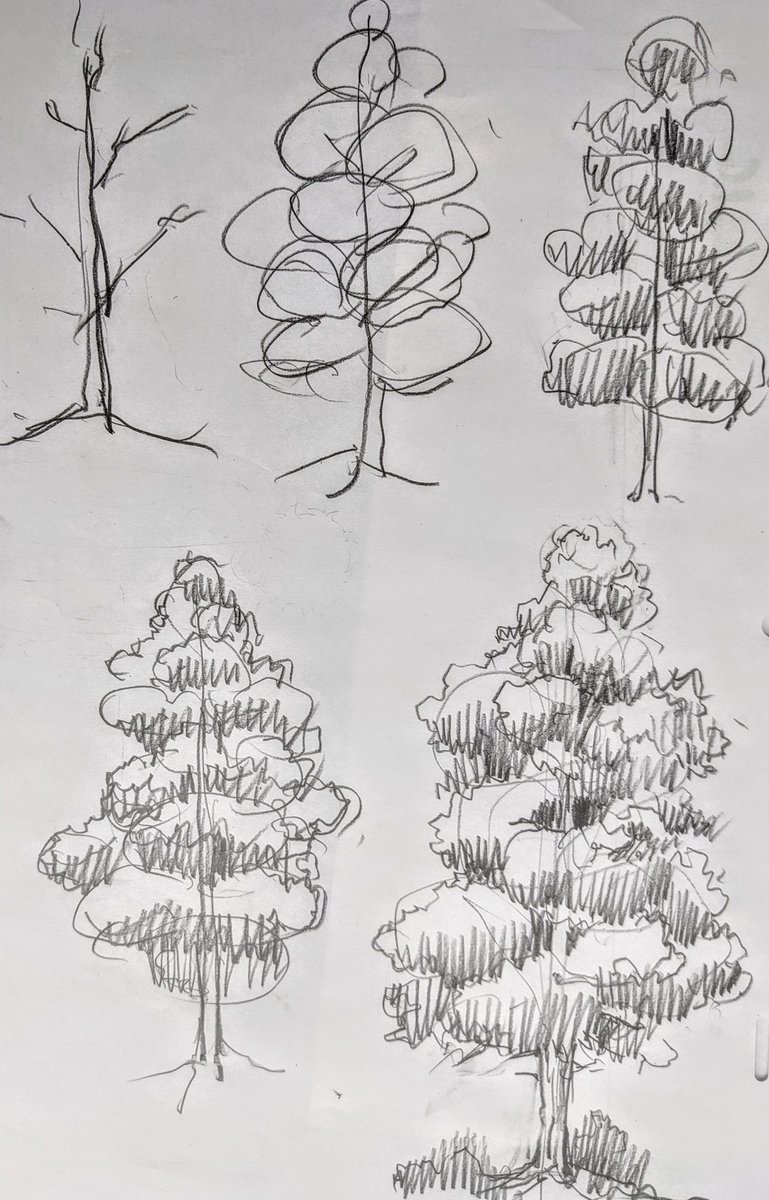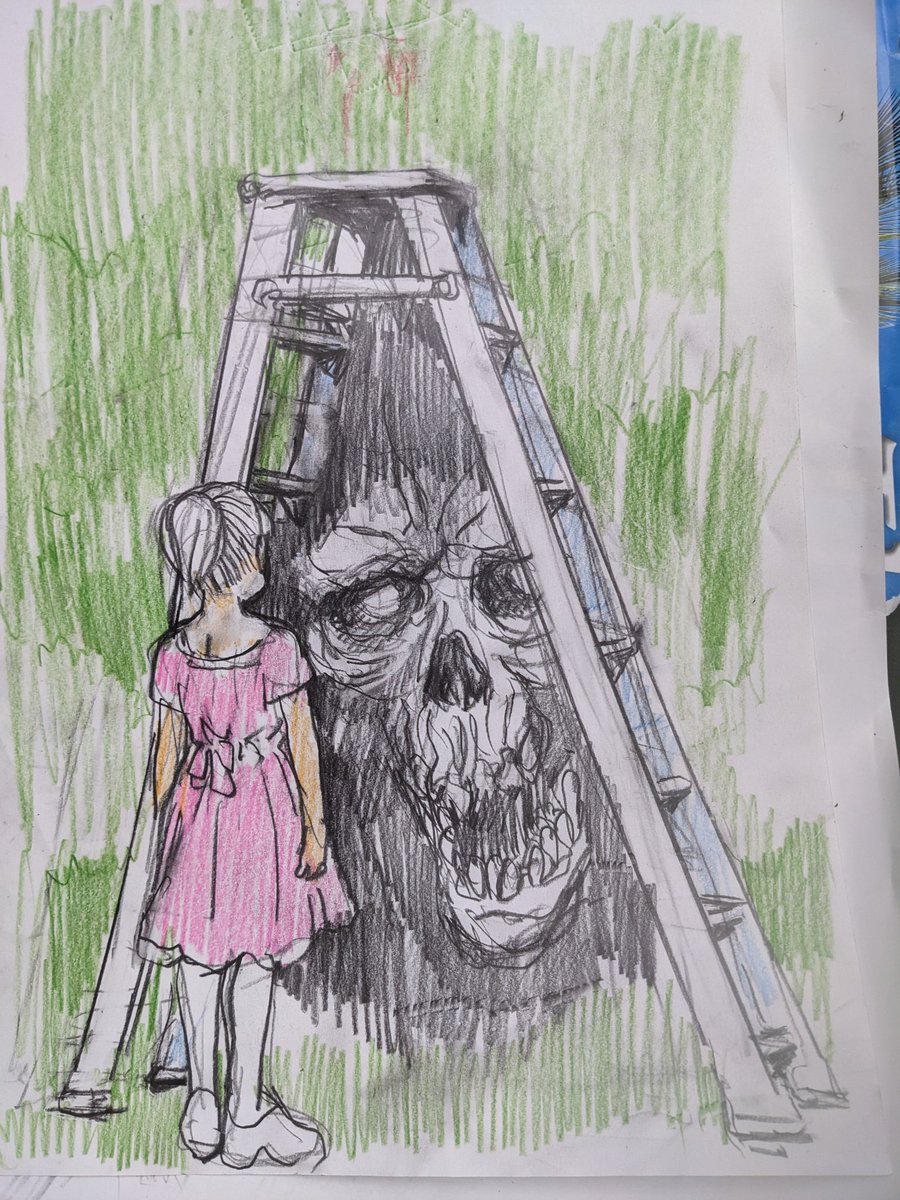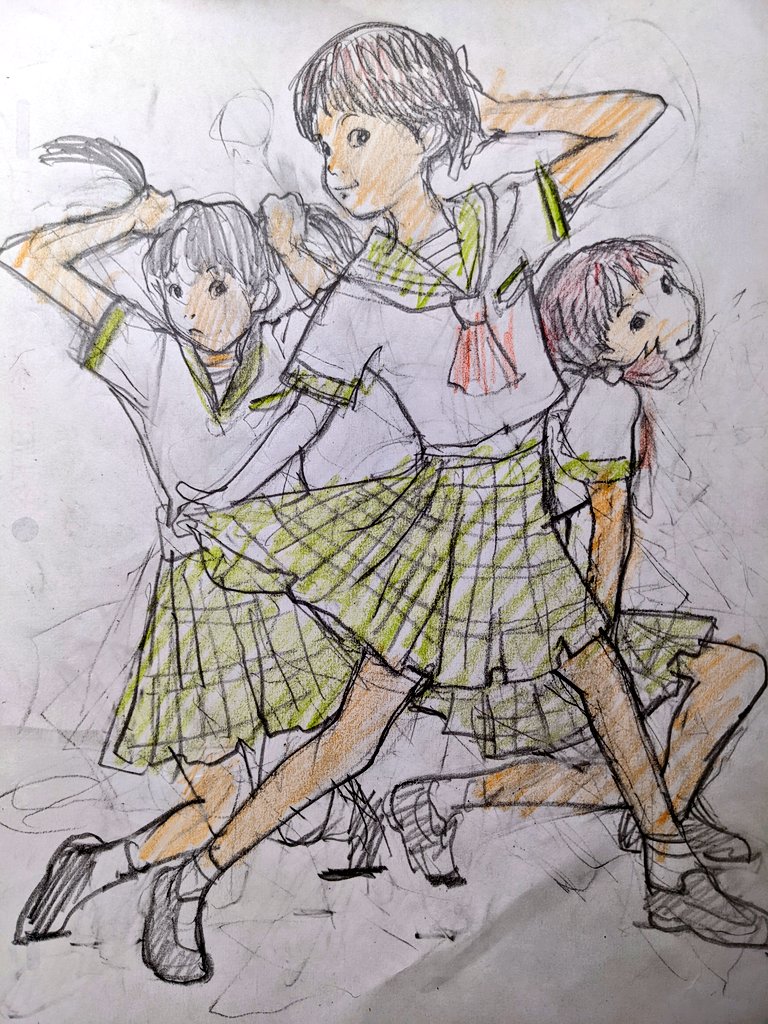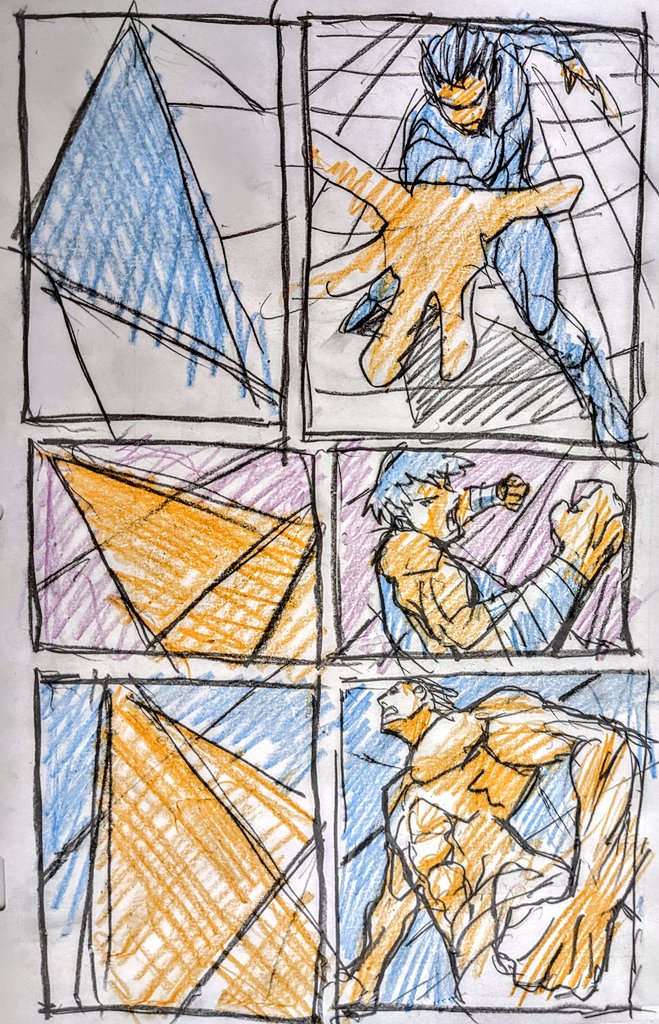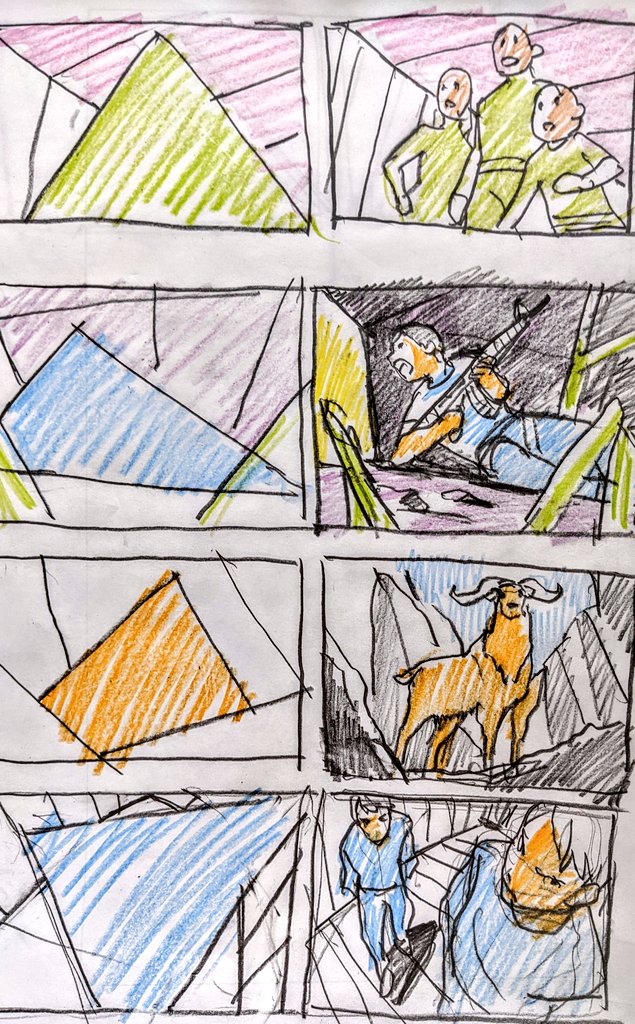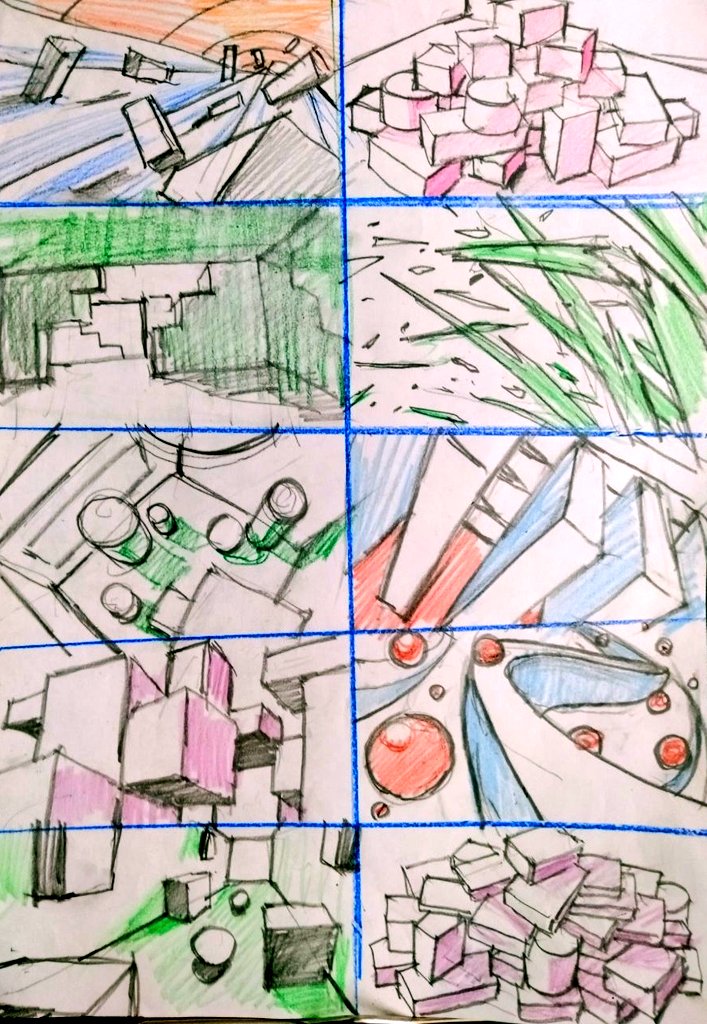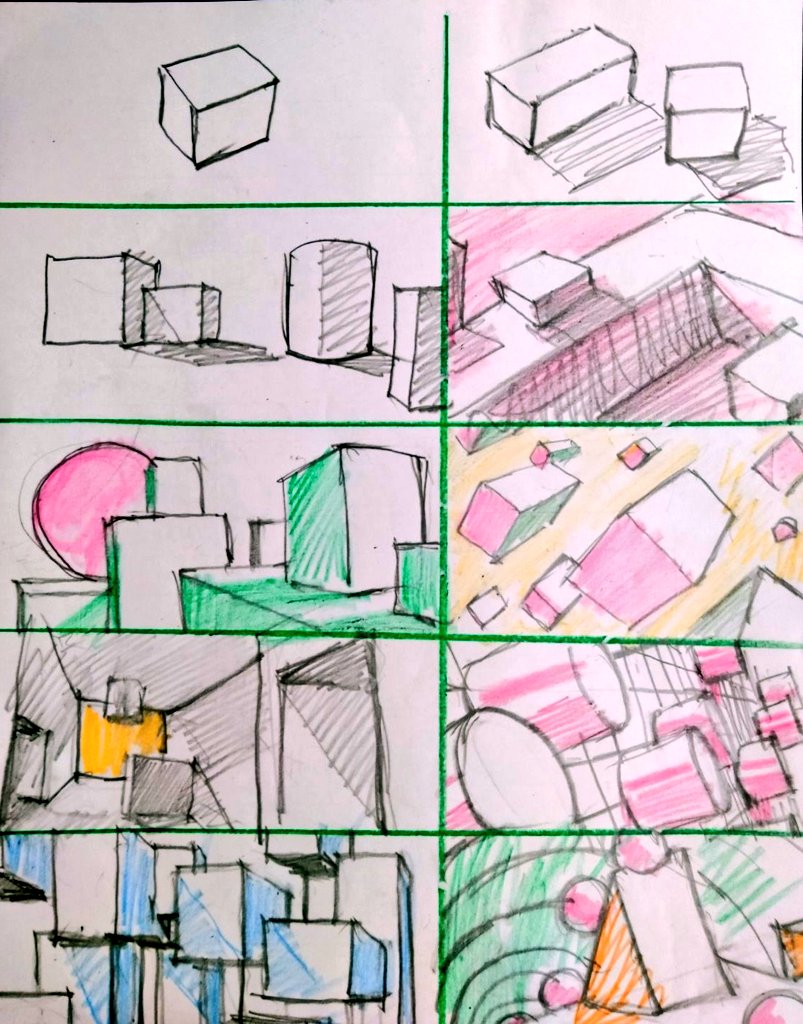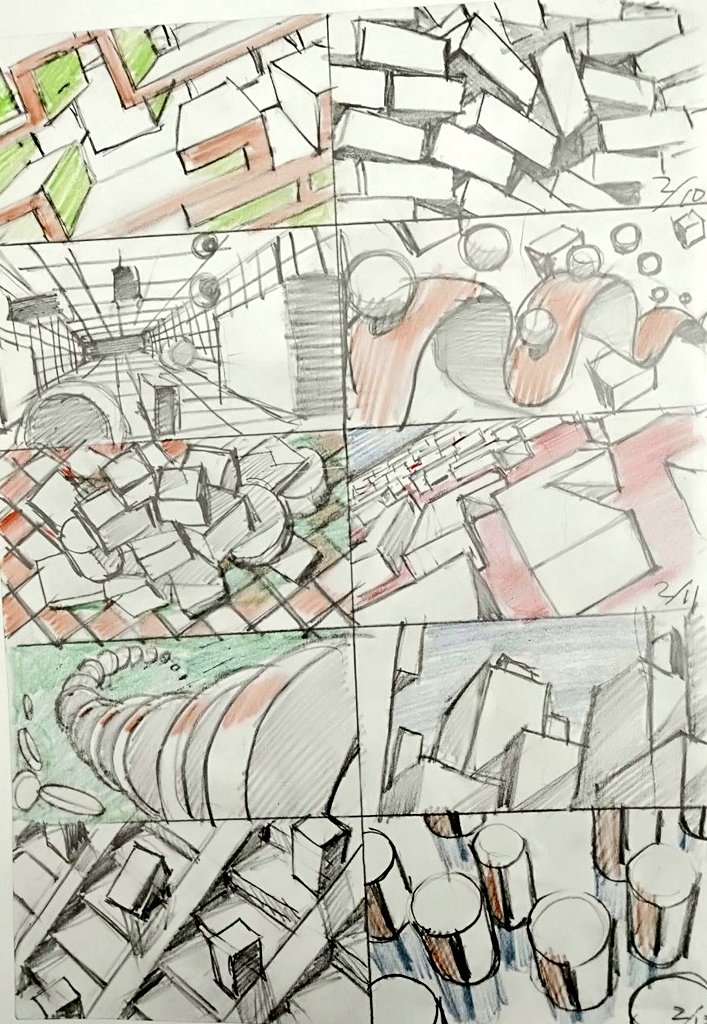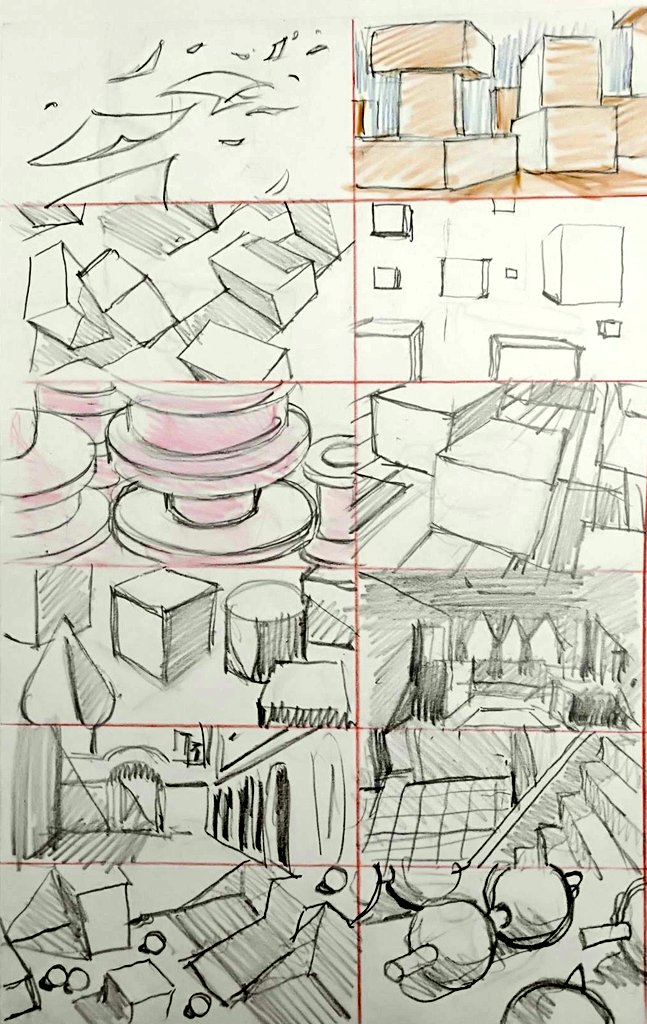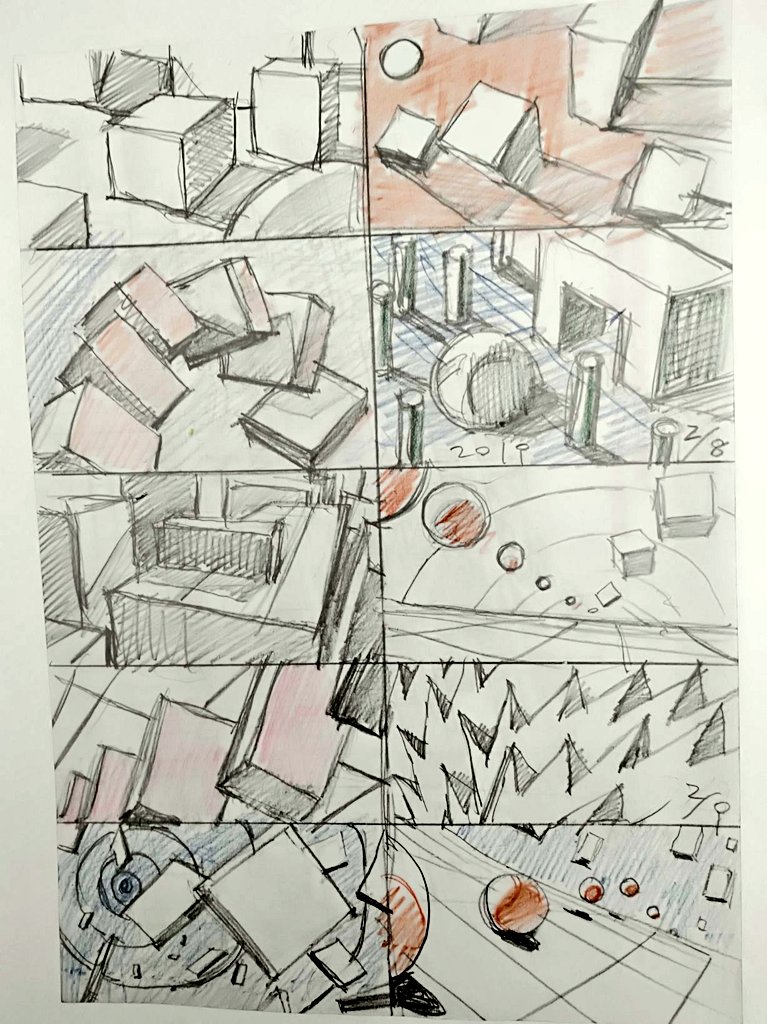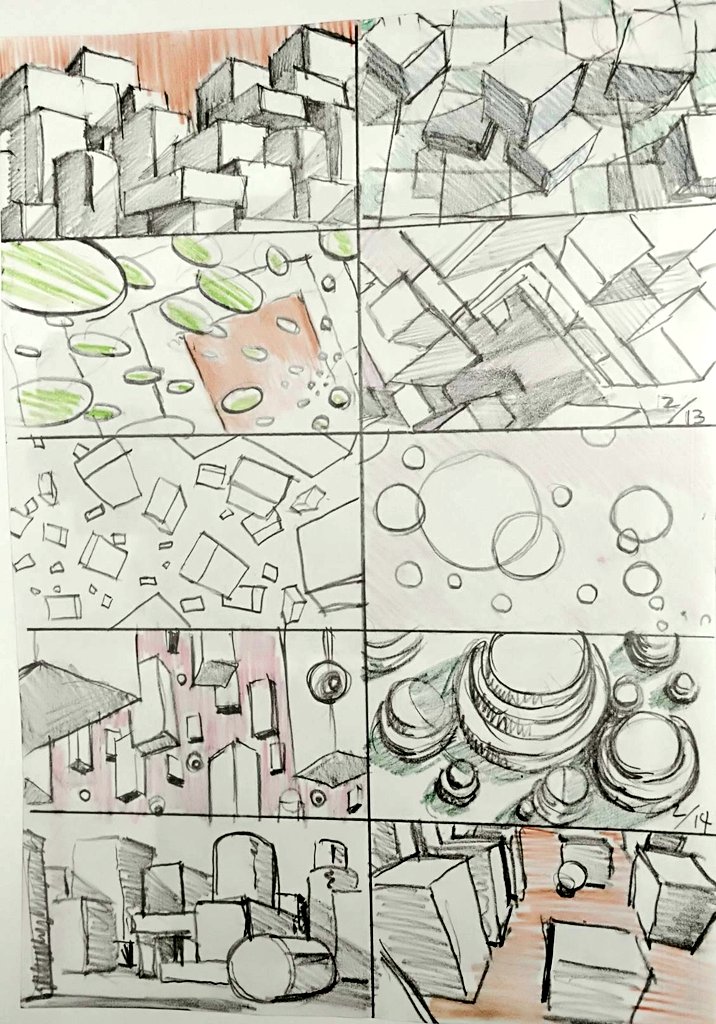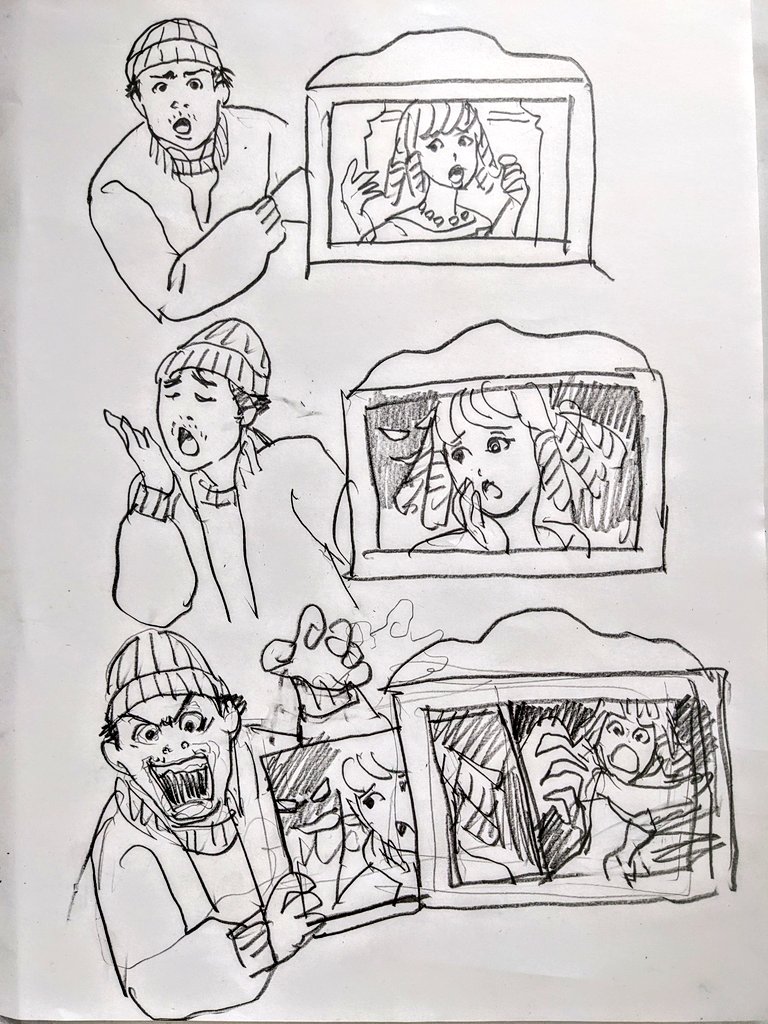2
3
4
5
11
16
17
18
20
25