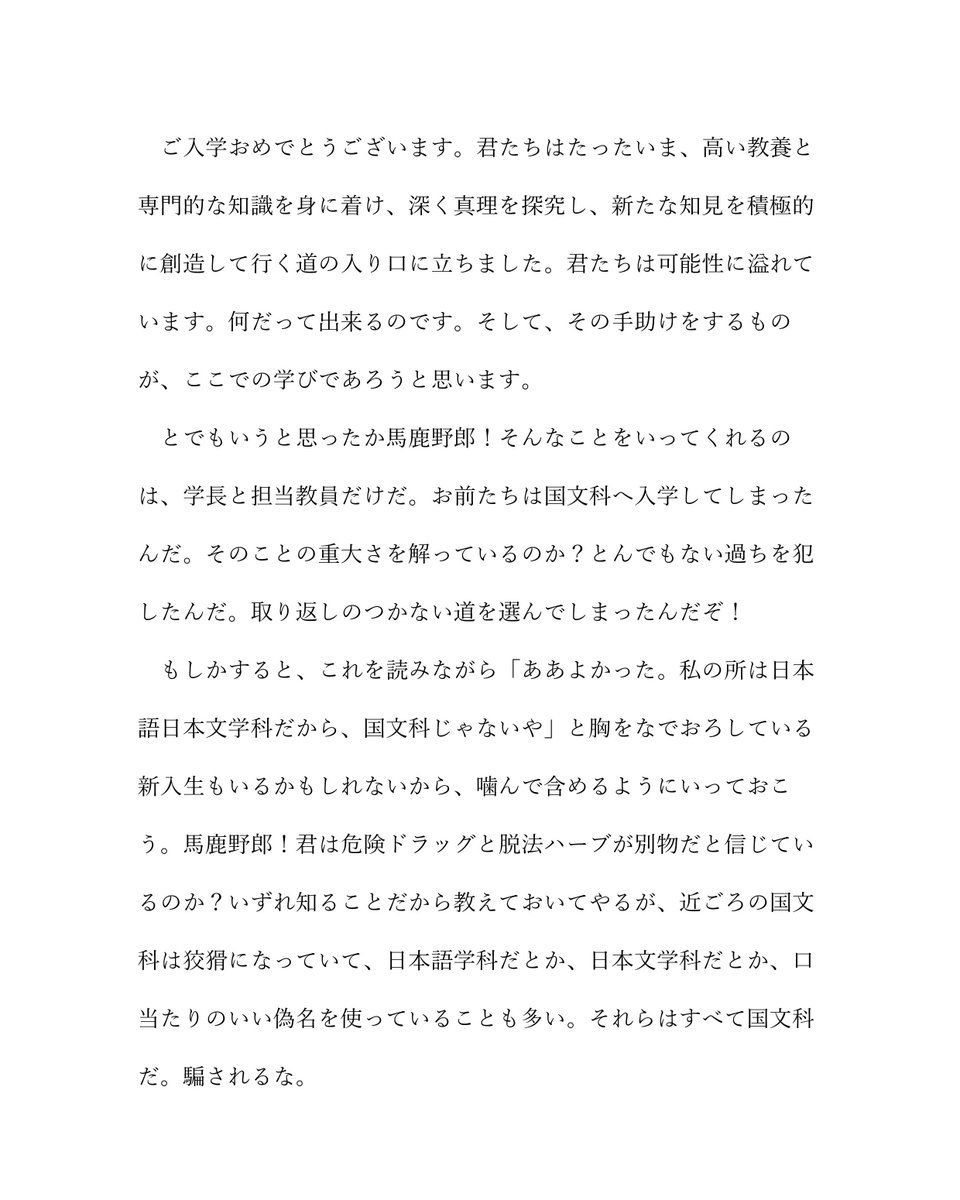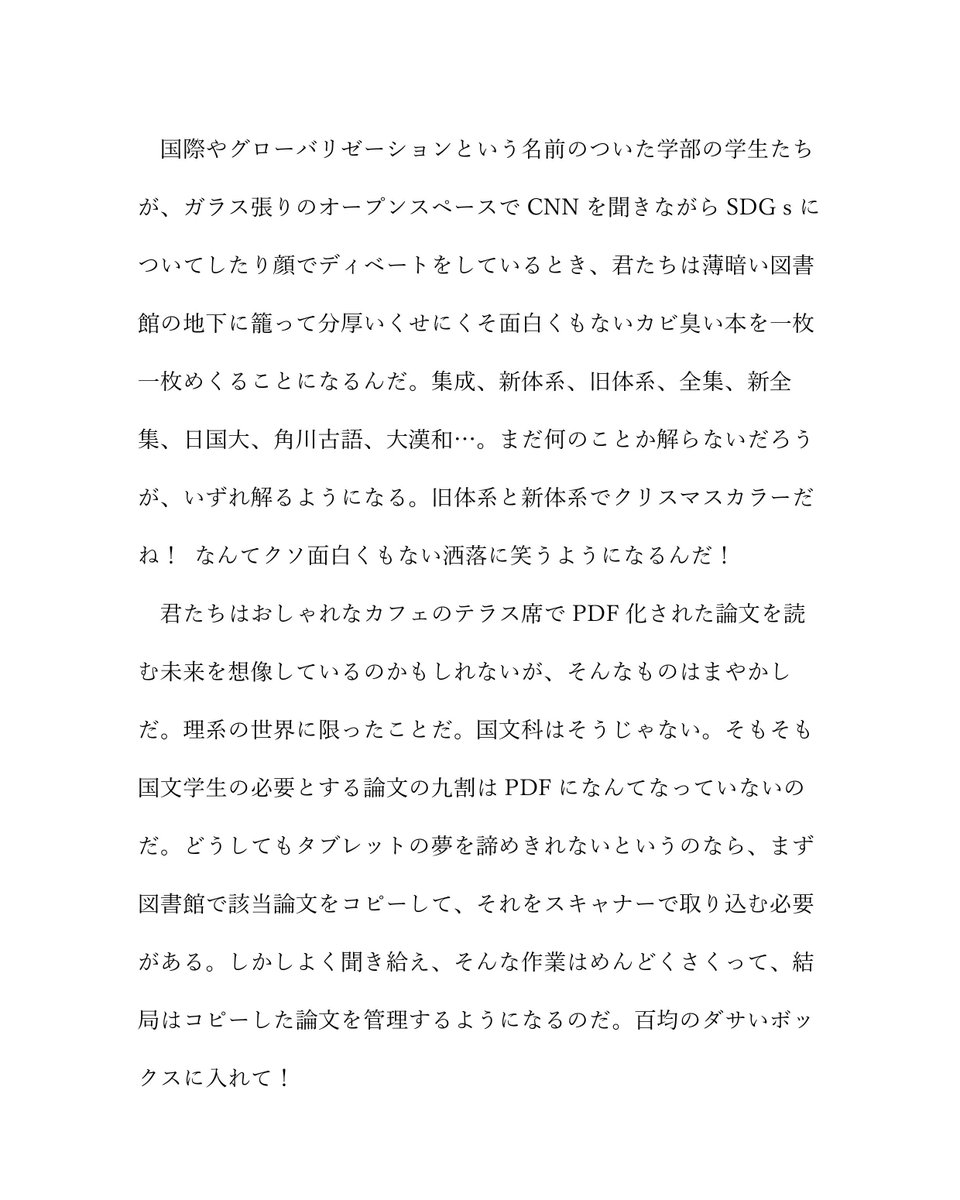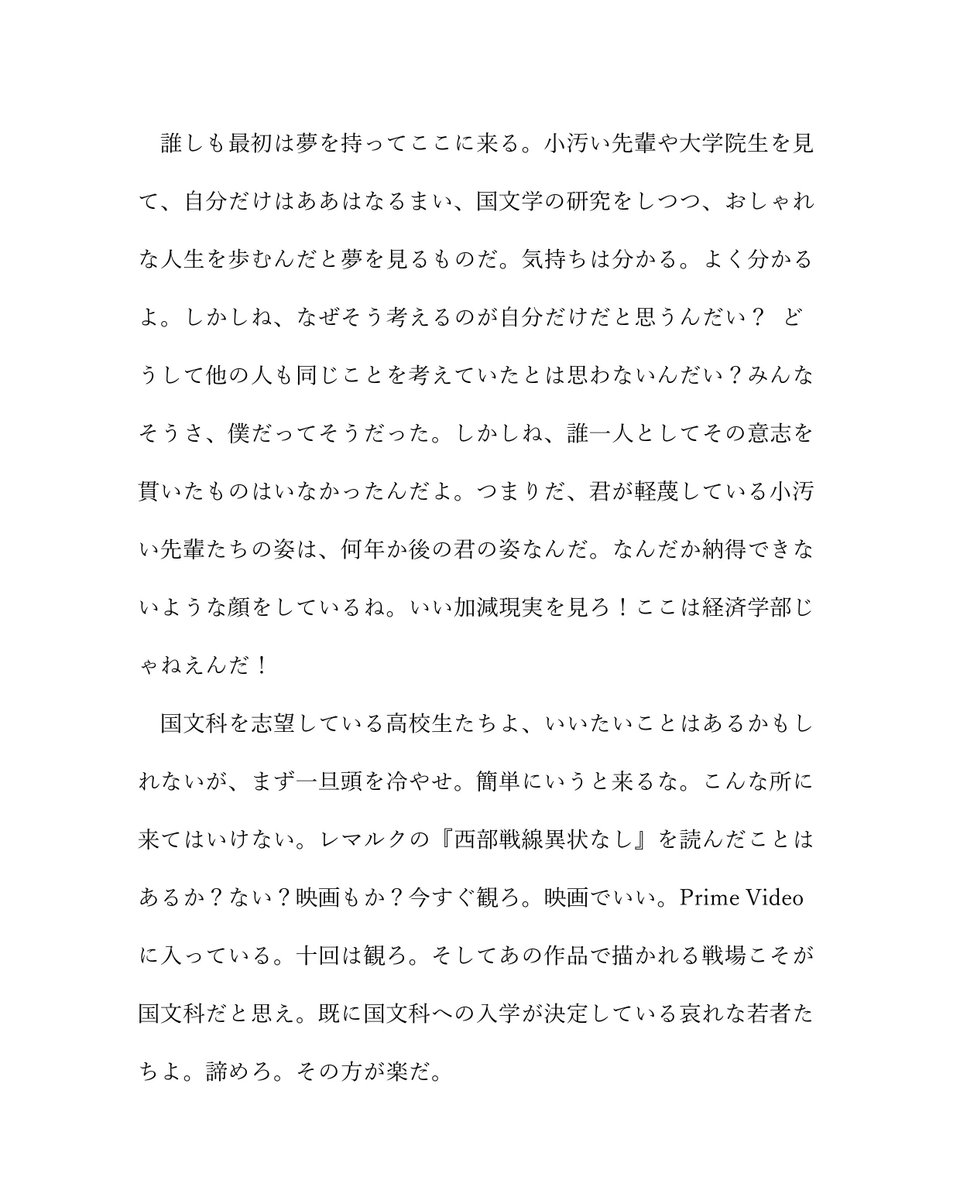1
挫折に次ぐ挫折の末に弊学へ流れ着いた私は、入学式で大学の名前の入った八つ橋が売られているのを、あんなもの誰が買うのだろうと小馬鹿にしながら眺めていた。けれど、その八つ橋を父が大量に買い込み、職場で「うちの子が大学へ入ったんです」と喜び配っていたという話を聞いて、とっても後悔した。
2
面倒くさい大学院生なので、ベッドで作業をしている恋人に「おい! ベッドでMacbookを使うな! そのベッドは無印のベッドなんだ! 無印のベッドに寝転がって、Macbookでスタバの新作ページを眺めるなんて、丁寧な暮らしじゃないか! 言語道断だよ!!!」と叫んだりします。
4
(どうして変わってしまったんでしょう?)もちろんコロナもありますが、やはり能を芸術として観るようになったのが大きいですね。そしてこの風潮は、関西より関東の方が強いです。(歌舞伎でも観劇中に何かを飲むと嫌な顔をする人がいますね)そういう人の方が野暮なんです。
5
先生:私が能を見始めた平成初期までは、観客は上演中にバナナ食べたりしてたんです。けど今では飴の袋をあけることすら憚られるでしょう。能の歴史を見ても、明らかに今が異常なんです。能の歴史の上からいえば、飲み食いをしながら観るのが普通なんですから。
6
7
駅が混んでいてお土産の551買って来られなかったや、ごめんねと祖母に伝えたら「もう生きとるうちに食べられへんかもしれんなァ…」というので、くそう、後期高齢者しか使えないずるい台詞を使いやがって…! と思いながらネットでお取り寄せの注文をしました。
8
結局、ある先輩の「立ち話もなんですから、カステラでもいかがですか?」のひと言で、先生方は生もののカステラを食べてお帰りになりました。生ものとは何だったのか、先生方はいまも不思議にお思いの事でしょう。カステラ騒動はこれにておしまい。めでたしめでたし。
9
もういっそ、お醤油とわさびを出して「先生方どうぞ、いま流行りの台湾カステラのお刺身です」といってしまおうかとも思いましたが、そうもいきません。第一先生方が本気になさってしまう可能性が二割くらいある。そんなはずがあるまいとお思いでしょうが、なにせここは国文科です。
10
運よく何人かの先生が院生の研究室まで来てくださいましたが、誰も机の上のカステラには触れません。距離を取りつつ世間話をなさっています。しかしそれでいて、時折ちらちらと部屋の中を見渡したりなさる。そうです「生もの」を探していらっしゃるのです。先生、生ものはそこです。そのカステラです。
11
きっと先生方は研究室の鍵を閉めながら、おや先生も国文科の研究室に? ええ、先生もですか。なんでも生ものがあるそうで…。いったい何があるんでしょうなあと、立派なカイゼル髭を触りながらお話なさったに違いありません。しかしあるのはカステラです。
12
ばかやろう、カステラは焼き菓子だぞ。んなこといったって緊張してたんだから仕方がないじゃねえか、次だよ次、次こそ気を付けりゃいいんだろ。そんなやり取りをしながら、今度は別の先生に電話をかける。「あのぅ、〇〇さんが生ものを…」また生ものです。
13
さっそくひとりの院生が電話をかけます。「あのォ、〇〇さんが生ものを差し入れて下さいまして…」ふいに出た生もの発言に、様子を見守っていた一同も一瞬怯みましたが、いってしまったものは仕方がない。先生方はきっとお刺身か何かとお思いになられた事でしょう。しかしあるのはカステラです。
14
ではどうやって教授たちを部屋に呼ぶか。ここが問題です。礼儀としてはこちらから研究室を訪ねてお誘いするのが本来だけど、それなら端から持参すべきだし。悩んだ末に、我々は内線で研究室に電話をかけることにした。そうです、内線というものを使ってみたかったんです。使ったことないから。
15
しかし一本のカステラには、コロナ世代の院生たちに夢を見させる何かがあったんです。寄席にいる前座のように細々とお茶やコーヒーの準備をしながら、耳をダンボにして教授たちのお話を聞く。そんな古き良き大学院の夢を、たとえ一時でも見る事のできる何かが、カステラ(福砂屋)にはあったんです。
16
幸い何人かの教授は各々の研究室にいるらしい。そこで我々は「このカステラをきっかけに教授を集める事ができれば(講義では聞かせてくれない)様々のお話が聞けるに違いない! カステラも片付くし…」と思い立ったわけです。いやあ短慮、短慮ですよ。コロナ禍だもの、とても呑気にお茶はできない。
17
昨日、先輩が研究室に、福砂屋の立派なカステラを差し入れして下さったんですね。文明堂ではなく福砂屋という時点で我々は大喜びなのですが、いかんせんその日は講義もなく、部屋に院生は三人しかいない。とても三人では食べきれないし、食べてしまうのも勿体ない。なにせ福砂屋です。
18
その間、切られ役のヘビは、まだ九月の暑い時分というのに、不自由な姿勢のままじっと刀を待っている。いまでこそ歌舞伎を観に行っても、田舎者とバレないようにすまして座っているけれど、いつかあのお神楽の晩のように「封印切ったらいけんわァ」と声に出してみたいなあ思う。
19
例年の通り、ヤマタノオロチが酔って寝てしまうと、かぶりつきの私たちは、口々に「寝たらいけんわァ」と声を漏らす。すると今まで筵に背を向けていたスサノオが、ひょいと振り返って「そうじゃなあ、寝ちゃいけんわなァ」という。私たちはおかしくって「そうじゃそうじゃ」と声をかける。
20
私の育った村は、毎年秋のお祭りにお神楽を呼ぶんです。演目は決まって『ヤマタノオロチ』なのだけれど、神社の境内に敷かれた筵の上で、小さな私たちは飽きもせず「今年もあのヘビがやられるんじゃ」「アホ、あれはヤマタノオロチいうんで」なんていいながら楽しく眺めていた。
21
父のお供で「シンドラーのリスト」を観てる。毎回、歴史と文学の教師が「私が役に立たない? 間違ってる、君たちは間違っている。私は歴史と文学の教師なんだぞ。それが役に立たない?」といいながら、SSに連行されるシーン(研磨工と偽ることで助かる)で泣いちゃう。
22
恋人の家にお招きされたんだけど、なに着て行ったらいいの?という私の質問に、TLの全裸中年男性フォロワーたちから「スラックスやろうなあ」「スラックス履いてこ」「スラックスに綺麗めのシャツがよい」と次々にアドバイスが届いて、全裸中年男性も恋人の実家に行くときは服を着るんだなあと思った。
23
知り合いのおねえさんは、京都へ嫁いだ最初の年に、近所から貰った祇園祭の粽を食べようとしたと言っていた。「ひとりで食べようと思って、旦那が寝静まったのを見図らって包を解いたら何も出てこないの。よそ者だからいじめられてるのかなって思った」とのこと。いい話だよね。
24
恋人、京都の大学に通い始めてもう三年になるのに、コロナ直撃世代だから、祇園祭を一度も見たことがないらしい。私が、食べられない粽の話をしたら「またまた~」という顔をしていたけど、本当だよ。京都の人はケチだから、食えない粽を売ってんの。
25
古文漢文不要論がTLを賑わすたびに、私はこの話を思い出すよ。エリートとパンピーの分断を生まないためにも、ある程度の教育は必ずあった方がいい。どんな田舎の貧乏人にも「春眠暁を覚えず」を習う機会があって、孟浩然先生に「ほんまそれな!」をすることのできるチャンスは残しておくべきだと思う。