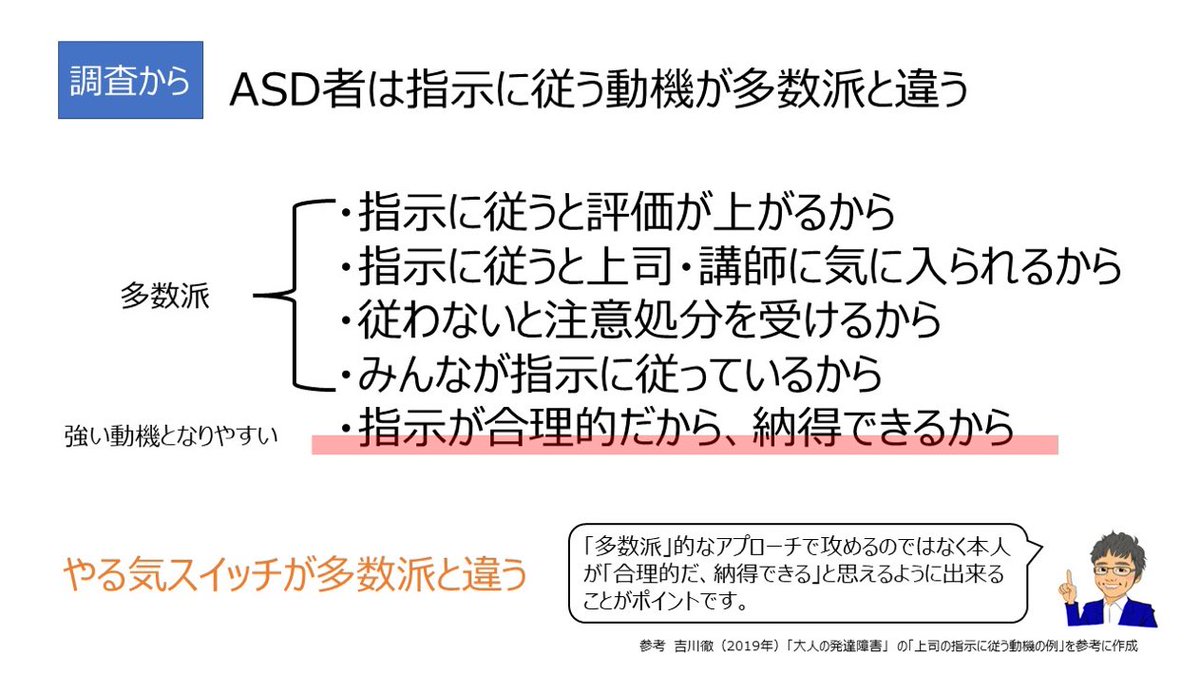1
2
ASD児者の傾向として「嫌いなものが増えていきやすい」ことがあげられる。記憶力が良く、一回嫌な思いをした場所、失敗した経験、酷いことを言ってきた相手はよく覚えている。結果的に行きたくない場所、関わりたくない人、やりたくないことなどが増えやすい。
3
ASD児者の課題は「選好形成(好きを増やす)」
児にとって「楽しいな」「面白いな」と「好き」が増えるようにサポートをする。例えば、一緒に何か活動して褒めたり感謝したり「上手だったね」とフィードバックを返したりして「嬉しい」を増やしてあげることで「好き」が増えていく助けになる。
4
ASD児者の傾向として「嫌いなものが増えていきやすい」ことがあげられる。記憶力が良く、一回嫌な思いをした場所、失敗した経験、酷いことを言ってきた相手はよく覚えている。結果的に行きたくない場所、関わりたくない人、やりたくないことなどが増えやすい。
5
親の躾とか育て方が原因で発達障害になることはないが、発達障害の素因を持った子どもが環境によって生きづらさを抱えたり、逆に長所を生かして、社会的に成功する人となることもあるので、環境の調整や育て方、接し方が重要であると思う。有名な話で、坂本龍馬が寺子屋で字が上手く書けなかったことや
6
ADHD者の衝動性には「内面の衝動性」がある。
素早い判断、決定が出来るという利点はある一方で後先考えずに簡単に物事を決めてしまうので後で後悔することも。心の中では様々なまとまらない考えが浮かんでは消えを繰り返しているので頭の中が多動な状態となっている。
7
8
障害者雇用に慣れていない企業さんで,超ありがちなこと.採用したばかりの方が1人で「寂しそうに」お昼を食べている場合,良かれと思って一緒にご飯を食べましょうと誘う.本人は貴重な休憩時間にクールダウンしたり頭の整理をしたいのにお昼も気が休まらない.本人にどう過ごしたいかを確認するのがベター
9
ASD者が定型発達のコミュニティーに適応するために取る対処行動として「社会的カモフラージュ行動」がある.
意識的・無意識的に定型発達者の行動を模倣することによって「ASDであることを隠そうとする行動」のこと. 信州大学の本田秀夫は「普通の人を模倣させることは精神衛生上よくない」更には
10
ADHD者に自尊心が育ちにくい理由
①成功体験を積むことができない
②周囲の評価が低い
③出来るのにやらない,怠けていると誤解されやすい
④無理解な親や教師から過大な期待をかけられる
⑤できたりできなかったりと症状が変動する
引用 星野仁彦「発達障害を仕事に活かす」朝日新書(86-106)
11
12
英国の研究者ハウリンはASD児者の特性として,「幼少期には同世代との接点を避け大人やより年少の子どもとの関りを好むが,成長するにつれ同世代との関係で自分が人に受け入れられるか,人の輪に入っていけるか,友人をつくれるかを非常に気にするようになる」と述べており、傾向として学年が上がるほど
13
ADHD(注意欠如多動症)は病名とは矛盾するが「注意力」が常に「欠如」しているわけではない。興味を感じる特定の対象に対してはむしろ過剰な注意、集中力が向けられる、一方でじっくり集中して行う作業などに対しては集中して課題に取り組むのが難しい。ゆえにADHD者は「注意の配分が不得手」と言える。
14
ASD児者の課題は「選好形成(好きを増やす)」
児にとって「楽しいな」「面白いな」と「好き」が増えるようにサポートをする。例えば、一緒に何か活動して褒めたり感謝したり「上手だったね」とフィードバックを返したりして「嬉しい」を増やしてあげることで「好き」が増えていく助けになる。
15
ASD児者の傾向として「嫌いなものが増えていきやすい」ことがあげられる。記憶力が良く、一回嫌な思いをした場所、失敗した経験、酷いことを言ってきた相手はよく覚えている。結果的に行きたくない場所、関わりたくない人、やりたくないことなどが増えやすい。
16
@NyoVh7fiap ASD児者の傾向として「嫌な出来事など、嫌いなものが増えていきやすい」ことがあげられます。記憶力が良く、一回嫌な思いをした場所、失敗した経験、酷いことを言ってきた相手はよく覚えていて忘れません。結果的に行きたくない場所、関わりたくない人、やりたくないことなどが増えやすいです。
17
信州大学の本田秀夫は、「定型発達と同じように振る舞うこと自体が『過剰適応』であり、この状態を続けているとうつや不安を生じる可能性が高い」と示唆。無理に周りに合わせようとすると心身共に変調のリスクが。周りが求める「普通」という服を無理矢理着こなそうとしなくていい。
18
親の躾とか育て方が原因で発達障害になることはないが、発達障害の素因を持った子どもが環境によって生きづらさを抱えたり、逆に長所を生かして、社会的に成功する人となることもあるので、環境の調整や育て方、接し方が重要であると思う。有名な話で、坂本龍馬が寺子屋で字が上手く書けなかったことや
19
発達障害者は特性が強いほど社会生活に支障をきたしやすく、弱いほど支障が少ないとは言い切れない。軽症であることは「生き辛さ」の程度が軽いことを意味するのではなく、かえって鬱などの二次障害による情緒的な問題を抱えやすいことが指摘されている。
20
21
22
我が家の施策。
これが正解ではないが、バウチャー制度を取り入れてはどうだろう。
nukui.link/article/475624…
23
哲学者キルケゴールは『誰かを理解するためには、その人が理解していることを先ず理解する必要がある』と言っている。親や教育者、支援者は自分たちの価値観、物差しを一旦横に置き当事者の物の見方、感じ方、文化、世界を理解することが大切であり、そこから支援は始まる。
24
学校の友達とオンラインゲームの場に集まり、その仮想空間で一緒に遊んでいる。一昔、放課後に公園に集まって野球をやっていたが、今はその公園が仮想空間になっている。ゲームを取り上げるということは子どもたちの公園を取り上げるということに。ゲーム=悪いものという親世代の価値観では気づけない
25
長男がオンラインゲームにハマり勉強をないがしろに。
「ゲームを止めなさい!」と言うのは簡単だったが、ゲームにハマっている理由を先ずはしっかり理解したかった。
そこで、一緒に遊んだり、ハマっている理由を聞くことに。そこで、気付いたのがオンラインゲームが「公園化」しているということ