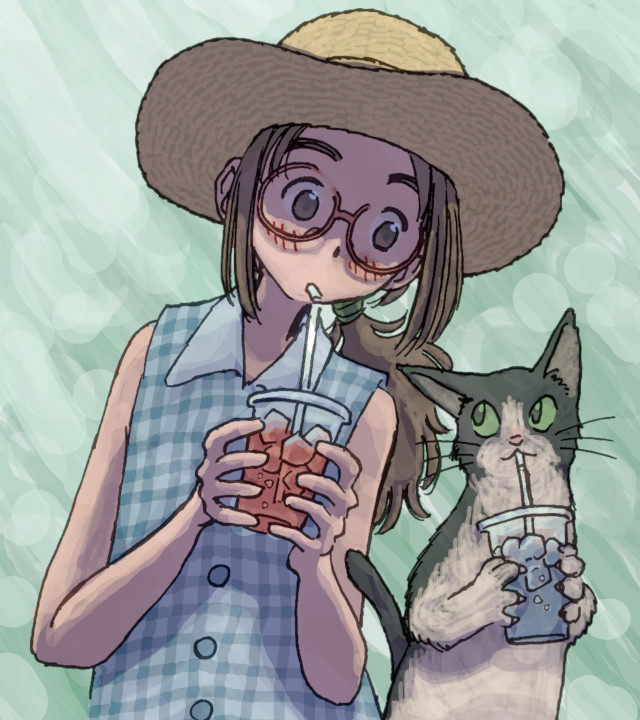2
「根拠がない」「デマだ」「似非理論だ」「ソースを示せ」といった意見に対しては、こちらは何を提示すればいいのか全くわかりません。「こういった諸史実はこう見ることができるね」という視点を提示しているだけで、別にこれが真実だとも信じてくれとも言ってないので。何を求められているのか謎。
3
それともう一つ。王朝貴族の防疫の風習はすばらしいものであり、我々もそれを見習おう、という主張を私は全く持っていません。というのは、王朝時代のそうした習俗はあくまで自分たち特権階級を(究極にはその最上位者を)守るためのものであり、現代社会にはそぐわない部分を多々含むからです。
4
世界のどの地域の社会集団も、それぞれの風土に即した生き延びるための知恵を持っているはずであり、それは宗教の戒律や因習になって継承されているのだろうと思います。そのそれぞれに優劣をつけて考えるのはあまり意味がないと考えます(だってそれはそれぞれの風土への「適応」なわけですから)
5
まず(最初の方にも書きましたが)これは「平安時代の日本人は感染対策を知ってた!すごい!」という意味合いではないです。おそらく当時の人々にとって疫癘(おそらく天然痘がその代表だったでしょう)は、今よりはるかに恐ろしいものであり、どういう条件だと感染りやすいか、どうやったら→
6
このうち「這い伏し」については「それは何じゃ」「どこに載っとるんじゃ」という声が多く寄せられたので別立てで紹介します。枕草子99段(本によっては95段)に、
唐繪にかきたる懸盤して、もの食はせたるを、見入るゝ人もなければ、家の主、「いとわかくひなびたり。かゝる所に來ぬる人は、→ twitter.com/GotoSesame/sta…
7
「でも夜這いは?」という趣旨のコメントもなかなか多いんですが、そりゃ子孫を増やすのは至上命題ですもん…
死の淘汰圧がむちゃくちゃ強い(うかうかしてると死ぬ。一族滅びる)時代なので、死の機会を減らす工夫と生殖の機会を増やす努力は、同時並行的に死に物狂いで行われていたのではないかと。
8
…の件については別スレッド twitter.com/GotoSesame/sta… を立てたので、そっちでまとめます(というか、何かあったらそっちにくっつけます)
9
平安京って約23km^2(4.5km×5.2km)の条里に14~17万人が居住していたので、人口密度は6~7千人ほど(東京23区の約半分。全ての人が平屋に住んでいたと考えるとかなり高い)
人が1日に出す排泄物は大200g+小1.2~1.5Lだそうなので、まあざっくり1.5kgと仮定して、京全体で毎日25tの排泄物が→ twitter.com/GotoSesame/sta…
10
そういえば平安京の屎尿処理ってどうやってたんだろう。貴人の大小便は香箱で受けて御厠人が処理するってとこまでは知ってるけど、その先(と、伸びてるツイにぶら下げて識者の知見を待つ)
11
もう言い古されたことなので、こんなハネるの全く想定外だったんですが(行って100RTくらいと思ってた)こういう爆発的に伸びるツイの常で「ありえない」「デマ」という反応も少なからずありました。特にそれを否定するつもりはないのですが、どこら辺をそう思ったのか少し詳しく聞きたくはあります。
12
したのは自然なことではないかなあと思います。
13
古代の人も病人やその亡骸、病人が触れたものや呼気、分泌物、排泄物などへの接触や接近によって同じ病に罹ることを経験的に知っていたのはほぼ間違いなく、位が高くなればなるほど(つまり血統を存続させる社会的要請が高いほど)、高い人的コストを払っても、そういうリスクを下げようと→
14
すごい勢いでコメントをいただいていて、一つ一つお返しできないですが、言いたかったことは「この諸々の作法はこの共通の目的で説明できるね」ということで、「平安時代の人は流行病の感染機序を知っていて、合理的な対策をしていた!」と主張したいわけではありません。
15
・昼御座や高御座といったカーテンで囲った王座
・殿上と地下を厳格に分けて、許された者にしか昇殿を許さなかったこと
・饗宴で上位が食べ終わってから家司に残肴を食べることが許される
…など挙げればきりがないけど、病原体が下から上に拡がらない工夫ということで説明できる風習がすごく多い。
16
18
別の説として、舵手は舵柄の右側に座るので、右回頭するには舵面を右に(=舵柄を押しやる、つまり面の向く方へ押す)、左回頭するには舵面を左に(=舵柄を引く、つまり取る)からというのもあり、こっちの方が説得力がある(前方へ押すことを面の方へやると表現するのがちょっと耳馴れないが)
19
21
#アイコン晒して10RTきたら有名人見た人もやる
あざといと言われてもやる