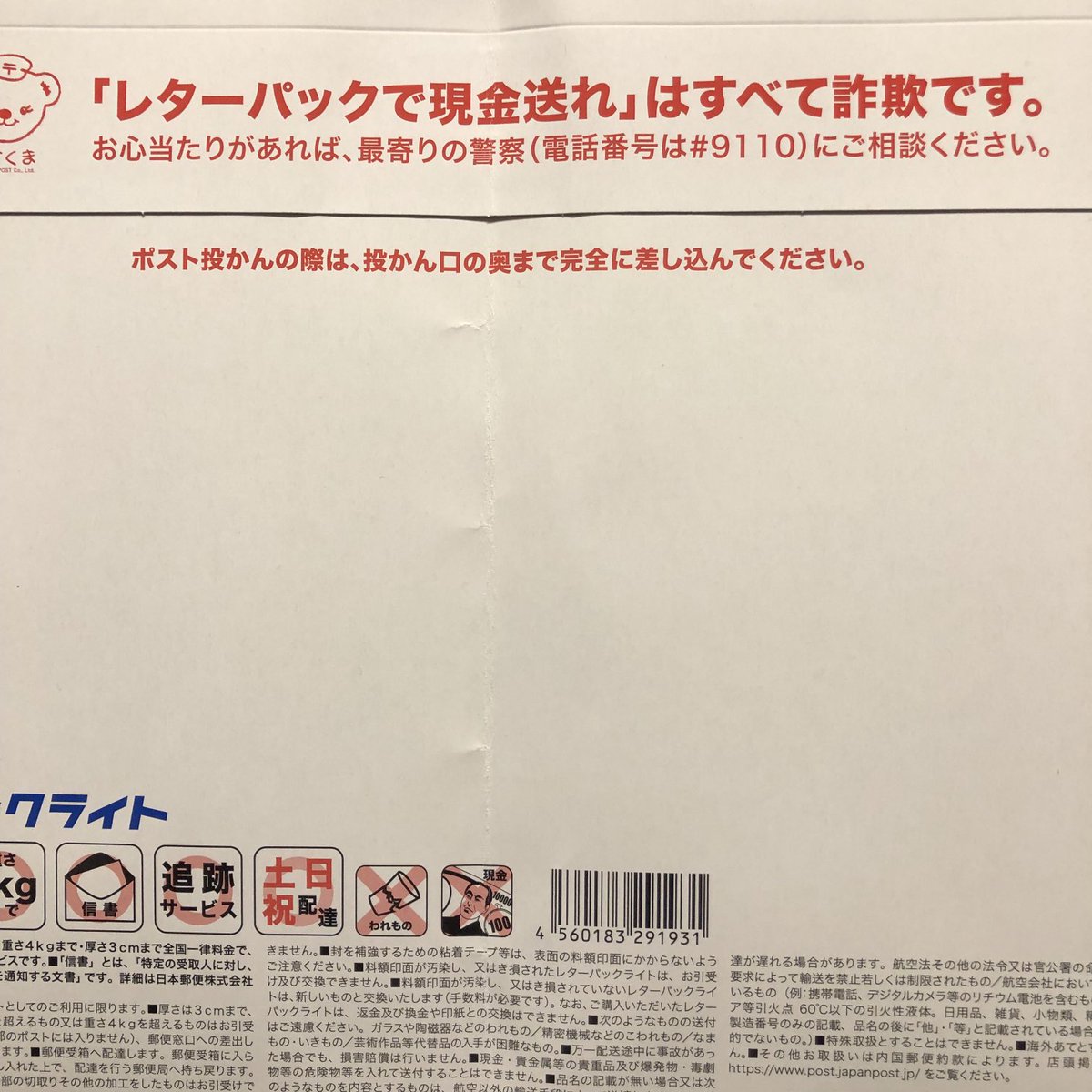1
卒論ゼミのあと指導室でワイン開けてチータラつまみつつ学生と卒論指導の続きやら人生相談をやっていた。「大学の教室で酒呑むなんてありえない」とかいう自粛根性に本学はまだ染まりきってないので大学教育を正常に行うことができる。それを外野に抗して踏ん張って維持するのが年配教員の仕事
2
まあオレは先人が死に物狂いで「母語による高等教育が可能な社会」を作って維持してきたのをコンパクトな能力なりに継承して次世代に受けわたすのがお仕事やとおもてます
3
人文系の博論出版って学術界向けというより「読書階級」(もはや死語に近いが)への貢献なんだよね。日本語圏のエクリチュールを豊かにした、という貢献への評価。まあネット全文公開でええやん、という主張も分かるしいずれそっちが主流になるだろうけど、現在は経路依存の過渡期なのだろう
4
文学部の学生の仕事は常時自分の関心あるテーマについての本や論文を読んでおくことで、それをやってない(やる気がしない)学生は卒論書けないのが普通です、くらいに常々アナウンスしとかんとあかんのやろな。授業受けて試験合格するだけで自動的に卒業できるわけやないんです。自動車学校とは違う
5
「なるべく思考を節約して何かをクリアする」のが「賢いやり方」と思われがちだけど、それが一番自分を無能にして危機的な局面で破滅するのに効率的なやり方であることは何度もアナウンスしておく必要がある
6
たぶんもっとも足りてないのは「勇気」で、大学とかに入った若い人はあとは勇気養うだけでいいとおもう。恥をかく勇気や教員に逆らう勇気やルールを破る勇気や倫理に従う勇気とか諸々。端的にその場の空気に抗う勇気。ほんまに感動したり絶望したり未知に出会ったり何かを愛したり、が勇気を育む
7
「規則を守る」ということが自明視され、「何のためにその規則があるのか」を問う能力が著しく減衰していると感じる。手続的正義は大事ですよ、でも手続的正義も暴走(という形容はイメージに合わないけど)するとクソな帰結に至ります。「規則を疑わず従う方が楽」という学生はとても増えた
8
丁寧に仕事をすればするほどブルシットジョブは増えていきオレたちは自分の首を絞めていく。「念の為に確認」「一応ご報告」「ご覧いただいた上でご意見下さい」。そこにあるのは官僚的組織における「丁寧さ」が量として個人の時間と思考を細切れに刻んでしまうシステムです。丁寧という名の責任転嫁
9
田中圭太郎『ルポ 大学崩壊』(ちくま新書)amzn.to/3Lg73m3 2023年。大学関係者必読の一冊。教職員のみならず学生や受験生も必ず目を通してくれ。いやむしろ受験生抱えた保護者こそが最も読むべきかもしれない。近年の大学業界の諸問題を地道な取材でありありと暴き出す。ほんますごい本
10
大学って学校やなくて遊び場なんですよね。「学校」的な空間で馴致された心身を解放しつつ自分の志向に基づいて再構成するところ。なので大学で使えるリソースは公園の遊具やと思ってください。図書館も教員も遊具。おもろそうな教員おったら「話聞かせてください」ゆうて誘って飯奢らせたらええねん
11
良い実例がありましたのでご覧ください。理解と同意を区別できない人ってほんとうにおるのよ twitter.com/fewlirpcd645/s…
12
「テロの背景を理解する」と「テロに同意する」を区別できない人々がいる。日本語で「理解する」という概念が「同意」の意味で誤用されることが多いためだ。オレ一回生には毎年「理解と同意を別物として区別しろ」「両者を曖昧に混ぜた「納得」という語は学術的議論で使うべきではない」と指導している
13
バイト先での動画が大炎上した22歳「僕の人生は終了した」300万円の賠償金、実家にまで誹謗中傷…炎上は本当に正義か
news.yahoo.co.jp/articles/2c56e… 処罰の「程度」のコントロールに誰も責任を持たなくなっている(そしてそのことに誰も気づかず、あるいは罪悪感を持たなくなっている)ようにおもえる
14
「女性は“誰かに属している”ことを求められる」 地方女子が感じる「生きづらさ」の正体〈dot.〉(AERA dot.)
news.yahoo.co.jp/articles/08695… たぶんここ読んでる君らの9割くらいにはさっぱり理解も共感もできない話。で1割くらいにはむちゃくちゃ切実で「当たり前の現実のそこから抜け出したい」話
16
明日から新たに就業・就学する皆さん!毎年この時期に申していることですが、社会人の基本とは「ほうれんそう」であります!放縦・恋愛・争議行為ですね。周りを顧みつつ好き勝手する。たくさん愛し合う。ストライキに立ち上がる。この三つこそ社会人が全うすべき責務であります。君らの前途に幸あれ!
17
教育学部の教授に小中高教員経験者、起用を義務化…文科省方針 : 読売新聞オンライン yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/… またうちの国はバカなことしてんな。「鳥類学者をクビにして鳥を教授にしよう」とほぼ同じ
18
むしろ感情を無視した定型的かつ非人情な儀礼こそがホロリと決定的に感情を揺さぶることが人生にはままあり、それを教育課程の仕上げとして最後に教えるのが卒業式の役割なのではないのかな。今日はうちの大学の学位記授与式。泣かせるようなことは一切喋るつもりはない。卒業生、最後にガンと呑むぞ!
19
息子の小学校の卒業式だった。最近の卒業式ってなんだろう「儀礼の実質化」をやたらと志向することで、その効果を逆に失っているようなところがあるように感じる。要するに「安っぽく泣かせようとする」。情緒的なBGM、児童が喋らされる感傷的な台詞、Jポップ風味のお別れの合唱、等々。
20
そこでは真理とかどうでもよく、「周りの人が自分にとって都合の良い反応をしてくれるためにはどう応答すれば良いか」を考える知性ばかりが異常に発達するだろう。ゆうたら悪いけど「工学的な知性」とゆうてもよい。難しい他人が思い通りに動く言動をすればよい。その原理への顧慮はまあ後回し
21
その場で周りを見渡して(正確には自分にとって重要な人だけ。どうでもいい人は無視)、周りの人らから「正解」と承認される応答をすること、もっといえば「周りの人が自分を承認してくれる答え」を探す能力を競っているのだろう
22
今の若人らが「正解」志向になってるとかよう言われるし、学生に授業コメントとか書かせても「私たちは教育の過程で唯一の正解を答えるよう教育されてきた」とか自己認識してるんだけど、そういうのって正解志向というより「その場での最適解志向」なのだろうとおもう。真理ではなく求められた答え志向
23
日本の最高学府の「大崩壊」が始まった…京大ほか国公立大で起きている「ヤバすぎる事態」(現代ビジネス)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/3d271…
24
いつの間にか「理解されることが最重要/理解されないものは意味がない」になってしまった。大学の授業などでも「わかりやすいこと」が最優先されるようになった。「自分の理解を隔絶したすごいもの」に触れてわかろうとする機会がものすごく減った。結果人類はどんどん無能になっていきます
25
査読って手を抜こうと思えばなんぼでも手を抜ける(し、それによって公然と批判されない匿名制)が、むちゃくちゃ丁寧にやっても得することはない。査読者の学問的良心と分野を支えるコミットメントだけが支えている制度で、業績主義が蔓延する昨今の学術業界ではその土台はやがて侵食されていくと思う