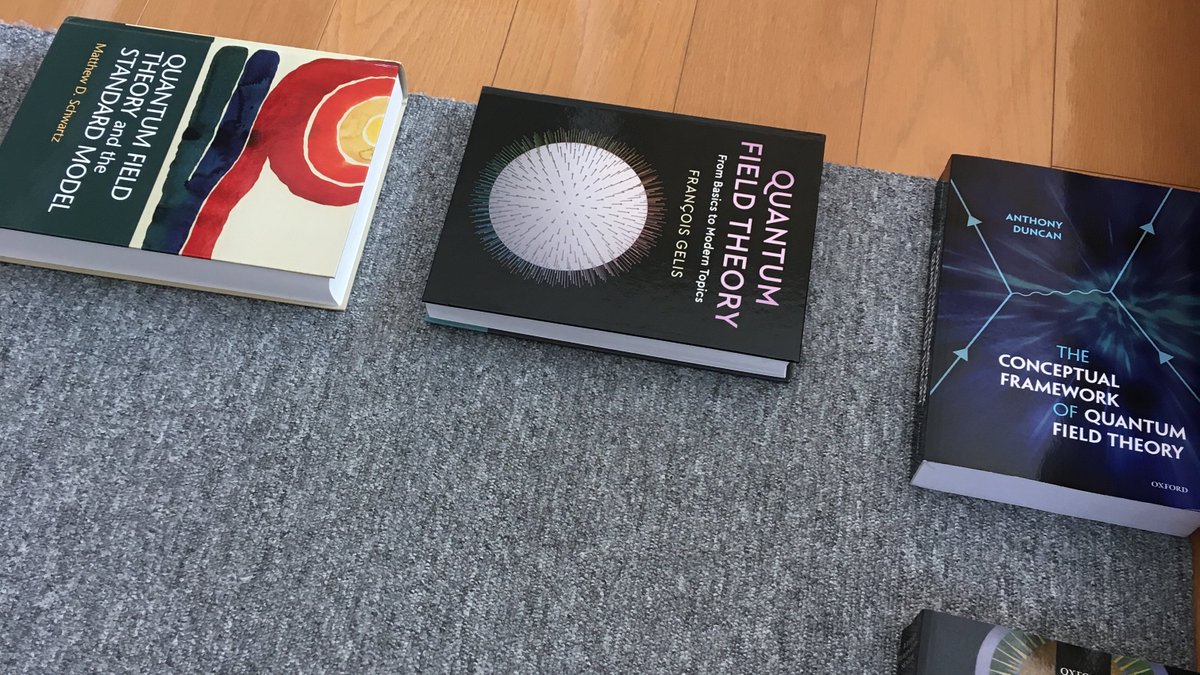1
石黒鎮雄『日本語からはじめる科学・技術英文の書き方』(丸善 1994) は絶版中とのこと。悲しい。
著者は英国の海洋物理学者。何とあのカズオ・イシグロの父!
2
日本物理学会誌は宝の山。これ読みたい。
doi.org/10.11316/butsu…
「削除しても文意の変わらない語句は全て冗長」。誇張語の使用は「野心に満ちた若い科学・技術者が初めて成功を経験した場合に使いやすい表現」。SNSは悪文であふれている。その倍は良文をよむべし。
3
日本物理学会誌は宝の山。積ん読ではもったいない。
doi.org/10.11316/butsu…
皿にこぼしたコーヒーの滴が乾くと円環状にあとが残る。なぜか。蒸発にともなう液滴中の水の流れのせい。蒸発とは何か。流体、相転移、拡散... 。身近な問題に微分方程式をあてはめて解く物理学の王道。
4
国際卓越研究大学に関するパブリックコメントとそれに対する反応(資料2)
mext.go.jp/b_menu/shingi/…
コメント「大学院生の研究職離れが深刻です。キャリアパスを見通せないことが原因です」
文部科学省の考え「博士課程学生支援を実施」
相変わらず現実が見えてないのか、見る気がないのか。
5
久保亮五の論文「不可逆過程の統計力学」。発表から65年を経て、引用数急増中。おそるべし。 twitter.com/inspirehep/sta…
6
「二年ごとの異動では感染症のエキスパートは育ちません。官僚にも五年、十年と感染症対策を担当させ... この分野では誰にも負けないという専門家を育ててほしい」
尾身茂氏が苦言「日本の政治には意思決定の文化が必要だ」 #文春オンライン bunshun.jp/articles/-/578…
7
強調したいデータ点を黒で塗りつぶし、対比する点は白抜きに。色をつけるなら白黒印刷でも判別できるように。昔は厳しく指導されたグラフの作り方は、いまは無法状態。
何を言いたいかというと、python+matplotlib (のデフォルト)で作った図は、色盲には判別不能です。イライラレフリーから一言。
8
若手を支援する研究費。そういうのを見るたびにため息が出る。若手が本当に必要としているのはそれではない。過去10年あまりのうちに激減した任期なしのポジション。政策担当の皆さんもわかっているはず。
9
全米で博士号を出している大学の教授のうち8割は、2割のエリート大学を出ている。出身大学より「格上の」大学で職を得た人はごくわずか。大学の先生の4分の1は両親のどちらかが博士。アカデミアは純粋培養装置か?
それが現実。何が問題か? 発想が偏ってしまうこと。 twitter.com/Nature/status/…
10
米国は論文のオープンアクセスを義務付けへ。英断だと思います。国民の税金を使って得られた成果は論文として公表されるわけですが、なぜか商業誌の記事として扱われ、お金を払わないと読めない。おかしいですよね。論文誌の最大の付加価値は査読なんだけど、査読者はほぼ無料で働いている。おかしい。 twitter.com/NewsfromScienc…
11
大学院入試の面接。部屋に入った瞬間、居並ぶ先生方の迫力に圧倒されて頭がまっ白。自分が何をしゃべっているのかもよくわからない始末。もう30年前のこと。
その後面接する側になってわかったこと。爽やかではきはき受け答えする人なんかいない。こちらも期待してない。考えながら答える姿を見たい。
12
高校化学で電子軌道とか共有結合とか楽しそうなことをやっているちょうどそのとき、高校物理では台車を転がして時間を測っている。
(いや、あれはあれで楽しいとは思いますが)高校生に興味をもってもらいたいなら、こうじゃないよね。昔から何も変わってない。
13
作用反作用の法則。ある力で机を押すA君は、逆向きの同じ力で机から押される。そんなわけないだろ、と思ってつまずいてしまった君。机を作っている原子のことまで考えないとわかるわけない、適当なことを言うな、と思ってしまうあなた。君こそ物理学者向きです。ぜひもっと深くはまってください。
14
機械学習はヒトの学習と比べてエネルギー効率が悪すぎる。考えてみれば当たり前。ヒトは学習するときに膨大な浮動小数点演算を繰り返して最小2乗法を計算しない。デジタルではなく、音や光の波を使った物理系でホントの「機械学習」ができないか。効率は悪いが、とにかく動くものができた。すごい。 twitter.com/QuantaMagazine…
15
抜群によい質問です。簡潔でかつ奥が深い。身近な現象と量子論の深いメカニズムをつなげる本質的な問いです。何が言いたいかというと、難しくて私にはちゃんと説明できません。どうしましょう。でもこれでは答... mond.how/topics/ja7xb0c… #Mond
16
大学院生の研究テーマ。意味のある研究で、学生さんが興味を持てて、かつ有限の時間(1〜2年)で終わるようなプロジェクトを人数分考えるのは、そんなに簡単ではないんですよね。教員も勉強を続け、技術を向上させないと追いつけない。書類書きや会議をこなしながら。ときどき愚痴も言いながら。
17
若者にこういう思いをさせているのがつらい。いま大きな顔をしている人たち(シニア世代)が大学生だったころ、学費は今の半額以下だった。経済成長のなかった20〜30年間、知らん顔で国立大の授業料を上げ続けた国は、何も知らない今の若者に負担を強いる。本当にずるいのは上の世代。 twitter.com/omusubi_phys/s…
18
マヨラナ準粒子を発見したとするグループがNature論文を撤回。今回で2本目。著者「データ公開の準備をしていたら、出版された図に使われたデータが不適切に切り落とされており、理論との一致に影響することがわかった」。めちゃくちゃ。
あれだけ騒がれた「マヨラナ粒子発見!」は嘘だった。 twitter.com/QuantaMagazine…
19
毎年のことですが、修士2年の学生に立派な研究計画を書かせるのはちょっと酷だと思うんです。経験がないから学びにきているのであって、ポスドクとは違う。自分の研究の全体像を勉強する機会になるという面はあるのですが、採択率2割で多くの人に小さくない挫折感が残るのは無視できない。
20
某有名大の名前を冠したクイズ番組が人気らしいんですけど、ああいうクイズの答は(とんち以外は)ネットで検索すれば出てくるんですよね。もちろんそれを覚えている出演者には感心するんですけど、誰も答を知らない問題に苦闘する大学院生のほうがほんとは格上だというのもぜひ知っておいてほしい。
21
英語の科学啓蒙書は妙に高尚な雰囲気を出すために分厚くなってることが多い気がして、そういう意味でもブルーバックスのレベルとか簡潔さはユニークだと思います。これは貴重な日本の文化なんです。
22
たとえプロの研究者といえども、他分野の情報を(それこそ近隣分野であっても)英語の本や雑誌を読んで仕入れるのはなかなかしんどいです。だからブルーバックスはありがたいな、と。特に第一線の若手や中堅が書かれたものは力が入っていて、これは結構すごいことだと思うんです。
23
世界初の電子計算機 ENIAC。計算の種類ごとにケーブルのつなぎ替えをしなくてすむプログラム方式を発想したのは数学・物理学者のノイマン。実際にコードを書いたのは妻のクララ。プログラマ兼コンパイラ。初期のコードは意味不明の数字の羅列。彼女こそすべての「ソフトウェア」の先駆者。 twitter.com/sciam/status/1…
24
え? もう10年も前に終わった米国フェルミ研究所の CDF 実験が、Wボソン質量の測定値を発表。標準模型の予言よりも 80 MeV 重い。誤差の7倍。すわ、新物理、ということだが、LHC ATLAS の測定とも合わない。どこかで何かが間違っている。 twitter.com/QuantaMagazine…