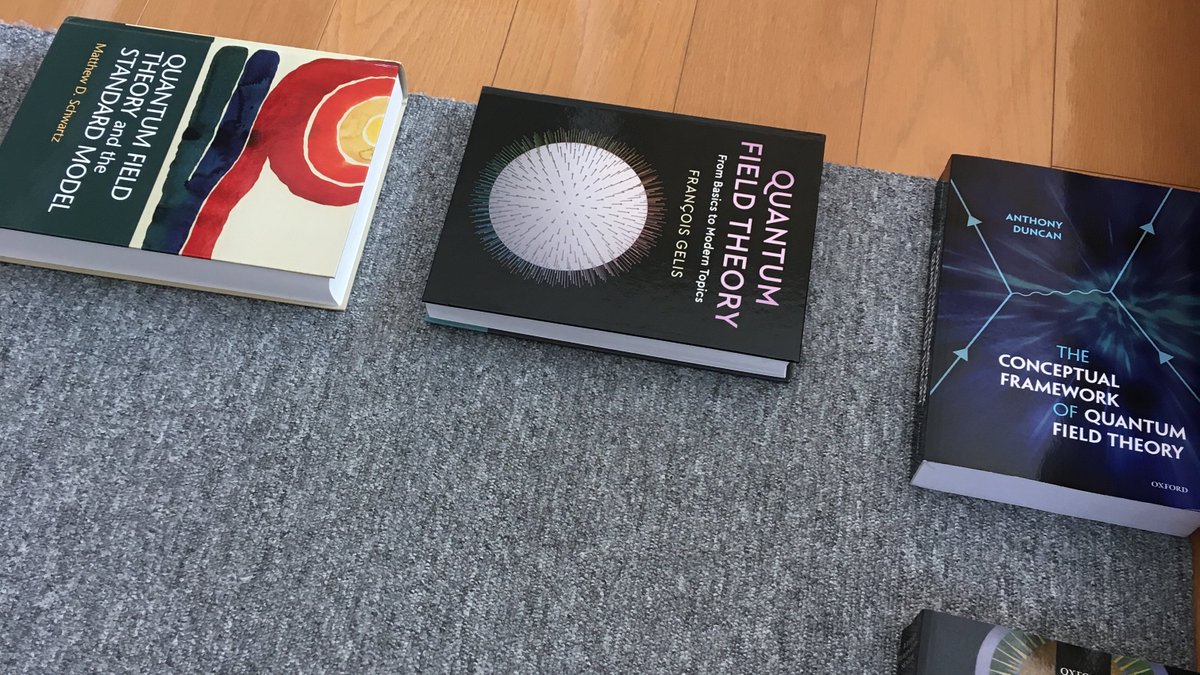1
抜群によい質問です。簡潔でかつ奥が深い。身近な現象と量子論の深いメカニズムをつなげる本質的な問いです。何が言いたいかというと、難しくて私にはちゃんと説明できません。どうしましょう。でもこれでは答... mond.how/topics/ja7xb0c… #Mond
2
日本物理学会誌は宝の山。これ読みたい。
doi.org/10.11316/butsu…
「削除しても文意の変わらない語句は全て冗長」。誇張語の使用は「野心に満ちた若い科学・技術者が初めて成功を経験した場合に使いやすい表現」。SNSは悪文であふれている。その倍は良文をよむべし。
3
ポスドクの推薦書でこれまで最も驚いたのは、ある大御所の先生からのもの。「彼は極めて優秀である。はっきり言ってずば抜けている。何しろ研究費があったら絶対うちで雇いたいくらいだ。実は今度、変な邪魔が入らなければ研究費が取れるはずなので、彼のことは雇わないでいただきたい」。
4
「Ph.D ポジションはありますか?」外国の大学院生(修士相当)から聞かれることは多い。「日本の制度は違っててそういうのはないんだよ。国費留学生に応募してみて」と説明してどれだけ優秀そうな学生さんを逃したか。大学院生への給与は、支援ではなく国際競争力の前提。大学ランキング低迷も当然。
5
米国は論文のオープンアクセスを義務付けへ。英断だと思います。国民の税金を使って得られた成果は論文として公表されるわけですが、なぜか商業誌の記事として扱われ、お金を払わないと読めない。おかしいですよね。論文誌の最大の付加価値は査読なんだけど、査読者はほぼ無料で働いている。おかしい。 twitter.com/NewsfromScienc…
6
68歳で医学部教授を引退してから、若い頃からの夢だった物理学の勉強を再開した。MITの講義を取りながら時間をかけて学び、ブラウン大で大学院へ。体調の問題で中断を余儀なくされつつも、ついに理論物理で学位を取得。「ボゾン化」に関する150ページを超える大作。89歳。「若者よ、まずは夢を追え」 twitter.com/NPR/status/145…
7
ドイツ首相を引退するメルケルさんは、元科学者(理論量子化学)。エビデンス重視の姿勢を貫いた。量子計算などの成長分野に投資しつつ、好奇心で進む研究も軽視しなかった。英国王立協会でのスピーチでは、「科学的発見がどう進むかを予言できるという政治家がいたら疑ってかかるべきだ」と述べた。 twitter.com/Nature/status/…
8
たとえプロの研究者といえども、他分野の情報を(それこそ近隣分野であっても)英語の本や雑誌を読んで仕入れるのはなかなかしんどいです。だからブルーバックスはありがたいな、と。特に第一線の若手や中堅が書かれたものは力が入っていて、これは結構すごいことだと思うんです。
9
選択と集中の現実。5年にわたって苦労して、ようやく軌道にのってきたプロジェクトは中止。雇われていた若手はクビ。流行に乗れそうなネタを新たにでっち上げて申請し、当たったらまた人集めから。繰り返すごとに劣化するのは道理。怨嗟と諦念の末に成し遂げた「効率化」は補正の大盤振る舞いでパア。
10
中3数学の模試で、正答率1%の難問。「父さんにまかせんさい。どれどれ.... ええっと.... あれ?」99%の仲間入り。 「大丈夫、物理学者に数学は必要ないよ」と、なぐさめてくれた。子育ては間違ってない。
11
大学院生へのアドバイス。指導教員とは、インプットを入れるとアウトプットが出てくるマシンだと思え。何も入れないと何も出てこない。ただし「彼(女)が先週何を話していたかを覚えていると思ってはいけない」。
他にもいろいろ。ぜひ。 twitter.com/AustinZHenley/…
12
某有名大の名前を冠したクイズ番組が人気らしいんですけど、ああいうクイズの答は(とんち以外は)ネットで検索すれば出てくるんですよね。もちろんそれを覚えている出演者には感心するんですけど、誰も答を知らない問題に苦闘する大学院生のほうがほんとは格上だというのもぜひ知っておいてほしい。
13
若者にこういう思いをさせているのがつらい。いま大きな顔をしている人たち(シニア世代)が大学生だったころ、学費は今の半額以下だった。経済成長のなかった20〜30年間、知らん顔で国立大の授業料を上げ続けた国は、何も知らない今の若者に負担を強いる。本当にずるいのは上の世代。 twitter.com/omusubi_phys/s…
14
大学院入試の面接。部屋に入った瞬間、居並ぶ先生方の迫力に圧倒されて頭がまっ白。自分が何をしゃべっているのかもよくわからない始末。もう30年前のこと。
その後面接する側になってわかったこと。爽やかではきはき受け答えする人なんかいない。こちらも期待してない。考えながら答える姿を見たい。
15
くやしいけど日本の大学院の仕組みを変えられるのは東大しかないと思うんですよね。各研究室に博士課程のポジション(給与付き)を1つずつつけて国際公募すれば流れが変わると思う。優秀な人がみんな応募するし、負けられない他大学もまねする。JST のとかファンドとか、資金はあるはず。今こそ。
16
毎年のことですが、修士2年の学生に立派な研究計画を書かせるのはちょっと酷だと思うんです。経験がないから学びにきているのであって、ポスドクとは違う。自分の研究の全体像を勉強する機会になるという面はあるのですが、採択率2割で多くの人に小さくない挫折感が残るのは無視できない。
17
物理学科の悪癖。「群論って大事らしいよ」「数学科に講義があるみたい」「よし取ろう」。大挙して講義に乱入。定義、定理、証明の美しい流れを、最前列から5分おきの「例をあげてください」攻撃でめちゃくちゃに。数週間後、「最後まで SU(2) は出てこない」と聞いて全員撤収。数学科に平和が戻る。
18
作用反作用の法則。ある力で机を押すA君は、逆向きの同じ力で机から押される。そんなわけないだろ、と思ってつまずいてしまった君。机を作っている原子のことまで考えないとわかるわけない、適当なことを言うな、と思ってしまうあなた。君こそ物理学者向きです。ぜひもっと深くはまってください。
19
「君はこの誤差に命をかけるか」戸塚洋二・元KEK機構長(故人)に問われたことがある。「実験家は誤差に命をかけている。君はどうだ。」眼鏡の奥の目は笑っていなかった。スパコンの説明をしたときのこと。しどろもどろで答えたが、「よしわかった」。予算を認めてくれた。今でもときどき夢に出てくる。
20
大学院生の研究テーマ。意味のある研究で、学生さんが興味を持てて、かつ有限の時間(1〜2年)で終わるようなプロジェクトを人数分考えるのは、そんなに簡単ではないんですよね。教員も勉強を続け、技術を向上させないと追いつけない。書類書きや会議をこなしながら。ときどき愚痴も言いながら。
21
アカハラを受けた人のうち、7割は報復を恐れて所属機関に報告しなかった。報告した人のうち、フェアに扱ってもらえたのはたったの8%。組織は自己防衛する習性がある。特に、金を取れる研究者を守りたい。
個々の訴えを読むのがつらい。泣き寝入りばかり。進んでいるはずのアメリカでもこれ。 twitter.com/ScienceMagazin…
22
強調したいデータ点を黒で塗りつぶし、対比する点は白抜きに。色をつけるなら白黒印刷でも判別できるように。昔は厳しく指導されたグラフの作り方は、いまは無法状態。
何を言いたいかというと、python+matplotlib (のデフォルト)で作った図は、色盲には判別不能です。イライラレフリーから一言。
24
高校生の子が学校で Wolfram Alpha を教わってきたらしい。神の道具だという子に父の威厳を見せるチャンス。「これを作ったウォルフラムさんは元素粒子理論の人だよ」「へ〜、たまには役に立つ人もいるじゃん。父さんもこういうの作ったら」「あれはもっと頭がいい人しか作れないの」。威厳喪失。
25
「大学で物理学科に入ると、きっと相対性理論とか量子力学とか、そういうあこがれの理論を学べるものだと思って期待するのだが、実は1年生ではそういう格好いい話は全然出てこない。高校で学んだニュートンの法則がもう一度始まるのでがっかりして意欲を失ってしまう人がいても不思議ではない。」