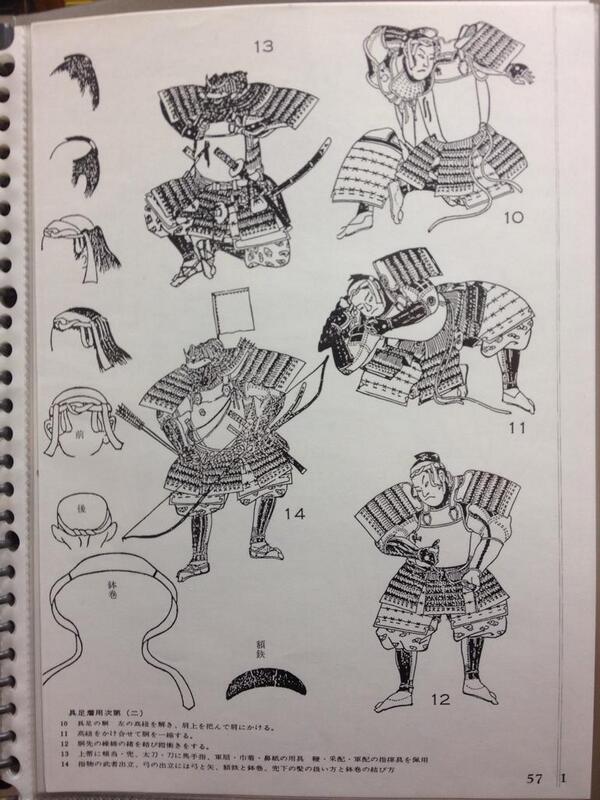26
28
29
30
31
33
勝鬨(かちどき)のエイ、エイ、オー!(鋭鋭応)の現代語訳は、大将が「用意はいいか?用意はいいか?」に対して家臣が「いいですよー!」と応えるものである。みんなでエイエイオーを全部言ってはならない。
34
【拡散希望】
恒例の鏡開き式・鎧着初めの一般募集
鎌倉時代の甲冑武者になろう
平成31年1月14日(月)成人の日
日本武道館
集合AM8時半
解散PM2時半
参加費8,000円(鏡開き式パンフ・絵馬・名前入袖印・草鞋・弁当・お屠蘇・お汁粉付・三月末まで甲冑会例会参加費千円)
以下参照
japanese-armor.org/jpn/archives/6…
36
38
40
41
45