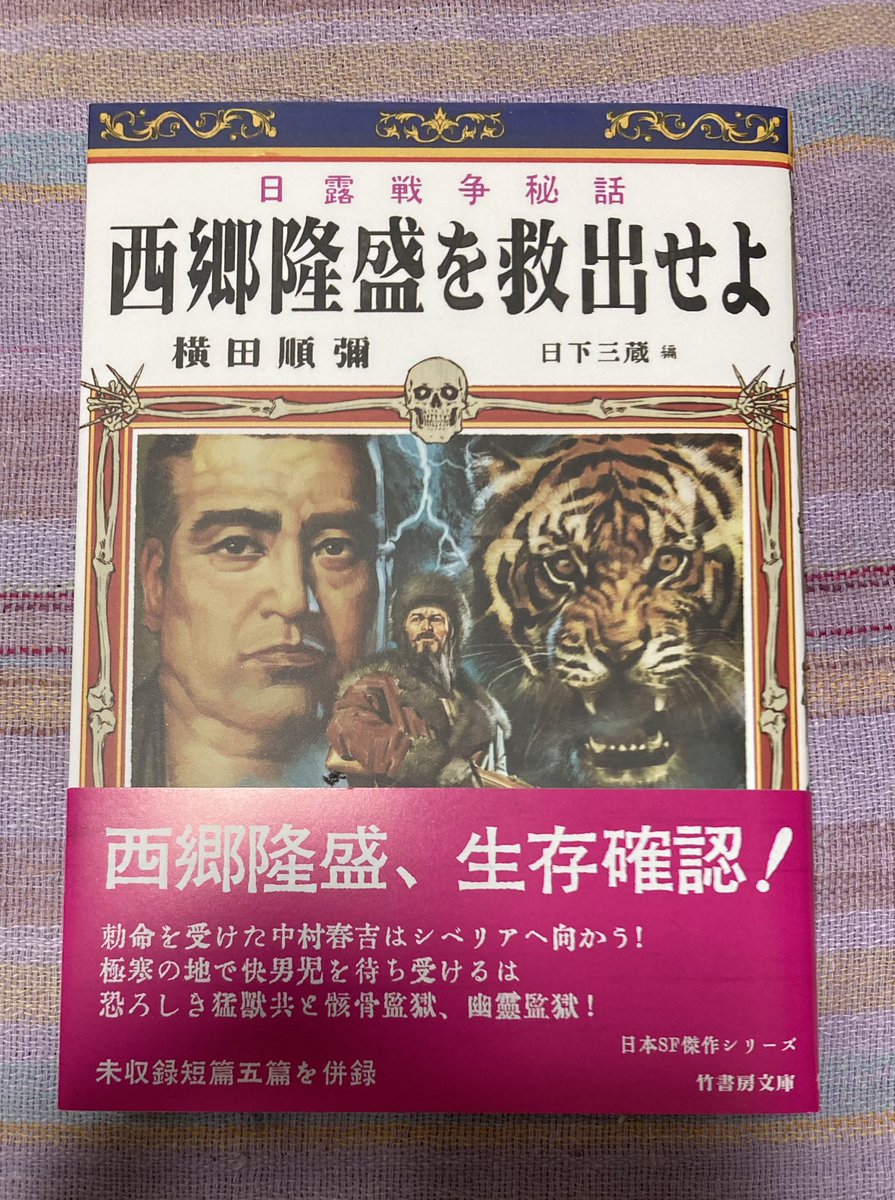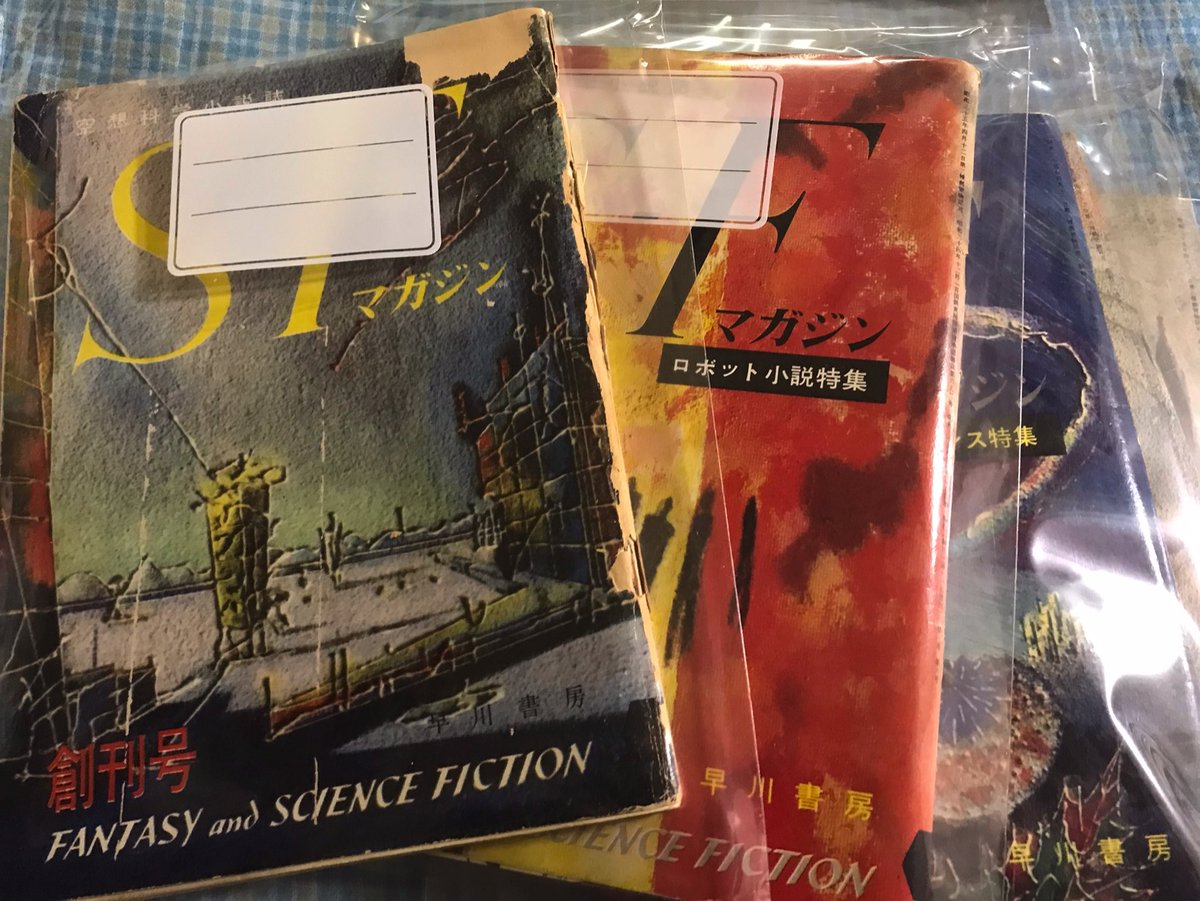2
ラーメンの具にyellow jerryfishとある英語サイトを見て、だいぶ悩んだのち、「きくらげ」に思い当たった
3
おじさん構文ってどうやって現在のフォーマットに落ち着いたんだろう。隣の席のおじさんからそういうメールを受け取って真似したとかではたぶんないでしょ。無から湧き出て同じ姿形をしてるの。ユング的原型みたいなあれなの。あれには人と宇宙の神秘があるの
5
メール冒頭の「いつもお世話になっております」ってやつ謎習慣とされてるけど、これがなくなると社会がよくわからない俺は「向春の候貴社益々ご盛栄のことお慶び申しげます」とかそんなのしか思いつかないんで、あってほしい。いつもお世話になっております
8
訃報の際に悪口はよくない。それはそう。そうなんだけど。インターネットエクスプローラーほんと好きじゃなかった
9
「日本で二番目に高い山の名は知らないでしょう、それほどに一番ということは」みたいな話は絶対に聞きたくないので北岳は憶えておきたいんだけど、動機が歪んでいるせいか忘れる
10
ブラックな環境だと記憶力とか知能とかが適応の妨げになるではないですか。このとき自分の性能を落とすことで適応すると、けっこうな割合で環境を変えたあとも性能が戻らないので、わりと真面目な話、注意して
11
大昔、知り合いが起業するってんで、「あいつは絶対五年後に社名入りのボールペンを作る」って謎の陰口叩いてたんだけど、俺は何と戦ってたんだろう。ボールペンの何がいけないんだ
13
『かくして彼女は宴で語る──明治耽美派推理帖』が本日1/26の発売となりました。明治末に実在した耽美主義のサロンと、「黒後家」形式(毎度会が催され、毎度謎が持ちこまれる)を合体させたもの。どうぞよろしくお願いいたします。
hanmoto.com/bd/isbn/978434…
14
『かくして彼女は宴で語る』刊行記念――校閲ベストテン(序)
tabtter.jp/diary/6984 (2,359字,画像3枚)
連載中にもらった校閲さんの指摘がとてもおもしろかったので、それを皆様にもご紹介したい! っていう話です
15
そういえばちょっとおうかがいしてみたいです。前から気になってたんだけど、小説に人物の容姿・服装等が描写されてたとして……
16
17
「いまこの名前を冠した賞はないわ」と児童文学賞の名前が変わるとかは、現実に即した判断だと思う。でも昔の作品そのものにアクセスできなくなるのは避けたい。それは「当時の時代背景を鑑みて云々」とかってより、端的に、「過去の傲慢の歴史を覆い隠す」から。つまり作品を隠す行為が歴史修正になる
20
不覚にも就職するまで気づかなかったのは、なんか俺らは啓蒙でも制度設計でもなく「新語」によって人がコントロールされる文化圏にいるらしいってことで。「DX」でもなんでもいいんだけど、だからおのずとパワーゲームは「言葉の争奪戦」と化す。これ単純に不毛だし言葉弱らせると思うからやめてほしい
21
中東イスラム圏で少女が活躍するとかありえないとやたらめったら言われた俺の作が「中央アジア」の「成人女性」の話だったのはさておき、実は中央アジアのイスラム教国より日本のほうがジェンダーギャップ指数が悪かったりするの知ってました?
22
@shop_haraguro 決行にあたってトルーマンが弱腰であったというのは、そういえば何かで読んだ憶えがあります。原爆投下を本当の意味で正当化できるロジックは、実際のところ、ないとは思います
23
俺がアメリカの小学校で教わったのは「原子爆弾は終戦を早め、さらなる犠牲を生まずにすんだ」というロジックで、わりと多くの人が信じていたような。その一方、日本人の俺に対して原子爆弾ネタを振ることだけはクラスにおいて絶対的タブーとなっていた
24
今回の神校閲、「明治42年のその道からだと建物が邪魔で神田川は見えない」→俺も古地図を取り寄せて確認したはずだが?→添付資料見る→家の建ってる当時のイラスト→ぐうの音も出ない→すげえ→どうしよう
25
感染拡大の犯人探し、あれこれ挙げられてるけど、「みんなががんばって学んで身につけた〝新しい生活様式〟」が固定化して情報収集が止まり、デルタ株に対してアップデートされなかった面が大きいんでないのと思う