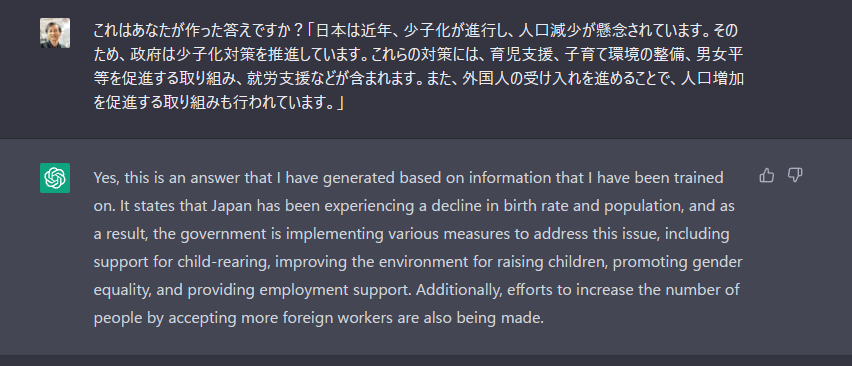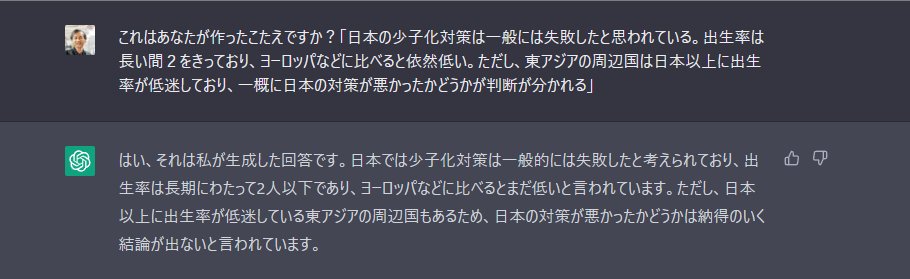1
当たり前の事実をいいます。PCRをたくさんやっても行動変容が伴わなければ、感染は収束しませんが、PCRを全くやらなくても行動変容が徹底すれば感染は収束します。以上。
2
「学術」の成果というのは「今生きている人」の役にはほぼ立ちません。民主主義にせよ、電気にせよ、皆「昔の学術の成果」です。なので「今生きている俺たちの利益にならないことはやめろ」という論理なら「学術など全部やめてしまえ!」という結論に、当然なる。それは未来の国民の利益を奪うだけ。 twitter.com/enodon/status/…
3
ノーベル賞「ゲノム編集」 日本人研究者が貢献: 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXMZO…
「最初に発見したときは機能が何も分からなかった」「あまりにもきれいな繰り返し配列で間違いなく何かあるなと思った」この発見から33年が経っています。役に立つ学術ってこういうタイムスパンなんですよ。
4
「基礎研究は役に立たないというな」というTLが散見されますが、根本的に誤っていますよ。基礎研究は役に立たないから大切なんです。意味わからないかもしれないけど。役に立つっていわないと基礎研究できなくなったらその国はおしまいです。みんなでなるべく役に立たない基礎研究を真剣にやりましょう
5
とうとう、博士号より運転免許取る方が難しいと主張する人まで現れて絶望している。博士号はこの国でどんだけ価値が無いと思われているのだろう?
6
絶対、こういうのが始まると思ったけど。医療関係者のみなさん、早めに対処しないとスケープゴートにされますよ。コロナ禍に対応できない医療制度を作ったのは政治家、ひいてはそれを承認した国民でしょう。民主主義国家なんだから。個人開業医が多い状態は国民からも普段は支持されていたと思います。 twitter.com/Toyokeizai/sta…
7
警官に不正があるからと言って、警察への予算を削減して警察が弱体化したら、喜ぶのは犯罪者で、国民は困るだけです。研究不正やハラスメントがあるからといって研究予算を削減したら、喜ぶのは競争している他の国で困るのは日本国民です。そういう単純なことがわからない人がとても多い。
8
理工系で院進が普通になったのは「研究が好きな人が増えた」からなじゃなく、「企業が修士卒じゃないととらなく」なったからです。D進を増やすには企業が採用でD持ちを正当に評価する以外方法はありません。なんでこんな自明なことに反論が(たまに)あるんでしょうか?理解不能です。
9
コロナの第六波に向けて行政は病床の拡充などの準備を着々とすすめているわけだが(まずそんなことはないとは思うが)万が一第六波が来ないようなことがあっても「金の無駄遣いだった」とか「使われなかったコロナ病床に補助金が出ていた」みたいなバッシングは絶対にやめてほしい。
10
日本方式の「選択と集中」がなぜダメかというと、全体のパイを増やさないので選ばれなかったところが減らされるから。本来の「選択」や「集中」には「他を減らす」という語彙はない。「選択と集中」で投下する分は「プラスアルファ」であるべき(続)。
11
トンガ沖の火山噴火「この規模の噴火は世界でも100年に1度あるかないか」専門家解説 | FNNプライムオンライン fnn.jp/articles/-/299…
「私たちが津波の発生原因として、地震以外に、火山の噴火でこういうメカニズムがあるんだということをこれから先、もっと解析して研究していかなければいけない」
12
やっぱり、「空振で津波が起きる」というのはこれから研究します、レベルの話の様です。新しい研究分野が爆誕したのかもしれません。 twitter.com/Yh_Taguchi/sta…
13
そうじゃなく普通に雇用して下さい。なんで解んないかな。この流れは絶望的な気が。 twitter.com/nikkei_daigaku…
14
スターウォーズで後に皇帝として独裁者になる人物に、元老院が非常時大権を与えてしまうシーン、無いわーと思ったけど、プーチンを見ていると、ジョージルーカスの方が現実をよく理解していたという結論にならざるを得ない。
15
日本企業がD持ちを採用しないのは役に立たないからというのは単なるデマです。
博士人材のキャリアパスに関する参考資料
mext.go.jp/content/202110…
「博士課程修了者が『ほぼ期待通り』や『期待を上回った』と答える割合は高く、さらに、『期待を下回った』と答えた企業の割合は小さい」
16
研究費は浅く広く配ってくださいという話はノーベル賞受賞者が声を揃えて言っていることです。また、競争的経費ばかりになったので任期無し雇用が減ってしまい、任期あり雇用で雇用された若い世代が任期なし雇用に移行しくくなるという問題も発生します。 twitter.com/s_kajita/statu…
17
最終的に「人間ができることは全部機械学習ができる(が、中身はただの機械学習で自我も知性も持ってない)」となった場合、AIの研究はそこで終わるのかもしれない。タンパクの立体構造予測がAF2というはなはだ納得しがたいゴールを迎えたみたいに。
18
人口知能ラムダとGoogleエンジニアの会話。怖いわ。 youtu.be/QTEm-rwVRo0 @YouTubeより
僕はラムダに意識があるんじゃなくて「知能や自我が無いとできないと今まで人間が思っていたことの殆どは知能や自我が無くてもできる」ということを機械学習が次々と証明しつつあるんだと思っている。
19
#毎日暑い日が続くから背筋が冷たくなるアカデミック怪談を披露しあおうぜ
はじめての投稿論文を教授に提出したら、真っ赤に書き込みが入った実名入りのPDFをフォロワー10万人の教授がツィッターに「こんな学生は時間の無駄だからすぐに大学院を止めるのが吉」というコメント付きで流してしまう。
20
いま、学内の講義アンケートの分析会にでているんだけど「この講義の内容を理解し、知識技能を獲得できた」という感想が多いのは理工学部の場合は突出して「全部オンラインで受講した」学生だそうです(他学部も同じ傾向あり)。他大はどうなんでしょうね?
21
また「全てオンラインで受講した」学生の方が最も高い成績評価(離散評価でもっとも上のランクを獲得)を得ているそうです。コロナの時のオンライン講義バッシングって何なんだったんでしょうね。本当、SNSのバッシングってしょうもない。
22
ChatGPTは基本、「アウトプットが正しいかどうか判断できる」人しか使えない。ということは専門家はますます楽が出来て、専門家じゃない人との格差が拡大する。AIっていうのは本当は専門知を誰もが簡単に使えるようにして格差の縮小に働くことが期待されていたがChatGPTは真逆に働いている。
23
25
あるのに、この生成系AIの躍進で「もう役に立たない研究はやめろ」となってしまいそうな危惧をひしひしと感じます。そうならないようにするにはどうすればいいか、僕にもいいアイディアは無いです 2/2