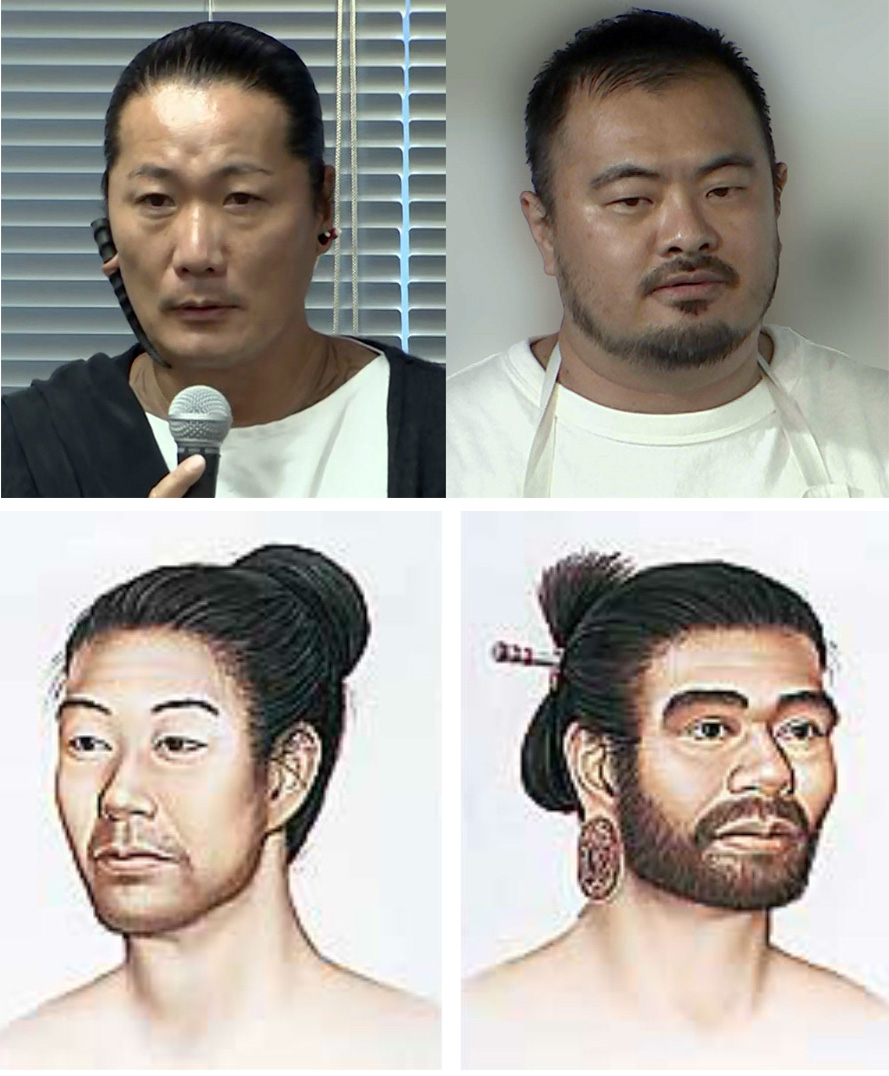2
3
小3の女の子に「先生は宝くじで1億円当たったら何買いますか?」と聞かれたので、「花子ちゃんちみたいな大きなお家を買いたいな!」と答えたら「え、うちは1億3000万だから買えないよ」と真顔で言われたので「そ、そっか…じゃあね…他にはね…車とかかな…」と答えた。
世の中厳しいなと思った🙂
4
@casandayo 80年も昔の帝国軍人である山本五十六が『やってみせ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ』という名言を残しているのに、21世紀のホテルマンが「できていたら黙っています。褒めませんので」というのはあまりに対照的ですね。
5
6
@Vb28N9vY4E96UlQ @GotoSesame いや、県はぱっと見、身体の一部とか入ってないじゃないですか!でも、念のため調べてみましょう。
県の旧字『縣』、左の「県」は人の首が逆さまになった物、右は「糸」。つまり木に首を逆さまにぶら下げていることを表し「かける」と読む。後に行政単位も指すようになった
(((( ;゚Д゚)))ヒィィィ!
7
@maymetz_do もう「首」が入っている時点で嫌な予感しかしませんが…調べてみました…
『切った首を持って道を行く。道を行くとき異族の人の首を刎ねて、道に潜む邪霊をその首の呪力で祓った』
(((( ;゚Д゚)))ヒィィィ!
8
小3の生徒に「どうして『取る』っていう字は耳へんなんですか?」と聞かれ、私も知らなかったのでその場で漢字字典で調べたところ『捕虜や敵の耳を戦功の印としてしっかり手に持つことを表す』と書かれていて、生徒と二人でぶるぶる震えた。